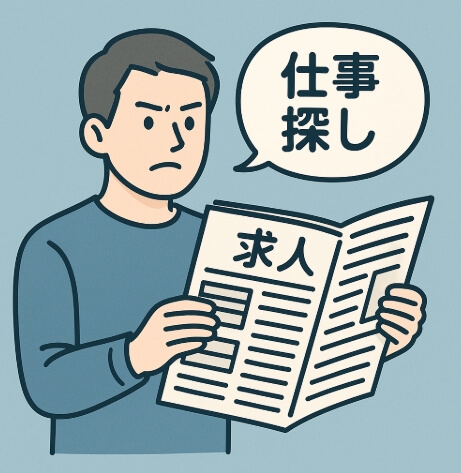「失業保険を受給していたら確定申告する必要があるの?」
「確定申告が必要な場合はどんな時?」
「確定申告をしたことがないからどうすればよいかわからない」
失業保険を受給したら、確定申告しなければならないのでしょうか。失業保険を受給中は、原則確定申告は不要ですが、場合によっては確定申告が必要となるケースもあります。
また、確定申告をしていないと損をする場合もあるため、どのような場合に確定申告をする必要があるかどうかをきちんと把握することは重要です。今回は、失業保険を受給中に確定申告が必要になる場合や、確定申告の手続きについて紹介します。
失業保険と税金のことが気になっている方はぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。
目次

社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
失業保険の確定申告は原則不要

失業保険の給付金は課税対象ではないため、原則確定申告をする必要はありません。確定申告とは、収入を得た人が自分で税金を計算し、税務署へ報告する手続きです。
ただし、失業給付金以外に所得がある場合には確定申告をする必要があります。次に、確定申告が必要なケースや確定申告をした方が得をするケースを紹介します。
失業保険受給後に確定申告が必要な7つのケース

失業保険受給後に確定申告が必要なケースを7つ紹介します。それぞれ詳しく解説します。
1.失業保険を受給中に収入を得た場合
失業保険受給中に、パートやアルバイト、ネットビジネス、在宅ワークなどで収入を得た場合には確定申告が必要です。失業保険を受給中も、要件を満たしていればパートやアルバイトできるからです。
要件とは、「週20時間未満の労働」「1日の労働時間が4時間未満」の場合に限ります。原則週に20時間以上の労働は「就職」として扱われる点に注意が必要です。
失業保険で受給する給付金は課税対象ではありませんが、パートやアルバイトなどの給料に対しては課税されるため、確定申告して納税する必要があります。
詳しくは、管轄の税務署にご確認ください。
2.投資で儲かった場合
受給中に投資をして儲かった場合にも、確定申告が必要になる可能性があります。例えば、株式投資をしている場合に、特定口座で源泉徴収なしを選択していたり、一般口座で取引していたりする場合には自分で確定申告しなければなりません。
不動産投資や仮想通貨で利益を得た場合にも、確定申告が必要です。きちんと申告しないと無申告として扱われ、後に高額な無申告加算税が課される可能性もあるので注意しましょう。
3.投資で損失が出た場合
株式投資をしている方で、「損失」が大きくなった場合にも確定申告すると税額を減らせる場合があります。上場株式の譲渡損失を、その年の配当所得、利子所得と相殺できる制度です。
また、損失が残った場合には損失発生の翌年から3年間にわたって繰越控除も可能です。投資で多額の損失が出た場合には確定申告をして、税額を減らすことを検討しましょう。
4.再就職しなかった場合
サラリーマンは毎月給料から源泉徴収されており、年末調整を実施することで払いすぎた税金が還付されます。失業保険を受給中で再就職していない場合には、年末調整をしないので年末に税金が還付されません。
そのため、年度途中で会社を辞めて年度内に再就職できなかった方は、自分で確定申告すると払いすぎた税金の還付を受けられる場合が多いでしょう。
確定申告には退職した翌年から5年間の期間制限があるので、該当する場合には早めに確定申告を行う必要があります。
5.退職金を得た場合
退職金を得ている場合には、確定申告を行うことで税金の控除を受けられる可能性があります。退職金には、所得税と住民税、復興特別所得がかかり、退職金の受け取り方は、一時金として受け取る方法と年金で受け取る方法の2種類があります。
ただし、退職一時金を受け取る際に、支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、支払者が適正な税額を源泉徴収してくれるため確定申告は必要ありません。
申告書を提出しない場合には、退職一時金に対して一律20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。しかし、退職金には退職所得控除を適用できるので、確定申告をすることで税金の負担が軽くなります。
税額を少しでも減らすためには、確定申告をするようにしましょう。
6.医療費控除や住宅ローン控除がある場合
医療費控除とは、生計を同一にする人にかかった医療費が年間で10万円を超えるときに所得額を減額してもらえる制度です。確定申告時に医療費の明細を提出すると、結果的に税額が低くなって払いすぎた税金を還付してもらえる可能性があります。
医療費控除の対象になる人の範囲は、「生計を同一にする人」全体に適用可能です。また、同居者だけではなく別居していても、生活費を送金するなど生計が同一といえるなら医療費控除の範囲に含まれます。さらに、それぞれの人が加入している健康保険は異なっていてもかまいません。
例えば、夫と妻の健康保険が異なる場合でも、妻や子どもにかかった医療費をまとめて計算し、夫の税金を減らすことも可能です。
医療費控除の対象になる費用の範囲は以下のような費用です。
- 病院に払った治療費
- 自費診療の費用
- 投薬料
- 薬代
- 交通費
健康保険が適用されるかどうかは関係なく自費診療分も含まれ、薬代や交通費など、病院に支払う以外のお金も含めて計算できます。医療費控除は適用範囲が広いので、前年に自分や家族に多額の医療費がかかった方はぜひ確定申告してみてください。
また、住宅ローン控除は、給与所得者は初年度に限り確定申告が必要ですが、通常2年目以降は年末調整により控除が反映されます。ただ、失業保険受給中で住宅ローンを組んでいる方は、会社で年末調整ができないので、自分で確定申告をする必要があります。
医療費控除や住宅ローン控除がある方は、忘れずに確定申告をしましょう。
7.個人事業主になって年間所得が48万円以上の場合
会社に就職せずに個人事業主になった場合、年末調整ができないため自分で確定申告をする必要があります。ただし、年間所得が48万円以上の方のみが対象です。
年間所得とは、事業収入から必要経費を引いた金額であり、収入とは異なる点には注意が必要です。
確定申告の手続き期間と手順

失業保険を受給した後に、確定申告が必要な場合を紹介しました。次に、確定申告の手続きの方法と手順を紹介します。
確定申告の手続き期間
手続き期間は、例年2月16日から3月15日です。ただし、所得税の還付を受ける場合、翌年の1月1日から申告書を受け付けてもらえます。
確定申告の手順
手順は以下の通りです。
1.確定申告の手続きに必要な書類を用意する
確定申告の手続きに必要な書類を用意しましょう。必要な書類は以下の通りです。
- 確定申告書
- 源泉徴収票(前職の退職時にもらう)や収入がわかる書類
- 生命保険や個人年金などの控除書類
- 住宅ローン減税を受ける場合には住宅借入金等特別控除額の計算明細書など
- 株式関係の所得を申告する場合には証券会社から送られてきた年間取引報告書
- 不動産収入がある場合の収入や経費に関する資料
- 医療費控除を受ける場合には医療費や薬代などの明細書、領収証など
- ふるさと納税を利用する場合には自治体から送られてきた寄付金控除証明書など
- マイナンバーのわかる資料(マイナンバーカード、マイナンバー通知書など)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 銀行口座の通帳(還付金を振込してもらうために必要)
確定申告書は、税務署の窓口でもらうか、国税庁のホームページから入手できます。生命保険料などの控除証明書は保険会社から送られてきます。
2.申請を作成する
必要な書類の準備ができたら、確定申告書に、納税者の情報、収入金額、所得金額、所得控除金額、税金額などの必要事項を記載します。
国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーや会計ソフトを利用すれば、必要事項を記載することで所得金額や税額を自動計算してくれるので、作成の手間が省けるでしょう。
3.税務署へ申告書を提出する
確定申告書が完成したら、以下3つの方法のいずれかで税務署に提出します。
- 税務署の窓口に提出する:作成した申告書とその控えを税務署の窓口に持参する
- 税務署に郵送する:所轄の税務署に郵送で確定申告書、申告書の控えと返信用封筒も同封する
- e-Taxを利用して提出する:電子データで、確定申告書などを税務署に提出する
税務署には管轄があるので、自分の住所地を管轄する税務署を調べて期間内に持参しましょう。
また、郵送の場合の提出期限については「消印の日付」が基準となります。申告期限ギリギリになると間に合わない可能性があるので、早めに送付しましょう。
e-Taxとは電子データで確定申告書などの書類を税務署に送信する方法です。利用すると税額の控除額が大きくなり、税金を減らせるケースもあります。ただし、e-Taxを適用するには事前に届出が必要なので、早めに対応を開始しましょう。
確定申告の際、納めるべき税金がある場合には期限内に納付する必要があります。納税はお近くの金融機関でもできますし、税額が30万円以下であればコンビニでも納税可能です。クレジットカードで納税する方法もあります。
ただし、期限内に支払わないと税金の滞納状態となり、延滞税が加算される可能性があるので注意してください。
医療費控除などの結果、還付を受けられる場合には申告後1~2ヶ月くらいの間に指定した口座へ還付金が振り込まれます。還付される場合には、特に何もする必要はありません。
失業保険を受給したい方は社会保険給付金サポートがおすすめ
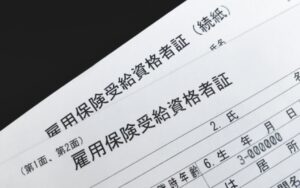
失業保険の申請にはいろいろな書類が必要です。退職理由によっては2ヶ月または3ヶ月の給付制限が適用されるケースもあります。そんな場合でも、社会保険給付金サポート会社でアドバイスを受ければ、給付制限なしですぐに失業保険を受け取れる場合もあります。
退職後、失業保険の受給を検討しているなら弊社の「社会保険給付金サポート」への相談がおすすめです。社会保険給付金サポートとは、失業保険などの雇用保険の受給を支援するサービスです。
また、失業保険の受給中にアルバイトやネットビジネスなどで収入を得る場合には、ハローワークへ申告する必要があります。確定申告だけではなく、ハローワークでの手続きも行わないと失業保険を停止されてしまう可能性があるので注意しなければなりません。
素人判断で適当に対応すると、本来受け取れるはずの失業保険を受け取れなくなったり、失業保険の不正受給とみなされたりするリスクも発生します。
スムーズに失業保険を申請し、満額を受給するには専門家によるアドバイスやサポートを受けておくと安心です。これから失業保険を受給しようと考えている方は、ぜひとも一度社会保険給付金サポートまでご相談ください。
日本全国、24時間土日祝日も無料で相談できます。また、万が一受給できなかった場合には全額返金してくれるので安心して利用できます。