「傷病手当金が終わったら失業保険へ切り替える方法は?」
「失業保険の金額はいくらもらえる?」
「傷病手当金と失業保険はどちらがお得なの?」
病気やケガをして働けなくなった場合には「傷病手当金」、働く意思があるのに再就職できない場合には「失業保険」を受給できます。傷病手当金の受給が終わり、就職できる状態になったら失業保険も受給可能です。
ただし、傷病手当金が終わったら失業保険に切り替える場合にはいくつかの注意点があります。
この記事では、
- 傷病手当金と失業保険の違い
- 傷病手当金が終わったら失業保険への切り替え方法
- 切り替える際の注意点
- 傷病手当金と失業保険はどちらがお得になるか
について解説します。傷病手当から失業保険へ切り替えをしたいと考えている方は最後まで読んで参考にしてください。
目次

社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
傷病手当金と失業保険の違い
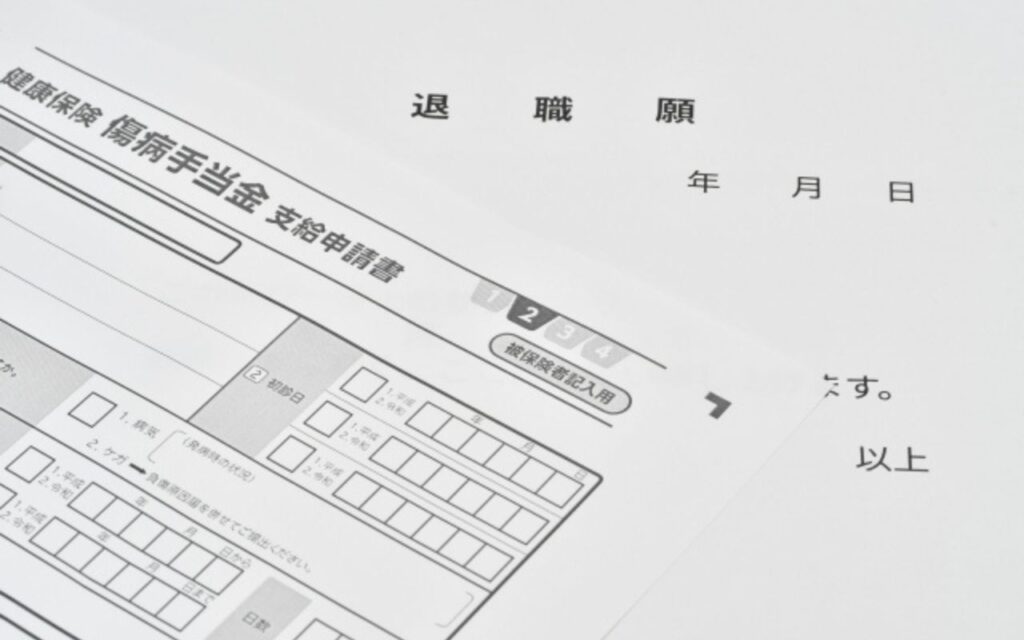
傷病手当金は病気やケガで働けない場合に受給でき、失業保険は働ける状態にある場合に受け取れます。そのため失業保険は、病気やケガで働けない場合には受給できません。
ここでは、傷病手当金と失業保険の違いについて詳しく解説します。
1.傷病手当金は病気やケガで働けない場合に受給できる
傷病手当金は、病気やケガが原因で働けず、給与の支払いがないときに受給可能です。給付は加入している健康保険や共済組合から行われます。
傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 業務外の原因の病気やケガで就労できない
- 健康保険に加入している
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる
- 給料を受け取っていない
受給できる金額は、給与額の3分の2程度です。傷病手当金を受給するためには、医師の診断書を取得して、健康保険組合に申請する必要があります。
病気やケガで就労できないまま退職した場合には、退職後も引き続いて傷病手当金は給付されますが、給付期間は最長でも1年6か月です。また、病気やケガが治癒したら、健康保険からの傷病手当金は受け取れなくなる点に注意してください。
なお、「傷病手当金」と「傷病手当」は、似ていますが異なります。傷病手当金は健康保険から給付され、傷病手当は雇用保険から給付されます。
傷病手当は、失業保険を受給できる資格のある人が、求職活動中に15日以上続く病気やケガで就労できない場合に支給される給付金です。傷病手当の金額は、失業保険の基本手当と同額です。
2.失業保険は働ける状態にある場合に受給できる
失業保険は、働ける状態にある場合に受給できます。失業保険を受給するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 離職の日以前の2年間に12が月以上の雇用保険の被保険者期間がある
- ハローワークで就職活動を行っている
失業保険の受給額の計算式は以下の通りです。
- 「失業保険の受給額」=「基本手当日額」×「給付日数」
- 「基本手当日額」=「賃金日額」×「雇用保険の給付率」
「基本手当日額」は、1日あたりの失業保険給付金額のことです。給付日数は、雇用保険への加入期間、退職時の年齢、離職理由によって変わりますが、90日~330日になります。
「雇用保険の給付率」は、年齢や賃金日額によって異なり、60歳未満は50%~80%、60~64歳の場合は45~80%です。賃金日額が高い場合には45~50%、賃金日額が低い場合には80%の給付率が適用されます。
傷病手当金が終わったら失業保険への切り替え方法2つ

傷病手当金を受給していて、失業保険への切り替える方法は2つあります。退職後30日より前か後かで切り替えるタイミングが異なります。
- 退職後29日以内に再就職できる場合
- 退職後30日以上再就職できない場合
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.退職後29日以内に再就職できる場合
退職後29日以内に再就職できる場合には、必要書類を準備し、ハローワークで失業保険を申請できます。通常の失業保険の申請手順とほとんど変わりません。
手順は以下の通りです。
- 失業保険の申請のための書類を準備する
- ハローワークで失業保険の申請手続きをする
- 7日間待機する
- 雇用保険受給者説明会に参加する
- 求職活動をする
- 初回の失業認定日にハローワークに行く
7日間の待機期間の終了後、「会社都合退職」であればすぐに失業保険の受給可能です。「自己都合退職」であれば給付制限期間2~3か月を経て失業保険を受給できます。
2.退職後30日以上再就職できない場合
退職から30日以上再就職できない場合には、傷病証明書の取得と失業保険の給付期間の延長手続きが必要です。
手順は以下の通りです。
- 傷病証明書を取得する
- 失業保険の給付期間延長の手続きをする
- ハローワークで失業保険の申請手続きをする
- 7日間待機する
- 雇用保険受給者説明会に参加する
- 求職活動をする
- 初回の失業認定日にハローワークに行く
失業保険の給付期間の延長手続きには、「傷病証明書」が必要です。「傷病証明書」は、本人情報、病名、病状、就労に関する事項などが記載されており、就労できる状態にない(就労不能)ことを証明する書類です。
働ける状態になったら、ハローワークで失業保険の申請手続きを行いましょう。
傷病手当金から失業保険へ切り替える際の2つの注意点

傷病手当金から失業保険へ切り替える際には、以下の注意点があります。
- 受給期間延長の申請はなるべく早く行う
- 受給期間を延長できる条件を確認する
それぞれ詳しく解説します。
1.受給期間延長の申請はなるべく早く行う
受給期間延長の申請はなるべく早く行う必要があります。受給期間延長申請には期限があり、期限を過ぎると延長できない可能性があるからです。
- 妊娠、出産、病気、ケガなどが原因で延長する場合:申請期間は離職日の翌日から30日過ぎた日~1か月以内
- 60歳以上の定年などが理由の場合:申請期間は離職日の翌日から2か月以内
受給期間延長期限を正確に確認し、なるべく早く手続きを行うようにしましょう。
2.受給期間を延長できる条件を確認する
受給期間を延長できる条件を確認しておく必要があります。延長できる条件は以下の通りです。
- 病気やケガの治療中である
- 妊娠や出産、育児(子供が3歳以下の場合)のために就労が難しい
- 親族の看護や介護をしていて働けない
- 定年退職の後に休養を希望していること
上記のいずれかの条件を満たして、すぐに働ける状態にない場合に延長できます。また、延長できる期間は定められており、定年退職後の休養の場合には2年間、それ以外の場合には4年間延長可能です。
受給期間を延長できる条件に当てはまるかどうかをきちんと確認しましょう。
傷病手当金と失業保険はどちらがお得になる?
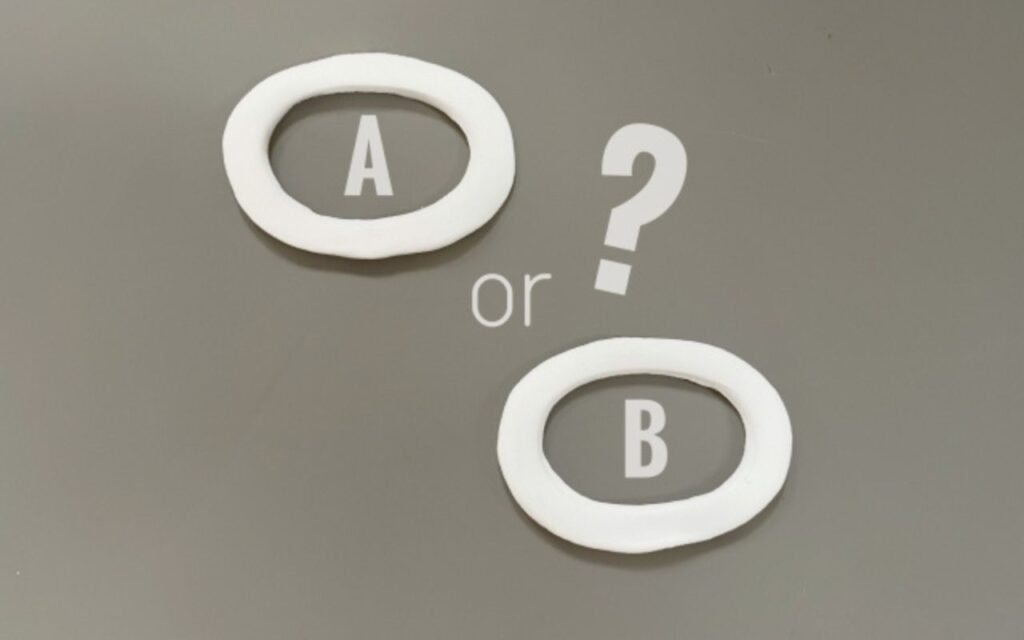
傷病手当金と失業保険はどちらがお得になるかは、人によって異なります。ここでは、以下の内容について解説します。
- 傷病手当金の受給金額
- 失業保険の受給金額
- 傷病手当金を受け取った方が得になりやすい
- すぐに就職先がみつかるなら失業保険が得になりやすい
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.傷病手当金の受給金額
傷病手当金の受給金額は、給与のおよそ2/3です。
| 1日あたりの支給額 =過去12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 ×2/3 |
また、支給期間は休職開始から最長1年6ヶ月までとなっています。
| 例:協会けんぽ加入期間:17年間、退職時の年齢:40歳、給与金額:38万円
傷病手当金の1日あたりの受給金額=38万円÷30日×2/3=約8,444円 |
2.失業保険の受給金額
失業保険の受給金額は、以下の計算式で算出されます。
- 「失業保険の受給額」=「基本手当日額」×「給付日数」
- 「基本手当日額」=「賃金日額」×「雇用保険の給付率」
| 例:協会けんぽ加入期間:17年間、退職時の年齢:40歳、給与金額:38万円
「賃金日額」=月給38万円×6か月÷180日=12,666円 |
同じ条件で算出すると傷病手当金は1日約8,444円、失業保険は6,333円になり、傷病手当金方がお得になります。ただ、人によって給与額や雇用保険の加入期間、年齢によって異なるので試算するのがおすすめです。
3.傷病手当金を受け取った方が得になりやすい
上記で算出したように、1日に受け取る受給額は傷病手当金を受け取った方がお得になりやすいでしょう。また、傷病手当金は最長1年6か月受給できますが、失業保険の支給期間は最長でも330日間です。
受給可能な日数を考慮しても傷病手当金を受給した方がお得になる可能性が高いです。
ただし、いったん失業保険を受け取り始めたらもう一度傷病手当金を受け取れない点に注意しましょう。
4.すぐに就職先がみつかるなら失業保険が得になりやすい
すぐに就職先がみつかるなら、失業保険の方がお得になりやすい場合もあります。傷病手当金は、病気やケガが治癒した場合には支給されないからです。
一方、失業保険は求職活動をしている間は支給されるため、失業保険の受給期間の方が傷病手当金の受給期間よりも長くなる可能性があります。
失業保険と傷病手当金のどちらがお得になるかは以下のケースで考えてみるのがおすすめです。
- 病気やケガの程度
- 雇用保険の金額と傷病手当金の金額の差額
- 求職にかかりそうな日数の見込み期間
病気やケガの程度について自分で判断できない場合には、担当医に聞いてみるとよいでしょう。
傷病手当金と失業保険に関するよくある質問
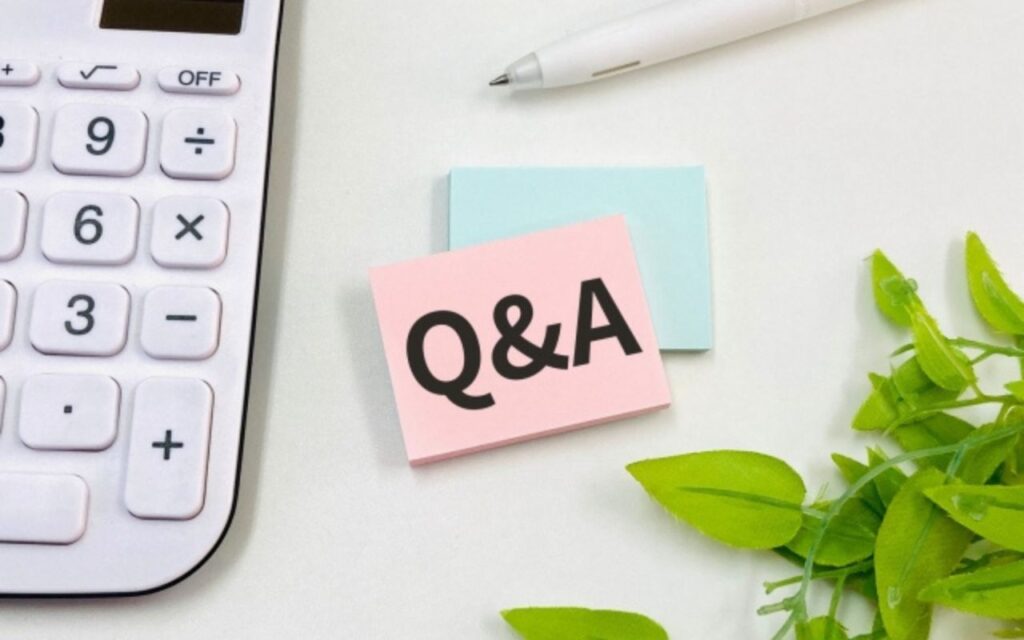
最後に、傷病手当金と失業保険に関するよくある質問を紹介します。
- うつ病で失業保険はもらえない?
- 休職のまま退職すると失業保険はもらえる?
- 傷病手当金と失業保険は同時にもらえる?
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.うつ病で失業保険はもらえない?
うつ病でも働ける状態なら、失業保険がもらえます。失業保険を受給するためには就労できる必要があるからです。
ただし、うつの症状が重く働けない場合には、失業保険はもらえません。
2.休職のまま退職すると失業保険はもらえる?
休職のまま退職すると「正当な理由のある自己都合により離職した者」という扱いになり、一般的な離職者と同様に失業保険を90~150日の給付ができます。
なお、失業保険の給付日数は、離職者の雇用保険加入期間と年齢によって異なります。
3.傷病手当金と失業保険は同時にもらえる?
傷病手当金と失業保険は、両方同時にはもらえません。失業保険は、就労できる状態である場合に受給できますが、傷病手当金は就労不能である場合に受給できるからです。
傷病手当金が終わったら失業保険への切り替えは専門家に相談しよう

健康保険の傷病手当金から失業保険へ切り替えをする際には、「病気やケガがいつ治ったのか」「切り替えをした方がお得になるのか」など、検討すべき内容が多いでしょう。また、切り替え申請手続きには手間がかかるので、自分で行うのを大変に感じている方もいるかもしれません。
そんなときには、社会保険給付の専門家に相談するのがおすすめです。
切り替え申請をした方が得になるのか、申請のために何をすればよいかなど、それぞれの状況に応じてアドバイスします。書類の作成方法や申請方法についても専門サポーターが案内しますので、お気軽に相談してみてください。
失業中に病気やケガをした場合には、健康保険から給付の「傷病手当金」ではなく、雇用保険から給付される「傷病手当」を受給できる場合もあります。申請に困っている場合には、一度お気軽にご相談ください。
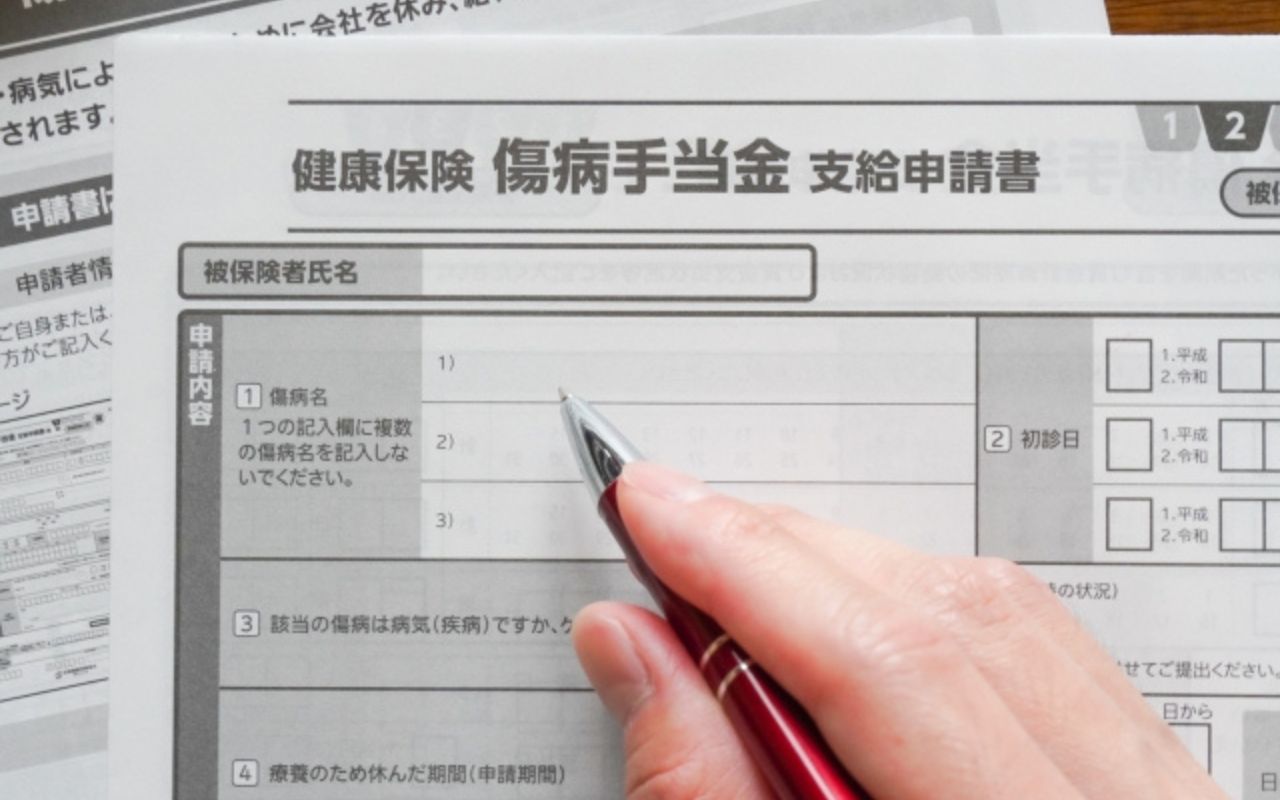










コメントを残す