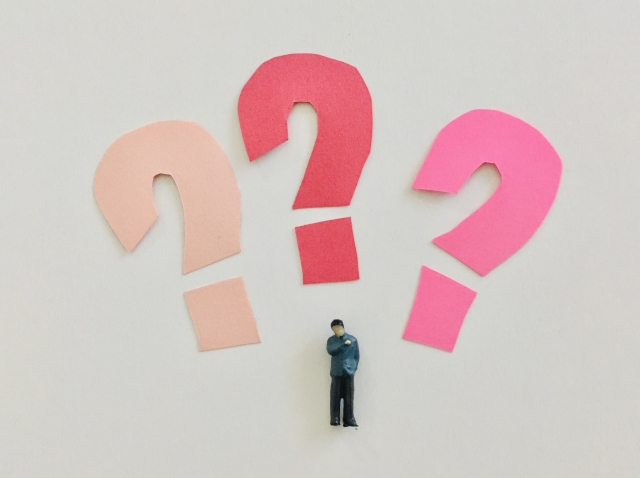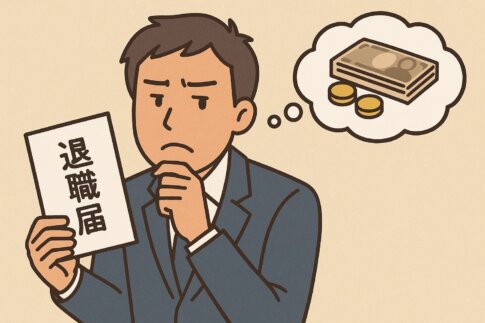「うつ病で退職しても失業保険はもらえる?」
「退職の仕方によってもらえる時期は異なるのだろうか?」
「失業保険と傷病手当金は併給できるの?」
といった悩みをお持ちの方がいるのではないでしょうか。うつ病で退職した場合には、生活のためのお金が必要です。
また、再就職に向けて早く元気になりたいと願う方もいるでしょう。
そこで本記事では以下のポイントについて解説します。
- 失業保険をもらえる3つのパターン
- 失業保険をもらうための条件
- 失業保険と傷病手当金の関係
- 失業保険や傷病手当金をもらうためのステップ
失業保険と傷病手当金は全く異なる給付ですが、両者を明確に区別しどちらの給付を受けられるのかを理解することで、退職後でも安心して生活でき次のステップに進めるでしょう。
目次

社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
うつ病で退職した際に失業保険をもらうための3つのパターン

うつ病で退職したときに失業保険をもらえるケースは、以下の3パターンです。
- 自己都合退職の場合
- 会社都合退職の場合
- 特定理由離職者の場合
まずは、自分がどのケースに該当するのかを確認しましょう。
1.自己都合退職の場合
うつ病の原因が業務に起因しなければ、自己都合退職として処理されます。
自己都合退職の場合、原則として給付制限期間が2ヶ月設定されており、7日の待機期間と給付制限が経過してから、認定日に支給が開始されます。
2.会社都合退職の場合
うつ病になった事由が会社側にあり退職した場合には、会社都合の退職となります。例えば、職場におけるパワハラや残業時間が多く心身を病んでしまった場合などです。
会社都合退職は、自己都合退職に比べて給付までの期間が短いのが特徴です。給付制限期間の2ヶ月がないため、7日の待機期間が満了すると翌日から給付を受けられます。
会社都合であるか自己都合であるかについて、裁判で争われた事例もあるため、会社都合で退職するためには、うつ病を発症した原因が業務に起因することを示す証拠を用意するのが望ましいです。
3.特定理由離職者の場合
うつ病の場合、特定理由離職者に該当する場合があります。特定理由離職者は、正当な理由によって体力の不足や心身の障害、疾病、負傷などで離職した者のことです。
会社都合退職が認められなくても特定理由離職者と認定されれば、2ヶ月の給付制限を受けずに失業保険をもらえます。
ただし、特定理由離職者であると認定を受けるためには、医師の診断書などが必要となります。
うつ病で退職したあとに失業保険をもらうための2つの条件
うつ病で退職したあとに失業保険をもらうためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 被保険者期間が離職前の2年間に12ヶ月以上あること
- 失業状態にあること
それぞれの条件について、詳しくみていきましょう。
1.被保険者期間が離職前の2年間に12ヶ月以上あること
雇用保険の失業保険をもらうためには、原則として離職前の2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あることが必要です。
ただし、会社の倒産や解雇によって離職した場合や有期契約労働者で契約が更新されなかったなどのやむを得ない事情がある場合には、離職前の1年の間に雇用保険の加入期間が6ヶ月あればよいです。
2.失業状態にあること
失業手当をもらうためには、失業状態であることが求められます。「失業状態である」とは以下の3つの条件を全て満たす状態です。
- 就職しようという積極的な意思がある
- 健康状態や居住環境に問題がなく、すぐにでも就職できる能力がある
- 現在、仕事を積極的に探しているが職業に就けていない
以下のような人は、上記の3条件に当てはまらないため失業保険を受けられません。
- 妊娠や出産、育児などですぐに就業できない人
- 病気や怪我の治療中ですぐに仕事ができない人
- 就職するつもりのない人
- 家事や学業に専念している人
- 会社の役員
- 自営業者
失業保険と傷病手当金は併給できる?

病気やケガの時に受給できるものに、傷病手当金があります。失業保険と傷病手当金は似ていますが、同時にはもらえません。
失業保険は、働く意思や能力があるにもかかわらず仕事に就けないときに支給されるものです。
一方、傷病手当金は業務外の病気やケガのために働けない場合に支給されます。なお、業務上の事由による病気やケガは労災保険の対象となります。
このように、働く意思や能力はあるものの仕事がない場合に支給される失業保険と、労務不能状態である場合に支給される傷病手当金は同時には支給されません。
| 失業保険 | 傷病手当金 | |
| 受給要件 | ・働く意思や能力がある
・失業状態である |
・業務外の事由によって労務不能状態である |
| 支給対象者 | 雇用保険加入者 | 健康保険加入者 |
| 申請先 | ハローワーク | 協会けんぽ、健康保険組合 |
また、失業保険と傷病手当金の金額にも違いがあります。自己都合退職の場合は失業保険を受けられる日数(所定給付日数)は90〜150日であるのに対して、会社都合退職の場合は90〜330日です。
一方、傷病手当金は日額を単位に計算されます。日額は、直近1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の3分の2です。
傷病手当金をもらうための4つのポイント

ここでは、傷病手当金をもらうためのポイントについて解説します。
- 4日以上休職している
- 給与が支払われていない
- 退職後でも受け取れる
- うつ病が再発しても傷病手当金はもらえる
傷病手当金で損をしないためにも、1つひとつのポイントについてしっかり理解しましょう。
1.4日以上休職している
傷病手当金を受けるためには、労務不能状態が連続4日以上であることが求められます。3日連続の待機期間を満たすことで、4日目から支給されます。
休職期間が3日の場合には支給はなく、また待機期間の3日が連続していない場合にも支給は行われません。
例えば、2日連続で休職したあとに1日だけ出勤して1日休職した場合には連続3日ではないので支給はされません。
2.給与が支払われていない
傷病手当金は、給与が支払われていない日について支給されます。休職中であっても、給与が支払われている日がある場合には支給はありません。
また、有給を取得した場合には減額して傷病手当金が支給されます。
3.退職後でも受け取れる
傷病手当金は、在職中に業務外の事由による病気やけがに対して支給が行われますが、条件を満たせば退職後にも傷病手当金をもらえます。
退職後も傷病手当金を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
- 退職日の前日までに連続3日以上出勤せず、退職日に出勤していない
- 退職日においても引き続き労務不能である
傷病手当金の申請には医師の証明が必要であるため、在職中に通院していることが求められます。
4.うつ病が再発しても傷病手当金はもらえる
傷病手当金は、労務不当となった病気やけがの状態がなくなった場合には支給はされなくなりますが、同一の病気やけがが再発すると再受給ができます。
受給期間は同一の病気やけがについて、傷病手当金の受給開始から通算して1年6ヶ月に達するまでです。
失業保険と傷病手当金の2つの選択パターン
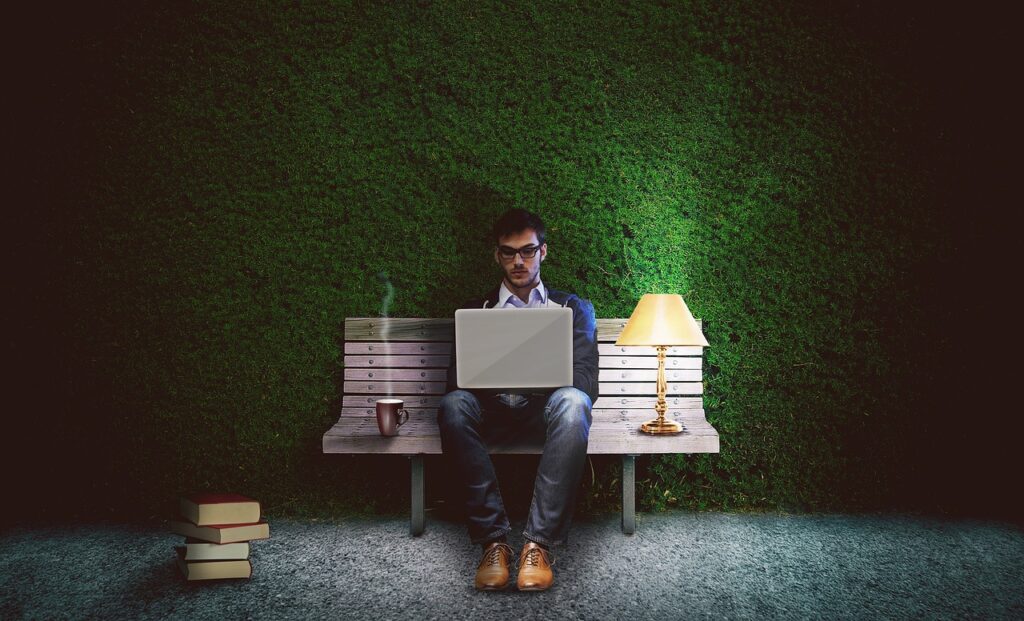
ここからは失業保険と傷病手当金のどちらを受給するのかについてみていきます。
- うつ病がひどくて退職後に働けない場合
- うつ病が軽くて退職後に働ける場合
心身の状態によって、受給できる給付金が異なるので注意が必要です。
1.うつ病がひどくて退職後に働けない場合
退職後にうつ病の症状がひどくて働けない場合には、傷病手当金を受給することになります。その後、働ける状態になった場合には、傷病手当金から失業保険に切り替えます。
ただし、雇用保険の失業保険を受けられる期間は離職日の翌日から1年間と限られているため注意が必要です。
離職日の翌日から1年以内に継続して30日以上働けない場合には、受給期間の延長を行えます。延長を行うことで、本来1年の受給期間を最大4年まで伸ばせます。
2.うつ病が軽くて退職後に働ける場合
退職後にうつ病の症状が軽く、仕事ができる状態である場合には就職するまで失業保険を受けられます。このとき、労務不能ではないので傷病手当金の申請はできません。
うつ病で退職した時の失業保険の申請のための6ステップ

退職後に失業保険を申請から支給までは、以下のステップに沿って行います。
- 離職票を会社からもらう
- 管轄ハローワークに求職の申し込みをする
- 受給資格説明会に参加する
- 求職活動を行う
- 失業の認定を受ける
- 支給決定
スムーズに支給決定がされるように、ぜひ参考にしてみてください。
1.離職票を会社からもらう
退職すると、まず会社から離職票を発行してもらいましょう。離職票は、在職中における雇用保険の被保険者資格を証明するもので、出勤日数や給与額などが記載されています。
2.管轄ハローワークに求職の申し込みをする
会社から発行された離職票を持って、住所地を管轄しているハローワークに求職の申し込みを行います。受給資格を確認したのち、受給説明会の日程について知らされます。
3.受給資格説明会に参加する
あらかじめ指定された日時で、受給資格説明会に参加します。この説明会に参加すると、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付され、第1回の失業認定日についても知らされます。
4.求職活動を行う
失業認定を受けるまでの間に、積極的に求職活動をする必要があります。求職活動をすることで、就職する意思があることが確認されます。
求職活動とは具体的にはハローワーク窓口で職業相談を受けたり、職業紹介を受けたりなどです。
5.失業の認定を受ける
失業状態にあることを確認するために、原則として4週間に1度、失業認定を受ける必要があります。
このときに雇用保険受給資格者証明とともに、失業認定申告書に求職活動の実績等を記入して提出します。
6.支給決定
失業認定を行った日から5営業日で、指定の金融機関口座に失業保険が振り込まれます。
うつ病で傷病手当金を申請するための4つのステップ

うつ病によって傷病手当金の申請から支給決定までは、以下のステップに沿って行います。
- 申請書類をもらう
- 会社証明と医師証明をもらう
- 本人記入欄を記入し提出する
- 支給決定
特に、医師の証明の発行には時間がかかる場合があるので、できるだけ早めに病院にもらいに行く必要があります。
⒈申請書類をもらう
まずは、申請用紙を手に入れる必要があります。在職中であれば会社から書類をもらえますが、協会けんぽのホームページなどでもダウンロードができます。
2.会社証明と医師証明をもらう
申請のためには、申請用紙2〜3枚目の会社証明と4枚目の医師証明が必要です。会社証明は申請期間中における出勤状況を記入したり、休業中に支払った有給手当などがある場合にはその金額を記入したりします。
医師証明欄には、病院での診断に基づき病名や労務不能であると認められる期間などが記載されます。
3.本人記入欄を記入し提出する
1枚目の用紙は本人が住所や電話番号、振込先の金融機関情報などを記載します。その後、1〜4枚目をまとめて協会けんぽまたは健康保険組合に提出します。申請の控えとして、コピーをとっておくとよいでしょう。
4.支給決定
申請書が到着してから約2週間後に支給決定がなされます。
失業保険や傷病手当金のことで迷ったら専門家に相談することも大切

うつ病で退職した場合には失業保険をもらえますが、働ける状態であるなどの条件を満たす必要があります。失業保険がもらえない場合であっても、健康保険に1年以上加入していれば退職後の傷病手当金が支給される可能性があります。
失業保険と傷病手当金のどちらを受給できるのかや申請方法が分からない場合には、専門家に相談するのがおすすめです。
失業保険や傷病手当金のことでお悩みの方は、ぜひ社会保険給付金アシストにお任せください。