「失業したら家賃補助をもらえる?」
「転職先が決まっていない状態で退職してしまったので家賃を支払えない」
「家を追い出されたらどうしよう」
会社を辞めると、収入がなくなって生活費に困る方が少なくありません。家賃も支払えなくなったら、家を追い出されるリスクも発生するでしょう。
実は失業者が一定の要件を満たすと「家賃補助」を受けられる可能性があります。
今回は失業者が家賃の支援を受けられる「住居確保給付金」制度の受給条件や受給金額、申請方法を詳しく解説します。
失業保険との関係についてもお話ししますので、退職後の生活が心配な方はぜひ参考にしてみてください。
目次

社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
失業時の家賃補助制度(住居確保給付金)とは

会社を退職した後に受けられる家賃補助制度を「住居確保給付金」といいます。これは、離職、休業、廃業などで収入が減った方へ家賃が補助される制度です(引用元:離職や解雇、やむを得ない休業等で生活に困窮する方へ|厚生労働省)。
住居確保給付金制度を実施しているのは国(厚生労働省)ですが、具体的にお金を支給してくれるのは自治体です。
もともと会社員だった方はもちろん、自営業やフリーランスで職を失った方、減収となった方も家賃補助を受けられる可能性があります。
住居確保給付金の受給条件

住宅確保支援金を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 離職・廃業後2年以内、または本人の責任や都合によらず収入が著しく減少している
住居確保給付金を申請できるのは、基本的に退職や廃業後2年以内の方です。ただし廃業していなくても、本人の責任によらずに収入が廃業したのと同程度に落ち込んでいたら申請資格が認められます。
- 離職・廃業時に主として生計を支えていた
退職、廃業した時点において、本人が主として生計を支えていたことが必要です。
- 世帯収入の要件
直近の世帯収入が、市町村民税の「均等割」が非課税になる額の1/12(基準額)と家賃の合計額を超えていないことも要件とされます。
- 預貯金額の要件
住居確保給付金の申請時において世帯全体の預貯金額が、各市区町村の定める金額を超えていないことが必要です。基本的には「基準額の6ヶ月分」が上限ですが、100万円をこる場合にも対象外となります。
- 求職活動を続けること
住居確保給付金を受け取るには、誠実かつ熱心に求職活動を続けなければなりません。求職活動をしなくなったら家賃補助を停止されます。
- 他の給付金を受け取っていない
申請者本人や同一世帯の人が住居確保給付金に類似する制度や「職業訓練受講給付金」などの雇用促進給付金を受け取っていないことが条件とされます。
住居確保給付金による支給額

実は住居確保給付金による支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。各市区町村によって「基準額」が異なるためです。
ここでいう「基準額」は、「市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12」をいいます。均等割とは、所得額に関係なく自治体内のすべての住民に同じ金額が課される住民税です。
住民税には、所得額に応じて算定される所得割と、所得に無関係に課税される均等割があります。
均等割の金額は自治体によって異なりますが、1000~数千円程度となるケースが多いでしょう。また所得が一定以下になると、均等割は免除され非課税になります。
住居確保給付金の金額、支給上限額は以下の通りです。
住居確保給付金の金額
住居確保給付金の金額の計算方法は以下の通りです。
| 住居確保給付金の支給額=基準額+家賃額-世帯収入額 世帯収入額が基準額以下の場合 → 家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限) ○世帯収入額が基準額を超える場合 → 基準額+家賃額-世帯収入額を支給(ただし、住宅扶助額が上限) |
つまり世帯収入額が基準額以下になると、家賃相当額の一部や全部が支給される計算です。ただし、支給額には上限があるので、必ずしも家賃の全額を受け取れるとは限りません。
また、支給対象額には「共益費、管理費」は含まれず「家賃部分のみ」となるので注意しましょう。
住居確保給付金の上限額
住居確保給付金の上限額は、各自治体によって異なります。東京都特別区の場合、支給上限額は下記の通りです。
| 世帯人数 | 住居確保給付金の上限 |
|---|---|
| 1人 | 53,700円 |
| 2人 | 64,000円 |
| 3人~5人 | 69,800円 |
(引用元:離職や解雇、やむを得ない休業等で生活に困窮する方へ|厚生労働省)
具体的な給付限度額については、お住いの地域の役所へ問い合わせてみてください。
住居確保給付金の支給期間

失業時の家賃補助制度である住居確保給付金の支給期間は、基本的に「3ヶ月間」とされています。ただしその間に就職が決まらず、一定要件を満たす場合には、延長申請可能で、延長は2回まで最大9か月間支給可能です。
3回目の延長申請(最長で12ヶ月間支給)は、令和4年3月31日で終了となっています。
住居確保給付金の申請方法・必要書類

次に、住居確保給付金の申請方法・必要書類について解説します。住居確保給付金を申請しようと考えている方は参考にしてください。
必要書類
住居確保給付金の申請に必要な書類は、おおむね以下のようなものです(自治体によって異なる可能性があります)。
自分で作成する書類
- 住居確保給付金支給申請書
- 離職状況等に関する申立書
- 収入状況等に関する申立書
- 賃貸借物件の契約状況に関する申立書
- 住居確保給付金申請時確認書
大家や不動産会社に記入してもらう書類
- 入居住宅に関する状況通知書
集める資料(作成や記入は不要)
- 離職票
- 給与明細書
- 預貯金通帳
- 賃貸借契約書
申請方法
書類が揃ったら以下の手順で申請をします。
1.支援機関に相談する
住居確保給付金を受け取りたいときには、自治体から委託された支援機関に相談するところから始めましょう。専門の支援機関を「自立相談支援機関」といいます。
具体的な自立相談窓口機関の窓口は、自治体のホームページなどで公表されているので、調べてみてください。一般には社会福祉法人やNPO法人が窓口となっている例が多数です。
支援機関がわかったら電話やメールで連絡して、面談の予約をとりましょう。
2.書類の作成と提出
支援機関で相談をすると、必要書類の種類や作成方法を教えてもらえます。
3. 審査
書類を提出すると、行政側で審査が行われます。
4. 決定通知と支給開始
審査に通過すると、住居確保給付金の受給決定通知書や対象者証明書が自宅に届きます。
支援金は自治体から大家や不動産管理会社へ直接振り込まれるので、全額補助してもらえる場合には自分で支払う必要はなくなります。
一部補助のケースで自己負担分がある場合、不足部分のみを期日までに大家や不動産管理会社へ支払いましょう。
5.延長申請の手続き
住居確保給付金の受給期間を延長したい場合にも、自立相談窓口機関への申請が必要です。受給の最終月に担当者へ相談して、申請手続きを行いましょう。
住居確保給付金と求職活動の関係

住居確保給付金を受け取るためには「求職活動」を継続しなければなりません。そもそも住居確保給付金は、「就職を支援する制度」であるからです。
就職の意思と能力があって実際に求職活動をしていなければ、支給を受けられません。就職活動を辞めると支援を打ち切られる可能性があるので注意しましょう。
また住居確保給付金を受け取るには、ハローワークへの「求職の申込み」をしなければなりません。これは「失業保険(雇用保険の基本手当)」と同じ手続きになります。
また住居確保給付金を受け取っている間、自治体へ「就職活動の報告」も続けなければなりません。必要とされる就職活動の方法は、おおむね以下のようなものです。
- 月に2回以上、ハローワーク(公共職業安定所)で職業相談を受ける
- 月に4回以上、支援員と面談して求職活動内容を報告する
- 週1回、求人へ応募する、または面接を受ける
就職活動をすることを前提に受け取れる点に注意してください。
住居確保給付金の4つのデメリット
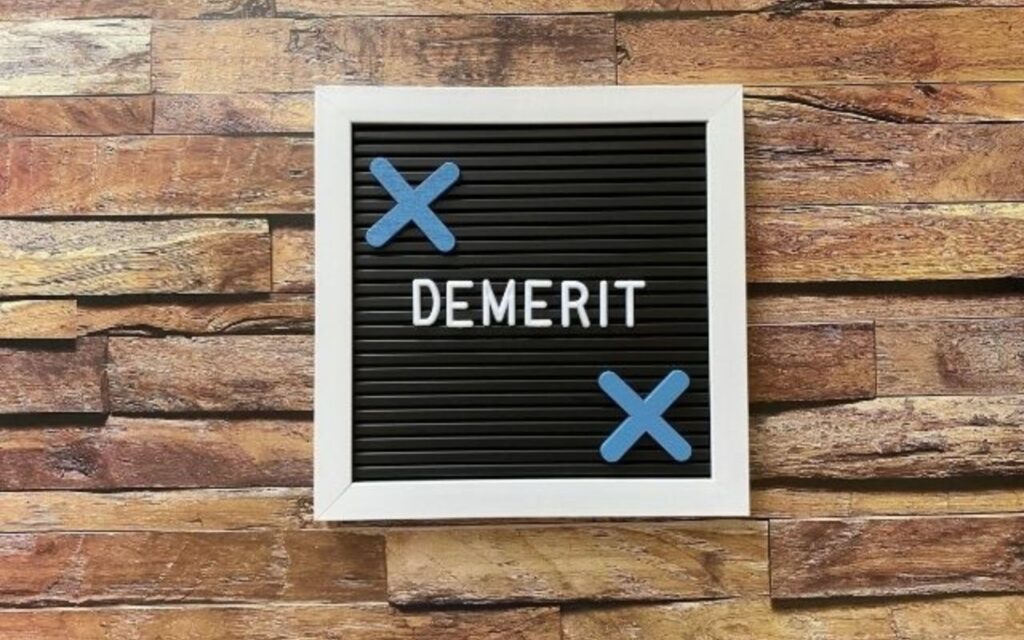
住宅確保給付金は、失業者が一定の要件を満たすと「家賃補助」を受けられる制度ですがデメリットもあります。デメリットは以下の通りです。
1.生計維持者が一定の要件を満たしている必要がある
住居確保給付金の受給条件で紹介したように、住居確保給付金を受給するためには生計維持者が一定の要件を満たす必要があります。
たとえば、貯金が「基準額の6ヶ月分」または、100万円以上あると受給できません。申請前には、自分が受給条件に合うかどうかしっかりと確認しましょう。
2.家賃額によっては給付額が一部支給になる場合もある
家賃の金額と収入の関係性で、給付額は一部支給になる場合もあります。支給額は以下のように計算されます。
| 住居確保給付金の支給額=基準額+家賃額-世帯収入額 世帯収入額が基準額以下の場合 → 家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限) ○世帯収入額が基準額を超える場合 → 基準額+家賃額-世帯収入額を支給(ただし、住宅扶助額が上限) |
収入が多い場合、給付額が全額ではなく、一部支給になってしまう点にも注意が必要です。
3.申請には手続きと審査があるためすぐに振り込まれない
申請方法でも解説しましたが、住居確保給付金を給付するには手続きと審査があるのですぐに振り込まれません。
支給日は支給決定通知書の発送日から3~4週間後です。約1か月程度の家賃は自分で支払う必要がある点も把握しておきましょう。
4.受給期間は申請当月から原則3ヶ月までである
受給期間は、申請当月から原則3ヶ月までである点にも注意が必要です。
ただし、3ヶ月間で就職が決まらず、一定要件を満たす場合には、延長申請可能です。延長は2回まで最大9か月間支給できますが、期限が決められている点も把握しておきましょう。
住居確保給付金の5つの注意点

住居確保給付金を受給する際には以下のような点に注意してください。
1.共益費や駐車場代は対象にはならない
住居確保給付金によって支給されるのは「家賃本体」部分のみであり、敷金や礼金、補償金、共益費や管理費は含まれません。
また、駐車場代も支給対象外です。住宅費用すべてを住宅確保給付金で補填できない点に注意が必要です。
2.事業用物件は対象外である
住居確保給付金は「申請者が居住する家」の家賃を支援する制度なので、店舗などの事業用物件は対象外です。
ただし住居兼店舗の場合、住居部分のみの支援を受けられる可能性があります。この場合、全体の免責のうち住居部分の割合を計算し、その部分に相当する家賃の支援を申請しましょう。
3.月1回の報告が必要である
住宅確保支援金を受給し続けるには月に1回、自立相談支援機関へ報告をしなければなりません。求職活動の内容や収入状況を届け出ましょう。
4.失業保険は収入として算定される
失業保険を受給している場合には、収入として算定されます。そのため、住居確保給付金の給付額が一部支給になる場合もあります。
就労での収入だけではなく、失業保険も収入として算出される可能性がある点にも注意しましょう。
5.ルームシェアは支給対象とならない
ルームシェアは、住居確保給付金の支給対象となりません。
1人暮らしではなく、シェアハウスに住んでいたり、友達や恋人とルームシェアをしたりしている場合には対象にならない点も把握しておきましょう。
住居確保給付金と失業保険との関係
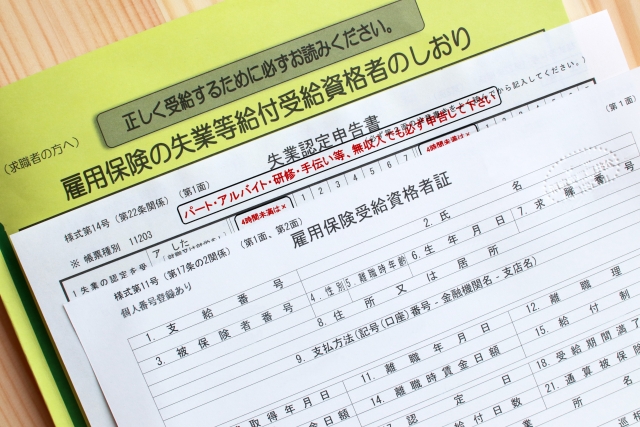
会社を辞めると、「失業保険」ももらえる可能性があります。ここでは、失業保険と住居確保給付金の関係について解説します。
失業保険の概要
失業保険とは、雇用保険から支給される基本手当です。
失業すると生活費や就職活動にかかる経費が必要なので、雇用保険から支援金としての基本手当が支給されます。
失業保険を受け取れるのは、以下の条件を満たす方です。
- 一定以上の期間、雇用保険に加入していた
基本的に退職前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に入っていたことが条件とされます。ただし会社都合退職や特定理由離職者の場合、退職前の1年間に6ヶ月以上雇用保険に入っていたら条件を満たします。
- 就職の意思と能力がある
就職する意思と能力を持っていなければなりません。病気やケガで働けない状態の方、しばらく働く気がない方は失業保険をもらえないと考えましょう。
- 実際に求職活動を行っている
実際にハローワークで職業相談を受けたり企業の面接を受けたりして、就職活動を継続しなければなりません。4週間に1回、ハローワークへいって求職活動を報告し、「失業認定」を受ける必要があります。
失業保険と住居確保給付金は同時受給できる
失業保険と住居確保給付金は別の制度であり、同時受給が可能です。家賃支援を受けながら失業保険を受け取れば、失業中の生活もずいぶん楽になるでしょう。
ただし失業保険も住居確保給付金も「ハローワークへの求職申込みと就職活動の継続」が要件となります。
受給を止められないように、まじめに就職活動を続けましょう。
申請の順番はどちらでも良い
失業保険と住居確保給付金を申し込む順序に決まりはなく、どちらに先に申し込んでもかまいません。
期間制限
失業保険には「退職後1年以内」の受給期間制限があります。また、住居確保給付金を申し込めるには「退職後2年以内」の人です。
このように、両方の制度ともに「期間制限」があるので、早めに申請するのがよいでしょう。
住居確保給付金についてよくある質問
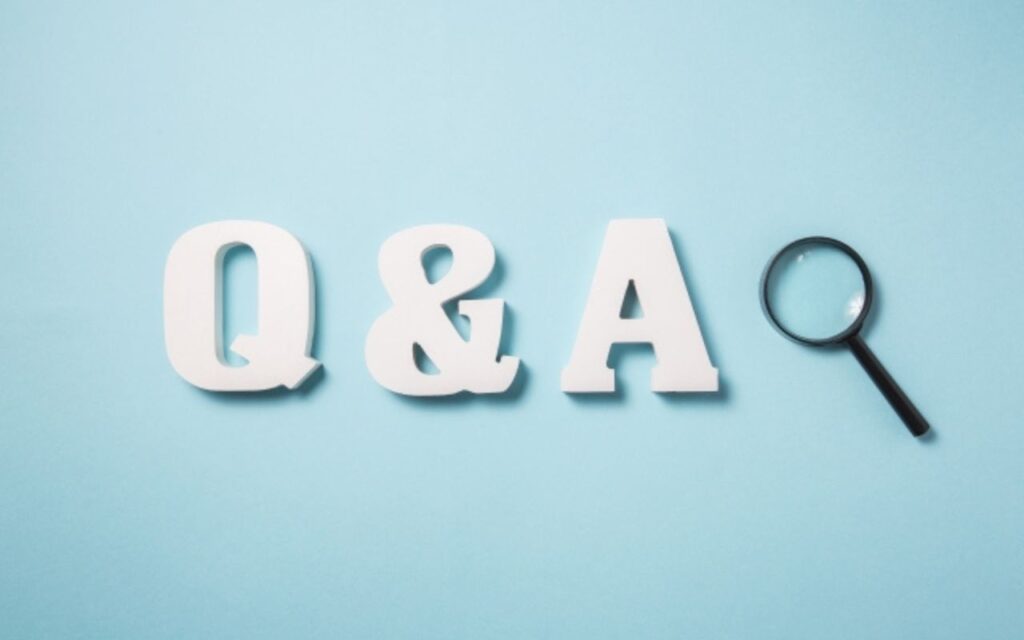
住居確保給付金についてよくある質問を紹介します。住居確保給付金の受給を考えている方は参考にしてください。
住居確保給付金申請の際に貯金があるとバレますか?
住宅確保給付金を申請した場合には、貯金があった場合にはバレます。住居確保給付金を申請するとどこの支店にその人が口座を持っているかすぐに調べて、全銀行に照会がかかるからです。
自分の使っていない銀行口座がないかを確認してから申請するのがおすすめです。
失業時の家賃補助は自己都合でももらえる?
失業時の家賃補助(住宅確保給付金)は、自己退職でも会社都合でもどちらでも関係なく受給できます。
失業保険とは異なり、待期期間もありません。
失業時の家賃補助は持ち家でももらえる?
住居確保給付金は、持ち家(住宅ローン)の方は対象外です。賃貸物件に住んでいる人のみが対象であるからです。
住宅ローンに関しては、金融庁や財務局、銀行協会、政府系金融機関等に相談窓口が設けられています。持ち家の住宅ローンの支払いで困っている場合には、上記の相談窓口に依頼するようにしましょう。
住居確保給付金と失業保険の申請は社会保険給付金サポート会社へ相談をしよう

会社を退職すると、住居確保給付金や失業保険などの各種給付金を受け取れる可能性があります。
ただこれらの制度は別々のものであり、申請先や申請方法も異なります。必要書類もそれぞれ揃えなければなりません。非常に手間がかかりますし、何から手を付けてよいかわからない方も多いでしょう。
申請に迷った場合には、社会保険給付金サポート会社へ相談してみてください。
社会保険給付サポート会社とは、雇用保険を始めとする社会保険金給付申請を支援してくれる専門会社です。相談すると、「受給できる給付金の種類」や「申請方法」「必要書類」などについてアドバイスを受けられます。
1人で対応するよりスムーズに申請手続きを進められるでしょう。
こうした会社では、相談料はかからないのが一般的です。自分1人で悩んでいても事態は良い方向に進みにくいので、まずは一度、専門知識を持った会社へ相談してみてください。










