「失業保険っていつからもらえるの?」
「会社都合退職か自己都合退職でもらえる時期が違うって本当?」
「失業保険をもらっている間は働けないのかな」
と、気になっていませんか。
退職は決まったが、次の就職先が決まっていない。そこで会社の人事担当者から失業手当の説明を受けた方も多いでしょう。
会社から書類を受け取った後の手続きは、自分で行わなければなりません。さらに、その手続きも1度ではありません。
正直、失業保険についてお金がもらえる以外分からないという人も多いでしょう。
そこでこの記事では、
- 失業保険について
- 振り込まれるまでの期間
- 少しでも早く失業保険をもらう方法
- 失業保険を受け取る流れ
などを詳しく解説します。失業保険をもらいたいけど、どうしたら良いか分からない人必見です。
目次

社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
失業保険についてサクッと説明

失業保険を一言で説明すると、離職したときに一定期間、雇用保険から受け取れる給付金のことです。
仕事を辞めた後、再就職先が決まっていないとお金が心配ですよね。仕事がなくても、お金は必要です。失業保険は、あなたの生活を守るためにあります。
失業保険をもらって生活が保障されれば、心に余裕を持って仕事探しができます。
失業保険を受給するには、以下の2つの条件を満たさねばなりません。
- 離職前の2年間に1年以上雇用保険へ加入していた
- 就職の意思と能力があり、ハローワークへ求職の申込みをしている
ただし会社都合で
- 退職した場合
- 病気
- けが
でやむなく退職した場合などには、加入期間の要件が緩和され、離職前の1年間に半年以上雇用保険に加入していれば雇用保険を受け取れます。
【朗報】失業保険は早ければ2週間で振り込まれる ※ただし

入金日について、ハローワーク渋谷に問い合わせてみたところ以下の回答がありました。
「失業手当は、ハローワークからの入金は手続きから約1週間で入金します。」ですので、少し時間がかかりますが1週間を見ておけば良いでしょう。
しかし、この1週間というのは、失業手当の申請をしてから1週間後にもらえるわけではありません。
失業手当の申請をするには、退職後約2週間後に離職票が届き、ハローワークに行き申請をします。そこから28日後に失業認定日があり、そこから1週間後となります。
つまり退職後からだとおおよそ7週間後に失業手当がもらえることになります。(会社都合の場合)
さらに自己都合退職の場合は給付制限期間が1か月増えるため、11週間後に失業手当がもらえることになります。
失業手当をもらえる期間は人によって異なる

失業手当を受給できる期間は、受給資格者の年齢や在籍数などによって異なります。大きく以下のつに分けられます。
| 受給資格者 | 受給期間 | |
| 1 | 45歳以上65歳未満の※就職困難者で在籍1年以上 | 1年+60日 |
| 2 | 45歳以上60歳未満の特定受給資格者・特定理由離職者で在籍20年以上 | 1年+30日 |
| 3 | 2・3以外(基本的には、これに該当) | 離職日の翌日から1年 |
※就職困難者とは、
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 刑法等の規定により保護観察に付された方
- 社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。
基本的には、離職日の翌日から1年間が受給期間です。
注意点として、受給期間内であっても支給残日数がなくなった時は、失業手当は支給されません。また、支給残日数があるにも関わらず、受給期間が経過した時も失業手当は支給されません。
さらに、手続きに時間がかかり受給期間が到来すると、受給できなくなる場合もあります。右も左もわからない状態で手続きをすると、遅れてしまう事があります。そんなことがない様に弊社の社会保険給付金アシストを利用してみるのも良いでしょう。
少しでも早く失業保険をもらう3つの方法

失業手当を早く貰う方法は3つあります。
- 会社都合退職
- 離職票をもらい次第ハローワークに行く
- 職業訓練を受ける
それぞれ解説します。
1.会社都合退職
会社都合退職とは、会社側の事情による退職です。
たとえば、
- 解雇
- リストラ
- 退職勧奨
- 倒産
- パワハラ
- セクハラ
などが会社都合退職の理由に当てはまります。
会社都合退職の場合、給付制限期間は適用されません。
失業保険の申請後7日間の待機期間が終了すると、すぐに支給が開始されます。自己都合退職より支給期間が延び、総支給額も高額になります。しかし、会社都合退職に会社はしてくれないことが一般的です。
2.離職票をもらい次第ハローワークに行く
失業手当を受給するには、まず失業の認定を受ける必要があります。
これは、離職者が離職後最初にハローワークに行った日から起算して4週間に1回ずつ行われます。そのため、会社から離職票が届いたら、可能な限り早くハローワークに行きましょう。
3.職業訓練を受ける
職業訓練とは、就職に必要な技術を原則無料で学べ、お金ももらえる(条件あり)公的な制度です。
さらに、職業訓練を受けると失業保険受給開始も早まるのが特徴です。(受講開始の段階で支給対象となります)
また、訓練延長給付と言い、訓練を受けてる間に失業していれば、延長して失業手当を受給できる制度も備わっています。
訓練延長給付
| 時期 | 延長期間 | |
| 1 | 待機中 | 90日 |
| 2 | 受講中 | 2年 |
| 3 | 終了後 | 30日 |
失業手当を受け取る流れ4ステップ

こちらでは、失業保険を受け取る流れを4つのステップにして紹介します。
- 会社から離職票を受け取る
- ハローワークに失業保険を申請する
- 雇用保険受給説明会に出席
- 失業認定と失業保険の振り込み
詳しく解説します。
1.会社から離職票を受け取る
退職したら、会社から離職票を受け取りましょう。正確には「雇用保険被保険者離職票1・2」という書類です。通常は退職後2週間くらい発行までに時間がかかります。
送ってもらえない場合、会社に連絡していつまでに届くか確認してください。
離職票が届いたら、離職理由の欄を確認しましょう。会社都合退職になるか、自己都合退職になるかはこの理由で異なります。
不審点があれば、会社に連絡をして訂正してもらいましょう。会社が話合いに応じない場合、ハローワークへ事情を話して相談してください。ハローワークが調査を行い、退職理由が訂正される可能性があります。
2.ハローワーク失業保険の申請をする
離職票が届いたら、ハローワークへ行って失業保険の申請をします。
必要書類は、
- 離職票(雇用保険被保険者離職票1・2)
- 写真つきの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
- 写真2枚(縦3cm×横5cm 3か月以内に撮影したもの)
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(失業保険の振込先を確認します)
- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
求職の申込みも同時に行いましょう。
3.雇用保険受給説明会に出席
求職の申込みをすると、7日間の待機期間が適用されます。この間にアルバイトやその他の仕事をすると、失業保険を受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。
その後、雇用保険受給説明会に参加します。
説明会が終わったら、初回の失業認定日が決まります。
4.失業認定と失業保険の振込
指定された失業認定日にハローワークに行き、失業の認定を受けましょう。すると1週間程度で失業保険が振り込まれます。
ただし自己都合退職の場合は、給付制限期間が発生します。初回の雇用保険説明会から1ヶ月間の給付制限期間が適用されるので、その後の失業認定からとなります。
失業保険は延長申請ができる

受給期限を超えたら、失業保険を申請できないとお伝えしました。とは言っても、すぐに申請できる人ばかりでもありません。
条件を満たせば受給期限を延長できます。
できる人は、
- ケガや病気で就職活動ができない
- 妊娠している
- 3歳未満の子供を育てている
- 60歳以上で定年退職をし、ひとまず休養したい
- 海外勤務の配偶者に同行するため日本で働けない
- 青年海外協力隊による海外派遣・派遣前に研修で働けない
などです。現在の状況が延長できるかどうか不確かな人は、専門家またはハローワークの人に確認すると良いでしょう。
延長すると失業保険の受給を止めた日数分、支給期間を延ばしてもらえます。たとえば病気療養のために50日間失業保険の受給を止めたら、1年と50日後まで失業保険を受け取れます。
受給期限を延長期間できるは最長で3年間です。本来の受給期限は退職後1年間なので、合計して「退職後4年間」まで失業保険を受給できる計算となります。
失業保険についてよくある質問5選

失業手当について、よくある質問を5つまとめました。
- 受給中は働けないの?
- 手当額の計算方法が知りたい
- 失業保険はまとめて受給できる?
- 正社員やアルバイト、公務員で違いは
- 受給が突然止まることはあるの?
それぞれ詳しく確認しましょう。
1.受給中は働けないの?
基本的に、受給中は働かないのがおすすめです。働くと減額または、失業認定を先送りされ受給が止まるからです。
失業手当受給中の就労は、2つに分けられます。
- 1日の就労が4時間未満:減額調整
- 1日の就労が4時間以上:就職(失業認定を先送り)
内職収入があった場合は、失業認定申告書の1枚目、上から2番目の内職収入があった日および金額に記入をしなければなりません。
減額の場合は、3パターンです。
- 内職収入が賃金日額の80%以上の場合は、不支給
- 内職収入+失業手当を合わせた額が賃金日額の80%を超える場合は減額
- 内職収入+失業手当を足しても賃金日額の80%より下回る場合は、減額なし
となります。ちなみに、賃金日額とは前職の1日分の平均給料を指します。
2.手当額の計算方法が知りたい
こちらでは、手当額の計算方法を説明します。
まず初めに、賃金日額と基本手当の日額を計算します。
月給者の場合は、賃金日額=退職月から遡り6か月間の平均の月給のことです。
基本手当の日額=賃金日額×給付率
給付率は60歳未満の方であれば80%~50%で一日の賃金が低いほど高くなります。
詳しくは下記をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf
出典:ハローワークインターネットサービス
分かりやすいように、事例でさらに詳しく解説します。
- 離職理由:自己都合退職
- 勤続期間:20年以上勤
- 月給:30万円
- 年齢:45歳
の場合を見ていきましょう
30万円×6か月=180万円(直近半年間の賃金)
180万円/180=1万円(1日分の賃金)
1万円×給付率(50%~80%をかける・ここでは50%とします。)=5,000円(失業保険支給額)
そしてこの金額に給付日数(下記参照)をかけた金額が総支給額になります。
5,000円×150日分=75万円
となります。これを1年間かけて受け取れます。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
出典:ハローワークインターネットサービス
こちらの動画でも解説しています
3.失業保険はまとめて受給できる?
失業保険をまとめて受給できません。基本的に、1か月に1回支給されます。
受給時期は、人によって異なります。一般的には自己都合と会社都合と2つに分けられますが、ここでは3つに分けてまとめました。
| 離職理由 | 受給開始時期 | 具体例 | |
| 1 | 自己都合 | 離職日の翌日から約2か月後 | 一身上の都合による退職(2,3以外) |
| 2 | 特定受給資格者 (会社都合) |
離職日の翌日から約7日後 | 倒産や解雇、パワハラなど |
| 3 | 特定理由離職者 | 離職日の翌日から約7日後 | 体力の衰え、親族の死亡など |
上記の表で分かる通り、自己都合で退職しない方が早く失業手当をもらえます。
条件を満たせば、開始時期は離職理由は異なるものの給付日数がなくなるまで毎月もらうことができます。
4.正社員やアルバイト、公務員で違いは
正職員やアルバイトの場合は、雇用関係は働いている会社から離職票が送付されてきます。
派遣社員の場合は、雇用関係は派遣元会社であるため、派遣元会社から離職票が送付されてくる点は抑えておきましょう。
離職票をもらったら、必要書類を揃えてハローワークで失業保険の申請を行いましょう。
公務員の場合は、原則として雇用保険に加入できないので、失業手当は受給できません。その代わりに失業手当相当額の退職手当があります。
5.受給が突然止まることはあるの?
可能性はあります。最も注意したいのは、不正受給と疑われる場合です。
・隠れて収入を得ていた
・就職しているにも関わらず、一切届け出ていない
といったケースが当てはまります。
該当すれば失業手当の受給が止まるだけでなく、返還命令がくだされます。
失業保険について迷ったら専門家に相談しよう

失業保険の申請方法はこちらに記載していますが、一つの手順を間違えるだけで、申請できなかったり、もらえても減額されることもあります。
ハローワークの窓口では、職員は自分の仕事が増えるため職員によっては説明をしっかりと行なってくれないことも。そのため、手続きが不安と感じている方は、社会保険給付金サポートの利用がおすすめです。
社会保険給付金サポートでは、社労士監修のもと専門家がアドバイスしてくれます。相談は無料なので、疑問や不安な人はぜひ一度問い合わせてみてください。
プロのアドバイスを受けることで、給付金が最大限受給しやすくなります。





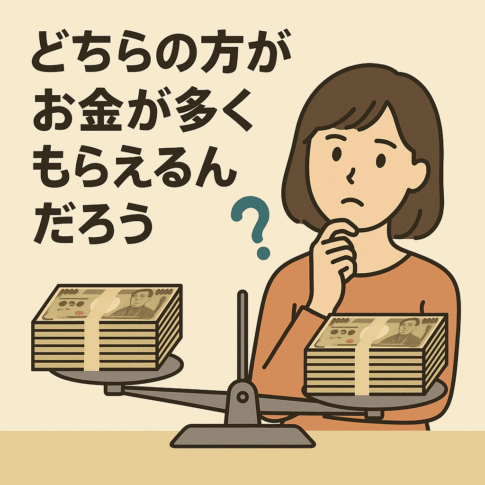





コメントを残す