派遣社員でも失業保険がもらえるのかな
派遣切りにあった…お金どうしよう…
次の派遣先が決まらない。お金がない
と悩んでいませんか。
派遣社員は、どうしても雇用が安定しません。景気が悪化すると、すぐに派遣切りに遭って職を失ってしまいがちです。
派遣社員で失業しても、失業保険を受け取れる可能性があります。失業保険をもらえたら、生活が安定して転職活動もしやすくなるでしょう。
今回は派遣社員が失業保険をもらうための条件や受給方法を解説します。派遣社員としてはたらいている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次

社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
【結論】派遣社員でも条件を満たせば失業保険をもらえる

結論から言うと、派遣社員でも条件を満たせば失業保険を受給できます。
ちなみに、失業保険とは雇用保険から支給される基本手当のことです。簡単に説明すると、失業中の労働者が転職活動をする間にもらえるお金のこと。
2020年10月に行われた労働派遣法の改正により、派遣社員が失業保険を受けるための待機期間が短縮されました。元々は3ヶ月の待機期間がありましたが、今では1ヶ月に。
つまり、雇用契約終了後に1ヶ月待てば失業保険を受給できます。経済的なサポートを早く受けられることで、金銭的に少し余裕を持って転職活動が可能になります。
もちろん、手続きを行わないと失業保険を受け取れないので、すぐに最寄りのハローワークにいきましょう。
派遣社員が失業保険を受給する条件

雇用保険に入っていないと、失業保険を受けることができません。
雇用保険とは、
- 失業
- 病気
- 出産
- 怪我
などで収入が得られないときに、一時的な支援を提供する社会保険制度です。
法律によって一定以上の条件を満たす場合、事業者は従業員を雇用保険へ加入させるように定められています。
また、会社側が入れていなくても自分で手続きすれば、雇用保険に加入できます。
【要チェック】派遣社員が雇用保険に加入する3つの方法

こちらでは、派遣社員が雇用保険に加入する3つの方法を紹介します。
- 雇用保険への加入が義務づけられている
- 日雇い労働者(日雇労働被保険者)
- 季節的労働者(短期雇用特例被保険者)
1つずつ詳しく解説していきます。
1.雇用保険への加入が義務づけられるケース
労働者が以下の2つの条件を満たす場合、法律により、雇用者は従業員を雇用保険へ加入させなければなりません。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上、継続してはたらく見込みがある
派遣社員であっても、上記の条件を満たすなら雇用保険へ加入しているはずです。
確認するには給与明細書に「雇用保険の天引き」があるかどうかみてみましょう。天引きされていれば雇用保険へ加入していることを意味します。
正社員より勤務時間が短くても失業保険を受け取れるケースも多いので、「失業保険をもらえない」などと決めつけずに雇用保険への加入状況を確認してみてください。
2.日雇い労働者(日雇労働被保険者)の場合
派遣社員の場合、1つ1つの会社との契約期間が短く、日ごとに単発で仕事をしている人もいます。日雇い労働者でも、雇用保険に加入できる可能性があります。
日雇い労働者や1つの勤務先での雇用期間が30日以下の方でも、勤務先が雇用保険の適用事業所であれば、自ら雇用保険に入って失業保険等の給付金を受け取れます。
この場合、雇用先は手続きしてくれないので、自分でハローワークへ行って加入手続を済ませ、日雇労働被保険者手帳の交付を受けましょう。
また、派遣社員は日雇い労働者ではないケースが多いです。理由としては、1つの派遣元の企業で働いているからです。勤務先がコロコロ変わったとしても、派遣先企業での仕事が30日以内で終わっても問題ありません。
大事なのは、派遣会社との労働契約が31日以上あるかどうかです。同じ派遣会社で30日以上働くのであれば、通常の労働者と同じで雇用保険に加入させなければいけません。
3.季節的労働者(短期雇用特例被保険者)の場合
派遣社員の場合、夏場や冬場などの特定の季節にのみ働く方も少なくありません。こういった方は「季節的労働者」として雇用保険に加入できる可能性があります。
季節的労働者となるのは、以下の条件を満たす場合です。
- 雇用契約期間が1年未満
- 季節の影響を強く受ける仕事内容
たとえば夏場の海やリゾート地の仕事、冬場にのみ需要のあるスキー場の仕事などが該当します。
季節的労働者の場合、以下の2つの条件を満たすと雇用保険へ加入できます。
- 雇用契約期間が4ヶ月以上
- 1週間の所定労働時間が30時間以上
季節的労働者の場合にも勤務先は手続きしてくれません。自分でハローワークへ行って雇用保険へ加入する手続きを行い、被保険者証の交付を受けましょう。
派遣社員が失業保険を受給できる条件3つ

雇用保険に加入していても、すべてのケースで失業保険を受給できるわけではありません。
失業保険を受給するためには、条件があります。主な条件は、以下3つです。
- 就職の意思・能力がある
- 失業中で就職活動をしている
- 一定期間は雇用保険に加入している
1つずつ詳しく確認しましょう。
1.就職の意思、能力がある
失業保険を受給する条件の1つが、就職する意思と能力があることです。
そのため、
- 働く気がない
- 病気
- 怪我
- 出産
など、働くことができない人は失業保険を受け取れません。働く意思があるかどうかの判断は、積極的に就職活動を行っているかです。
2.失業中で就職活動をしている
失業保険を受給するには、就職活動を継続する必要があります。定期的にハローワークへ就職活動の内容を報告しなければなりません。
ハローワークに登録し、求人情報を受け取り面接するなどが含まれています。
また、失業保険は失業中に受給できる手当なので、再就職先が決まったら受け取れません。
3.一定期間以上、雇用保険に加入している
在職中に一定期間以上、雇用保険へ加入していたことが必須です。
基本的には「退職前の2年間に12ヶ月以上加入」が要件となりますが、会社都合退職や病気、けがによる退職などの場合には「退職前の1年間に6ヶ月以上加入」でも要件を満たします。
詳しくは、ハローワークに確認しましょう。
失業保険がすぐもらえるかは退職理由で異なる

派遣社員が失業保険の申請をするとき「退職理由」によって申請できる要件や受給開始時期、受給期間が異なってきます。
「会社都合退職」と「自己都合退職」の2種類があるので、それぞれの違いをサクッと確認しましょう。
| 会社都合退職 | 自己都合退職 | |
| 必要とされる雇用保険の加入期間 | 退職前1年間に6ヶ月以上 | 退職前2年間に12ヶ月以上 |
| 給付制限期間適用の有無 | 適用されない(7日の待機期間後、すぐに失業保険を受け取れる) | 適用される(7日の待機期間後、3ヶ月間は失業保険を受け取れない) |
| 失業保険の給付期間 | 90~240日 | 90~150日 |
さらに詳しく、解説していきます。
1.会社都合退職
会社都合退職とは、会社側の事情で職を失った場合に使います。
たとえば、
- 倒産
- 解雇
- リストラ
- 長時間労働
- パワハラやセクハラの被害を受けた
- 配置転換や転勤でやむを得ず退職した
- 退職勧奨を受けた
などです。
ちなみに、派遣社員で会社都合になるケースは、
- 派遣社員は3年以上同じ派遣会社で働いていたのに契約を更新してもらえなかった
- 契約を更新すると言われていたのに更新してもらえなかった
- 派遣会社が倒産した
などです。
会社都合退職になるメリットは、失業保険の受給資格を満たすために必要な雇用保険加入期間が短くなります。具体的には、退職前のに1年間に6ヶ月以上加入していたことが条件に。
さらに、失業保険を申請したら早期に受給できます。
また、受給可能日数が90日から240日延長されるので焦らずに転職活動が可能です。
2.自己都合退職
労働者が自分の事情によって自ら退職する場合です。以下のようなケースが該当します。
- ステップアップのための転職
- 今の会社の仕事が気に入らないので退職
- 雇用条件が気に入らないので転職
- 引っ越しをするので退職
派遣社員の場合、
- 次の派遣就業先を紹介してもらったけれど、拒否して退職
- これ以上同じ派遣会社からの紹介を希望しないので退職
などで自己都合退職を選ぶことが多いです。
3.自己都合退職でも会社都合退職と同様の取扱いを受けられるケース
労働者の都合による退職でも、会社都合退職と同じ扱いを受けられるケースがあります。自己都合で退職していても、会社都合と同じ待遇を受けられないかハローワークで相談してみましょう。
会社側から「自己都合退職」と通知されても、実際には会社都合退職扱いにしてもらえるケースがあります。たとえば
- 長時間労働
- セクハラ
- パワハラ
- 転勤
- 契約更新拒否
- 退職勧奨
などの事情があれば、会社都合退職となります。
会社側からの説明内容を鵜呑みにせず、状況を分析してみてください。
派遣社員が失業保険を受け取る流れ4ステップ

派遣社員が失業保険を受け取るまでの流れを紹介します。
- 会社から離職票を受け取る
- ハローワークに失業保険を申請する
- 雇用保険受給説明会に出席
- 失業認定と失業保険の振り込み
詳しく解説します。
1.会社から離職票を受け取る
退職したら、派遣会社から離職票を受け取りましょう。正確には「雇用保険被保険者離職票1・2」という書類です。通常は退職後10日が経過する頃までに送られてきます。
送ってもらえない場合、会社に連絡していつまでに届くか確認してください。
離職票が届いたら、「離職理由」の欄を確認しましょう。特に「労働者からの契約の更新又は延長」の部分が重要です。
「延長を希望する旨の申出があった」にチェックがついていたら「会社都合退職扱い」となるので失業保険をすぐに受け取れます。
一方「延長を希望しない旨の申出があった」「延長の希望に関する申出はなかった」にチェックがついていると「自己都合退職扱い」となり、3ヶ月間失業保険を受け取れず給付日数も短くされてしまいます。
不審点があれば、派遣会社に連絡をして訂正してもらいましょう。派遣会社が話合いに応じない場合、ハローワークへ事情を話して相談してください。ハローワークが調査を行い、退職理由が訂正される可能性があります。
2.ハローワーク失業保険の申請をする
離職票が届いたら、ハローワークへ行って失業保険の申請をします。
必要書類は、
- 離職票(雇用保険被保険者離職票1・2)
- 写真つきの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
- 写真2枚(縦3cm×横5cm 3か月以内に撮影したもの)
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(失業保険の振込先を確認します)
- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
求職の申込みも同時に行いましょう。
3.雇用保険受給説明会に出席
求職の申込みをすると、7日間の待機期間が適用されます。この間にアルバイトやその他の仕事をすると、失業保険を受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。
その後、雇用保険受給説明会に参加します。
説明会が終わったら、初回の失業認定日が決まります。
4.失業認定と失業保険の振込
指定された失業認定日にハローワークに行き、失業の認定を受けましょう。すると1週間程度で失業保険が振り込まれます。
ただし自己都合退職の場合は、待機期間が異なります。雇用保険説明会から3ヶ月間の給付制限期間が適用されるので、その後の失業認定となります。
確実に失業保険を受給したいなら専門会社への相談がおすすめ

派遣社員が失業保険を申請するには、さまざまな準備が必要です。会社都合退職か自己都合退職かによっても大きく受給条件が異なるので、注意深く対応しなければなりません。
スムーズに申請を進め、素早く失業保険を受け取るには専門家によるサポートが必要です。
ちゃんと申請できるか不安な人は、社会保険給付金サポートを利用してみてください。専門知識を持った担当者がアドバイスをしてくれるので、ベストな方法で失業保険を申請できます。
「派遣社員をやめるかもしれない、契約を更新してもらえないかも」と不安な人は、ぜひとも一度相談してみてください。
派遣社員であっても失業保険を受給できる可能性はある
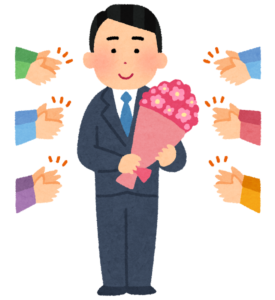
繰り返しになりますが、派遣社員であっても条件を満たしていれば失業保険を受給できます。2020年の法改正に伴い、失業保険を受け取るための待機期間が短縮されています。
少しでも早く受給することによって、心にもゆとりができます。そのため、転職活動に集中できより良い環境で働けるチャンスも掴みやすいです。
派遣社員だから失業保険はもらえない、と諦めずに雇用保険に加入しているかどうかを確認しましょう。
自分の知識だけだと不安な人は、専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。少しでも金銭的な心配を減らし、転職活動を頑張ってくださいね。










