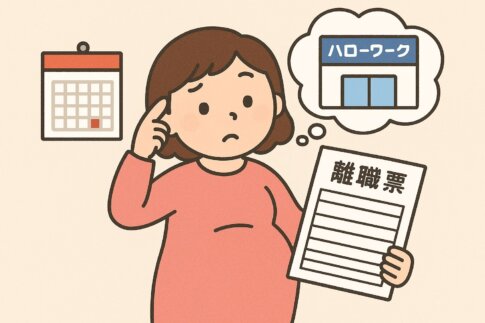「雇用保険の給付金の種類は何があるの?」
「どんな条件で受け取れる?」
「金額の目安は?」
こうした疑問を持つ方は多いでしょう。
雇用保険は、失業中や再就職時、育児や介護、さらには学び直しなど、幅広い場面で生活を支えてくれる制度です。
しかし、制度の種類や条件を正しく理解していないと、本来受け取れる給付を逃してしまう可能性もあります。
この記事では、雇用保険の4つの給付の種類とそれぞれの受給条件をわかりやすく解説していきます。
なお、雇用保険の中でも特に利用者が多い「失業保険」については、以下の記事で詳しく解説しています。
初めて申請する方や、仕組みをしっかり理解したい方はこちらもあわせてご覧ください。
※本記事は、雇用保険・社会保険制度に精通した編集チームが、厚生労働省・ハローワーク(公共職業安定所)・協会けんぽ・日本年金機構などの公的情報を参照して作成しています。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

結論|雇用保険の給付は4種類
雇用保険の給付は、大きく分けて4つの制度があります。
- 求職者給付(失業中に受けられる給付)
- 就業促進給付(早期の再就職や転居を支援)
- 教育訓練給付(資格取得やスキルアップの費用を補助)
- 雇用継続給付(育児・介護・高齢者の継続就労を支援)
それぞれ支給対象や金額、申請先(多くはハローワーク)が異なります。
自分の状況に合わせてどの給付を利用できるかを把握することで、受け取れるお金を最大限に活用することができます。
参照:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」
雇用保険の給付をはじめ、退職後にもらえるお金にはほかにもさまざまな制度があります。
「どんな給付がいつ申請できるのか」をまとめて知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
求職者給付(失業中に受けられる支援)
まず最も多くの方が利用するのが、この「求職者給付」です。
失業したあと、次の仕事が決まるまでの生活を支えるために支給されるもので、いわゆる「失業保険」もこの中に含まれます。
基本手当(いわゆる失業保険)
雇用保険の中でも代表的な給付が「基本手当(失業保険)」です。
離職後、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない人を対象に支給されます。
給付率は離職前6か月の賃金日額の45〜80%で、自己都合退職・会社都合退職・年齢などによって支給日数が変わります。
- 所定給付日数:90〜150日(自己都合)/最大330日(会社都合)
- 受給期間:原則、離職日の翌日から1年間
基本手当の申請は、離職票を持参してハローワークで求職登録を行うところから始まります。
7日間の待期期間が設けられ、その後に失業認定を受けることで初めて支給が始まります。
自己都合退職の場合は、待期期間(7日間)のあとに原則1か月間の給付制限がありますが、会社都合退職の場合は待期期間が終わるとすぐに支給が開始されます。
この違いによって、受給開始時期や総支給額が変わるため、退職理由の確認は非常に重要です。
なお、病気や出産などで求職活動ができない期間がある場合、失業保険の受給期限を最大3年間延長できる制度があります。
詳しい条件や手続き方法は、こちらの記事で解説しています
雇用保険の「傷病手当」
失業保険を受給できる状態の人が、病気やケガで求職活動が一時的にできなくなった場合に支給される制度です。
健康保険の「傷病手当金」とは別制度で、両方を同時に受け取ることはできません。
| 比較項目 | 雇用保険の傷病手当 | 健康保険の傷病手当金 |
|---|---|---|
| 対象 | 離職後・求職中に病気やケガで働けない場合 | 在職中に病気やケガで働けない場合 |
| 支給期間 | 最長1年6か月 | 最長1年6か月 |
| 管轄機関 | ハローワーク | 各健康保険組合/協会けんぽ |
参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
同じ「傷病手当」という名前でも、雇用保険と健康保険では制度の目的や条件がまったく異なります。
詳しい違いや併給の可否については、こちらの記事で解説しています。
高年齢求職者給付金
65歳以上で離職し、再就職を希望している方に支給される一時金です。
通常の失業保険(基本手当)とは異なり、一括で支給されるのが特徴です。
- 支給日数:被保険者期間1年未満=30日分/1年以上=50日分
- 支給条件:離職前1年間に通算6か月以上の被保険者期間があること
- 待期期間:7日間
- 給付制限:自己都合退職の場合、1か月の給付制限あり
この制度は高齢期の生活を支える重要な支援策であり、申請は他の雇用保険給付と同様、ハローワークで行います。
詳しい条件や申請手順については、こちらの記事で詳しく解説しています。
なお、上記以外にも、特定の条件を満たす場合に受け取れる給付があります。
たとえば、公共職業訓練中に支給される「技能習得手当」や「寄宿手当」、
短期雇用特例被保険者向けの「特例一時金」、
日雇労働者向けの「日雇労働者給付金」などです。
いずれも現在も制度としては存続していますが、対象となる人は限られています。
参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
就業促進給付(早く働く・働き方に応じた支援)
「就業促進給付」は、失業中の方が早期に再就職したり、安定した雇用を確保したり、就職活動を行う際に発生する費用を支援する給付制度です。
① 就職促進給付
就職促進給付には、再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当の3種類があります。
いずれも早期再就職や安定的な雇用を支援する目的で設けられています。
再就職手当
失業保険(基本手当)の受給中に早期に再就職した場合、支給残日数が3分の1以上残っていれば再就職手当を受け取ることができます。
- 給付残日数が3分の2以上:基本手当日額 × 残日数 × 70%
- 給付残日数が3分の1以上:基本手当日額 × 残日数 × 60%
参照:ハローワークインターネットサービス「再就職手当のご案内」
申請条件や手続きの流れについてはこちらで詳しく解説しています。
就業促進定着手当
再就職先で6か月以上継続勤務し、かつ再就職後の賃金が前職より低い場合に支給されます。
支給額は、前職と再就職後の賃金差額に基づいて算定されます。
実際の支給額や計算例についてはこちらをご覧ください。
常用就職支度手当
身体障害者・知的障害者・精神障害者・高年齢者など、ハローワークで「就職困難者」として認定された方が再就職した場合に支給されます。
再就職手当の支給対象にならない場合でも、1年以上の継続雇用が見込まれる職に就いたときに受け取れる手当です。
対象となる条件や手続きの詳細についてはこちらで確認できます。
② 移転費
ハローワークの紹介で就職したり、職業訓練を受けるために引っ越しが必要になった場合に支給されます。
交通費・移転料・着後手当などが含まれ、家族を伴う転居では支給額が増えることもあります。
③ 広域求職活動費
遠方の企業への就職活動(面接・試験・説明会など)で200km以上の移動距離や宿泊が伴う場合に支給されます。
交通費や宿泊費の実費を支援する制度です。
手続きの流れや受け取る際の注意点については、こちらで詳しく解説しています。
④ 短期訓練受講費
1か月未満の教育訓練を受ける場合に支給され、支払った訓練費用の20%(上限10万円)が戻ってきます。
スキルアップのために短期講座を受講する際に活用できます。
自分に合った制度の選び方については、こちらで解説しています。
⑤ 求職活動関係役務利用費
就職活動や職業訓練の際に、子どもを保育園などに預けた場合、その保育料の80%が補助されます。
特に子育て中の方が再就職を目指す際に役立つ制度です。
https://syoubyouteate.com/2025/06/10/%e4%bf%9d%e8%82%b2%e5%9c%92%e3%81%8c%e6%b1%ba%e3%81%be%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%be%e9%80%80%e8%81%b7%e5%a4%b1%e6%a5%ad%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa/
教育訓練給付(学び直しの費用補助)
スキルアップや資格取得を目指す人を支援する制度で、働く人の学び直しを後押しする目的で設けられています。
雇用保険の被保険者期間など一定の条件を満たすことで、受講費用の一部が支給されます。
教育訓練給付には、以下の3種類があります。
- 一般教育訓練給付金:受講費用の20%(上限10万円)
- 専門実践教育訓練給付金:受講費用の50%(上限年間40万円・最大3年)
- 教育訓練支援給付金:離職後1年以内、45歳未満など一定の条件を満たす場合に支給
これらを活用すれば、資格取得や転職に必要なスキルを費用面から支援してもらうことが可能です。
教育訓練と職業訓練の違いや、どちらを選ぶべきか迷う方はこちらも参考にしてください。
関連制度:教育訓練休暇給付金
在職中に教育訓練を受ける場合には、教育訓練休暇給付金が利用できます。
会社を休んでスキルアップや資格取得を目指す従業員を支援するための制度で、休暇中の所得の一部が支給されます。
参照:厚生労働省「令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます」
対象資格や支給金額の目安については、こちらも参考にしてください。
雇用継続給付(働きながら支援を受ける制度)
雇用継続給付は、出産・育児・介護・高齢による賃金低下などで働き方が変わった人を支援する制度です。
仕事を辞めずに生活の安定を図ることを目的としており、次の3つの給付があります。
育児休業給付
育児休業を取得した雇用保険加入者が対象です。
支給額は、育児休業開始から180日目までは休業前給与の67%、181日目以降は50%が支給されます。
保育園の入園待ちや配偶者とのダブル育休の場合は、最長で2歳まで延長できるケースもあります。
育休後に退職しても失業手当をもらえる条件についてはこちらで解説しています。
介護休業給付
家族の介護のために休業したとき、十分な給与が得られない場合に支給される制度です。
支給額は、休業開始時賃金の67%で、最長93日(3ヶ月)まで受け取れます。
介護対象となるのは、配偶者・父母・子・配偶者の父母に加え、同居している祖父母・兄弟姉妹・孫も含まれます。
参照:厚生労働省「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」
高年齢雇用継続給付
60歳以降も働き続ける場合、再雇用や給与減少があっても生活を支援するための制度です。
支給対象は、60歳到達時の賃金が75%未満に下がった方で、賃金低下率に応じて給付金が支給されます。
老齢年金との調整もあるため、受給を検討する際は金額シミュレーションを確認しておきましょう。
定年後も働く場合の支援制度についてはこちらを参考にしてください。
まとめ|自分に合った雇用保険の給付を正しく活用しよう
雇用保険には、失業中の生活を支える「求職者給付」だけでなく、
再就職・スキルアップ・育児・介護・高年齢就労など、さまざまな給付があります。
ただし、条件や申請のタイミングを誤ると、本来もらえるはずの給付を逃してしまうことも少なくありません。
「自分がどの給付に当てはまるのか分からない」「退職後の手続きが不安」という方は、専門家に相談するのがおすすめです。
弊社「社会保険給付金アシスト」では、退職後の失業保険をできるだけ多く受け取れるようにサポートしています。
また、傷病手当金や再就職手当などの関連制度の申請サポートも行っております。
まずはお気軽にご相談ください。