「公務員を辞めたら、失業保険がもらえる?」
「公務員だと退職しても失業保険がもらえないって聞いたんだけど…」
「仕事を辞めた後、すぐ再就職先が決まるか不安」
と悩んでいませんか。
結論から言うと、基本的に公務員は失業保険が受給できません。しかし、例外的に受け取れるケースもあります。ただ、受給できる資格があっても申請しなければもらえません。
そこで、この記事では
- 公務員が失業保険を受け取れない理由
- 受け取れるケース
- 申請する方法
などを詳しく紹介します。受け取れないと決めつけずに、確認しましょう。
公務員が失業保険を受け取れない理由を知りたい人や、受給するために必要な申請方法を知りたい人は最後までご覧ください。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

【結論】公務員は失業保険を受け取れない

公務員は、基本的に失業保険を受け取れません。理由は、雇用保険に加入していないからです。
なぜ公務員が雇用保険に加入していないのかと言いますと、景気の動向に雇用がされやすい民間企業とは異なり、不景気だから人員を削減すると言ったことが起こりにくいからです。
雇用保険は、会社の都合で収入源を失うこともあり得るという不安定な状況にある労働者を守り、失業中の生活を支えて再就職を促すのが目的の1つです。
そのため、安定して働ける公務員を辞めても雇用保険に加入していないため失業手当を受け取れません。
失業保険についてサクッとおさらい

失業保険をもらうためには以下二つの条件を満たす必要があります。
- 離職前の2年間に1年以上雇用保険へ加入していた
- 就職の意思と能力があり、ハローワークへ求職の申込みをしている
ただし
- 会社都合で退職した場合
- 病気
- 怪我
でやむなく退職した場合などには、加入期間の要件が緩和されます。離職前の1年間に半年以上雇用保険に加入していれば、失業保険を受け取れます。
失業後の求職活動中にも生活費がかかるので、雇用保険が生活保障のために支給してくれます。
失業保険が給付されるのは、基本的に離職後1年間です。受給できる金額は人によって異なり、年齢や離職前の賃金額等によって決まります。
失業保険を一言でまとめると、労働者が離職したときに雇用保険から受け取れる給付金です。
公務員には退職手当がある

失業保険が受け取れないから、退職後はお金に悩む必要はありません。国家公務員や地方公務員には、失業保険がない代わりに退職手当が給付されます。
勤続年数や離職前の給与額に応じて、給付されます。退職手当とは、簡単にいうと民間企業の退職金のようなものです。平均的に民間企業の退職金より高額に設定されています。
また、退職手当は失業手当とは異なり退職時に一括払いをしてもらえます。失業手当のように、再就職先が決まってストップされることもありません。
公務員が失業保険を受け取れる2つのケース

公務員は、失業保険を受け取れないとお伝えしました。しかし、例外もあります。
公務員でも以下の2つのうちどちらかに当てはまれば、失業保険を受け取れます。
- 退職手当の金額が失業保険より少ない
- 期間雇用の公務員
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.退職手当の金額が失業保険より少ない
公務員に失業保険が給付されないのは、高額な退職手当を受け取れるからです。
そのため、退職手当の金額が少なく失業保険の給付見込額の方が多くなる場合は、差額を受け取れます(雇用保険法6条7号)。
勤務期間が短い方は、公務員であっても退職手当が少なくなりがちです。そういった方はハローワークへ行って申請をすれば、差額を失業保険としてもらえる可能性があります。
退職後に支払われた退職手当が少ない方は、一度ハローワークへ行って失業保険をもらえるかどうか確かめてみてください。
手続きの流れはハローワークに行き、失業保険の申請をする際に、「退職手当を受け取っていますが、少ないために失業保険の申請がしたいですと言えばOKです。
その際に必要なものとしては、退職手当支給決定通知書、退職票(離職票の公務員版)、雇用保険非適用証明書となります。
2.期間雇用の公務員
公務員の中でも、期間雇用の方は失業保険を受け取れる可能性があります。期間雇用の公務員とは、半年以内の期間を設定して雇用される公務員です。
公務員であっても、以下の要件を満たせば雇用保険の被保険者となり、失業手当の対象になります。
雇用保険の加入条件(一般職と同様)
-
31日以上の雇用見込みがある
-
週20時間以上の勤務がある
-
学生でない(例外あり)
→これらを満たす期間雇用職員(たとえば1年契約でフルタイム勤務)は、原則として雇用保険に加入しています。
つまり正規の無期雇用の公務員は雇用保険の適用外(その代わり退職手当がもらえる)、非正規の公務員は雇用保険の適用の可能性がある ということになります。
もしわからなければハローワークに確認してみましょう。
退職した公務員が失業保険を申請する3ステップ

こちらでは、退職した公務員が失業保険を申請するときの流れを3つのステップで紹介します。
1つずつ詳しく確認していきましょう。
【ステップ1:雇用保険加入の有無を確認】
まずは、自分が在職中に雇用保険に加入していたかを確認します。
原則として、週20時間以上の勤務で31日以上の雇用見込みがあった場合は加入対象です。不明な場合は所属していた役所や勤務先に確認しましょう。
【ステップ2:離職票を受け取りハローワークへ】
退職後、公務員であっても雇用保険に加入してると職場から離職票(1・2)を受け取ることができます。それを持って居住地を管轄するハローワークへ持参します。
離職票は退職後に勤務先が交付しますが、交付までに2週間程度かかる場合もあります。マイナンバーカードや印鑑、本人名義の銀行口座、写真なども必要です。
【ステップ3:求職申込みと説明会・認定手続き】
ハローワークで求職申込みを行い、初回の説明会に参加します。
説明会後、待機期間(通常7日)と給付制限期間(自己都合退職なら1ヶ月)を経て、認定日ごとに基本手当が支給されます。
失業保険について迷ったら専門家に相談しよう

公務員でも失業保険を受け取れるケースがあります。ただし失業保険は離職後1年以内にしか支給されないので、条件を満たすなら早めに申請を行いましょう。
ただ自分では失業保険を受け取れるか分からない、どのように手続きを進めたら良いかわからない方も多いですよね。特に公務員の場合、失業保険はもらえないと思い込んでいる方も多く、情報も集めにくくなっています。
困ったときには社会保険受給アシストの利用がおすすめです。
公務員の雇用保険申請に関する知識があるので、状況に応じてアドバイス致します。書類の集め方、申請書類の作成方法なども的確に説明してくれるので安心ですね。
退職手当が少なかった、期間雇用の方など、心当たりのある人はまずは相談してみましょう。




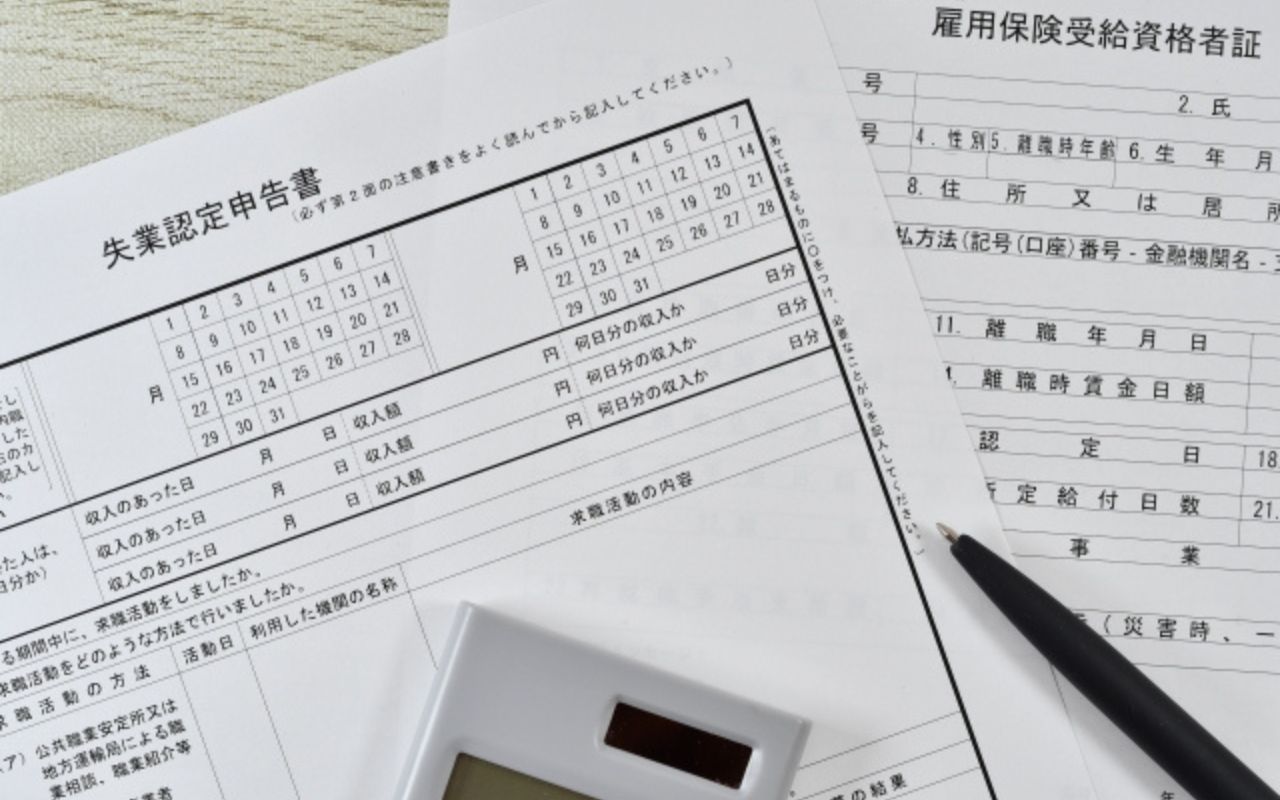











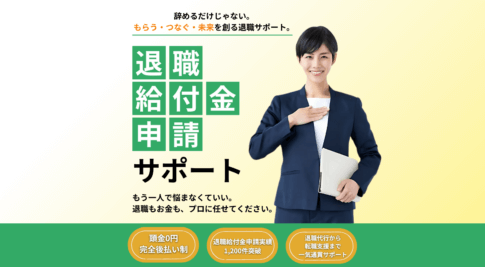






コメントを残す