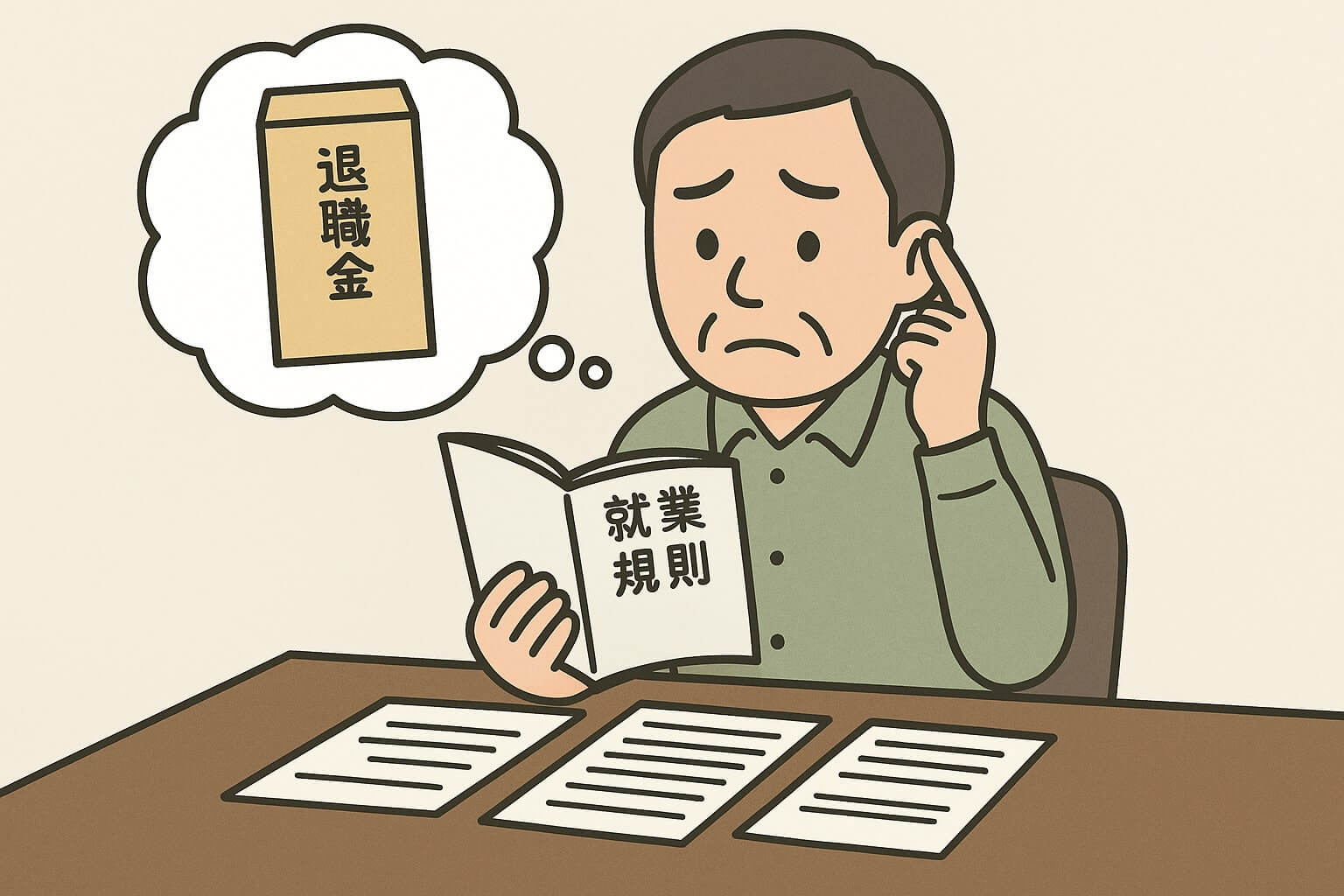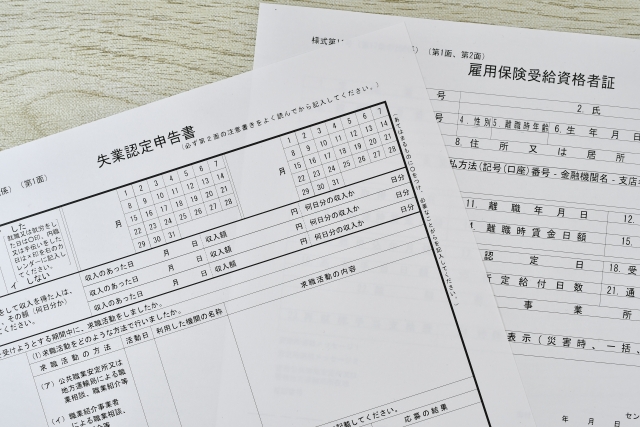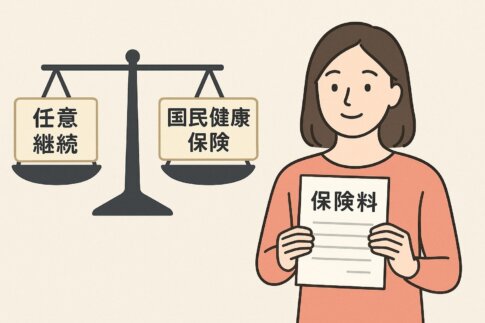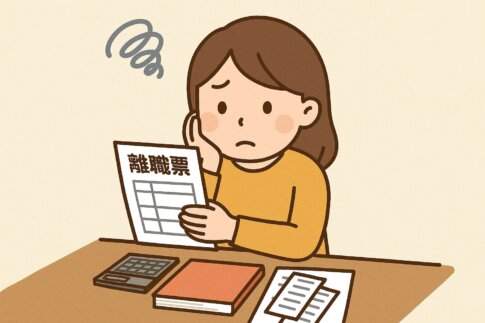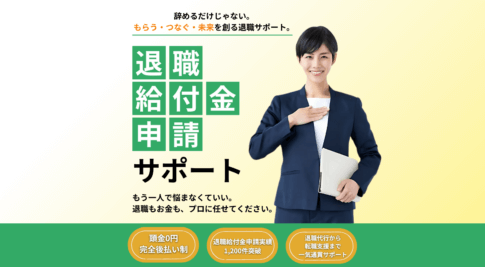「退職金って自分ももらえるの?」と不安に思う方は少なくありません。
特に中小企業や非正規雇用で働いていた方は、制度があるのかどうかさえわからないというケースも多く見られます。
実は、退職金は法律で必ず支給されるものではなく、会社ごとの制度によって支払われるかどうかが決まります。
本記事では、退職金の有無を確認する方法と、退職金がもらえない・少ない場合でも活用できる公的制度について詳しく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

退職金とは?まずは基本を確認
退職金とは、長年勤めた会社を退職する際に支給される金銭のことを指します。
勤続年数への労いの意味を込めた「功労金」としての性質が強く、老後や次の就職までの生活費にあてられることが多い給付です。
注意したいのは、退職金は法律で支給が義務付けられている制度ではないという点。
各企業の就業規則や退職金規程に基づいて運用されており、制度の有無や内容は企業ごとに大きく異なります。
多くの場合、退職金制度の対象は正社員が中心ですが、企業によっては契約社員やパート・アルバイトなどの非正規雇用者にも支給されるケースがあります。
まずは「自分の勤務先に退職金制度があるか」「対象となっているか」を確認することが重要です。
退職金の主な形式と支給タイミング
退職金の支給には、大きく分けて以下の2つの形式があります。
- 退職一時金型:退職時に一括でまとまった金額が支給される方式
- 企業年金型:退職後、年金のように一定額が分割で支給される方式
中小企業では一時金型が多く、大企業では企業年金型を採用しているケースも見られます。
いずれの形式であっても、実際に支給されるのは退職後1〜3か月以内が一般的です。
金額の算定には以下のような要素が影響します。
- 勤続年数
- 最終月給(または退職時点の平均給与)
- 退職理由(自己都合か会社都合か)
特に「自己都合退職」の場合は、企業によっては支給額が減額される規定があるため、あらかじめ退職金規程を確認しておくと安心です。
退職金がもらえるかどうかの確認方法
「自分は退職金をもらえるのだろうか?」
退職を考えるうえで、多くの方が気になるポイントです。
退職金制度は会社ごとに大きく異なるため、自分が該当するかどうかは、事前にしっかりと確認しておく必要があります。
退職金の支給有無や金額を調べるには、以下の3つのステップが有効です。
① 就業規則・退職金規程を確認する
まず最初に確認すべきは、会社の就業規則や退職金規程です。
これらの書類には、「退職金制度があるか」「どんな条件で支給されるか」といった内容が明記されています。
多くの企業では、これらの規程を入社時に配布された資料や、社内のイントラネットで閲覧できるようにしています。
確認できる項目の一例は以下の通りです。
- 退職金制度の有無
- 対象となる雇用形態(正社員・契約社員など)
- 支給条件(勤続年数・退職理由など)
- 計算方法や支給時期
まずはこれらの文書をチェックして、自分が制度の対象になっているかを確認しましょう。
② 人事・総務部門に直接問い合わせる
文書だけでは分かりづらい場合や、退職金の具体的な金額が知りたい場合は、人事部門や総務部門に直接問い合わせるのが確実です。
とくに退職が近づいている方にとっては、
- 「どのくらいの金額が支給されるのか」
- 「いつ頃支給されるのか」
といった実務的な情報は重要です。
退職後の生活設計や税金の準備にも関わるため、早めに確認しておくことで不安を減らすことができます。
③ 雇用形態や退職理由を確認する
退職金の支給対象は、多くの場合正社員が基本となりますが、契約社員やパート・アルバイトでも規程によっては対象になる場合があります。
また、退職理由によっても支給額が変わる可能性があります。
- 自己都合退職の場合 → 減額の対象になることがある
- 会社都合退職や定年退職 → 全額支給や優遇されるケースが多い
特に非正規雇用者の方は、契約書の確認や会社の制度の個別ルールをチェックしておくと安心です。
退職金がない・少ない場合に使える制度とは?
「退職金がない」「思ったよりも金額が少なかった」
そんな場合でも、退職後に利用できる公的な支援制度を活用することで、生活の不安を大きく軽減できます。
ここでは、特に活用しやすい代表的な制度をご紹介します。
① 失業手当(基本手当)
雇用保険に加入していた人が退職後に受け取れる給付です。
支給日数は、年齢や加入期間、退職理由によって異なり、最大で330日分まで支給されます。
「就職困難者」に認定されると、支給期間が最大360日まで延長されるケースもあります。
② 再就職手当
失業手当の支給を待たずに早く就職が決まった場合、残りの失業手当の60〜70%相当額が一括でもらえる制度です。
たとえば、60日分が残っている場合は、約42日分相当の金額が支給される仕組みです。
再就職のタイミングによっては数十万円の支給となることもあります。
③ 傷病手当金
退職前に病気やケガで休職していた人は、退職後も傷病手当金を受け取り続けられる場合があります(最大1年6か月間)。
うつ病などの精神的理由による退職も対象になることがあり、すぐに働けない方にとって重要な支援となります。
このように、退職金が少なくても複数の制度を組み合わせることで、収入を補うことが可能です。
まずは自分がどの制度を使えるかを確認して、無理のない生活再建を目指しましょう。
退職後の“もらえるお金”取得ステップ
退職後すぐに再就職できない場合や、体調が優れない状態では、頼れる制度がいくつも存在します。
それぞれの制度の特徴を理解し、状況に応じて順番に活用していくことで、退職後の経済的な不安を大きく減らすことが可能です。
以下に、代表的な活用例をご紹介します。
① まずは傷病手当金を受給(最長18か月)
退職前に病気やケガで休職していた場合、健康保険から支給される「傷病手当金」の継続受給が可能です。
退職後も条件を満たせば最大で1年6か月間、月給の約2/3程度が支給されます。
→傷病手当金のもらい方を完全ガイド|申請から受給までの流れ・必要書類・注意点を解説
② 傷病手当の終了後に、失業手当へ切り替え
傷病手当金の受給が終わった後は、「失業手当(基本手当)」へ切り替えて申請することができます。
この際、ハローワークで「就職困難者」に認定されれば、所定給付日数が最大で360日まで延長される可能性も。
「働ける状態に戻ってから申請する」ことで、無理のないタイミングで社会復帰を目指せる仕組みになっています。
→傷病手当金が終わったらどうする?失業保険への切り替え方と金額を解説!
③ さらに、早期に再就職できれば再就職手当も
失業手当の一部を残した状態で就職が決まると、「再就職手当」が一括で支給されます。
これは、残り日数の60~70%相当額が一括でもらえる制度で、数十万円レベルの支給となることもあります。
→再就職手当の受給条件と申請手続きの全て|早く働いた方が得?
このように、
- 傷病手当金
- 失業手当
- 再就職手当
という3つの制度を状況に応じて順に利用することで、合計100万円以上の給付を受けられるケースもあります。
「退職金がない」「少ない」と悩んでいる方でも、公的制度を知っているかどうかで受け取れる金額に大きな差が出るのです。
詳しくはこちら:傷病手当金と失業手当、どちらを先にもらうべき?順番で受給額が変わる!
よくある質問(Q&A)
Q. 退職金がなくても失業保険はもらえますか?
A. はい、退職金の有無にかかわらず、条件を満たせば失業保険は受給可能です。
Q. 退職金制度がない会社もありますか?
A. はい、法律上の義務はないため、制度がない会社もあります。
Q. 契約社員でも退職金がもらえることはありますか?
A. 会社の規程により、一定の条件を満たせば支給されることがあります。
Q. 自己都合退職だと退職金は減額されますか?
A. 多くの企業では、自己都合の場合は減額規定が設けられています。
Q. 就業規則がもらえない場合はどうすれば?
A. 労働基準監督署への相談や、社労士への確認を検討してください。
まとめ|退職金がない場合でも備えはできる!
退職金がもらえるかどうかは、会社の制度次第です。
まずは就業規則の確認から始めましょう。
もし制度がなかったとしても、失業保険や傷病手当金、再就職手当などの公的支援制度を活用すれば、経済的な不安を大きく軽減することが可能です。
「制度が複雑でわからない」「自分がどれに該当するか知りたい」という方は、専門サポートを活用するのが安心です。
退職後の不安を減らすために、使える制度はしっかり活用したいところ。
「自分の場合はどうすれば?」と迷ったら、ぜひお気軽にご相談ください。