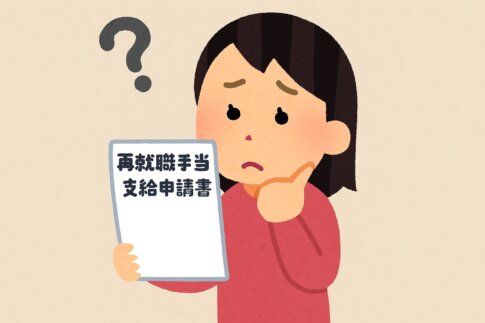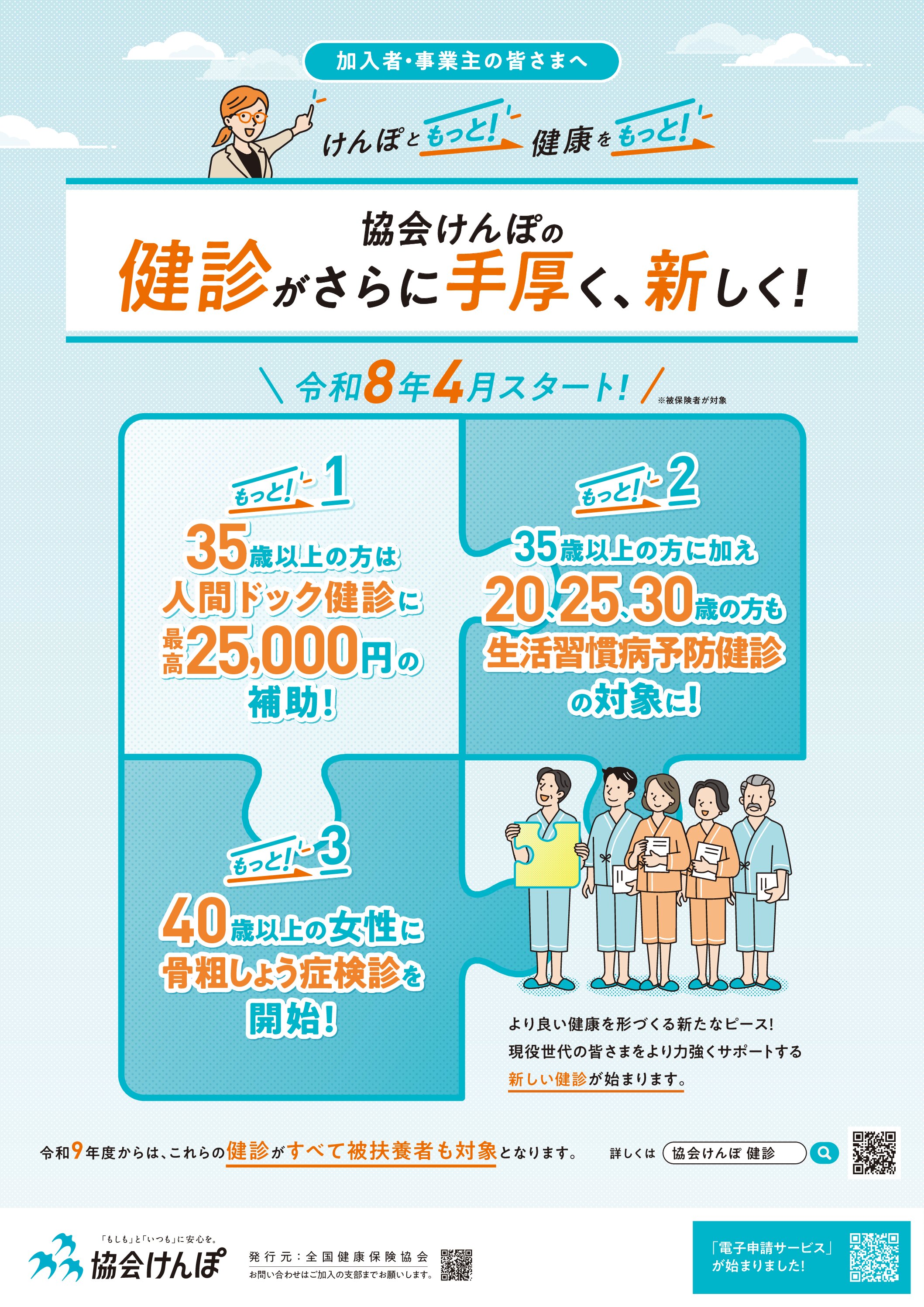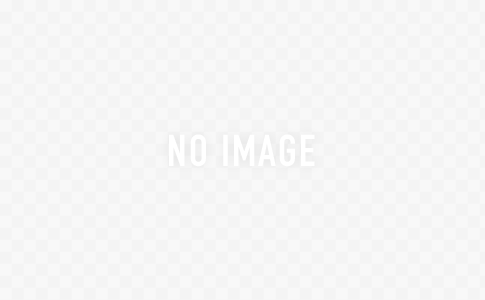「65歳を過ぎたら、もう失業保険はもらえないの?」
こんな疑問を持つ方は非常に多いです。
結論から言うと、65歳を超えると通常の失業保険(基本手当)はもらえません。
しかし、その代わりに
「高年齢求職者給付金」という“一時金”を受け取ることができます。
しかもこの制度には、64歳以下にはない大きなメリットがあります。
それは、年金を減らされずに “給付金と年金の二重取り” ができること。
この記事では、65歳以上の方が知るべき「いくら?どうやって?いつもらえる?」をまとめて解説します。
なお、64歳までの定年退職で受け取れる失業保険(基本手当)については、こちらの記事で詳しく解説しています。
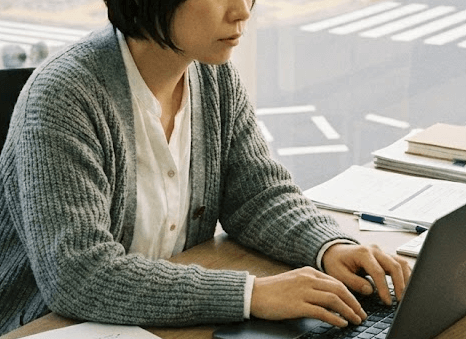
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

65歳以上は失業保険の代わりに「高年齢求職者給付金」になる
65歳の誕生日を迎えた翌日以降に離職すると、
通常の失業保険(基本手当)ではなく 「高年齢求職者給付金」 の対象になります。
切り替えの仕組みは非常にシンプルです。
- 64歳までに退職 → 失業保険(基本手当)
- 65歳以上で退職 → 高年齢求職者給付金(一時金)
このように、退職日がどちらの制度になるかを左右するため、
「いつ退職するか」で受給総額が大きく変わるケースもあります。
参照:離職されたみなさまへ〈高年齢求職者給付金のご案内〉|厚生労働省
いくらもらえる?高年齢求職者給付金の計算式
高年齢求職者給付金は、金額の算出方法がとてもシンプルです。
支給日数は 「雇用保険の加入期間」 だけで決まり、以下の2パターンしかありません。
支給日数の区分
| 雇用保険の加入期間 | 支給内容 |
|---|---|
| 1年以上 | 基本手当日額 × 50日分 |
| 1年未満 | 基本手当日額 × 30日分 |
※基本手当日額の求め方は、通常の失業保険と同じで
離職前6カ月の給与総額 ÷ 180日 で計算されます。
基本手当日額の算出方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。
一括で振り込まれるのが最大の特徴
高年齢求職者給付金の最大の特徴は、一度の手続きで全額が一括支給されることです。
通常の失業保険(基本手当)のように、毎月の失業認定や認定日の出頭、求職活動の確認といった手続きは一切不要です。
具体的には、
- 認定日は 1回だけ
- 待機期間(7日)終了後にすぐ支給
- 毎月の失業認定は 不要
- 手続きが非常に簡単
というメリットがあります。
【最大のメリット】年金と給付金の「二重取り」が可能
65歳以上になると、高年齢求職者給付金と年金を同時に満額受け取れるという大きなメリットがあります。
通常、64歳以下で失業保険(基本手当)を受給すると、老齢厚生年金が一部または全部停止される場合があります。
しかし65歳以降は、
- 年金:満額支給
- 給付金:満額支給
- 併給調整なし(減額なし)
となり、いわゆる「二重取り」が可能になります。
ただし、ここでひとつ誤解してはいけません。
「二重取りできる=65歳退職のほうが絶対お得」ではないということです。
制度としては、年金が満額もらえる代わりに、
給付金(高年齢求職者給付金)の日数・金額が大幅に減るように設計されています。
- 64歳まで:90日〜最大240日(就職困難者に該当すればさらに増加)
- 65歳以上:30日または50日の“一時金”のみ
つまり、
年金を優先する代わりに、失業給付は縮小される仕組みです。
では、総額としてどちらが得なのか?
ここが最も重要なポイントになるため、次で「64歳退職 vs 65歳退職」をわかりやすく比較します。
【徹底比較】64歳退職と65歳退職、どっちが得?
結論から言うと、総支給額を重視するなら64歳退職(=基本手当)のほうが有利になるケースが非常に多いです。
その理由を順番に整理します。
① 一見「65歳退職」のほうが得に見えるが、実は違う
65歳で退職すると、
- 年金:満額支給
- 高年齢求職者給付金:一時金で満額支給
という“二重取り”が可能になります。
この点だけを見ると「65歳のほうが断然お得」と感じる人も多いでしょう。
しかし、制度の本質はここからです。
② 給付日数が「最大240日 → 最大50日」に激減する
64歳までに退職した場合は、通常の失業保険(基本手当)が支給されます。
その給付日数は次のとおりです。
- 90日〜最大240日(会社都合の場合)
- 就職困難者に該当すれば最大360日まで増える可能性あり
参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
一方、65歳以上の場合は高年齢求職者給付金になり、
- 雇用保険1年以上:50日分
- 1年未満:30日分
となり、最長でも 50日分の“一時金”のみ です。
| 年齢 | 給付内容 | 最大日数 |
|---|---|---|
| 64歳まで | 基本手当 | 90日〜最大240日(就職困難者に該当すればさらに増加) |
| 65歳以上 | 高年齢求職者給付金 | 最大50日(一時金) |
給付日数に“3倍以上”の差 が出るため、当然総額にも大きな違いが生まれます。
③ 高年齢求職者給付金は“短期給付が前提の制度”
65歳以上は年金が満額受け取れる年齢のため、
失業給付は 「短期・少額・一時金」 を前提に制度設計されています。
その結果、
- 給付日数が短い
- 毎月積み上がる給付がない
- 一時金なので“受給額が伸びない”
という構造になっており、総額は64歳退職のほうが高くなりやすいのです。
結論:総額を比較すると「64歳退職」が有利なケースが多い
- 65歳退職:年金+給付金の二重取り。ただし給付金は30日〜50日の一時金のみ
- 64歳退職:90日~最大150日(会社都合ならさらに増加)。就職困難者なら360日も可能
- 結果 → 総額は64歳退職のほうが圧倒的に多いケースが一般的
65歳直前の方で、退職時期を選べる場合には、
「誕生日の前々日までに退職して通常の失業保険を受給する」
という選択肢を検討する価値があります。
アドバイス:65歳目前なら「誕生日の前々日」退職も検討を
もし現在64歳で、退職日をいつにするか選べる状況なら、
退職日を“65歳の誕生日の前々日”に設定することを検討してみてください。
この日付なら、制度上はまだ「64歳で退職した扱い」となり、
通常の失業保険(基本手当)を受給できるからです。
その結果として、
- 最大150日(会社都合ならより長期)の給付が可能
- 高年齢求職者給付金(30日〜50日)より総額が大幅に増える
- ケースによっては数十万円以上の差が生まれる
といったメリットが期待できます。
つまり、総受給額を重視する場合は、64歳退職のほうが圧倒的に有利になりやすいということです。
ただし、
- すでに65歳を過ぎている方
- 定年年齢が65歳の会社に勤めている方
- 再雇用制度を利用しない方
などの場合は、高年齢求職者給付金を正しく申請することが最優先になります。
高年齢求職者給付金の申請方法と手続き期限
高年齢求職者給付金には、必ず押さえるべき重要なルールがあります。
それは、
退職日の翌日から “1年以内” に申請しないと、一切受給できません。
たとえ理由があっても、
1日でも期限を過ぎると 0円 になる という非常に厳しい制度です。
「退職後しばらく休んでいたら、気づいたら期限切れだった…」
というケースは実際に多いため、退職したら早めに手続きへ向かうことが重要です。
ハローワークでの申請の流れ
高年齢求職者給付金の手続きは、基本的に通常の失業保険と同じ流れで進みます。
ただし、認定日は1回のみで、その後はすぐに一括支給される点が大きな特徴です。
手続きの流れは次のとおりです。
- 離職票など必要書類を準備する
- 住所地のハローワークで求職申込み
- 7日間の待機期間(働かずに待機)
- 認定(1回のみ)
- 給付金の一括支給
65歳以上の場合、通常の失業保険よりも手続きがシンプルで、短期間で受け取れるのがメリットです。
まとめ
65歳以上で定年退職した場合、これまでの「基本手当(失業保険)」ではなく、高年齢求職者給付金(一時金) が支給されます。
給付日数は30日または50日のみと短い一方で、年金と同時に満額受け取れるというメリットがあります。
一方、64歳までに退職した場合は「基本手当」の対象となり、90日~最大240日(就職困難者なら最大360日)の受給が可能です。
そのため、総支給額だけで比較すると64歳退職のほうが有利になるケースが多い点には注意が必要です。
社会保険給付金アシストでは、
- 「自分は64歳と65歳のどちらが有利なのか?」
- 「申請すればいくら受け取れるのか?」
- 「退職日をいつにすべきか?」
といった複雑な判断を、制度に精通したスタッフがわかりやすくサポートします。
条件次第では、最大360日分の給付 を確保できるケースもあります。
退職後の生活を少しでも安定させたい方は、まずはお気軽にご相談ください。