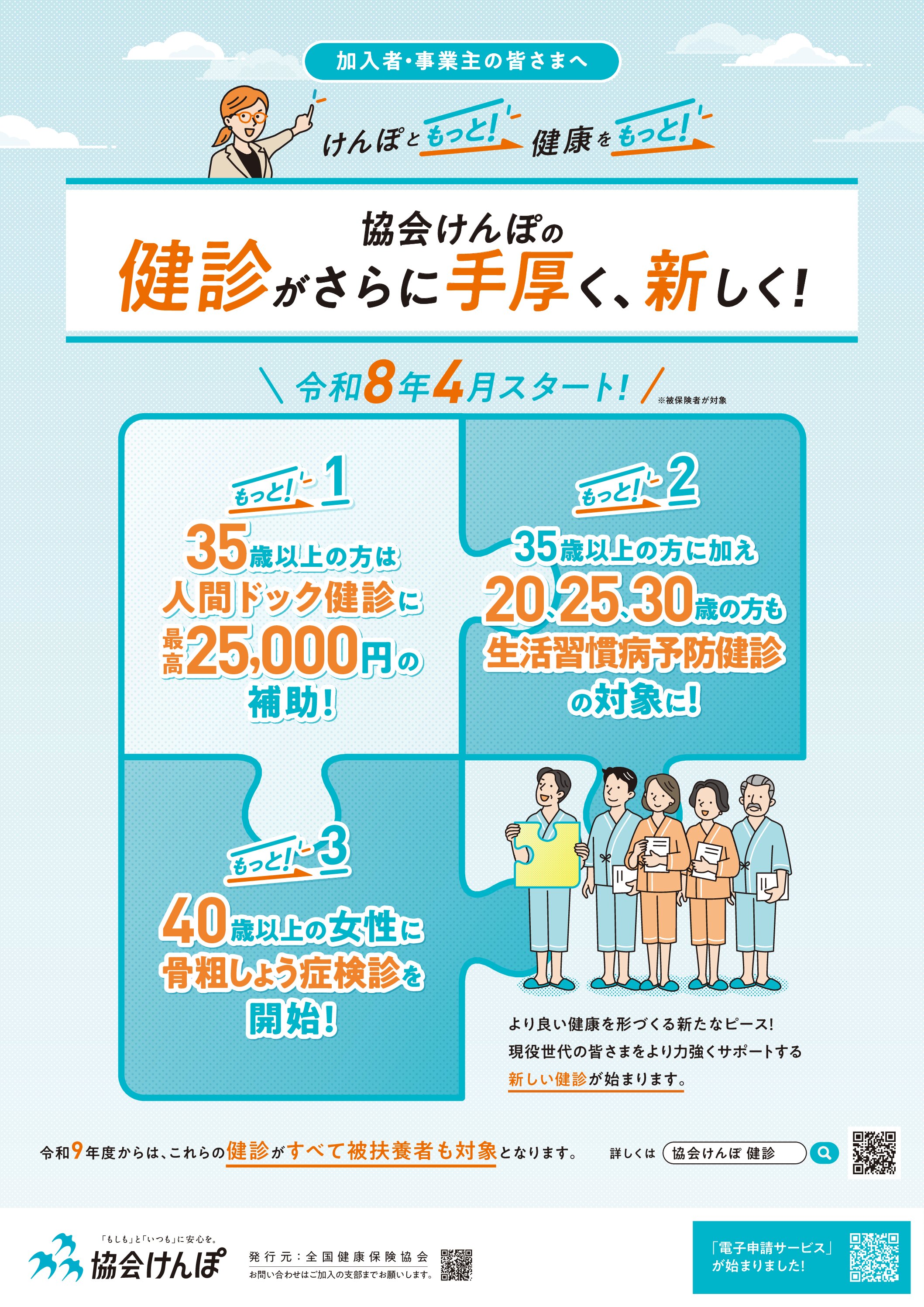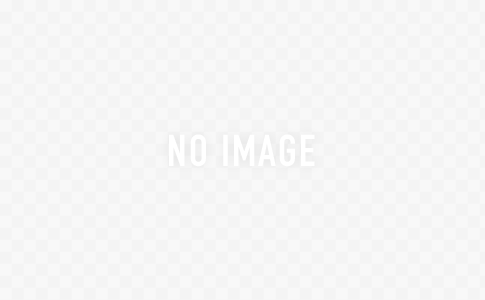「定年退職したけれど、もう少し働きたい」
「次の仕事が見つかるまでの生活費が不安」
そんな方にとって、失業保険(基本手当)は大きな支えになります。
実は60〜64歳の失業保険は計算式が他の年代とは異なり、上限額も別枠で設定されています。
この記事では、「結局いくらもらえるのか?」「いつ振り込まれるのか?」を中心に、定年前後の方が最も知りたいポイントだけに絞って解説します。
定年退職時に失業保険をもらうための条件は以下の記事をご覧ください。
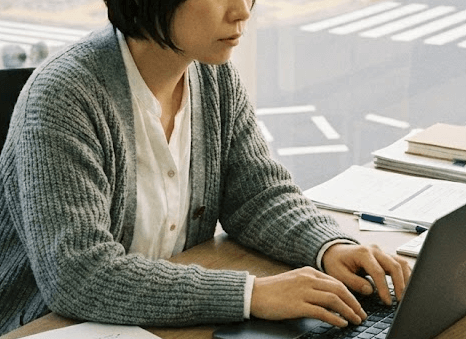
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

定年退職後の失業保険はいくら?受給額の計算方法
定年退職後に受け取れる失業保険(基本手当)の金額は、2つの要素で決まります。
受給額を決める「賃金日額」と「給付率」
失業保険の金額は、以下の計算式で導き出されます。
- 賃金日額
退職前の6か月間に受け取った給与総額(残業代・手当を含む)を 180日で割った数値 - 給付率
年齢と賃金日額に応じて決められる割合(60〜64歳は 45〜80%)
賃金日額の上限(令和7年8月1日時点)
| 年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 60~64歳 | 16,940円 | 7,623円 |
給付率(60〜64歳)
| 賃金日額(円) | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 3,014~5,340未満 | 80% | 2,411~4,271円 |
| 5,340~11,800以下 | 80~45% | 4,272~5,310円 |
| 11,800超~16,940以下 | 45% | 5,310~7,623円 |
| 上限超 | ― | 7,623円(上限) |
60歳以上の場合は、他の年齢層と比べて給付率が低めに設定されているため、賃金日額が高くても受給額の伸び方に上限があります。
参照:厚生労働省|2025年8月1日からの「賃金日額・基本手当日額」の上限額および給付率の改定
【シミュレーション】60歳・退職前月給42万円の計算例
実際にどれくらい受け取れるのか、具体的な例で見ていきましょう。
① 賃金日額を計算
退職前月給が42万円の場合
420,000円 × 6か月 ÷ 180日 = 14,000円
② 基本手当日額を計算
給付率は60〜64歳の場合 45%。
14,000円 × 45% = 6,300円
③ 給付日数
勤続20年以上の自己都合の場合
給付日数 = 150日
④ 総支給額
6,300円 × 150日 = 約945,000円
このように、賃金日額・給付率・給付日数がわかれば、あなた自身の受給額も正確に試算できます。
もらえる日数は?「自己都合」か「会社都合」で変わる
失業保険(基本手当)の受給日数は、同じ定年退職でも、
「再雇用制度を利用しなかったか」
「そもそも再雇用制度がない会社か」
によって大きく変わります。
ここを誤解している人が非常に多いため、まずは確実に押さえておくことが大切です。
参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
再雇用制度を使わずに辞めた場合(自己都合扱い)
会社に継続雇用制度・再雇用制度が用意されているのに、本人が辞退して退職した場合、
ハローワーク上は「自己都合退職」と扱われます。
この場合の給付日数は下表のとおりです。
給付日数(65歳未満・自己都合)
| 加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上~5年未満 | 90日 |
| 5年以上~10年未満 | 120日 |
| 10年以上~20年未満 | 150日 |
| 20年以上 | 150日 |
自己都合になるケースや、給付制限がつくタイミングについては、以下の記事で詳しく解説しています。
再雇用制度がなく、定年で辞めた場合(会社都合扱い)
一方、会社に継続雇用制度そのものが存在しない場合は、
「本人が選べない=会社都合退職扱い」となります。
このケースでは、給付日数が自己都合よりも大幅に増えます。
給付日数(60~64歳・会社都合)
| 加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上~20年未満 | 150~240日 |
失業保険はいつからもらえる?(待機期間とスケジュール)
失業保険が「いつ振り込まれるのか」は、多くの方が最も気になるポイントです。
実は、自己都合か会社都合かによって支給開始のタイミングが大きく変わります。
ここでは、それぞれのケースを具体的に解説します。
給付制限がある場合(自己都合退職)
自己都合で退職した場合、まず 7日間の待機期間 が発生し、そのあとに 給付制限期間 が付与されます。
給付スケジュール(自己都合)
- 待機期間:7日
- 給付制限:1か月
※2025年4月の法改正により、従来の「2か月 → 1か月」に短縮されました。
そのため、自己都合退職の場合は、
退職から約1.5〜2か月後に初回の振込となるのが一般的です。
自己都合特有の待機期間と給付制限のしくみは、以下の記事で詳しく解説しています。
給付制限がない場合(会社都合退職)
会社都合退職の場合、給付制限は一切つきません。
給付スケジュール(会社都合)
- 待機期間:7日
- 初回認定日を経て、約1週間〜10日後に振込
最短の場合、
退職から1か月程度で受給がスタートします。
定年退職後の失業保険申請手続き5ステップ
失業保険(基本手当)を受け取るためには、退職後にハローワークで一定の手続きを行う必要があります。
定年退職であっても申請の流れは同じで、次の5ステップで進みます。
- 離職票を準備する
退職後、会社から郵送される離職票(1・2)を手元に揃えます。 - ハローワークで求職申込みを行う
住所地を管轄するハローワークで、求職申込みを行います。 - 7日間の待機期間
求職申込み後、最初の7日間は働かずに“待機期間”を過ごす必要があります。 - 受給者説明会に参加する
失業保険の仕組みや受給条件についての説明を受けます。 - 初回認定日に出頭する
初回認定が終わると、最初の受給額が確定し、振込に進みます。
より詳しい手続きや注意点については、以下の記事で網羅的に解説しています。
【注意】65歳の誕生日を過ぎると制度が変わります
失業保険(基本手当)が受け取れるのは 「64歳までに退職した場合」 です。
65歳の誕生日を迎えた翌日以降に退職すると、制度が切り替わり、「高年齢求職者給付金(一時金)」の対象となります。
つまり、
- 60〜64歳 → 基本手当(通常の失業保険)
- 65歳以上 → 高年齢求職者給付金(受給は一括支給)
という仕組みで、受け取れる金額や日数が大きく異なります。
参照:離職されたみなさまへ〈高年齢求職者給付金のご案内〉|厚生労働省
まとめ
定年退職後の失業保険は、退職する年齢や離職理由によって受け取れる金額・日数が大きく変わります。
特に、60〜64歳で受け取れる「基本手当」と、65歳以上で支給される「高年齢求職者給付金」では、受給できる日数や総額が大きく異なります。
64歳までに退職すれば90日〜最大240日の受給が可能ですが、
65歳以上は一時金(30日または50日分)となるため、金額差が生じやすい点には注意が必要です。
社会保険給付金アシストでは、こうした複雑な区分や提出タイミングを踏まえ、定年退職後の失業保険の申請サポートも行っています。
ご自身で手続きする際に見落としがちなポイントを整理し、受給できる日数やタイミングを最適化できるよう、制度に精通したスタッフが丁寧にサポートします。
条件次第では、最大360日 の受給が可能になるケースもありますので、
まずはお気軽にご相談ください。