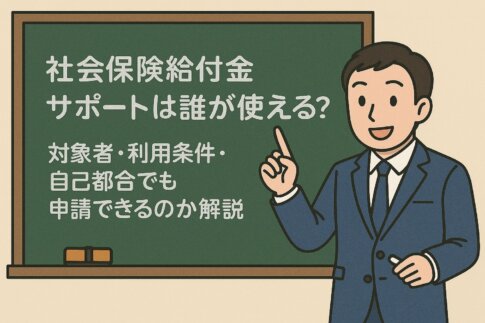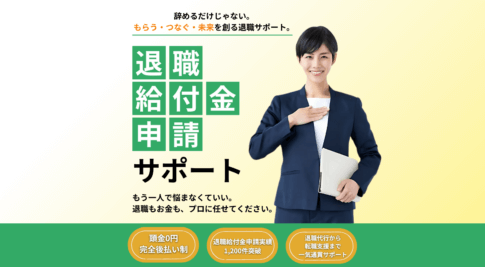退職後、「どんなお金がもらえるの?」「健康保険や年金はどうなるの?」「税金の支払いは?」と悩む方は多いでしょう。
この記事では、退職後にもらえる手当・給付金・社会保険・年金・税金のすべてをわかりやすくまとめました。
- どの制度を使えるのか
- どの順番で申請すればいいのか
- どこで手続きをすればいいのか
「退職後のお金のすべて」を一度で理解できる総合ガイドです。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

第1章|退職後にもらえるお金と支払うお金の全体像
退職後の生活では、「もらえるお金」と「支払うお金」の両方を把握しておくことが大切です。
どちらも手続きをしないと受け取れなかったり、思わぬ出費が発生したりするため、まず全体の流れを整理しておきましょう。
🟢 もらえるお金(給付金)
退職後に条件を満たせば、以下のような給付を受け取ることができます。
| 給付名 | 主な対象者 | 支給の目的・特徴 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | 在職中に病気・ケガで働けなくなった人 | 給与の約3分の2を最長1年6か月支給。 退職後も条件次第で継続可能。 傷病手当金のもらい方を完全ガイド|申請から受給までの流れ・必要書類・注意点を解説 |
| 失業保険(基本手当) | 働く意思と能力がある失業者 | 退職後の再就職までの生活支援。 最長360日支給(就職困難者など)失業保険の申請から受給まで完全ガイド|申請時の注意点・必要書類・社会保険も解説 |
| 再就職手当 |
早期に再就職した人 | 再就職を早めた人へのボーナス的給付。 給与が下がった場合は差額補填も。再就職手当(就職祝い金)とは? 受給条件と申請手続きの全て|早く働いた方が得? |
| 住居確保給付金 | 家賃の支払いが困難な人 | 最大9か月間、家賃を自治体が補助。 失業保険と併用可能。退職後の家賃補助(住居確保給付金)と失業保険は両方もらえる?受給条件や受給金額を詳しく解説! |
| 職業訓練受講給付金 教育訓練給付金 |
再就職に向けてスキルアップしたい人 | 職業訓練受講給付金はハローワーク経由の訓練で月10万円+交通費支給。 教育訓練給付金は指定講座を受講した際に最大70%(上限56万円)が支給。 |
関連記事
就業促進定着手当とは?条件・金額・申請方法をわかりやすく解説
教育訓練と職業訓練の違いとは?本気で資格を取りたい人が選ぶべきはどっち?
🔴 支払うお金(退職後の固定費)
給付をもらう一方で、退職後は自分で払うべきお金も発生します。
健康保険・年金・税金の支払いを把握しておくことで、退職後の生活設計が立てやすくなります。
| 支払い項目 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 任意継続健康保険料 | 退職後も前の会社の健康保険を最長2年間継続できる制度。 保険料は全額自己負担(会社負担分も含む)だが、国保より安くなる場合もある。 退職日から20日以内に申請厳守!! |
| 国民健康保険料 | 任意継続を選ばなかった場合に加入。 前年の所得で保険料が決まるため、思ったより高額になることも。 所得が減った場合は減免申請が可能。 |
| 国民年金保険料 | 20歳以上60歳未満は全員加入義務あり。免除・猶予制度を使えば負担を軽くできる。 将来の年金額にも影響するため要チェック。退職後の国民年金、払えないなら免除できる?条件や手続きまとめ |
| 住民税 | 前年の所得に基づいて課税される。 退職時に一括徴収されることもあり、翌年6月まで支払いが続く。退職すると住民税はどうなる?一括徴収と普通徴収の違い・免除制度まで完全ガイド |
| 所得税(確定申告) | 年の途中で退職した場合は、医療費控除や給付金の非課税扱いで還付を受けられるケースも。 |
第2章|傷病手当金|病気やうつで働けないときの生活支援
退職後に体調を崩した、あるいは退職時点でまだ働けない状態が続いている――
そんなときに頼れるのが健康保険から支給される「傷病手当金」です。
もともとは「在職中の休職者向けの制度」ですが、一定の条件を満たせば退職後も継続して受け取ることができます。
✅ 退職後ももらえる主な条件
- 退職時点で働けない(労務不能)状態であること
在職中の医師の証明が必要です。退職後に新たに発症した場合は対象外です。 - 健康保険に1年以上継続して加入していたこと
転職などで保険を引き継いでいる場合も通算で1年以上あればOK。 - 給与の支払いを受けていないこと
有給消化中は支給対象外となることがあります。
これらの条件を満たしていれば、退職後も最長1年6か月間、給与の約3分の2を受け取ることができます。
病気やうつでしばらく働けないときの生活を支える大切な制度です。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
第3章|失業保険|退職後の生活を支える基本給付
退職後、すぐに次の仕事が決まっていない場合は、ハローワークから支給される「失業保険(基本手当)」を活用できます。
この制度は、「働く意思と能力がある人」を支援するもので、再就職までの生活費をサポートしてくれます。
✅ 受給の主な条件
- 離職前の2年間に、通算で12か月以上の被保険者期間があること
(病気などで働けなかった場合は特例あり) - 働く意思と能力があること
「すぐにでも働ける状態」であることが前提です。 - 実際に求職活動を行っていること
ハローワークでの申込みや、認定日に活動報告をする必要があります。
💰 給付期間と金額の目安
- 給付期間は 90〜330日(就職困難者の場合は最長360日)
- 支給額は、退職前の給与の約50〜80%
退職理由や年齢、勤続年数によって受給期間が変わるため、早めに条件を確認しておくことが大切です。
また、2025年からは自己都合退職の給付制限が2か月→1か月に短縮されています。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
第4章|再就職手当・就業促進定着手当|早く働く人への支援制度
失業保険を受け取っている途中で早く再就職や開業をした場合、「再就職手当」というボーナス的な給付を受け取ることができます。
さらに、再就職後の給与が以前より下がった場合には、「就業促進定着手当」でその差額を補うことも可能です。
✅ 再就職手当の主な条件
- 失業保険の残日数が3分の1以上ある状態で再就職していること
- 1年以上の勤務が見込まれる就職先であること
これらを満たすと、残りの支給日数に応じて最大失業手当の50〜60%相当が支給されます。
開業・個人事業主として働き始める場合も、条件を満たせば対象になることがあります。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
💡 就業促進定着手当とは?
再就職手当を受けたあと、再就職先で6か月以上勤務し、給与が以前より下がってしまった場合に支給される制度です。
差額を一部補填することで、再就職後の生活を安定させる目的があります。
支給対象となるのは、再就職手当を受けた人に限られるため、まずは再就職手当の条件を確認しておくのがポイントです。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
第5章|社会保険の切り替え|国保と任意継続どちらが得?
退職すると、会社の健康保険の資格を失うため、「任意継続」または「国民健康保険」のどちらかに切り替える必要があります。
どちらが得かは、収入や家族構成によって大きく異なります。
✅ 任意継続とは?
会社員時代に加入していた健康保険を、最長2年間そのまま継続できる制度です。
ただし退職後は保険料の会社負担分がなくなり全額自己負担になるため、人によっては保険料が倍近くになることもあります。
それでも、高所得者や家族を扶養している人の場合は、国保より安くなるケースもあります。
✅ 国民健康保険とは?
市区町村が運営する保険で、前年の所得に応じて保険料が決まります。
所得が低かった人や無収入の人は、所得割が下がるため安くなる傾向があります。
さらに、退職した人向けの減額制度(軽減措置)があり、「退職者医療制度」や「所得割・均等割の7割軽減」などが適用される場合もあります。
💡 どちらを選ぶべき?
- 退職前の給与が高かった人 → 任意継続のほうが安い可能性あり
- 所得が大幅に下がる人 → 国民健康保険+軽減制度のほうが安くなる傾向
退職後すぐにどちらかへ加入しないと無保険状態になるためになるべく早めに手続きを行いましょう。
比較記事はこちら
第6章|年金の手続き|厚生年金→国民年金へ
退職すると、会社員時代に加入していた厚生年金の資格を自動的に喪失します。
そのため、退職後14日以内に「国民年金」への切り替え手続きを行う必要があります。
✅ 手続き先
お住まいの市区町村役場(または年金事務所)で行います。
退職日が確認できる書類(離職票・退職証明書など)と本人確認書類を持参しましょう。
💡 保険料が払えないときは「免除」や「猶予」制度を活用
退職して収入が減った場合、国民年金の保険料を免除または猶予してもらうことができます。
免除には4段階あり、前年所得が一定以下なら全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかが適用されます。
20代や学生などの場合は「若年者納付猶予制度」も利用可能です。
免除・猶予期間も将来の年金額に反映されるため、未納のまま放置するよりも手続きをしておくことが重要です。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
第7章|税金・住民税の注意点
退職したあとも、税金の支払い義務はなくなりません。
特に注意が必要なのが「住民税」と「所得税(確定申告)」です。
✅ 住民税は前年の収入に応じて課税される
住民税は「前年の所得」に基づいて計算され、翌年6月から翌年5月まで課税されます。
そのため、退職して収入がなくなっても、前年に働いていた分の住民税を支払う必要があります。
会社員のときは給料から天引きされていましたが、退職後は自分で納付書で支払う「普通徴収」に切り替わります。
もし支払いが厳しい場合は、分割・減免制度の申請を行えば負担を軽減できる場合があります。
✅ 所得税は確定申告で調整が必要な場合も
退職時に年末調整をしてもらえなかった場合や、途中退職・副業・バイト収入がある場合は、自分で確定申告をして精算する必要があります。
医療費控除や社会保険料控除などを申請すれば、税金が還付されるケースもあります。
第8章|退職金の税金と控除制度
退職金は、長年働いた人への労いと生活保障のための給付として支払われるお金です。
ほかの給与とは違い、税金面で大きな優遇措置(退職所得控除)が設けられています。
✅ 退職所得控除とは?
退職金には「退職所得控除」があり、勤続年数が長いほど非課税枠が広がる仕組みです。
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数−20)
この控除額を差し引いた残りの金額に対して、さらに1/2をかけて課税されるため、
退職金の税金は非常に軽く抑えられます。
✅ 一括受け取りと分割受け取りの違い
原則として、退職金は一括で受け取った方が税制上有利です。
分割受け取りにすると「年金扱い」となり、雑所得として課税されるため、税額が増えるケースがあります。
また、再就職先でも退職金を受け取る場合は、勤続期間の通算や退職時期によって控除額の扱いが変わるため注意が必要です。
💡 退職理由による違いも確認
退職金の有無や金額は、退職理由(自己都合・会社都合など)によっても異なります。
就業規則で明確に定められていることが多いため、事前に確認しておきましょう。
くわしくはこちらの記事で解説しています。
第9章|もらえるお金を最大化する順番とタイミング
退職後は、同時にもらえない制度が多いため、受給の「順番」が非常に重要です。
手続きを正しい順序で行えば、給付金を途切れさせずに最長2年半ほどの支援を受けることも可能です。
✅ おすすめの受給ステップ
- 傷病手当金(体調不良時)
- 失業保険(回復後)
- 再就職手当(早期就職時)
この流れを意識して申請すれば、
「傷病手当金 → 失業保険 → 再就職手当」の順で、無駄なく給付をつなぐことが可能です。
具体的な切り替え手続きはこちらで詳しく解説しています。
第10章|迷ったら専門家に相談を
退職後は制度が複雑で、「どれを使えばいいのか」「いつ申請すればいいのか」がわかりにくいものです。
社会保険給付金アシストでは、あなたの状況に合わせた最適な手続きをサポートしています。
申請が通らなければ全額返金保証がついています。
まずはLINEでお気軽にご相談ください。