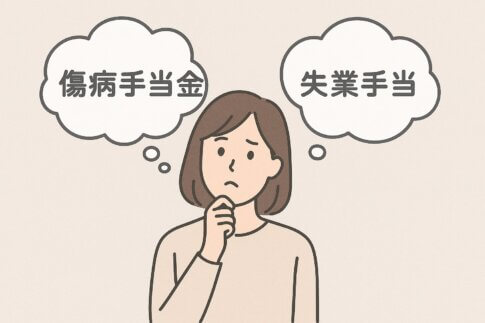傷病手当金は”申請すれば必ずもらえる”わけではありません。
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった会社員が一定期間、健康保険から給付を受けられる制度です。ただし、「申請すれば誰でも必ずもらえる」と誤解されている方が多く、実際にはさまざまな理由で却下・不支給になるケースがあります。
この記事では、「傷病手当金 もらえない」「不支給 理由」「申請 危険」など検索されているテーマに基づき、不支給の原因やその対策をわかりやすく解説します。
特に、初めて申請を考えている方や、うつ病など精神的な不調で退職を考えている方には、知っておくべきポイントが詰まっています。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

傷病手当金を受給できる対象者
では、まずそもそもあなたが傷病手当金をもらう対象者なのか確認してみましょう。
傷病手当金の対象となるのは、協会けんぽや健康保険組合に加入している会社員・公務員など(被保険者)です。
自営業・フリーランスなどの国民健康保険加入者は対象外となります。
基本的に会社に勤めている人が受給できることになります。
傷病手当金を受給するための条件
では続いて、受給するための条件について確認してみます。
まず在職中に傷病手当金をもらうには、以下すべての条件を満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガで療養中であること(労災は対象外)
- 医師に「就労不可」と診断されていること
- 4日以上仕事を休んでいること(3日間の待期期間を含まない)
- 給与の支払いがないこと(支給が一部ある場合は差額支給)
ここでポイントなのが、業務外の病気やケガであることです。
例えば業務内に起きた事故、出張中、通勤途中であれば労災の対象となります。
そのため業務外で起きたケガや病気
例えば、趣味のドライブ中に起きた事故、車が突っ込んできた、といったものが原因で会社を休む必要があります。
また、就労不可という項目も重要です。
傷病手当金は、そもそも病気やケガで働きたくても働けない時にもらえる給付金です。
そのため就労ができる状態であれば働けることになり傷病手当金がもらえません。
以上は傷病手当金を貰うための原則の条件です。
傷病手当金は条件を満たすと退職後ももらうことが可能です。
退職後も継続して傷病手当金を受給する条件(資格喪失後の継続給付)
退職後も受給するには、以下の追加条件を満たす必要があります。
- 退職日までに待期3日間が完成していること
- 退職日前から継続して労務不能であること
- 被保険者期間中に発症・初診していること
- 支給開始日から1年6ヶ月以内であること
- 退職日当日は休んでいること
この中で特に重要ことは、退職日当日を休むことです。
なぜなら、退職日当日に出勤してしまうと、その日以降は「労務不能」ではなかった=就労可能とみなされるため、退職後の継続給付が認められなくなるからです。
退職日に出勤してしまうと、制度上「もう働ける状態だった」とみなされ、支給対象外となってしまいます。
会社から「退職日だけは挨拶に出てきてほしい」と言われても、物理的に出勤するとアウトです。
どうしても対応が必要な場合は、電話や郵送で対応するなど、退職日当日に出勤記録が残らないようにすることが重要です。
傷病手当金の支給期間と金額の目安
では次に、傷病手当金の支給期間と金額の目安について見ていきましょう。
- 支給期間:同一傷病につき最長1年6ヶ月
- 支給金額の目安:標準報酬日額の約2/3 × 支給日数(例:月給30万円 → 約20万円/月)
まず支給期間についてですが、傷病手当金は同一の傷病につき最長で1年6ヶ月まで受給することができます。
この期間は「申請した日から」ではなく、実際に支給が開始された日から起算して1年6ヶ月です。
例え途中で回復して一度復職し、再び同じ傷病で休職したとしても、通算で1年6ヶ月が上限となります。
退職後であっても条件を満たしていれば、1年6ヶ月間は受給が可能です。
次に支給金額についてですが、これは「標準報酬日額」の約3分の2(=約66.67%)が日額ベースで支給されます。
例えば、月給30万円の方の場合、傷病手当金の支給額は月あたり約20万円程度が目安となります。
傷病手当金がもらえない!?よくある不支給理由8選
傷病手当金は、条件を満たせば誰でも受け取れる制度と思われがちですが、実際には不支給となるケースも少なくありません。
申請してから「受け取れませんでした」とならないよう、よくある不支給理由とその対策をあらかじめ把握しておきましょう。
1. 医師の診断があいまい・軽症すぎる
「抑うつ傾向」「不安あり」などあいまいな診断書では通らないことがあります。
診断名(うつ病・適応障害など)と「労務不能」がはっきり書かれていることが重要です。
2. 初診日が退職後になっている
傷病手当金は、在職中に発症・初診を受けていることが大前提です。
退職後に初めて病院にかかった場合は、そもそも資格がなく支給対象外になります。
退職を考えている方は、必ず退職前に医療機関を受診しましょう。
3. 通院が不定期・空白期間が長い
前回の受診から1ヶ月以上間隔が空くと「症状が安定している」と判断されるリスクがあります。
診断後も、定期的な通院を継続することが重要です。
4. バイト・副業などで就労可能と判断される
傷病手当金は、「働けない状態」の人が対象の制度です。
副業収入があったり、短期バイトなどをすると就労可能と判断されてしまうことがあります。
関連記事:失業保険を「不正受給」したらどうなる?
5. 申請書の不備・記載ミス
本人記入欄はもちろん、医師記入欄や事業主記入欄の書き間違い・空欄・日付のズレなどは、審査で引っかかりやすいポイントです。
不支給の直接原因になるだけでなく、返戻や大幅な審査遅れの原因にもなるため、提出前にしっかりと確認しましょう。
6. 社会保険の加入期間が1年未満
傷病手当金の在職中の受給には加入期間の要件はありませんが、退職後の継続給付(資格喪失後の継続給付)を受けるためには、退職日時点で健康保険に継続して1年以上加入していることが条件となります。
つまり、加入期間が1年未満のまま退職すると、退職後の支給は認められないということです。
7. 生活保護や失業手当との併用不可ケース
傷病手当金と生活保護、失業手当など、他の制度を同時に受け取ることはできません。
例えば、すでに失業手当を受け取っている方が、後から傷病手当金の申請を行っても、「時期が重なる」と判断されて却下されます。
8. 障害年金との併用不可ケース
傷病手当金と障害年金は、同じ傷病で両方を同時に受け取ることは原則できません。
併給調整により、差額支給またはどちらか一方のみの支給になります。
申請を通すために今からできる3つの対策
傷病手当金は制度としてしっかり整備されている一方で、書類の記入ミスや手順の誤り、医師選びの失敗によって不支給となるケースも多く見られます。
では、これから申請を考えている方が、今の段階でやっておくべきことは何か?
ここでは、申請成功のために押さえておきたい「3つの実践的な対策」をご紹介します。
1. 信頼できる医師に早めに相談する
傷病手当金の可否を左右する最大のポイントは、医師の診断内容です。
とくに精神疾患(うつ病・適応障害など)の場合は、病名の明確さや「労務不能」の判断がはっきりしていなければ、申請が通らないこともあります。
制度への理解がある医師を選ぶことが非常に重要であり、診断経験が豊富な医師に早めに相談することが成功の第一歩です。
弊社では、制度に精通した提携のオンライン診療クリニックをご紹介することも可能ですので、通院が難しい方やどこを受診すべきか迷っている方も、ぜひご相談ください。
2. 書類は第三者のチェックを受ける
傷病手当金の申請書類は、本人・医師・事業主の3者で記入する複雑な構成になっています。
たった一箇所の記載ミスや日付のズレ、表現のあいまいさでも、審査が長引いたり、不支給となることがあります。
弊社では、提出前に全項目を丁寧に確認し、不備やミスを未然に防ぐサポートを行っています。
自分だけでは見落としやすい部分をプロの目でチェックすることが、安定した受給への近道です。
3. 制度全体を見据えて退職・申請を計画する
傷病手当金を確実に受け取るには、「退職のタイミング」「初診日」「申請順序」など、複数の要素が複雑に絡み合います。
特に退職後も継続して給付を受けたい場合は、退職日当日の扱いや保険加入期間など細かな条件をクリアする必要があります。
申請直前になって慌てるのではなく、制度の流れを理解したうえで、初診から退職、申請までを逆算して準備することが成功の鍵です。
弊社では、おひとりおひとりの状況に合わせた制度活用プランの立案・実行サポートも行っております。
不支給になってしまったときの対応策
「申請したのに不支給通知が届いた…」
そんなとき、多くの方が「もう受け取れないんだ…」と諦めてしまいがちです。
不支給=完全に終わりというわけではありません。
実は、記載内容の修正や資料の追加によって再申請し、支給が認められるケースも多くあるのです。
- 医師の記載ミスを修正して再提出
- 初診日や申請期間の設定ミスを見直す
- 記録不足を補う資料を添付
弊社ではこれまで、
「最初は不支給だったけれど、再申請で受給に成功した」というケースを数多くサポートしてきました。
-
医師への記載依頼の仕方
-
不支給理由の分析と戦略的な申請修正
-
添付資料の選定とアドバイス
など、再申請に向けた実践的なサポート体制を整えています。
最後に:傷病手当金の申請でお悩みの方へ
傷病手当金は、制度を正しく理解し、計画的に進めることで確実に受け取れる制度です。初診や書類の準備、会社とのやりとりなど、専門的な部分は弊社がフルサポートいたします。
「どこに相談すればよいかわからない」そんな方こそ、まずはLINEでお気軽にご相談ください。