「求職者支援制度って何?」
「失業保険がもらいみたい…どうしよう」
「転職先が全然見つからない…」
と悩んでいませんか。
アルバイトやパートなどで雇用保険に加入していない人も少なくありません。また、加入歴が少なく失業保険を受給できない人も。
いきなり仕事を失ったり、資格が欲しくて職業訓練校に通ったりしたら金銭面が心配ですよね。貯金が十分にあれば良いですが、なかったら来月の家賃などを心配事が絶えません。
その結果、焦って最初に受かった会社に入ることになります。運良く、相性の合う会社に入社できれば良いですが、最悪の場合はブラック企業で体調を崩すリスクもあります。
資格も取ってより良い環境で仕事をしたい人におすすめなのが、就職者支援制度です。
就職者支援制度とは、簡単にいうと失業保険がもらえない人で職業訓練を受けている人を金銭的に支援してくれる制度のことです。
こちらでは、就職者支援制度についてより詳しく知りたい人のために
- 就職者支援制度について
- 対象になる条件
- 就職者支援制度が対象となる職業訓練の内容
- 受給できる給付金
- 受給までの流れ
などを詳しく紹介しています。条件も厳しく、申請方法も複雑ですが申請が通れば金銭的に余裕が生まれます。ぜひ、最後までご覧ください。
目次

社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
【失業保険を受給していたらもらえない】求職者支援制度とは

就職者支援制度は、雇用保険に加入していなくても受給できる制度です。
失業後、失業保険がもらえないとかなり厳しいですよね。このままだと、貯金がつきてしまうと焦る人も多いです。
失業保険についてと、就職者支援制度について詳しく解説します。
失業保険についてサクッとおさらい
実は失業保険は正しい呼び方ではなく、正確には雇用保険の基本手当といいます。雇用保険から支給される基本的な手当、という意味です。ただ、この記事ではわかりやすく失業保険と表現していきます。
失業保険とは、労働者が離職したときに一定期間、雇用保険から受け取れる給付金です。
失業保険を受給するためには条件があります。離職前の2年間に1年以上は雇用保険に加入していることと、就職意思と能力が必要です。条件を満たしていたら、ハローワークで申請できます。
ただし、会社都合で退職した場合など、やむなく退職した場合には加入期間の要件が緩和されます。
失業保険が給付されるのは、基本的に離職後1年間です。
雇用保険に入っていなくても利用できる求職者支援制度
求職者支援制度とは、就職の意思や能力があるにもかかわらず、失業保険の受給資格を満たさない方を支援するための制度です。
失業保険をもらえなくても、資格を取得したりスキルを身に付けたりするために職業訓練を受ける方へ、
- 受講料
- 交通費
- 宿泊費
などの支援が行われます。
【具体例も紹介】求職者支援制度の対象者になる条件

気づいていると思いますが、就職者支援制度を受けるためには失業保険の受給資格がないことが絶対条件です。
他にも、対象者になるには様々な条件が必要です。
こちらでは
- 就職者支援制度の対象者になる要件
- 特定就職者に該当する具体例
- 求職者支援制度の対象外とされる人
の3つに分けてより詳しく紹介します。順番に確認しましょう。
1.求職者支援制度の対象者になる要件
求職者支援制度の適用を受けるには、以下の要件を満たさねばなりません。
- ハローワークへ求職の申し込みをしている
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でない
- 労働の意思と能力がある
- 職業訓練などの支援が必要とハローワークが認めた
これらの要件をすべて満たす人を、特定求職者と呼びます。
2.特定求職者に該当する具体例5つ
特定求職者に該当する具体例を5つ紹介します。
- 雇用保険に加入できなかった
- 失業保険(雇用保険の基本手当)を受給していたが、再就職できないまま支給期間を終えてしまった
- 雇用保険の加入期間が不足して失業保険を受給できない
- 自営業を廃業したため、雇用保険へ加入していない
- 学生が就職内定をもらえないまま卒業したため、雇用保険へ加入していない
ちなみに雇用保険に加入できないのは、労働時間や雇用期間が短いと起こります。
なお上記に該当する場合でも、ハローワークが個別に再就職のために訓練の必要がないと判断したら、求職者支援制度を適用してもらえない可能性があります。
3.求職支援制度の対象外とされる人
以下のような方は、求職者支援制度を適用してもらえません。
- 現在、別の会社で働いている(週の所定労働時間が20時間以上)
- 自営業を行っている
- 会社役員
- 大学や専門学校などの学生
- 短時間や短期間のみの就労を希望している
1つでも当てはまったら、残念ですが就職者支援制度の対象外とされます。
求職者支援制度で対象となる職業訓練の内容

求職者支援制度では、一定の職業訓練を受けるときに限って各種の手当てを受けられます。職業訓練を受けずに生活費だけ支援してもらえるわけではないので、注意しましょう。
対象となる職業訓練は、厚生労働省が認定する求職者支援訓練です。
こちらでは、
- 職業訓練の種類
- 基礎コース
- 実践コース
に分けてさらに詳しく紹介していきます。
1.職業訓練の種類
支援対象となる訓練には、以下のようなものがあります。
- WEBソフト開発技術者、サーバー管理者、システム管理者、ネットワーク技術者などのIT分野
- 営業マン、事務員などの営業、販売、事務分野
- 医療事務員、歯科助手などの医療事務分野
- 訪問介護、施設介護、看護助手などの介護、医療、福祉分野
- 農業分野、林業分野
- 旅行、観光分野
- 警備員などの警備、保安分野
- 広告ディレクターやイベントプランナーなどのクリエイト分野
- グラフィックデザイナー、webデザイナーなどのデザイン分野
- 料理人、菓子職人などの調理分野
- 電気、機械関連分野
- 金属関連分野
- インテリアコーディネーターなどの建設関連分野
- 理容師、美容師、エステティシャン、ネイリストなどの美容分野
- パソコンインストラクター、マンション管理人、ペットトリマーなど
全国の職業訓練施設は、こちらのサイトから検索できます。
https://www.jeed.or.jp/js/kyushoku//shien/index.html
自分の身に付けたいスキルを習得できる職業訓練施設を、探してみましょう。
2.基礎コース
基礎コースとは、就労に必要な基本的な能力を短期間で習得するためのコースです。
提供される内容は、
- 基本的なコミュニケーションスキル
- 職場での基本的なマナーやルール
- チームワークやリーダーシップの基礎
- 職場での基本的なコンピュタースキル
などです。
訓練期間は2~4ヶ月となっています。
基礎コースは、限られた経験しかない人を対象にしています。職業訓練校を通して、新しい職業に就くための土台を築きたい人におすすめです。
3.実践コース
実践コースとは、各種の職業で必要となる実践的なスキルや資格を獲得するためのコースです。
提供される内容は、
- 職業・業界における実践的なスキルトレーニング
- 専門的な知識や技術に関する情報の提供
- 実際の業務環境での模擬訓練や実地プロジェクト
- 業界のニーズに合わせた特殊なスキルや資格の取得
などです。
実践コースは即戦力として活躍できるようになるトレーニングを行っています。訓練期間は3~6ヶ月です。
求職者支援制度で受給できる職業訓練受講給付金3種類

求職者支援制度を適用されると職業訓練施設に通っている間、職業訓練受講給付金というお金が給付されます。
職業訓練受講給付金には
- 職業訓練受講手当
- 通所手当
- 寄宿手当
の3種類があるので、順番にみていきましょう。
1.職業訓練受講手当
職業訓練を受講するとき、職業訓練受講手当として月額10万円の生活費支援を受けられます。
毎月の振込となります。受給を続けるには、1ヶ月ごとにハローワークへ行ってください。そして、職業訓練受講給付金の支給申請と職業相談を続ける必要があります。
2.通所手当
通所手当とは、通学のために発生する費用の一部を援助してくれる手当のことです。通所手当には
- 電車
- バス
- 自転車
など様々な交通手段に対する費用が含まれます。
月額の上限は4万2,500円です。もちろん、通学方法などによって支給額が変わります。
3.寄宿手当
職業訓練施設に通うため、宿泊が必要になるケースで支給されます。
施設が運営する宿泊施設、民間の賃貸アパートや下宿代などが対象です。金額は1万700円となります。
求職者支援制度でもらえる職業訓練受講給付金の条件7選
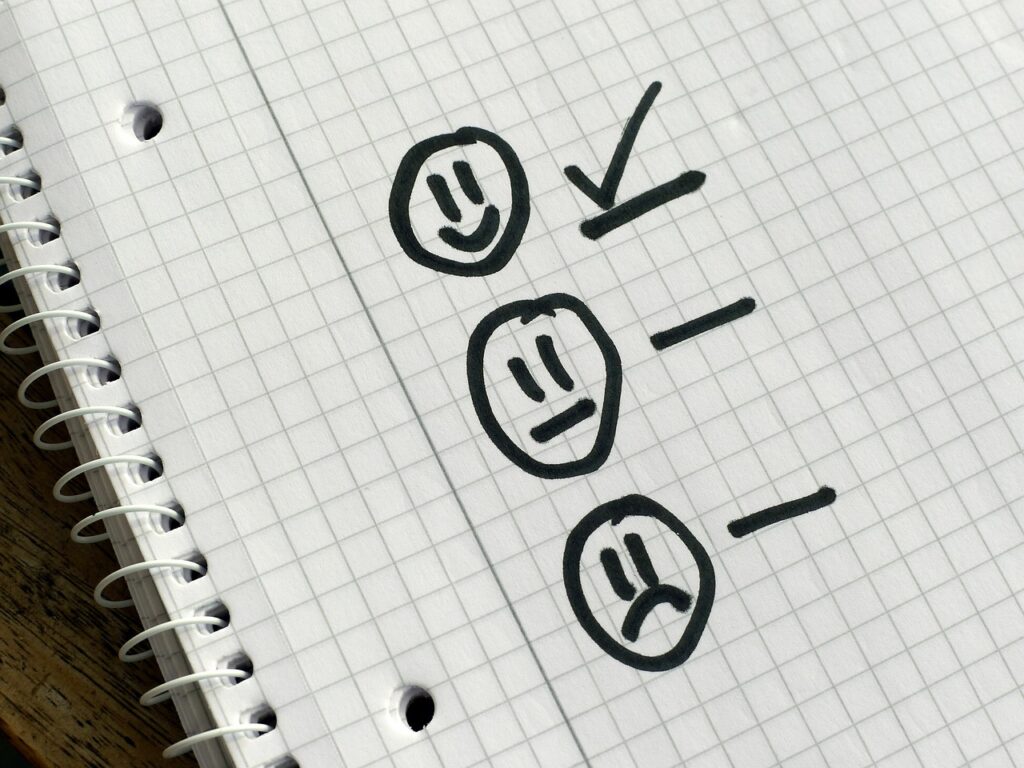
求職者支援制度を受けるのは難しいと言われています。却下される多くの理由は、失業保険を受給しているから。
こちらでは、それ以外の求職支援制度で職業訓練受講給付金を受給するための条件を7つ紹介します。
- 本人の収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月25万円以
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在の居住場所以外に不動産を所有していない
- 全ての訓練実施日に出席している
- 同一世帯の人が給付金を受給していない
- 不正行為によって国の給付金を受給していない
詳しく確認していきましょう。
1.本人の収入が月8万円以下
特定求職者本人の前月の収入が8万円以下であることが必要です。
収入には給与だけでなく賞与も含、税引前の金額で算定します。通勤手当は除かれます。
また不動産賃貸収入や年金、親族からの仕送りや養育費なども含んで計算します。
2.世帯全体の収入が月25万円以下
本人だけでなく、
- 同居の配偶者
- 親
- 子ども
などを含み世帯全体の収入が月25万円以下であることが必要です。
別居していても家計が1つになっていたら、世帯収入に加算しなければなりません。
また住民票上は世帯分離していても、同一住所なら同居の親族扱いとなります。
3.世帯全体の金融資産が300万円以下
- 本人
- 同居の親族
- 家計を同一にする別居の親族
など「世帯全体の金融資産」が300万円以下でなければなりません。
4.現在の居住場所以外に不動産を所有していない
現在の自宅以外に
- 土地
- 建物
- マンション
などの不動産を所有していると、求職者支援制度の対象になりません。
共有名義になっている場合も含まれるので、遺産相続によって兄弟と不動産を共有している場合などには注意が必要です。
5.すべての訓練実施日に出席している
基本的に、職業訓練施設における訓練実施日にはすべて出席しなければなりません。遅刻、早退もしてはなりません。
ただしやむをえない事由によって
- 出席できなかった
- 遅刻
- 早退
などの日がある場合出席日数が8割以上になっていれば足ります。
また遅刻や早退により訓練の2分の1以上を受講した場合には、2分の1出席として出席日数を計算します。
6.同一世帯の人が給付金を受給していない
同居の家族や生計を一つにしている親族が求職者支援制度を適用していないことが必要です。
同じ世帯では、2人以上の人が同時に求職者支援制度を利用できないので注意しましょう。
7.不正行為によって国の給付金を受給していない
不正行為によって国の給付金を受給していないのも、条件の1つです。
過去3年以内に、虚偽申告やなりすましなどの不正行為によって給付金の支給を受けていると、求職者支援制度の対象になりません。
求職者支援制度の申し込みから受給までの流れ7ステップ

求職者支援制度を利用して給付金を受け取りたいときには、以下の流れで進めましょう。
- 求職申込み、制度の説明
- 訓練コースの選択
- 受講申し込み
- 選考試験
- 合否結果、就職支援計画書を受け取る
- 訓練の受講開始
- 給付金が振り込まれる
1つずつ詳しく説明します。
1.求職申込み、制度の説明
まずはハローワークへ行って、求職の申込みをしましょう。このとき、ハローワークの担当者から求職者支援制度についての説明をしてもらえます。
制度の対象者となるか要件を確認してもらい、どういった給付金を受け取れるのか、どのような訓練施設があるのかなどを確認しましょう。
2.訓練コースの選択
求職者支援制度の要件を満たし、本人も利用を希望する場合には訓練コースを選択します。
受講申込書や事前審査書などの必要書類を受けとりましょう。
3.受講申込み
ハローワークの窓口で、受講の申込みを行います。すると、ハローワークから受付印を押した受講申込書を返してもらえます。
次に受付印のある受講申込書と事前審査書などの必要書類を揃えて、受講予定の訓練施設へ提出します。これで、事前審査の申込みが完了します。
書類の提出方法は、持参または郵送となるケースが多数です。具体的には対象となる訓練施設へ問い合わせてください。
4.選考試験
事前審査を申請すると、各訓練施設にて選考試験が行われます。
試験内容は施設によって異なります。指定された日時・場所で面接や筆記試験を受けましょう。
5.合否結果、就職支援計画書を受け取る
試験が終了すると、訓練施設から合否を知らせる選考結果通知書が自宅宛てに郵送されてきます。
合格した場合、訓練開始日の前日までにハローワークへ行って就職支援計画書を受け取りましょう。これを、支援指示といいます。
就職支援計画書を受け取らないと訓練を受講できず、給付金も受け取れないので注意してください。
また地域のハローワークによっては、就職支援計画書の交付日を指定するケースもあります。
6.訓練の受講開始
実際に訓練施設での受講を開始します。
受講中は、ハローワークから指定された日(月1回)にハローワークへ行き、職業相談を受け続けなければなりません。また訓練の修了後も3ヶ月間はハローワークで職業相談を続ける必要があります。
毎月きちんとハローワークへ行かないと給付金を受け取れないので、注意しましょう。
7.給付金が振り込まれる
ハローワークから指定された日にきちんと職業相談を行い「給付金申請書」を提出すると、1週間から10日後に指定した口座へ給付金が振り込まれます。
初回の振り込み時期は、訓練を開始してから1ヶ月半から2ヶ月後になることが多いです。
求職者支援制度を受け取るときの注意点3つ

求職者支援制度を受けるときの注意点が3つあります。
- 受給の手続きが複雑
- 定期的な通所が必須
- 申請の期限を守る
大変ですが、しっかりと行わないと手当をもらえません。給付金がもらえなかったと後悔しないためにも、頑張りましょう。
1.受給の手続きが複雑
求職者支援制度による給付金受給手続きは非常に複雑です。ハローワークや訓練施設にさまざまな書類を提出したり、試験を受けたり報告をしたりしなければなりません。
手順を間違えると受給できないリスクが高まります。
わからないときには社労士や専門会社などの支援を受けましょう。
2.定期的な通所が必須
受給開始後は、ハローワークへの月1回の来所が必須となります。受講中だけでなく修了後の3ヶ月間も通所が必要なので注意が必要です。
ハローワークが指定した日に来所しないと、以降の給付を受けられません。受講手当はもちろん、通所手当や寄宿手当も振り込まれません。
ハローワークの指示に従わない場合、既に支給された給付金の返還命令を受ける可能性もあります。少々面倒でも、必ずまじめに通ってください。
3.申請期限を守る
申請期限を守りましょう。就職者支援訓練は、都道府県ごとさらに開校月ごとに申請受付期間が決まっています。
いつでも受け付けているわけではありません。
そのため、申請期限を超えないように早めにハローワークに相談しましょう。
困ったら社会保険給付金サポートを利用しよう

求職者給付金制度を利用すると、給付金を受け取りながらスキルを身に付けられるので、大きなメリットを得られるでしょう。ただ手続きが非常に面倒でわかりにくいので、ハードルが高いと感じる方も多いのが現実です。
そんなときには、プロの社会保険給付金サポートサービスを利用するのがおすすめです。給付金サポートのスペシャリストが受給要件を判断し、スムーズに受給できる様、適切なアドバイスをしてくれます。










