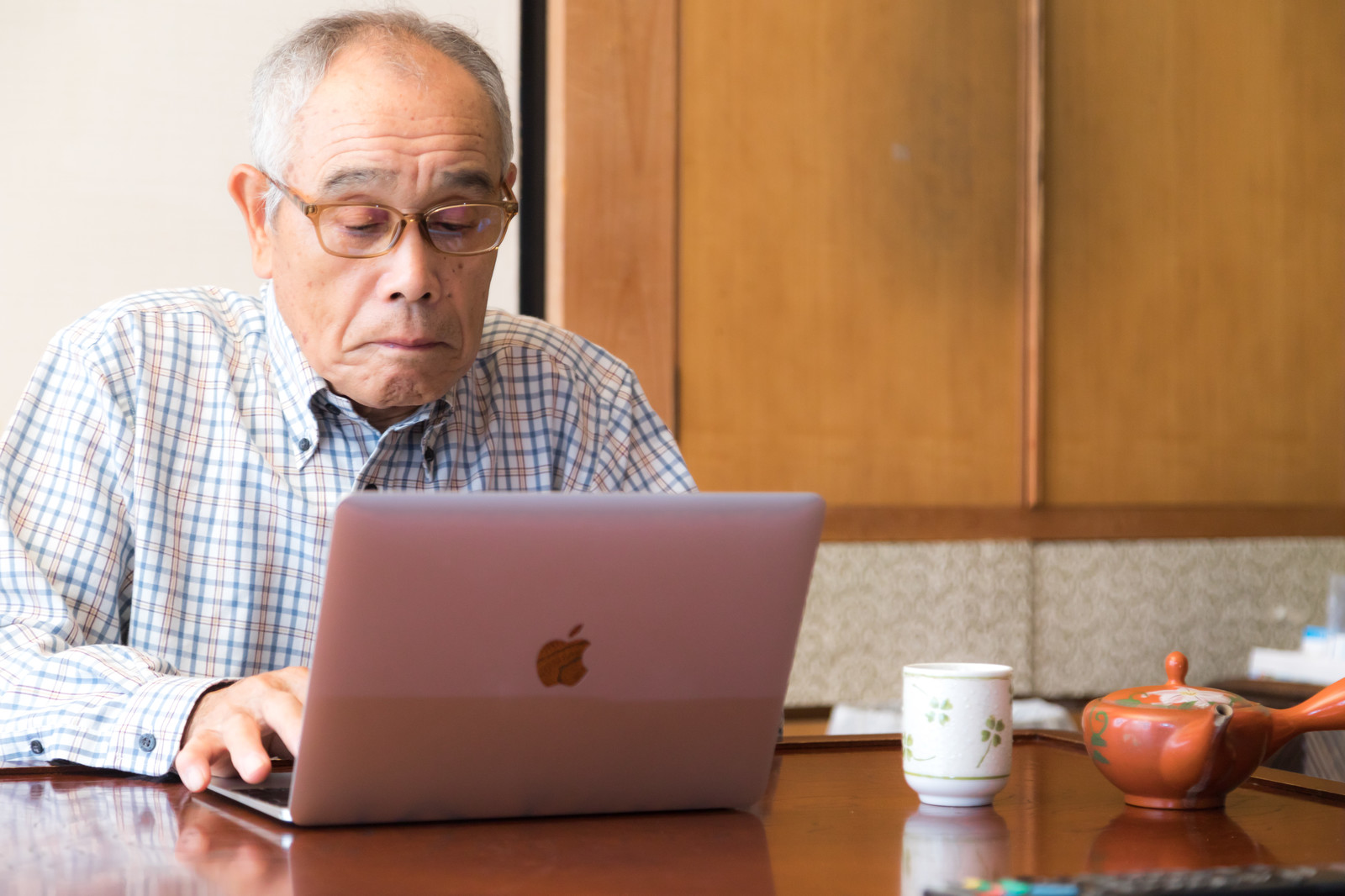「仕事を辞めたいけどお金がないので辞められない」
「仕事を辞めたいけど次の就職先がないからどうすればよい?」
「仕事を辞めるときには、貯金はどれくらい必要?」
仕事に悩んでいる方はこのような悩みを抱えていませんか?お金がないからといって、辛い仕事を我慢して続ける必要はありません。
しかし、お金がないと生活をしていけないので、お金がないときの対処法や退職後にかかるお金を把握しておく必要があります。
今回は会社を辞めたいけれどお金がないときの対処方法を15個紹介します。日々の仕事が辛くてお悩みの方は、最後まで読んでぜひ参考にしてみてください。

社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
仕事を辞めた後にかかるお金

仕事を辞めた後にかかるお金を把握しておくと、仕事を辞めた後の生活をイメージしやすいでしょう。お金がないのにいきなり会社を辞めることはリスクが高いからです。収入が途絶えるので、たちまち生活に困ってしまいます。
仕事を辞めた後にかかるお金は主に、生活費、就職活動にかかるお金、健康保険料、国民年金保険料、住民税です。それぞれ詳しく解説します。
生活費
生活費は以下のような項目にお金がかかります。
- 家賃
- 食費
- 水道光熱費
- 通信費
- 衣類や美容関連費
- 交際費
- 交通費
生活レベルや居住地によって価格の変動はあるかもしれませんが、月10~20万円は必要です。そのため、貯金がまったくないとすぐに生活が苦しくなる可能性があります。
就職活動にかかるお金
就職活動をする際にお金がかかります。転職活動する際の転職エージェントは無料で利用できますが、交通費や資格取得などにお金がかかってしまいます。
ただし、「12.就職活動支援費をもらう」で解説しますが、就職活動の際に補助される給付金があるので活用するのがおすすめです。
健康保険料
日本は国民皆保険制度なので、常に保険に加入する必要があります。そのため会社を退職した場合には、以下の4つから健康保険を選ぶ必要があります。
- 再就職した場合には、次の会社の健康保険に加入する
- 任意継続被保険者になる(退職前の会社の健康保険を最長2年間継続できる)
- 国民健康保険に加入する(14日以内に市区町村に申請)
- 家族の健康保険の被扶養者になる
家族の健康保険の扶養に入ると保険料の払い込みは必要ありませんが、任意継続被保険者や国民健康保険に加入した場合には健康保険の支払いが必要です。
健康保険料は「前年度の所得に応じて」計算されるため、無職になっても会社員時代の給与額に応じた健康保険料を支払う必要があります。思った以上に高額になる可能性がある点に注意しましょう。
住民税
住民税も前年度の所得に応じてかかるので、無収入にもかかわらず高額な納付が必要です。
国民年金保険料
退職後は、国民年金に加入して保険料を払わなければなりません。毎月16,520円(2023年度)の出費が発生します。
以上のように、会社を辞めると無収入でも月20万円以上の出費が発生するケースが多いでしょう。日々の生活費を切り詰めても、支払いが難しいと感じる方が多いのではないでしょうか。
次に、お金がないときの対処方法を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
仕事を辞めたいけれどお金がないときの対処方法15選
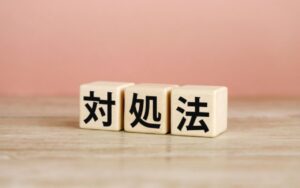
会社を辞めたいけど、お金がないときの対処方法を15選紹介します。自分に合ったものを見つけて、ぜひ実践してみてください。
1.転職先を決めてから会社を辞める
就職している間に転職先を決めておくのがおすすめです。無職の期間がなければ、継続して給料をもらえるので生活に困ることはありません。
また、健康保険料や住民税、国民年金の支払いにも困らないでしょう。
2.ボーナスをもらった後で退職する
ボーナスがもらえる人はボーナス後に退職するのがおすすめです。ボーナス後に会社を辞めると、しばらくは生活しやすくなるでしょう。
3.退職金を計算して離職後の計画を立てる
会社を辞めると退職金をもらえる企業がたくさんあります。ただし、すべての企業で退職金が支給されるわけではありません。退職金を受け取れるかどうかは、勤務先に「退職金規程」があるかどうかで決まります。
また、就業規則の中で退職金について定められている会社もあります。まずは自社に退職金規程があるかどうかを調べて、どれくらいの金額が支給されるかは勤続年数によって異なるので、試算してみるのがおすすめです。
その金額を前提に、退職後の生活設計をしてみてください。
4.副業をする
お金がないなら、在職中に副業をして収入を増やす方法も有効です。最近では、せどりや不用品販売、クラウドソーシングなどでお金を稼いでいる副業サラリーマンが増えています。
副業が軌道に乗ったら、会社を辞めても困らないでしょう。フリーランスとして独立できる可能性も出てきます。
また、職場で副業が許可されているのであれば、土日などにアルバイトをしてお金を貯める方法もあります。
5.住民税の減税措置を受ける
生活費の項目で住民税の支払いが必要だと記載しましたが、自治体では住民税の減税措置があります。困ったときには役所へ連絡して現状を話し、適用可能なら減税してもらいましょう。
適用になる要件は以下の通りです。
- 収入が大きく減少した
- 予測できない失業状態である
- 生活保護を受けている
- 災害による被害を受けた
- 新型コロナウイルスの影響で失業や収入が減少した
失業状態にあることがわかる書類や前年の所得がわかる書類などが必要です。また、減免措置の要件は自治体によって異なるので、居住している役所に問い合わせてください。
6.国民年金を免除してもらう
国民年金保険料にも減免措置があります。失業して所得がなくなった人や低所得の人は、年金事務所へ申請すると国民年金保険料の支払いを免除や猶予してもらえます。
免除してもらえた場合には、免除期間については「本来の2分の1の金額」を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。ただし、猶予してもらった場合には、猶予期間は年金を払ったことにならないので、将来の年金額が増えません。
どちらにしても申請しないと適用されないので、困ったときには管轄の年金事務所で相談してみてください。
7.国民健康保険料を減額してもらう
無収入になって国民健康保険料を払えない場合、各自治体に減額制度があるので早めに相談しましょう。国民健康保険料は前年度の所得に応じてかかるので、会社員時代の給料が高かった方には数十万円もの高額な金額になる可能性があるからです。
所得金額に応じて「2割」「5割」「7割」を減額してもらえます。各自治体の窓口に相談しましょう。
8.生活費を見直して節約する
生活費の中でかかる固定費(通信費、光熱費、保険、車など)を見直すのがおすすめです。たとえば、通信費であれば大手キャリアから格安スマホに変更するだけで1ヶ月1,000円~3,000円程度削減できる可能性もあります。
また、保険の契約を見直して必要な保険について再検討して、保険費を減らせないかを考えてみるのもよいでしょう。
9.住居確保給付金を受給する
居住している自治体で「住宅確保給付金」を受け取れるケースもあります。これは、失業して求職中の人を対象に市区町村ごとに定める額を原則3か月分が支給される制度です。給付期間は2回まで延長できるので、最大9か月間の家賃を援助してもらえます。
対象者の要件は以下の通りです。
- 主たる生計維持者が①離職、廃業後2年以内である場合または、②個人の責任や都合によらず給与等を得る機会が、離職、廃業と同程度まで減少している場合
- 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額(基準額)の1/12であり家賃の合計額を超えていないこと
- 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分で100万円を超えない額)を超えていないこと
- ハローワークなどに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動をしていること
申請しないと受け取れないので、早めに役所へ相談に行ってみてください。
10.アルバイトで祝い金をもらえる求人サイトを利用する
退職後に新しい職が見つかるまでアルバイトをする場合には、アルバイトの採用が決まっただけで祝い金をもらえる求人サイトの利用がおすすめです。
祝い金の金額はサイトにもよりますが、数1,000円~30,000円程度になります。手元にお金がなくてもアルバイト収入と祝い金があれば生活を守りやすくなるでしょう。
11.傷病手当金をもらう
病気やケガによって仕事を辞める方は、健康保険から傷病手当金を受け取る方法がおすすめです。傷病手当金とは、健康保険組合に入っている方が業務外の理由によって病気やケガをしたときに支給されるお金です。仕事ができなくなって休職し、会社から給料が出ない場合に支給されます。
離婚やプライベートな辛い出来事で「うつ病」になったり交通事故に遭ってけがをしたりしたときに受け取れると考えましょう。
ただし、給付期間は基本的に「1年6か月まで」であり、1年6か月が経過するとその時点で働けない状態でも打ち切られる点には注意が必要です。
また、傷病手当受給期間中に仕事を辞めた場合、健康保険の資格を喪失するので傷病手当金を受け取れなくなると思っている方がいますが、誤解です。被保険者の資格を失っても、以下の要件を満たすなら傷病手当金の給付が続きます。
- 退職日までに社会保険に継続して1年以上加入していた
業務外の事情で病気やケガをしたら、健康保険へ傷病手当金の申請をして受け取りを開始してから会社を辞めると良いでしょう。
12.求職活動支援費をもらう
求職活動時にかかる交通費や宿泊費、教育訓練受講費が支給される制度を利用するのもおすすめです。求職活動支援費には、広域就職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費の3種類があります。
広域就職活動費
広いエリアで就職活動をして費用が高額にかかった場合には、電車・新幹線代、バス代、飛行機代、宿泊費などの支給を受けられます。
交通費については全額、宿泊費については8000円前後が支給されます。交通費の場合はハローワークからの距離が200km以上、宿泊費の場合はハローワークからの距離が400km以上の場合が支給条件です。
短期訓練受講費
再就職に向けて1ヶ月未満の教育訓練を受講するときに支給されます。コースを修了すると、支払った教育訓練費の20%を受け取れます。ただし、上限は10万円です。
求職活動関係役務利用費
企業の就職説明会への参加や、面接、試験を受けに行く、または職業訓練を受講するために、保育園や幼稚園、子ども園などに子どもを預けるときの費用を支給してもらえます。
保育サービスの利用料の80%が支給されます。
13.失業保険をもらう
失業保険とは、「失業した労働者が求職活動する際の生活費を支援する給付金」です。正式には「雇用保険の基本手当」と呼ばれます。会社員の方は、在職中雇用保険に加入しているケースが多いでしょう。
雇用保険とは、労働者の雇用や生活を守るための保険です。失業すると求職活動をするための経費や生活費がかかるので、雇用保険から基本手当としての給付金(いわゆる失業保険)を受け取れるのです。
失業保険を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 失業状態にある
- 就職の意思と能力がある
- 求職活動をしている
- 会社都合退職の場合、退職前1年間に6か月以上雇用保険へ加入していた
- 自己都合退職の場合、退職前2年間に12か月以上雇用保険へ加入していた
このように、会社都合退職と自己都合退職とで支給要件が異なるので注意しましょう。
会社都合退職とは
解雇やリストラなど、会社側の事情によって離職を余儀なくされた場合です。
自己都合退職とは
転職やキャリアアップ、条件待遇への不満など、従業員側の事情によって自ら辞職した場合です。
失業保険をもらえる時期と金額について
自己都合退職と会社都合退職を比べると、失業保険をもらえる「時期」や「金額」も大きく異なるので注意しましょう。
自己都合退職の場合、失業保険をもらえるのは「申請してから原則2か月と7日後」からです。申請してから7日間の「待機期間」、その後2か月の「給付制限期間」が適用されます。
失業保険を申請しても、2か月以上自力で生活しなければなりません。給付期間が短くなり、総支給額も少なくなるでしょう。
会社都合退職の場合、2か月の給付制限期間が適用されないので、申請後7日が経過したらすぐに失業保険を受け取れます。自己都合退職のケースよりも給付期間が長くなり、総支給額も高額になります。
自己都合退職と会社都合退職を比べると、会社都合退職の方が圧倒的に有利といえるでしょう。
自己都合退職でも会社都合退職にしてもらえる場合がある
解雇やリストラ、倒産などの会社都合退職でなくても、会社都合退職扱いにしてもらえるケースがあります。たとえば以下のような場合です。
- 長時間労働によってやむなく退職した
- パワハラを受けてやむなく退職した
- 退職勧奨を受けて退職した
- 転勤で勤務地が遠くなったので退職した
- 病気やけがで退職した
- 妊娠、出産のため、退職した
- 親族の介護のために退職した
上記のような事情があれば、会社都合退職と同じ取扱いをしてもらえてすぐに失業保険を受け取れます。給付日数が増えて、支給額も自己都合の場合よりも高額になるので、労働者にとっては非常に有利になるでしょう。
ただし、ハローワークで事情を説明するためには診断書などの資料も必要なので、事前に必要な書類については確認してみてください。
14.職業訓練を受ける
ハローワークが実施している、就職に活かせる知識やスキルを無料で習得できるサービスを受けるのもおすすめです。「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」の2種類があります。
公共職業訓練
失業保険を受給している求職者が対象の職業訓練です。訓練期間は3か月〜2年とさまざまであり、受講費用はテキスト代などの実費を除き無料です。
訓練延長給付制度を利用すれば、失業保険の所定給付日数が一定数残っている場合に、訓練の受講を開始すると訓練が終了するまで保険の手当の支給が延長されます。この制度を利用すれば、失業保険の給付日数が短い場合にも給付日数を増やせます。
たとえば、失業保険の給付日数が90日の場合に6ヶ月(180日)の職業訓練を受講すれば、最長で270日の給付金を受け取れるでしょう。ただし、「給付制限や所定給付日数」によって違いはありますが、原則として、所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わるまでに訓練を開始しないと、延長給付を受けられない点に注意が必要です。
求職者支援訓練を受ける
失業保険を受給できない求職者を対象とする職業訓練であり、主婦やニート期間を過ごしていた人も利用できます。訓練期間は2~6ヶ月であり、受講料はテキスト代などの実費を除いて無料で受けられます。
求職者支援訓練を受けている間は公共職業訓練と異なり、失業給付は受けられませんが、以下の手当を受給可能です。
- 職業訓練受講給付金:月10万円+通所手当
- 寄宿手当:月10,700円(職業訓練を受けている間、家族と離れて生活する場合)
支給するには以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 本人収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月 25 万円以下
- 世帯全体の金融資産が 300 万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- すべての訓練実施日に出席している
(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる各訓練期間の8割以上出席している) - 同世帯の中に同時に給付金を受給して、支援訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に偽りや不正行為により、給付金を支給したことがない
15.再就職手当をもらう
早期に就職が決まったら雇用保険から「再就職手当」という祝い金を受け取れます。再就職手当が支給されるのは、失業保険の給付日数が3分の1以上残っている段階で再就職できたケースです。フリーランスとして独立する場合にも再就職手当はもらえます。
給付残日数が3分の2以上であれば日額手当の70%、給付残日数が3分の1以上であれば日額手当の60%の金額が支給されます。金額的には数十万円単位となるので、心の安定につながるでしょう。
雇用保険からの給付金を受け取るには専門家に相談するのがおすすめ

会社を辞めるとき、お金がないと思っても意外にたくさんの対処方法があります。今この瞬間には手元にまとまったお金がないように思えても、辛い仕事を我慢する必要はありません。
雇用保険からの社会保険給付は、失業者にとって非常に大きな助けとなってくれます。今回紹介した、求職活動支援費、失業保険、再就職手当などを受給するためにはハローワークへの申請が必要です。
書類の準備や手続きを大変に感じる方は、専門家に相談するのがおすすめです。手続きに迷われた場合には便利な社会保険給付金サポートサービスがあるので、ぜひ利用してみてください。