「失業保険の受給期限って延長できるの?」
「1年間留学することにした。帰国後に失業保険をもらうことは可能?」
「失業保険の受給期限の延長方法が知りたい」
と気になっていませんか。
退職後に失業保険を受給しようとしても、すぐに受け取れるとは限りません。
- 怪我
- 病気
- 妊娠や出産
などで働けない場合は、失業保険を受給する資格がないからです。
今現在働けない人は、失業保険の受給期限を「延長」しましょう。
今回は失業保険の「延長手続き」について解説します。失業保険を確実に受け取りたい方はぜひ最後までご覧ください。
目次

社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
失業保険の受給期限は退職して1年以内

失業保険には、退職して1年以内と受給期限が設けられています。受給期限とは、退職してから失業保険を申請できる期間のことです。
つまり、1年以内に申しこなければ無職であっても受給する資格を失ってしまうのです。
可能であれば、退職後早めに申し込んだほうが良いでしょう。
失業保険をすぐに受け取れない人もいる

失業保険は、失業した人が誰でもすぐにもらえるものではありません。失業保険を受け取る条件として
- 雇用保険に加入している
- 働く意思と能力がある
- 就職活動をしている
などが挙げられます。
失業保険は、働く意欲と能力はあるけど就職できていない労働者に支給されるものです。
つまり、働く意思と能力がない人は申請できない制度です。
たとえば、
- 病気
- 怪我
- 妊婦ですぐに働けない
- 出産
- 親族の介護のために退職し、働ける目処がたっていない
などに当てはまる人は失業保険を受け取るのは難しいです。
ただ、1年という受給期限があるので1年後に就職活動を始めても、失業保険を受け取れません。
【知らないと損】失業保険の受給期限は延長できる

受給期限を超えたら、失業保険を申請できないとお伝えしました。とは言っても、すぐに申請できる人ばかりでもありません。
条件を満たせば受給期限を延長できます。
できる人は、
- ケガや病気で就職活動ができない
- 妊娠している
- 3歳未満の子供を育てている
- 60歳以上で定年退職をし、ひとまず休養したい
- 海外勤務の配偶者に同行するため日本で働けない
- 青年海外協力隊による海外派遣・派遣前に研修で働けない
などです。現在の状況が延長できるかどうか不確かな人は、専門家またはハローワークの人に確認すると良いでしょう。
延長すると失業保険の受給を止めた日数分、支給期間を延ばしてもらえます。たとえば病気療養のために50日間失業保険の受給を止めたら、1年と50日後まで失業保険を受け取れます。
受給期限を延長期間できるは最長で3年間です。本来の受給期限は退職後1年間なので、合計して「退職後4年間」まで失業保険を受給できる計算となります。
失業保険の受給期限を延長する注意点

失業保険の受給期限を延長する注意点を3つ紹介します。
- 延長期間中は失業保険をもらえない
- 失業保険の受給額は増えない
- 延長日数を過ぎると受給額が減る
もらえるはずの失業保険がもらえなくなってしまった、とならないためにも注意してくださいね。1つずつ詳しく紹介します。
1.延長期間中は失業保険をもらえない
1つは、延長期間中の生活の問題です。延長すると「失業保険の受給期限」が伸びますが、延長中は失業保険をもらえません。他の方法で生活を維持する必要があります。
2.失業保険の受給額は増えない
失業保険の受給期限を延長しても、失業保険の受給額が増えるわけではありません。
単に受給を先延ばしにする制度です。勘違いしないようにしましょう。
3.延長日数を過ぎると受給額が減る
延長日数を超えてしまうと、受給額を減らされる可能性があります。
受給期限を延長するときには「3か月間」など延長日数を決定されます。延長されるのはその日数だけなので、定まった日数を過ぎても失業保険受給を開始しないと、受給日数が減ってしまう可能性があるのです。
たとえば50日間受給期間を延長した場合、失業保険をもらえるのは1年と50日後までです。50日を過ぎてもすぐに受給を開始せず、60日後に失業保険を受け取り始めたら、10日分もらえなくなる可能性があります。
この問題を回避するため、早めに再受給の申請をしましょう。再受給を申請すると、そのときから失業保険を受給できるので権利を失うリスクがなくなります。再受給の手続き方法については後の項目でご説明します。
失業保険の受給期限を延長する方法4ステップ
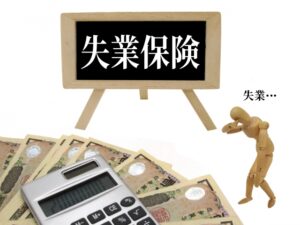
こちらでは、失業保険の受給期限を延長する方法を4ステップで紹介します。
- 失業保険の延長申請
- 延長申請に必要な書類を集める
- 失業保険の受給期間延長申請書を入手する
- 申請書の記入
1つずつ確実にこなすようにしましょう。間違ってしまうと、また一からやり直しになってしまいます。
1.失業保険の延長申請
失業保険の延長申請は、ハローワークで行えます。
申請方法は、
- 本人が窓口で申請する
- 代理人が申請する
- 郵便で書類を提出する
の3つです。
ただし60歳以上の方が定年退職による一時休養として受給期限を延長したい場合、原則的に本人の来所による申請が必要です。
2.失業保険の延長申請に必要な書類
失業保険の延長申請の際、以下の書類が必要です。
- 受給期間延長申請書
- 延長理由を証明できる資料
- 雇用保険受給資格者証
- 離職票-2
- 印鑑
- 預金通帳やキャッシュカード
代理人を通じて申請する場合、上記に足して委任状も必要です。
延長理由を証明できる書類は、診断書や母子手帳などです。雇用保険受給資格者証と離職票は、会社から受け取る必要があります。
3.失業保険の受給期間延長申請書の入手方法
受給期間延長申請書は、ハローワークの窓口または郵送でもらえます。申請書を受け取るだけであれば、委任状なしで家族などの代理人でも受け取れます。
郵送で送ってもらう場合は、ハローワークの雇用保険給付・教育訓練給付窓口に電話をして住所など必要な情報を伝えましょう。
4.失業保険の受給期間延長申請書の書き方
受給延長申請書の記載方法を詳しく説明します。

1.申請者
雇用保険を受け取る本人の氏名や住所、電話番号、性別を書きましょう。
2.3.離職年月日と被保険者番号
「2.離職年月日」「3.被保険者番号」の欄には会社から受け取った「離職票-2」や「雇用保険被保険者証」を見ながら正確に記入しましょう。
4.支給番号
「4.支給番号」の欄は、何も書かなくてかまいません。支給番号は失業保険の受給申請をしてからハローワーク側で決定されるので、申請段階では決まっていません。
5.この申請書を提出する理由
受給期限を延長したい理由を書きましょう。
「イ 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により職業に就くことができないため」と「ロ 定年等の理由により離職し、一定期間求職の申込をしないことを希望するため」の2種類があるので、どちらかを選びます。親族の介護や海外派遣などの選択肢にない事情の場合には、「イ」を選んでください。そして「具体的な事情」の欄に詳細を記入しましょう。
6..職業に就くことができない期間又は求職の申し込みをしないことを希望する期間
ここには「仕事ができないので受給期限を延長してほしい期間」を記入します。
医師の指示などによって休みたい期間がわかっているなら書き込みましょう。わからない場合、空欄でもかまいません。
7.5のイの理由が病気又は負傷の場合
受給延長したい理由が病気や負傷の場合、病気の名称と診療担当者の名前を書きます。診断書を見て、診断名と医師の名称を記入しましょう。
申請日記入、署名押印
最後の欄に申請日と管轄のハローワークの名称を書き、署名押印をすれば申請書が完成します。
上記の書類を揃えて提出すると、ハローワークで書類の審査があり、要件を満たしていれば受給期限が延長されます。その際、いつまで延長されるかも決まります。期限までに状況が変わらなければ再延長申請しましょう。
期限を延長した人が失業保険を受給するには

失業保険の受給期間延長を終了して基本手当を受け取るには、受給申請をしなければなりません。以下の流れで手続きを進めましょう。
- 求職の申し込み
- 雇用保険説明会への出席
- 失業認定
- 失業保険の入金
求職の申し込みは、ハローワークで行えます。7日間の待機期間を終えた後、雇用保険説明会へ出席します。この間に就職をすると失業保険はもらえません。
自己都合退職の場合、3か月の給付制限期間が課されます。ただ受給延長期間も給付制限期間にカウントされるので、3か月以上受給期間を延長した場合には給付制限期間が適用されません。
会社都合退職、病気やけが、介護などのためにやむなく離職した方等の場合、給付制限期間は適用されないのですぐに失業保険を受け取れます。
失業保険を受給するには、1か月に1回ハローワークで就職活動の状況を報告し、失業の認定を受ける必要があります。
受給期限の延長で迷ったら専門家に相談しよう

今は失業保険を申請できないけど、就職活動ができるようになったら申し込みたいと考えている人も多いです。
- 病気
- ケガ
- 妊娠
- 出産や育児
- 介護
などで退職した場合、失業保険の受給期限を延長しておかないと受け取れる金額が減ってしまいます。最悪の場合は、全くもらえないことも。
そうならないためにも、必要に応じて失業保険の受給期限を延長しましょう。
とはいっても、自分で動きを取れない人や方法が分からなくて困っている人もいますよね。社会保険給付サポートの専門会社がおすすめです。
現在のあなたの状況に最も適した方法を伝えてくれます。また申請書の書き方も分かりやすく説明してくれるので、何度もハローワークに行く必要がありません。










