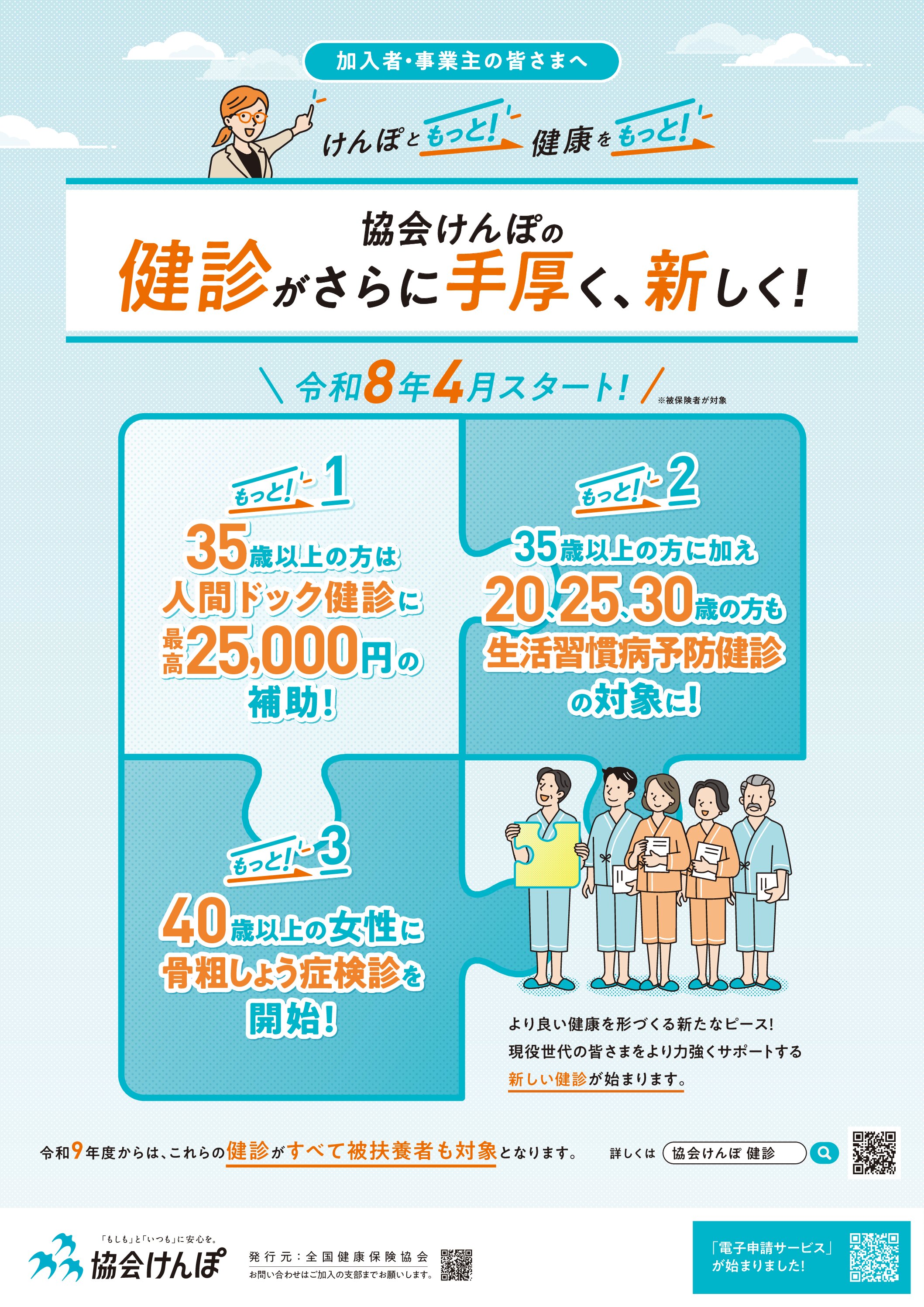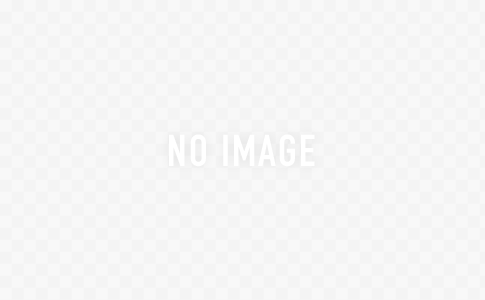退職後の生活で気になるのが「お金をどう確保するか」です。
会社からの退職金がない、あるいは少ない場合でも、社会保険の制度を活用すれば一定の生活資金を確保できます。
条件を満たして申請すれば、数百万円規模のお金を受け取れるケースもあります。
本記事では、具体的なモデルケースを使ってシミュレーションし、退職給付金がどれくらいの金額になるのかをわかりやすく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

退職給付金とは?
「退職給付金」とは、退職後の生活を支えるために社会保険から支給される給付金を指します。
一般的に会社から支払われる「退職金(一時金)」とは異なり、国の制度に基づいて支給されるのが特徴です。
代表的なものは次の2つです。
- 傷病手当金:病気やケガで働けなくなった人に対して、給与のおよそ3分の2が支給される生活補償
- 失業保険(基本手当):離職後に再就職を目指す人が受け取れる生活資金
これらを正しく理解し、制度のルールに沿って順番に活用することで、退職後も安定した収入を確保することができます。
傷病手当金の計算方法
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときに給与の約67%(2/3)が支給される制度です。
計算方法はシンプルで、以下の式で算出されます。
標準報酬日額 × 2/3 × 支給日数
- 標準報酬日額:退職前の給与を30日で割った金額
- 支給日数:休業4日目以降の日数(待機期間3日を除く)
例えば、月給30万円の人であれば、1日あたりの標準報酬日額は約1万円。
これに2/3を掛けた約6,700円が1日の支給額になります。
支給期間は最長で 1年6か月(18か月)。退職後であっても「資格喪失日の前日までに受給要件を満たしている」などの条件を満たしていれば、継続して受け取ることが可能です。
失業保険の計算方法
失業保険(基本手当)は、退職前の給与を基準に算出されます。
基本的な計算式は以下の通りです。
賃金日額 × 給付率(50〜80%) × 支給日数
- 賃金日額:退職前6か月の平均給与を180日で割った金額
- 給付率:年齢や給与水準によって50〜80%の範囲で決定
- 支給日数:雇用保険の加入期間や退職理由によって3〜12か月
例えば、退職前の月給が30万円であれば、賃金日額はおおよそ5,000円前後。
これに給付率を掛けた金額が1日の給付額となります。
なお、自己都合退職の場合は通常3〜5か月分の支給にとどまりますが、ハローワークで「就職困難者」と認定されれば、10〜12か月に延長されるケースもあります。
退職理由や状況によって受給期間が大きく変わるため、自分の条件をしっかり確認しておくことが重要です。
モデルケースでシミュレーション
ここからは、実際に給与水準ごとに退職給付金がどれくらい受け取れるのかを試算してみましょう。
あくまで目安の金額ですが、イメージを持つことで退職後の資金計画を立てやすくなります。
ケース1:月収20万円で退職した場合
- 傷病手当金:約13万円/月 × 18か月 = 約234万円
- 失業保険:約10〜12万円/月 × 3〜10か月 = 約30〜120万円
- 合計:約264〜354万円
ケース2:月収30万円で退職した場合
- 傷病手当金:約20万円/月 × 18か月 = 約360万円
- 失業保険:約15〜18万円/月 × 3〜10か月 = 約45〜180万円
- 合計:約405〜540万円
ケース3:月収40万円で退職した場合
- 傷病手当金:約26万円/月 × 18か月 = 約468万円
- 失業保険:約20〜24万円/月 × 3〜10か月 = 約60〜240万円
- 合計:約528〜708万円
このように、給与が高いほど退職給付金の総額も大きくなり、場合によっては数百万円単位の生活資金を確保できる可能性があります。
退職後の生活設計を考えるうえで、試算してみる価値は十分にあるでしょう。
再就職手当を加えた場合
失業保険を受給中に早期に再就職した場合には、残りの給付日数に応じて 「再就職手当」 を受け取ることができます。
これは、失業保険を最後まで使い切らずに働き始めても不利にならないよう設けられた制度です。
例えば、失業保険の給付がまだ90日分残っている段階で再就職した場合、そのおよそ70%程度が一括で支給されます。
つまり、残りの給付が消えてしまうのではなく、まとまった金額として受け取れる仕組みになっているのです。
この制度により、失業保険を最後まで受給するよりも、早めに安定した職に就いた方が結果的にメリットが大きくなることもあります。
生活の再建がスムーズになり、安心して新しい職場でのスタートを切れるのが大きな魅力です。
退職給付金を最大限もらうための注意点
退職給付金をしっかりと受け取り、退職後の生活を安定させるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
1. 順序を守る
退職給付金は同時に受け取ることができないため、正しい順番で活用することが大切です。
- 病気やケガで働けない間は 傷病手当金
- 回復して働けるようになったら 失業保険
- 早期に再就職できれば 再就職手当
この流れを踏むことで、最長で数年間にわたり生活資金を確保できます。
2. 証明書類を揃える
申請には診断書や離職票、雇用保険被保険者証などが必要です。
必要書類を早めに揃えておくことで、申請がスムーズに進み、支給遅延のリスクを防げます。
3. 申請期限に注意する
- 傷病手当金:時効は2年。遅れるとさかのぼって受給できない場合があります。
- 失業保険:退職後1年以内が原則。療養中に受給できない場合は「受給期間延長」を申請しておくことが重要です。
4. 就職困難者認定を検討する
一定の年齢や条件を満たすと「就職困難者」と認定され、失業保険の受給期間が通常より大幅に延びます。
自己都合退職であっても長期的な生活保障につながるため、該当する可能性がある方は必ずハローワークで確認しておきましょう。
専門家に頼るという選択肢
退職給付金を確実に受け取るには、制度の理解や正しい申請手続きが欠かせません。
しかし、実際には診断書や離職票の取り寄せ、ハローワークや健康保険組合とのやり取りなど、煩雑なプロセスが多く、不安を感じる方も少なくありません。
こうしたときに役立つのが、申請を専門的にサポートしてくれるサービスです。
弊社 「社会保険給付金アシスト」 では、以下のようなサポートを行っています。
- 退職後も傷病手当金を受け取り続けられるよう調整・支援
- 失業保険をできるだけ多く受給できるよう申請方法をアドバイス
- 提携クリニックによるオンライン診療・診断書取得の支援
制度の複雑さに悩むよりも、専門のサポートを活用することで、安心して退職後の生活設計を進めることができます。
まとめ
退職給付金とは、退職後に受け取れる 「傷病手当金」と「失業保険」 を中心とした公的な給付金の総称です。
シミュレーションで見た通り、条件を満たせば数百万円規模の生活資金を確保できる可能性があります。
- 働けないときは 傷病手当金
- 働けるようになったら 失業保険
- 早期就職すれば 再就職手当
この順序を理解し、必要書類をきちんと揃えて申請すれば、退職後の生活を安定させることができます。
制度を上手に活用することが、不安なく次のステップへ進む大きな力になるでしょう。