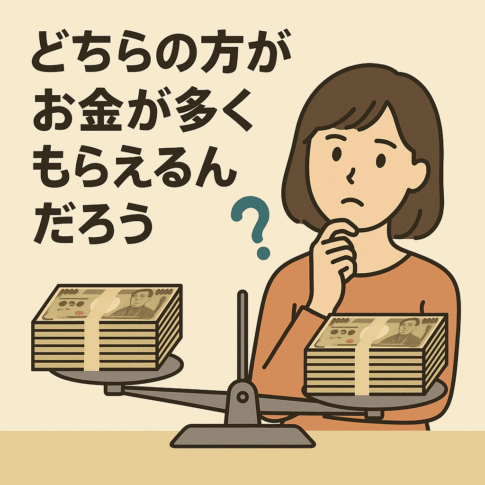「体調がつらくて今はとても働けない」――
そんな状態のなかで、休職して回復を待つか、退職して一旦リセットするかを迷っている方は少なくありません。
特に、うつ病や適応障害など精神的な不調に悩む方にとって、今後の収入や生活費の確保は大きな不安材料です。
この記事では、休職と退職それぞれのメリット・デメリットを制度面から解説し、自分にとって最適な選択ができるよう情報を整理します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

休職と退職、制度的に何が違う?
「体調が悪いけど、休職すべきか、それとも退職すべきか…」と悩んだときに知っておきたいのが、それぞれの制度的な違いです。
どちらを選ぶかによって、使える公的制度や将来の選択肢に大きな差が出てきます。
まず、どちらのケースでも「在職中に初診を受けていれば」傷病手当金は申請可能です。
つまり、休職して療養する場合でも、退職して療養に専念する場合でも、要件を満たせば一定期間の生活費補填は可能です。
しかし、それ以外の制度面には以下のような違いがあります。
- 休職中は失業手当はもらえない
休職中は「働けない状態」とみなされるため、失業手当は受給できません。
一方、退職後であれば、体調が回復したあとに申請可能です。
また、体調がすぐに戻らなくても「就職困難者認定」を受ければ、長く・多く受給できる場合もあります。
→就職困難者になると失業手当はいくらもらえる?通常ケースとの比較で徹底解説 - 社会保険の扱いにも違いがある
休職中は在職扱いのため、社会保険はそのまま継続され、会社が保険料を一部負担してくれます。
退職すると、任意継続や国民健康保険に切り替える必要があり、保険料は全額自己負担になります。 - 精神的なプレッシャーにも差が出る
休職中は「復職」が前提になるため、職場との連絡や復帰のタイミングに悩む人も多いです。
退職すれば、会社との関係が切れるため、気持ちが楽になるという声もあります。
このように、制度面での条件は一見似ていても、今後の生活やメンタル面での影響は大きく異なります。
選択に迷った場合は、自分の体調・職場環境・家計状況を冷静に整理して考えることが重要です。
休職を選んだ方が良いケース
以下のような場合には、まず休職を検討するのが良いかもしれません。
- 病状が比較的軽く、回復後に復職できる見通しがある
- 職場に相談しやすく、理解がある
- 会社の環境や待遇に未練がある(長年勤めてきた、再就職が不安 など)
- 傷病手当金の支給を受けつつ、療養期間を確保したい
休職であれば、在職扱いのまま傷病手当金を受給できるため、医師の指示に従いながら無理なく療養を続けることが可能です。
ただし、最終的には「復職ありき」の制度であるため、復職が困難なケースでは逆にストレスが増すリスクもあります。
退職を選んだ方が良いケース
一方で、次のような状況では退職を検討した方がよい場合もあります。
- 精神的に職場に戻ることが困難(パワハラ・人間関係の悪化など)
- 休職しても復職できる見込みが立たない
- 会社に頼らずに療養・再就職の準備を進めたい
- 傷病手当金と失業手当の両方を視野に入れて収入を確保したい
退職しても、在職中に初診を受けていれば傷病手当金は申請可能です。
さらに、回復後には失業手当や再就職手当も受けられるため、「退職=損」とは限りません。
傷病手当金と失業手当の上手な使い方
退職後に経済的な不安を感じている方の多くが見落としているのが、「傷病手当金」と「失業手当」は両方使えるという点です。
条件を満たせば、これら2つの制度をうまく切り替えて利用することで、長期間の生活支援を受けることが可能です。
まずは在職中に初診を受けておくのがカギ
ポイントになるのが「初診日」です。
退職前に病院を受診しておくことで、傷病手当金の対象になる可能性があります。
初診が退職後だと、制度の対象外になるケースがあるため注意が必要です。
傷病手当金 → 失業手当へと切り替えて支援を継続
たとえば、以下のような流れで制度を活用することができます。
- 在職中に体調が悪化
→ 病院で「うつ病」などの診断を受ける - 退職後、傷病手当金を申請
→ 最大で1年6か月間受給可能 - 体調が回復したらハローワークへ
→ 「就職困難者認定」を受ければ、給付日数が延長される可能性も - 失業手当を申請
→ 最大360日分の支給を受けられるケースも
このように、正しい順序で制度を使えば、合計で2年半以上の経済的サポートを受けることも可能です。
「傷病手当金だけ」あるいは「失業手当だけ」と考えず、両方を組み合わせて活用することで、回復に専念しながら、生活を安定させることができます。
制度に詳しい専門家のサポートを受けることで、損なく、スムーズに申請を進めることができるでしょう。
退職前にやっておくべき5つのこと
退職を決意したとき、心の負担が大きくなるあまり「とにかく辞めたい」という気持ちが先行しがちです。
しかし、辞めた後に「こうしておけばよかった」と後悔する人も少なくありません。
ここでは、退職前に必ずやっておくべき準備を5つに絞ってご紹介します。
- 医療機関を受診しておく(特にメンタル不調の方)
傷病手当金の申請には、在職中の初診が必須条件です。
退職前に「うつ病」などの診断を受けておけば、退職後も傷病手当金を最大1年6か月受給できる可能性があります。 - 会社からもらう書類を確認する
退職時に必要な書類(離職票、源泉徴収票、健康保険資格喪失証明書など)がきちんと用意されているか確認しておきましょう。 - 社会保険と年金の手続き内容を把握しておく
退職後の保険料や年金の切り替えについて、あらかじめ流れを理解しておくことでスムーズな対応ができます。
国民健康保険・任意継続・国民年金の免除など、選択肢も含めて確認しておくのが賢明です。 - 離職理由を整理する
体調不良などやむを得ない理由がある場合、「自己都合退職」でもハローワークに正確に伝えることで就職困難者認定や給付制限の免除が受けられる場合があります。 - 制度の全体像を理解する
退職後には傷病手当金・失業手当・各種免除制度など多くの選択肢があります。
どれをどう使えば損をしないか、自分の状況に合わせて戦略を立てることが重要です。
社会保険給付金アシストでできること
退職や休職を考えるとき、多くの方が「制度が難しそう」「手続きが面倒」と感じ、結果的に体調を悪化させながら働き続けてしまいます。
そんなとき、制度に詳しいサポートがあることで、選択肢が大きく広がります。
社会保険給付金アシストでは、以下のような支援を行っています。
- 傷病手当金や失業手当を中心とした制度設計と受給の流れを個別にご提案
- 協力的な医療機関の紹介や、受診時に気をつけるポイントのアドバイス
- 就職困難者認定を受けるための準備や、ハローワークでの対応方法の支援
- 書類の記入・提出に関する不安や疑問への対応
あなたの体調や状況に合わせて、「損をしない・後悔しない選択肢」を一緒に考え、制度を最大限に活用するサポートを行っています。
まとめ:制度を正しく使えば、休職も退職も「損しない」選択ができる
休職と退職、どちらにもメリット・デメリットがあります。
一番大切なのは、「今の自分の状態」と「これからの回復見込み」に合わせて選ぶこと。
そして、制度を正しく理解して活用すれば、経済的に困窮することなく次のステップへ進むことができます。
「どちらが正解か分からない」「今からでも制度を使えるか不安」という方は、ぜひ一度、制度に詳しい専門サポートを活用してください。
あなたにとって最適な道筋を一緒に見つけましょう。