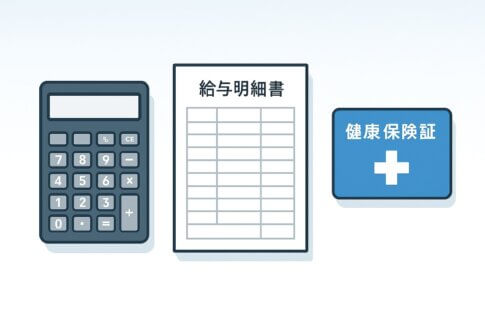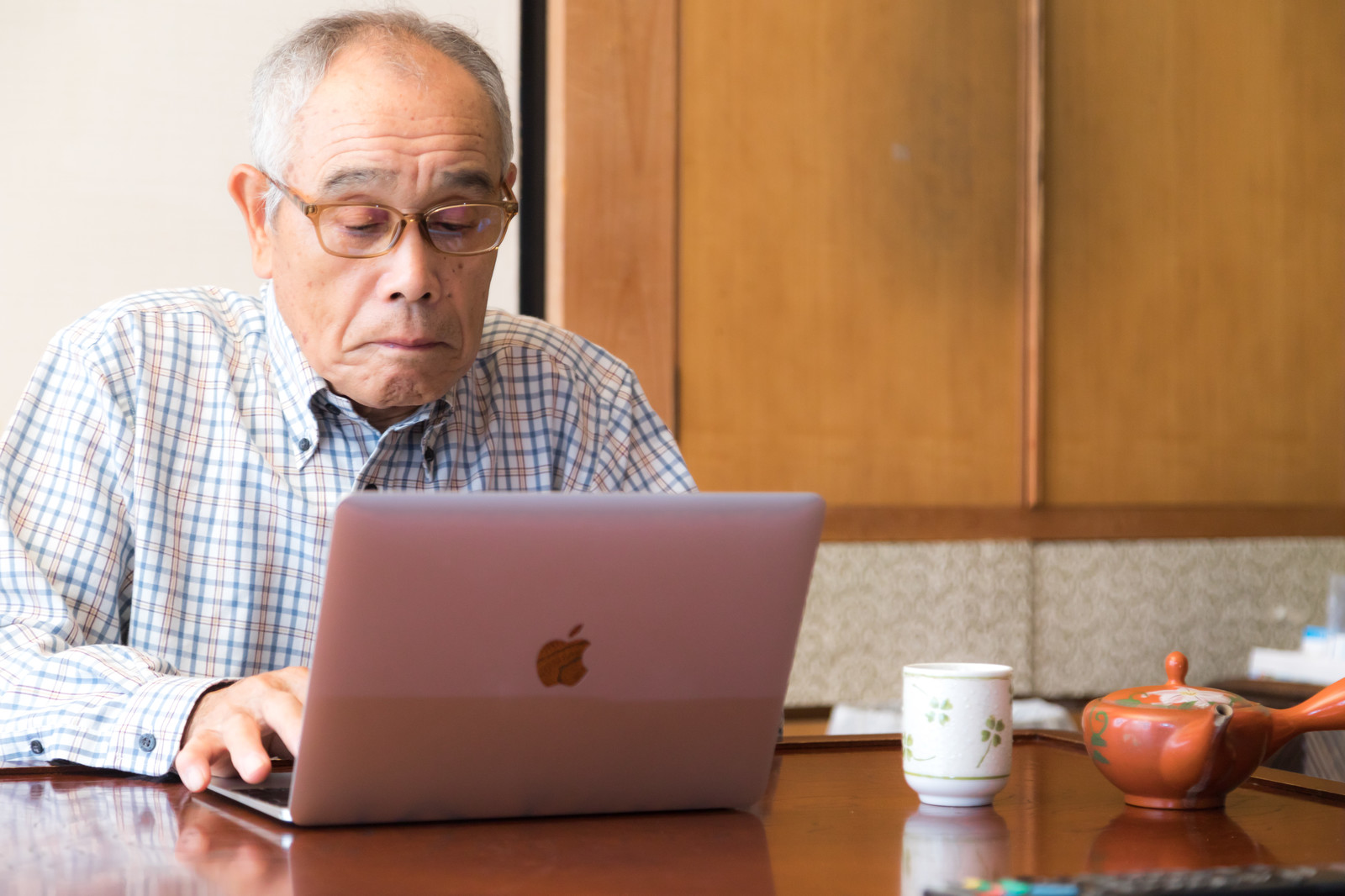うつ病で働けない状態になったとき、「退職しか選択肢がない」と考えてしまう方は少なくありません。
しかし、在職中や休職中にも活用できる公的制度や会社制度は数多く存在します。
これらを正しく理解し、組み合わせて利用することで、生活の安定と治療の継続が可能になります。
本記事では、休職中・在職中・退職後といった状況別に使える制度や給付金を整理し、効率的な活用方法をご紹介します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

うつ病で働けないときに考えるべき選択肢
うつ病で働けない状態になったからといって、必ずしもすぐに退職する必要はありません。
まずは会社に相談し、以下のような選択肢を検討してみましょう。
- 休職制度の利用
就業規則に基づき、一定期間職場を離れて治療に専念できる制度です。
傷病手当金などの収入補填制度と組み合わせることで、生活の安定を保ちながら回復を目指せます。 - 時短勤務
労働時間を短縮し、心身への負担を軽くする方法です。
フルタイム勤務が難しい場合でも、仕事を続けながら収入を確保できます。 - 配置転換
部署や業務内容を変更し、環境そのものを改善する方法です。
人間関係や仕事内容が原因でストレスが蓄積している場合に有効です。
無理に退職してしまうと、収入源を失って生活の不安が増す可能性があります。
まずは在職中に利用できる制度で収入減を補いながら、心身の回復を優先することが重要です。
在職中・休職中に使える制度
在職中や休職中でも、状況に応じて活用できる公的制度があります。
これらをうまく組み合わせることで、収入減や医療費負担を軽減しながら治療に専念できます。
- 傷病手当金(健康保険)
業務外の病気やケガが原因で働けない場合、最長1年6か月間、給与のおよそ3分の2が支給されます。
うつ病による休職も対象となり、生活費の大きな支えとなります。 - 高額療養費制度
医療費の自己負担額が高額になった場合、所得に応じた上限額を超えた分が後日払い戻されます。
入院や薬代がかさんだときに負担を軽減できます。 - 自立支援医療制度(精神通院医療)
精神科や心療内科への通院にかかる医療費が1割負担になる制度です。
長期的な通院治療が必要な場合でも、経済的な負担を抑えられます。 - 障害年金
うつ病で長期間にわたり働くことが難しい場合、障害基礎年金や障害厚生年金の受給対象となることがあります。
生活費の補填だけでなく、将来的な生活設計にも役立ちます。
退職後に使える制度
退職後も、状況に応じて利用できる支援制度があります。
これらを知っておくことで、収入が途絶えた後の生活を安定させやすくなります。
- 失業手当(雇用保険)
自己都合退職であっても、雇用保険の加入期間や就職の意思・能力など一定の条件を満たせば受給可能です。
特に、退職前に傷病手当金を受給していた場合、その後に失業手当を申請する流れを取ることで、受給期間を延ばせる場合があります。 - 住居確保給付金
一定の収入・資産要件を満たす人に対して、最大9か月間、家賃の一部を自治体が補助してくれる制度です。
賃貸住宅に住んでいる方にとって、家計の固定費を軽減できる大きな助けとなります。 - 生活福祉資金貸付(緊急小口資金など)
一時的に生活費が足りない場合、無利子で貸付を受けられる制度です。
緊急小口資金は比較的少額かつ迅速に利用でき、総合支援資金と組み合わせることで長期的な生活支援も可能です。
制度を組み合わせて受給期間を延ばす方法
うつ病で長期間働けない場合、退職前に医師の診断書を取得し、「傷病手当金」→「失業手当」の順で申請することで、条件次第では最大28〜30か月の給付を受けられる可能性があります。
ただし、この方法を成功させるには、申請の順序・期限・書類準備など、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
1. 申請順序とタイミングの戦略
傷病手当金と失業手当は同時に受け取れないため、必ず順番を意識しましょう。
- ステップ1:退職前に医師の診断書を取得
- ステップ2:在職中または退職直後から傷病手当金を申請(最長1年6か月)
- ステップ3:傷病手当金の支給が終了したら失業手当を申請(最長10〜12か月)
この順序を守ることで、最長28〜30か月の給付が可能になります。
逆に、退職後すぐに失業手当を申請してしまうと、傷病手当金が受けられず、受給期間が大幅に短くなるリスクがあります。
2. 申請期限の管理
制度には必ず申請期限があり、期限を過ぎると一切受給できなくなるため注意が必要です。
- 傷病手当金:支給対象期間の翌日から2年以内に請求
- 失業手当:離職日の翌日から1年間以内に受給(延長申請可)
- 住居確保給付金などは申請時点の収入条件を満たす必要があり、遅れると対象外になることも
期限管理はカレンダーやリマインダーを活用し、余裕を持った申請を心がけましょう。
3. 必要書類の事前準備
スムーズに制度を利用するには、退職前から必要書類を揃えておくことが大切です。
主な書類は以下の通りです。
- 健康保険証(傷病手当金用)
- 離職票(失業手当用)
- 医師の診断書(病名・発症日・就労不可期間を明記)
特に診断書は医師の作成に時間がかかる場合があるため、早めの依頼が重要です。
4. 医師との情報共有
診断書は制度申請の合否を左右します。
医師に「どの制度に使用するか」「必要な病名や記載内容」を正確に伝えることで、不支給リスクを減らせます。
例:傷病手当金や失業手当では「うつ病」や「適応障害」など明確な病名が必要。
5. 専門家のサポート活用
複数制度の併用は、申請書の書き方・提出順序・期限管理など複雑な条件が絡みます。
弊社『社会保険給付金アシスト』では、オンライン診療での診断書取得から、複数制度の組み合わせ提案、申請期限の管理、不支給リスク回避まで一括でサポート可能です。
こうした計画的な制度利用は、受給期間の最大化だけでなく、精神的な安心感の確保にもつながります。
退職前から準備を始めることで、数十万円〜数百万円単位の差が生まれることもあります。
アシストを使った制度活用サポート
うつ病で働けない状況に直面したとき、制度を正しく活用するには「どの順番で」「どの書類を」「いつまでに」申請するかという複雑な計画が必要です。
弊社 『社会保険給付金アシスト』 では、この一連の流れを“利用者が自分で迷わず進められる”状態にすることを重視しています。
- 診断書取得のスムーズ化
提携する協力的なオンライン診療クリニックを紹介し、初診予約から診断書発行までを最短ルートで案内。通院が難しい方でも自宅で手続きが完結します。 - あなた専用の制度活用プラン作成
収入・勤務状況・退職時期などを踏まえて、傷病手当金や失業手当を「どの制度から申請すべきか」を個別に設計。 - 申請の失敗を防ぐ仕組み
書類不備や期限切れによる不支給を防ぐため、必要書類の取得・記載内容のチェック・提出スケジュール管理まで伴走します。
さらに、アシスト利用者は退職代行SARABAを無料で利用可能。
仕事を続けられない状況でも、精神的・金銭的負担を最小限にして新しい生活をスタートできます。
まとめ
うつ病で働けないときは、退職後だけでなく在職中や休職中にも活用できる制度が数多く存在します。
これらを上手に組み合わせれば、収入の途絶を防ぎ、生活を安定させながら治療に専念することが可能です。
また、申請の順序や書類の記載内容によっては受給額や期間に大きな差が出るため、専門的なサポートを受けることで最大限のメリットを引き出せます。
まずは無料相談で、あなたが利用できる制度やおおよその受給額を確認してみてください。