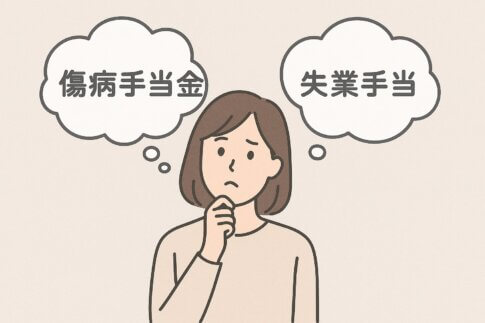「退職後の社会保険の手続きには何がある?」
「退職後にも健康保険を使って病院に行きたい」
「失業保険などの給付をスムーズにもらいたい」
と考えていませんか?
退職後には、これまで会社が負担してくれていた保険料相当分まで自分で負担する必要があるため、家計を逼迫させる恐れがあります。一定の要件を満たせば、負担を抑えて社会保険の利用が可能です。
そこで本記事では、以下のポイントについて解説します。
- 退職後の社会保険の手続き方法
- 退職後の保険料を減額させる方法
- 失業保険を受けるための条件とステップ
- 失業保険を受けるときの注意点
退職後は、次の仕事が見つかるまでさまざまな負担があるため、なるべく金銭的な負担は減らしたいものです。本記事を読むことで、退職後の社会保険や給付の手続きをスムーズに行えるようになるでしょう。
目次

社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
社会保険とは

社会保険とは、会社に勤める人を対象に加入義務がある保険制度の総称です。広義に社会保険と呼ばれる制度は、以下の5つです。
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
狭義での社会保険は健康保険、介護保険、厚生年金保険を指します。このとき、雇用保険と労災保険は労働保険と呼ばれます。社会保険は、労働者が安全かつ健康に生活するための制度で、要件を満たす人は加入が必要です。
退職後の社会保険の手続き方法3選

ここでは、退職後の社会保険の手続きについて解説します。
- 国民健康保険と国民年金に加入する
- 家族の被扶養者となる
- 任意継続被保険者になる
どれを選択するかによって負担は大きく異なるので、家庭の事情をしっかり考慮することが大切です。
1.国民健康保険と国民年金に加入する
退職後は原則として国民健康保険と国民年金に加入します。国民健康保険は、会社勤めの方の健康保険に相当する制度で市町村が運営元です。一方、国民年金は国が運営している年金制度です。
国民健康保険と国民年金に加入すると、自分で保険料を支払う必要があります。国民健康保険は前年の所得によって決まりますが、国民年金の保険料は一律です。退職後には、会社が負担してくれなくなるため自己負担分が多くなります。
2.家族の被扶養者となる
会社勤めなどをしている家族の扶養に入れてもらうのも1つの方法です。社会保険の扶養とは労働者の配偶者や親、子どもなどの親族を同じ社会保険に加入させることです。扶養に入ることで、自分自身は保険料を支払うことなく健康保険証をもらえます。
ただし、扶養に入るためには以下のような条件を満たす必要があります。
- 扶養者によって生計を維持されていること
- 年収が一定額以下であること
年収については、130万円以下であることが原則ですが、60歳以上の方は180万円以下であることが条件です。
また、家族の扶養に入る方の収入証明書や住民票などの書類が必要なのであらかじめ用意しておきましょう。
3.任意継続被保険者になる
任意継続に入る方法もあります。任意継続とは退職後の2年間に限って引き続いて在職時と同じ社会保険に入る制度です。
任意継続被保険者となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 退職までに2か月以上、健康保険の被保険者期間があること
- 退職後に20日以内に在職時に加入していた健康保険組合または協会けんぽに任意継続の申請をすること
任意継続被保険者となれば、家族の扶養を継続できる反面、保険料を全額自己負担する必要があります。会社に在職時は保険料の半分は会社が負担してくれていましたが、退職後の任意継続では本人が全て負担する必要があるのです。
扶養家族の有無によっては国民健康保険の方が保険料が安く済む場合があるため、どちらの方が安く済むかについて検討が必要です。
退職後の保険料が減額される3つのパターン

退職後の保険料が減額されることがあります。
- 本人の意に反する退職である
- 所得が一定額以下である
- 国民年金保険料の猶予または免除を受けている
1つずつ詳しくみていきましょう。
1.本人の意に反する退職である
退職が本人の意に反する場合には、社会保険料が減額されます。例えば以下のような場合です。
- 会社が倒産した
- 会社に解雇された
- 雇止めにあった
- 退職勧奨を受けた
- 天災等によって事業の継続が困難となった
このような事由によって所得が大幅に減少した場合に、減額措置を受けられます。自己都合ではなく会社都合で退職した場合に国民健康保険料が減額されます。
2.所得が一定額以下である
所得が一定額以下の場合にも、国民健康保険料が減額されます。減額される率は7割、5割、2割のいずれかであり、世帯全体の所得を勘案して決定されます。自己都合退職の場合でも減額の対象です。
3.国民年金保険料の猶予または免除を受けている
退職後は、所得に応じて国民年金の保険料の猶予や免除を受けられます。免除には以下の4種類があります。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
免除された分は、後から追納が可能です。追納しない場合には、将来受け取る年金額が少なくなるというデメリットがあります。
国民年金の猶予についても、猶予を受けた期間分は10年以内であれば遡って納められますが、こちらも追納しない限りは将来の年金額が少なくなるので注意が必要です。
雇用保険から失業保険を受けるための2つの要件

失業保険を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者期間が一定以上ある
- 失業状態であると認められている
いざ受給しようとして条件を満たしておらず不支給とならないために、詳しくみていきましょう。
1.雇用保険の被保険者期間が一定以上ある
失業保険を受けるためには、退職前の雇用保険の加入期間が2年の間に12か月以上あることが求められます。1ヶ月ごとに区分された各期間について、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 賃金の支払いとなった基礎日数が11日以上あること
- 労働時間が80時間以上あること
11日未満かつ80時間未満の月は要件を満たせずカウントしないので、注意が必要です。
2.失業状態であると認められている
失業保険を受けるためには、失業状態であることが求められます。失業状態であるためには、以下の全てに該当する必要があります。
- 積極的な就職の意思がある
- 心身ともに健康でありいつでも就職できる
- 就職活動を積極的に行っているが職が見つからない
出産や育児などをしている方の場合は「いつでも就職できる」状態ではないので条件を満たしません。
失業保険を受給するための5ステップ

失業保険を受給するためのステップについてみていきます。
- 離職票を発行してもらう
- 求職の申し込みをする
- 雇用保険説明会に参加する
- 失業認定を受ける
- 受給開始
1つひとつのステップをしっかり確認することで、スムーズに失業保険を受給できるでしょう。
1.離職票を発行してもらう
まずは、退職した会社から離職票を発行してもらいましょう。離職票には、退職までに支払われた賃金や出勤日数、退職の理由などが記されています。
2.求職の申し込みをする
離職票を持参してハローワークで求職申し込みを行います。ハローワークでは受給資格となる「失業の状態である」ことの確認が行われます。この際には、以下の書類が必要です。
- 身元確認書類
- 写真
- 金融機関の通帳
- 印鑑
求職申込書に、就きたい仕事や希望の収入などを記入します。
3.雇用保険説明会に参加する
雇用保険説明会では失業保険を受けるための手続きや、就職活動について説明を受けます。このときに、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ります。
自己都合退職の場合と会社都合退職の場合で失業保険を受けられるまでの期間は異なるので、注意しましょう。
4.失業認定を受ける
失業保険を受けるためには、ハローワークで4週間に1度失業状態であることの認定を受ける必要があります。このときには、積極的に就職活動を行い就職の意思があるかについても確認されます。
5.受給開始
失業の認定を受けた日数分だけ、失業保険を受給できます。失業保険はあらかじめ登録した金融機関に振り込まれます。
失業保険を受ける際の2つの注意点

失業保険を受ける際には、以下の点に注意が必要です。
- 求職活動を継続する必要がある
- 不正受給にならないようにする
1.求職活動を継続する必要がある
失業保険を受け続けるためには、積極的な就職活動を継続することが求められます。失業保険は新たな職が見つかるまでの生活を支えるための給付であり、就職の意思のない人には支給は行われません。そのため、4週間に1度ハローワークに出向き失業認定を受ける必要があるのです。
2.不正受給にならないようにする
失業保険を受ける際には、不正受給にならないようにしましょう。失業保険は、就職した場合には支給はされません。実際は働いているのに受給したり、就職できない状態になったのに申告しないといった場合には不正受給となります。
不正受給をすると返還金額が3倍となるなどペナルティが大きいので、注意が必要です。
退職後の手続きや給付申請で悩んだら専門機関に相談しよう

退職後は、在職時のような社会保険料の会社負担分がなくなり、全て自己負担となります。負担を軽減するためには、家族の扶養に入ったり免除制度を利用したりとできることはたくさんありますが、どの選択肢を取ればよいか迷う方もいるでしょう。
また、失業保険についても自己都合退職と会社都合退職の場合は受け取れる金額は違うため、損をしている方もいます。
社会保険に関することでお悩みの際は社会保険アシストにおまかせください。専門家がお悩みに沿った最適なソリューションを提示いたします。