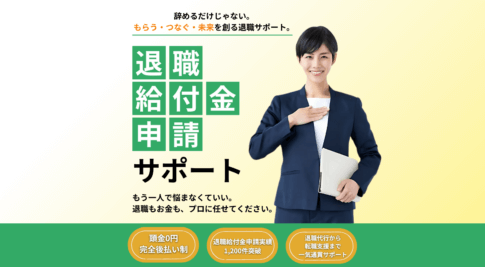適応障害で仕事を休んだり、退職したりしたときに「傷病手当金はもらえないの?」「退職後でも申請できるの?」と不安に感じる方は多いでしょう。
結論から言えば、適応障害でも条件を満たせば退職後でも傷病手当金を受け取ることは可能です。
ただし、申請内容に不備があったり、退職タイミングを誤ったりすると「もらえない」ケースも少なくありません。
この記事では、適応障害で傷病手当金をもらえない理由・いくらもらえるのか・デメリット・退職後の注意点・申請方法まで、わかりやすく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

結論:適応障害でも傷病手当金はもらえる(退職後もOK)
傷病手当金は、病気やけがで働けなくなったときに、健康保険から支給される生活補償制度です。
業務外の理由で働けない状態にあるときに利用でき、うつ病や適応障害などの精神疾患も対象となります。
適応障害の場合も、医師から「労務不能(仕事ができない状態)」と診断され、一定の条件を満たしていれば問題なく受給できます。
また、退職したあとでも、在職中に初診を受けており、退職時点で治療継続中であれば『退職後の継続給付』として支給対象になります。
つまり、「退職後はもうもらえない」というのは誤解です。
大切なのは、“退職前に受診しておくこと”です。
実際の申請手順や必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
適応障害で傷病手当金がもらえない主なケース
適応障害であっても、条件を満たしていなければ傷病手当金がもらえないことがあります。
ここでは実際に多い不支給の原因と、その対策を紹介します。
① 医師の診断書に「就労可能」と書かれている
診断書に「労務可能」「軽作業可」などの記載があると、ハローワークや健康保険組合は「働ける」と判断します。
その結果、支給対象外とされるケースが多いです。
医師には「仕事に支障がある状態」であることを正確に伝えましょう。
② 初診日が退職後になっている
最も多い不支給理由がこれです。
傷病手当金は“在職中に初診を受けていること”が大前提のため、退職後に初めて通院した場合は対象外になります。
退職を決める前に一度、心療内科や精神科を受診しておくことが重要です。
③ 社会保険の加入期間が短い
一般的には、1年以上の加入があることが望ましいとされています。
ただし、勤務実態や退職時期によっては1年未満でも受給できる場合もあります。
詳細は健康保険組合に確認しましょう。
④ 会社の証明欄が未記入
申請書の「事業主記入欄」に不備があると、健康保険組合で受理されません。
担当者の押印忘れ・記載漏れなど、思わぬミスが原因で支給が遅れることも。
提出前に必ずコピーを取り、記載漏れがないかチェックしておきましょう。
⑤ 受診日と休職日の整合性が取れていない
「休職前に通院していた」「初診日より先に欠勤していた」など、日付の整合性が取れないと審査で疑義が出ます。
受診日・休職日・退職日を正確に記録し、必要に応じて診療明細や勤怠記録で裏づけを取りましょう。
退職前に心療内科や精神科で受診し、「労務不能(働けない状態)」と診断してもらうことが最も重要です。
このタイミングを誤ると、受給資格を失ってしまう可能性があります。
不支給の原因や対策をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
適応障害で傷病手当金はいくらもらえる?
傷病手当金の支給額は、働けない期間の生活費を一定程度カバーする目的で設けられています。
そのため、いくらもらえるのかを知っておくことは非常に重要です。
支給額の計算式
支給額 = 標準報酬日額 × 3分の2
たとえば月収30万円の場合、1日あたりの支給額はおよそ 6,600円前後、
1か月あたりで換算すると 約20万円程度 が目安となります。
この金額は、会社から給与が出ない期間でも一定の収入を確保できるように設計されています。
つまり、働けない期間も「社会保険による最低限の生活保障」が受けられる仕組みです。
支給される期間と開始時期
傷病手当金の支給期間は、最長で1年6か月(18か月)。
同じ病気が再発しても、合計でこの期間を超えて受給することはできません。
また、支給開始のタイミングにもルールがあります。
初めの3日間は「待期期間」とされ、この期間は支給されません。
4日目以降から支給が始まる仕組みになっています。
(例)
- 1月1日〜3日:待期期間(支給なし)
- 1月4日〜:4日目以降から支給開始
退職後も支給されるケース(継続給付)
「退職したらもう傷病手当金はもらえない」と思っている人も多いですが、実はそうではありません。
退職前に受診していて、退職時点で療養を継続している場合は、「資格喪失後の継続給付」として退職後も支給が続きます。
つまり、在職中に医師の診断を受けていれば、退職後でも制度を利用できるのです。
退職した後の扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
傷病手当金をもらう前に知っておきたい注意点
傷病手当金はとても助かる制度ですが、申請前にいくつか注意点があります。
後で困らないよう、代表的な4つをチェックしておきましょう。
① 会社に病名が知られる可能性
傷病手当金申請書の医師の意見欄には病名が記載されるため、会社の担当者が内容を確認することになります。
どうしても気になる場合は、人事や上司など最小限の範囲だけに共有してもらうようお願いしましょう。
安心して休職するためには、職場の理解を得ることも大切です。
② 転職時に「休んでいた期間」を聞かれることがある
前職の在籍期間は履歴書などでわかりますが、その会社で傷病手当金を使っていたかどうかまでは分かりません。
ただし、退職後に一定期間ブランクがある場合は、「その間は何をしていましたか?」と聞かれることがあります。
そのときは、療養していたことを正直に伝える程度で問題ありません。
③ 支給まで1〜2か月かかる
申請から入金まで時間がかかるため、最初の1〜2か月は生活費の備えが必要です。
記入漏れや押印忘れがあるとさらに遅れるので、提出前にしっかり確認しておきましょう。
④ 退職後の手続きはやや複雑
退職しても受給は可能ですが、「資格喪失後の継続給付」など手続きが少し増えます。
退職前に受診して診断書をもらっておくことがスムーズに進めるポイントです。
こうした注意点はありますが、傷病手当金は治療に専念するための大切な支えになります。
もし「申請したのに振り込みが遅い」「生活費が不安」という場合は、原因と対処法をまとめたこちらの記事も参考にしてください。
傷病手当金をもらうための条件と退職後の申請方法
「退職したあとでも傷病手当金はもらえるの?」という質問はとても多いです。
結論から言うと、条件を満たしていれば退職後でも受給可能です。
ただし、申請のタイミングや書類の準備を間違えると、不支給になることもあります。
ここでは、退職後にもらうための条件と申請の流れをまとめます。
退職後でももらえる条件
退職後に傷病手当金を受け取るには、次の4つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 社会保険に継続して1年以上加入している
退職前までに健康保険(社会保険)へ継続して1年以上加入していること。 - 在職中に初診を受け、「労務不能」と診断されている
退職前に医師から働けない状態と診断されていること。
退職後に初診を受けた場合は対象外です。 - 3日間の待機期間を満たしている
連続した3日間の休職(待期)を終えてから退職していること。 - 退職日当日に出勤していない
退職当日は出勤しないこと。
出勤すると「退職日時点で労務可能」と判断され、退職後は支給対象外になります。
この4つを満たしていれば、退職後でも傷病手当金を受け取ることができます。
退職後の申請方法と流れ
退職後に傷病手当金を申請する流れは、以下の6ステップです。
難しそうに見えますが、順番に進めればそれほど複雑ではありません。
① 初診を受けて「労務不能」の診断をもらう
まずは心療内科や精神科を受診し、働けない状態(労務不能)と診断してもらいます。
この初診日が「退職前」であることがとても重要です。
② 再診時に、医師に申請書の記入を依頼する
再度受診したときに、傷病手当金申請書の医師記入欄を記載してもらいます。
診断書は不要で、この医師欄の記入が代わりになります。
③ 会社に「事業主証明欄」を記入してもらう
会社が在職中の勤務状況や給与支払い状況などを記入します。
退職後でも、連絡すれば対応してくれることがほとんどです。
④ 自分の記入欄を書く
住所・振込口座・休職期間など、本人記入欄を記載します。
記入漏れがあると審査が遅れるので、提出前に一度コピーを取って確認しておきましょう。
⑤ 健康保険組合へ申請書を提出する
すべて記入が終わったら、在職中に加入していた健康保険組合または協会けんぽに提出します。
郵送でOKです。
⑥ 審査・支給決定(2週間〜1か月後)
提出からおおよそ2週間〜1か月程度で結果が届きます。
支給が決定すると、指定した口座に傷病手当金が振り込まれます。
診断書を別途提出する必要はなく、申請書一式で完結する手続きになっています。
焦らずに順を追って進めれば、スムーズに受給までたどり着けます。
詳しい申請書の書き方や提出時の注意点は、こちらの記事で解説しています。
まとめ:適応障害でも条件を満たせば退職後も傷病手当金はもらえる
適応障害で仕事を続けるのが難しくなっても、条件を満たしていれば退職後でも傷病手当金を受け取ることができます。
もう一度ポイントを整理すると――
- 退職前に初診を受け、「労務不能」と診断されていること
- 社会保険に1年以上加入していること
- 3日間の待機期間を満たしていること
- 退職日に出勤していないこと
この4つを満たしていれば、退職後でも受給可能です。
申請手続きはやや複雑に感じるかもしれませんが、診断書は不要で申請書1枚で完結します。
流れを理解して準備すれば、スムーズに受給まで進められます。
もし「自分の場合も対象になるのか分からない」「申請が難しくて不安」という方は、
社会保険給付金アシストにご相談ください。
専門スタッフがヒアリングを行い、受給可能性の確認から書類の準備まで丁寧にサポートします。