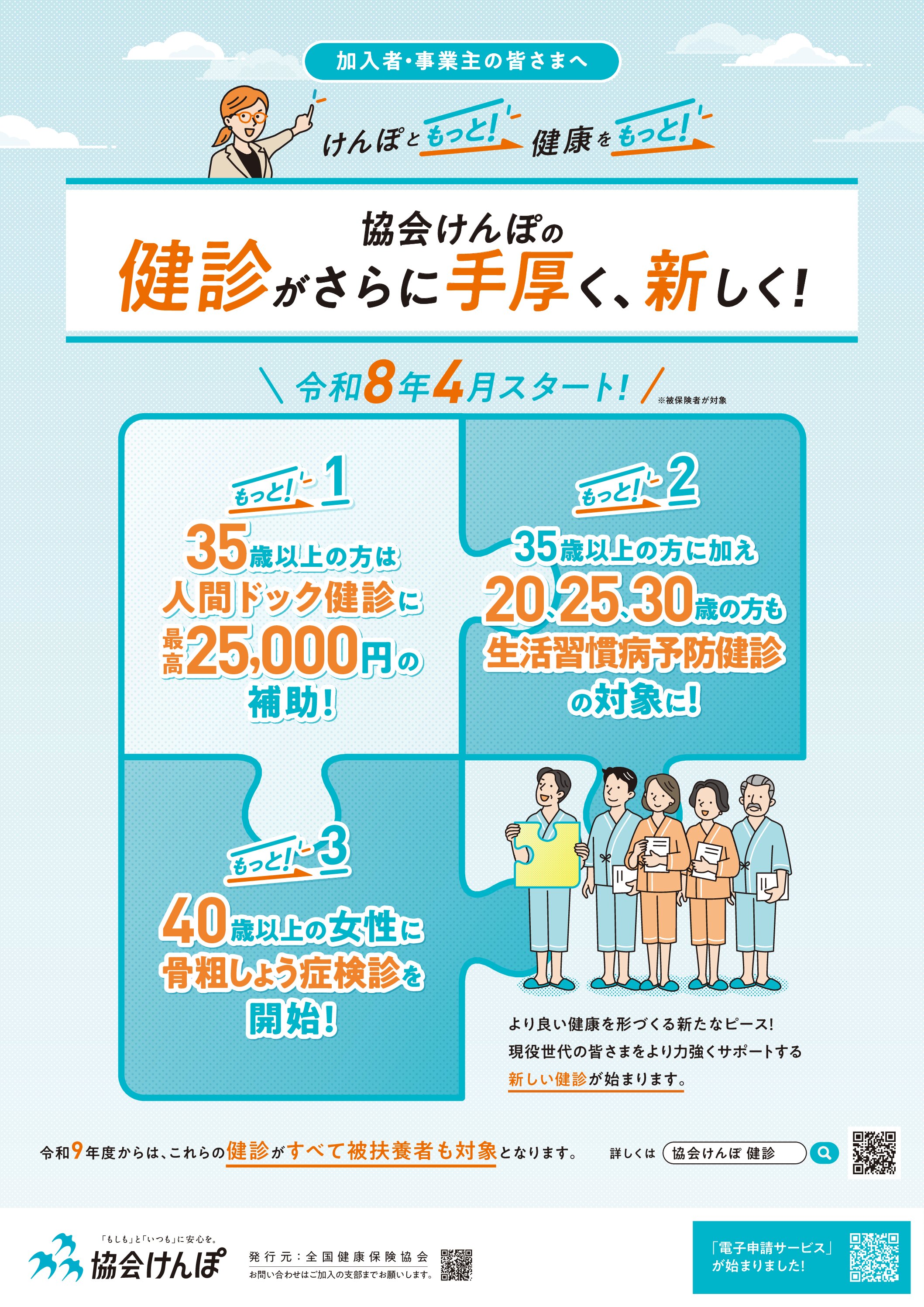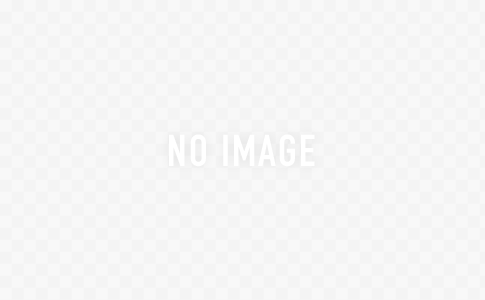「お金がないのに働きたくない」──
そんな気持ちを抱えているあなたへ。
まず伝えたいのは、それは怠けではなく、心と体からのSOSです。
現代社会では、疲弊して動けなくなる人が増えています。
この記事では、無理をせず最低限の生活を守るための“現実的な生存戦略”を紹介します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

まず「働かない自分」を責めないことから始めよう
働きたくないのにお金がない状態は、焦りと罪悪感が入り混じる非常に苦しい状況です。
しかし、「働けない」には必ず理由があります。
長時間労働、メンタル不調、人間関係、経済的ストレス――
どれも心身を限界まで追い詰める要因です。
社会では「働かない=悪」とされがちですが、一度立ち止まることは“生きるための戦略”です。
あなたが疲れ果てているなら、それは立ち止まるタイミングです。
まずは「自分を責めない」ことから始めましょう。
最低限の生活費を守るための3つの柱
働けなくても、生活を支える仕組みはいくつもあります。
重要なのは、「すぐに働こう」と焦るのではなく、制度を上手に組み合わせて生活費を確保することです。
ここでは、最低限の生活を守るための3つの柱
――「収入を確保する」「支出を減らす」「支えを得る」――について解説します。
1. 収入を確保する(給付金・貸付金制度)
まず最初に考えるべきは、今すぐに生活費の“流れ”を止めないこと。
公的な給付金や貸付制度を利用すれば、一定期間の生活費を確保できます。
傷病手当金
在職中に体調を崩した人が対象で、給与の約3分の2が最長1年半支給されます。
退職後でも「退職前に初診を受けている」場合は申請可能です。
失業手当(雇用保険)
働ける状態に回復したら、ハローワークで申請しましょう。
自己都合退職でも給付制限は2025年以降1か月に短縮されています。
さらに、うつ病などで「就職困難者」と認定されれば、最長300日(45歳以上の場合360日)まで給付期間が延長されることもあります。
緊急小口資金・総合支援資金
無利子で最大20万円前後を借りられる制度で、社会福祉協議会が窓口です。
返済が難しい場合、返済免除が認められるケースもあります。
生活困窮者自立支援制度
自治体の福祉課で相談すれば、生活費の支援や就労支援を受けられます。
「今すぐ現金が必要」「家賃を払えない」といった相談にも対応しています。
2. 支出を減らす(免除・猶予制度)
収入を増やすだけでなく、「出ていくお金を減らす」ことも大切です。
保険料や税金は、事情を伝えれば免除・猶予が受けられることがあります。
国民年金保険料の免除・猶予
所得に応じて全額または一部が免除され、免除期間も将来の年金額に反映されます。
支払いを止めるより、必ず「免除申請」を出すのがポイントです。
国民健康保険料の減免
退職などで収入が減った場合、自治体に申請すると保険料が軽減されることがあります。
市区町村の国保窓口で相談しましょう。
住民税・公共料金の支払い猶予
役所や電力・ガス・水道会社に相談すれば、一時的な猶予が認められることもあります。
支払いを止める前に、必ず「相談する」ことが重要です。
住居確保給付金
家賃を自治体が肩代わりしてくれる制度で、最長9か月間支援を受けられます。
家賃の支払いが難しい場合は、早めの申請が生活維持のカギです。
3. 支えを得る(相談窓口・支援サービス)
経済的に苦しいときほど、一人で抱え込まないことが大切です。
相談するだけで利用できる制度が見つかるケースも少なくありません。
社会福祉協議会
緊急小口資金・総合支援資金の申請窓口です。
生活再建に向けた相談も可能です。
自治体の福祉課
生活困窮者自立支援、家賃補助、就労支援などを総合的に案内してくれます。
法テラス・自立支援センター
借金、家賃滞納、離職トラブルなど、法的な問題も無料で相談できます。
社会保険給付金サポート会社(民間サービス)
最近では、社会保険制度の申請をサポートする民間の給付金サポート会社も増えています。
傷病手当金や失業手当など、複数の制度を横断的に整理し、申請の流れをサポートしてくれるのが特徴です。
一般的なサポート内容としては、次のようなものがあります。
- 提携クリニック紹介(オンライン診療)
- 医師の診断書取得や申請書類の書き方サポート
- 退職理由や離職票内容の確認アドバイス
- ハローワークや健康保険組合との手続きサポート
- LINE・メール・電話・ZOOMなどによる相談対応
公的機関では手が回らない細かなフォローまで行ってくれるため、
「制度の仕組みが難しくてよく分からない」「どの順番で申請すべきか整理できない」といった人にとって、現実的な選択肢の一つです。
「お金がないけど働けない」ときは、焦らず、まずは制度と支援を最大限に活用すること。
国や自治体、そして民間サービスを上手に組み合わせることで、生活の基盤を守ることができます。
「働かずに過ごす期間」を設計する
無計画に「とりあえず休む」と、途中で生活費が途切れてしまうことがあります。
安心して療養するためには、どの制度をどの順番で使うかを把握しておくことが大切です。
1. 医師に相談し、初診を受ける(退職前)
まずは医師の診察を受けることから始めましょう。
傷病手当金を利用するには「退職前に初診を受けていること」が条件です。
この初診日が基準となるため、退職を決める前に必ず受診しておくのがポイントです。
2. 退職手続きと書類整理
初診を済ませたら、退職の準備を進めます。
離職票・健康保険資格喪失証明書・源泉徴収票などは、会社に「発行をお願いします」と必ず伝えておきましょう。
これらはのちに保険の切り替え手続きやや失業保険の申請で必要になるため、早めに依頼しておくのが安心です。
3. 年金・住民税の免除申請
退職後は収入がなくなるため、年金や住民税の免除・減免申請を市区町村で行います。
申請しておけば督促や延滞を防げるので、早めの行動が安心です。
4. 傷病手当金を申請して生活費を確保
健康保険加入者であれば、退職後も傷病手当金を受け取れます。
退職前に初診を受けていれば、最長1年半、給与の約3分の2が支給されます。
この期間は治療と生活立て直しに専念しましょう。
5. 傷病手当金が終わったら → 失業保険に切り替え
体調が回復して働ける状態になったら、失業手当(基本手当)を申請します。
うつ病などで「就職困難者」と判断されると、最大300日(45歳以上の場合360日)まで延長されます。
自己都合でも給付制限は1か月に短縮されているため、スムーズに切り替え可能です。
6. 失業保険申請後:住居確保給付金・国保の減免申請
住居確保給付金や国民健康保険料の減免は、原則として失業保険申請後に対象となります。
そのため、傷病手当金を受けている間は利用できず、受給が終わってから切り替える流れになります。
ただし、自治体によっては離職日以降にさかのぼって国保の減免を適用してくれる場合もあります。
その際、すでに支払った保険料の一部が還付される可能性もあるため、申請時に窓口で「遡及適用ができるか」確認しておきましょう。
いずれも自治体ごとに条件が異なるため、早めの相談が安心です。
まとめ:順番を守れば「無収入期間」は最小限に
制度を正しく組み合わせれば、働かずに過ごす期間でも生活を守ることができます。
- 医師に相談・初診を受ける
- 退職手続き・書類整理
- 年金・住民税の免除申請
- 傷病手当金を申請
- 終了後に失業保険へ切り替え
- 失業保険申請後に住居給付金・国保減免
この流れを意識すれば、「働かない期間」を安心して過ごす計画が立てられます。
社会保険給付金アシストによるサポート
退職後の手続きは、「どの制度を、どの順番で使うか」によって受け取れる金額が大きく変わります。
しかし、実際には制度が複雑で、「自分が何に該当するのか分からない」「申請の書類が難しい」と悩む人も少なくありません。
そこで役立つのが、社会保険給付金アシスト のサポートです。
アシストでは、うつ病などで働けなくなった方を対象に、各種給付金の申請をトータルで支援しています。
- 傷病手当金サポート:提携クリニック紹介、初診から申請書類の取得まで一貫サポート。
- 失業手当サポート:就職困難者認定や、離職票の記載確認を丁寧にサポート。
- 住居確保給付金・各種減免制度の案内:退職後の生活支援策までフォロー。
- 再就職手当、就業促進定着手当の申請サポート:再就職後の賃金差補填までサポート。
また、年中無休・24時間対応で、LINEやメール相談はもちろん、電話・ZOOM面談も回数無制限。
成果報酬ではなく固定料金制のため、安心して相談できます。
制度を自力で調べるのが難しい方や、手続きの順番に不安がある方は、
こうした専門サポートを活用することで、無理なく確実に受給まで進めることができます。
まとめ:焦らず、制度を使って「立て直す時間」をつくろう
「お金がないのに働けない」と感じているとき、最も大切なのは焦って無理をしないことです。
うつ病などで心や体が限界に達しているときに再び働こうとしても、長くは続きません。
今回紹介したように、傷病手当金・失業手当・住居確保給付金・国保の減免など、
働かなくても生活を支える制度は複数あります。
順番を間違えずに申請すれば、収入ゼロの期間を最小限に抑えることができます。
制度の仕組みが複雑で不安なときは、社会保険給付金のサポート会社や専門窓口に相談することも一つの選択肢です。
正しい手続きを踏めば、あなたの生活は必ず守られます。
立ち止まることは、逃げではなく「次に進むための準備期間」です。
今は無理をせず、制度を活用して“自分を取り戻す時間”を大切にしてください。