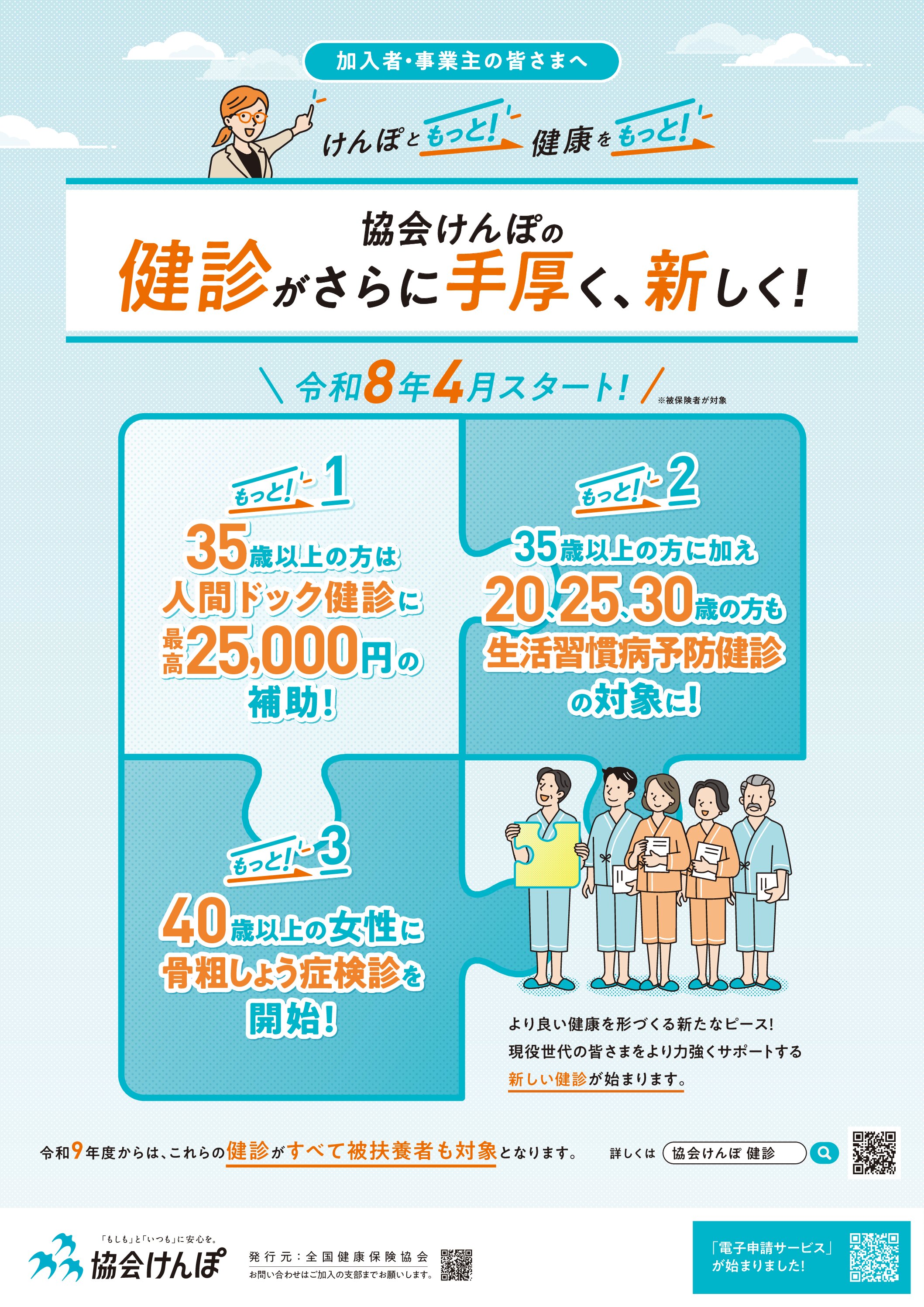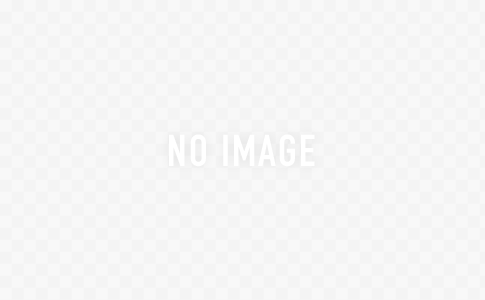「うつ病でつらいのに仕事を休めない」「辞めたいのに辞められない」という状況に悩んでいる方は少なくありません。
責任感や経済的不安から無理を続けてしまうと、心身に深刻なダメージを与える可能性があります。
本記事では、うつ病なのに仕事を休めない理由、無理を続けるリスク、そしてどうしても辞められないときの最終手段、さらに退職後に生活を守る給付金制度までを解説します。
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

うつ病でも仕事を休めないと感じる理由
うつ病の症状が出ていても「休めない」「辞められない」と感じてしまう人は少なくありません。
その背景には、真面目で責任感の強い人ほど抱きやすい“思い込み”や“周囲の空気”があります。
ここでは代表的な4つの理由を紹介します。
職場に迷惑をかけたくない
「自分が休むと同僚に負担をかけてしまう」と考えて、無理をして出勤する人は多いです。
しかし、その我慢が症状を悪化させ、長期休職や退職につながることもあります。
短期的には周囲を気遣っても、長期的には逆効果になることもあるのです。
上司や同僚の理解が得られない
「気の持ちよう」「根性で乗り越えろ」と言われ、精神的な不調を軽視されるケースもあります。
こうした職場では「休む=怠けている」と見られることを恐れて無理をしてしまいがちです。
しかし、うつ病は気の問題ではなく治療が必要な病気。
理解されない職場では、専門家への相談を優先しましょう。
「休む=甘え」という思い込み
責任感の強い人ほど「休むのは甘え」と思い込みやすいものです。
けれど、限界まで我慢すれば症状は悪化します。
「休むことも仕事の一部」と考え、早めに休養を取ることが自分と職場を守ることにつながります。
経済的不安
「休んだら生活できない」と不安に感じ、無理に働き続ける人もいます。
しかし、社会保険の制度を活用すれば休職中も収入を補える場合があります。
たとえば傷病手当金を利用すれば、給与の約3分の2が最長1年半支給されるため、経済的不安を減らすことができます。
無理をして働き続けることは、結果的に自分にも職場にも悪影響を及ぼすリスクがあります。
「休めない」ではなく、「どうすれば安心して休めるか」を考えることが、回復への第一歩です。
無理を続けるリスク
「まだ大丈夫」と思って無理を続けると、心身の状態は確実に悪化していきます。
うつ病は努力で克服できるものではなく、放置すれば回復に何倍もの時間がかかることもあります
ここでは、仕事を休まずに頑張りすぎたときに起こりやすい3つのリスクを簡潔にまとめます。
症状の悪化
体調不良を我慢し続けると、うつ病の症状が進行し、集中力の低下や不眠、無気力などが強くなっていきます。
結果的に長期間の療養が必要になり、復職までに何ヶ月、場合によっては1年以上かかるケースもあります。
突発的な欠勤・退職
限界を超えると、ある日突然出勤できなくなることがあります。
これはいわゆる“燃え尽き”の状態で、急な欠勤や退職に発展すれば、自分にも職場にも大きな負担となります。
無理を感じた段階で、医師や上司に早めに相談することが大切です。
再就職への影響
症状が重くなると療養期間が長引き、再就職のハードルも上がります。
逆に、早めに休養を取り「傷病手当金」などの制度を活用すれば、生活を安定させながら回復に専念できます。
無理をしないことが、結果的に社会復帰を早める最善の選択です。
頑張り続けることが美徳とされがちですが、休む勇気こそが本当の自己管理です。
どうしても休めないときの対処法
「体調がつらいのに休めない」「周りに言い出せない」と悩んでいる場合でも、できることはあります。
いきなり退職を決断する前に、まずは正しい手順で環境を整えることが大切です。
ここでは、うつ病でも休めないときに取るべき現実的な対処法を紹介します。
医師に相談し、診断書をもらう
最初の一歩は、医療機関を受診して医師の診断を受けることです。
「忙しいから」「大げさにしたくない」と我慢してしまう人も多いですが、診断書があれば会社に休職を申し出る際の強い根拠になります。
また、診断書の有無が「傷病手当金」の支給にも関係するため、早めに医師へ相談しておくことが重要です。
産業医や人事に相談する
会社によっては、従業員の健康を守るために産業医や人事部の相談窓口が設けられています。
体調や勤務状況を正直に伝えれば、勤務時間の短縮や在宅勤務などの調整を提案してもらえることもあります。
「完全に休む」だけでなく、「少しでも働きやすい形を探す」ことも選択肢の一つです。
就業規則の確認
多くの企業では、就業規則に休職制度の内容や期間、手続きの流れが明記されています。
どのような条件で休職できるのか、給与や社会保険の扱いはどうなるのかを確認しておくと、余計な不安を減らせます。
必要であれば上司や人事に「制度について確認したい」と伝え、正式なルールに基づいて行動しましょう。
辞められないときの最終手段「退職代行」
「もう限界なのに、上司に辞めたいと言えない」「話す気力すら残っていない」——
そんなときに頼れるのが、退職代行サービスです。
本人に代わって退職の意思を伝えてくれるため、会社と直接やり取りする必要がありません。
退職を切り出せない人のためのサービス
退職代行は、LINEやメールで依頼でき、やり取りもすべて代行業者が対応します。
特にうつ病の状態では、人と話すこと自体が大きなストレスになることもあります。
退職代行を使えば、精神的な負担を最小限に抑えながら退職手続きを進められます。
即日退職も可能
法律上、労働者には退職の自由が認められており、退職代行を利用すれば即日退職も可能です。
「辞めさせてもらえない」「引き継ぎが終わるまで待て」と言われても、法的には退職を妨げることはできません。
翌日から出勤せずに退職を完了できるケースも多く、心身を守るための現実的な選択肢です。
退職代行SARABAの特徴
中でも 退職代行SARABA は、即日退職の実績が多い業界大手です。
LINEで簡単に依頼でき、夜間や休日も対応してくれる柔軟さが高く評価されています。
「会社に連絡するのもつらい」という状況でも、安心して任せられるサービスです。
退職は逃げではなく、自分を守るための行動です。
限界を感じたら、退職代行という方法で環境をリセットする勇気を持ってください。
退職後に生活を守る「給付金」
退職後は「この先どうやって生活していけばいいのか」と不安を感じる方が多いでしょう。
しかし、社会保険の制度を正しく活用すれば、働けない期間の生活を支える資金を確保することができます。
ここでは、退職後に利用できる代表的な給付金をわかりやすく紹介します。
傷病手当金
うつ病などの療養が必要な場合、健康保険に加入していれば傷病手当金を受け取ることができます。
支給額は給与の約3分の2で、最長で1年6か月間受給可能です。
療養中でも収入を確保できるため、「休みたいけど生活が心配」という方にとって非常に心強い制度です。
失業手当
退職後に求職活動を行う場合、雇用保険から失業手当(基本手当)が支給されます。
受給期間は退職理由や勤続年数によって異なりますが、一定期間、生活費を補える仕組みになっています。
特に精神的な理由で退職した場合、条件を満たせば就職困難者扱いとして長期間の支給を受けられる可能性もあります。
両方を組み合わせて受給する方法
状況によっては、「傷病手当金」→「失業手当」という順で両方を受け取ることができます。
この組み合わせにより、最大で約30か月近くの給付を受け取ることも可能です。
しっかりと手順を踏めば、退職後の生活を長期間安定させることができます。
給付金サポートの活用
傷病手当金や失業手当は、自分で申請することも可能ですが、実際には手続きが複雑で、医師の診断書や役所への提出書類など、多くの準備が必要になります。
特に体調がすぐれない時期にこれらを一人で進めるのは、大きな負担となりがちです。
そこで近年は、給付金の申請を専門的にサポートするサービスが注目されています。
これらのサービスでは、必要書類の取得方法や申請の流れをわかりやすく案内し、状況に応じて医療機関やハローワークとの調整まで支援してくれる場合もあります。
「自分でやるのは不安」「手続きで失敗したくない」という方にとって、こうした給付金サポートを活用することで、
制度をより確実かつ安心して利用できるようになります。
まとめ
うつ病でつらい状態でも、「仕事を休めない」「辞められない」と感じてしまう人は多くいます。
しかし、無理を続けることで症状が悪化し、長期的に見れば回復や再就職が難しくなるリスクもあります。
まずは医師や会社に相談し、必要であれば休職制度を活用することが第一歩です。
それでも状況が変わらない場合は、退職代行などの専門サービスを利用して環境をリセットすることも選択肢の一つです。
退職後は、傷病手当金や失業手当といった制度を活用すれば、生活を支えながら回復に専念することができます。
大切なのは「我慢すること」ではなく、「自分の心と体を守ること」。
制度やサポートを上手に使い、安心して次の一歩を踏み出しましょう。