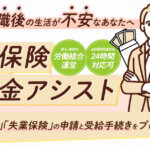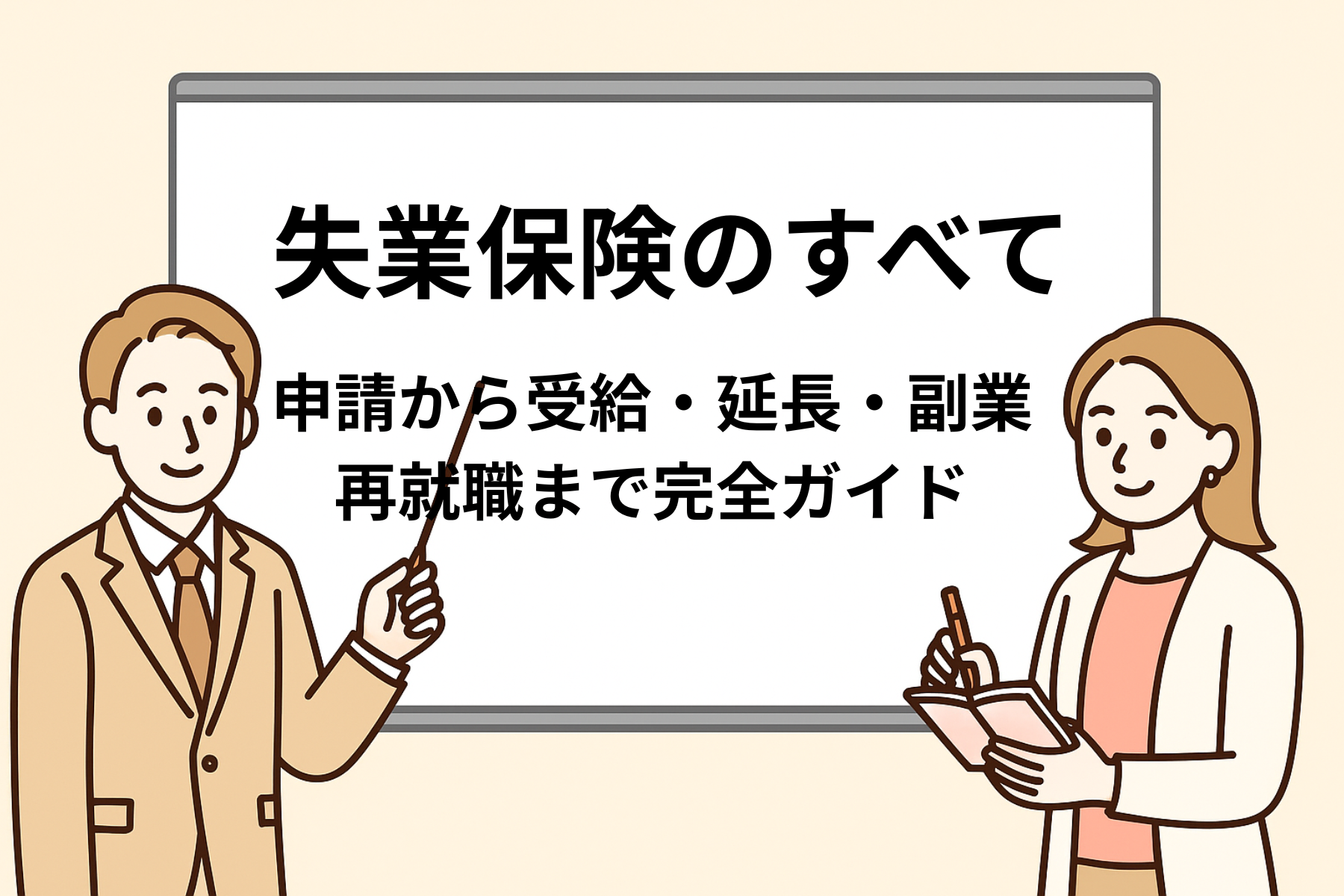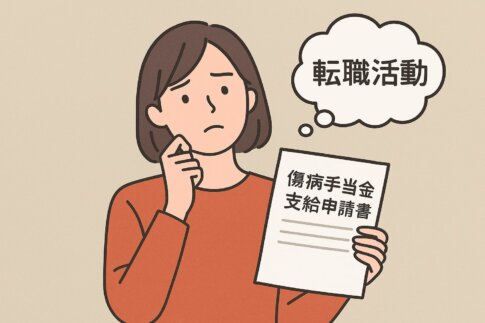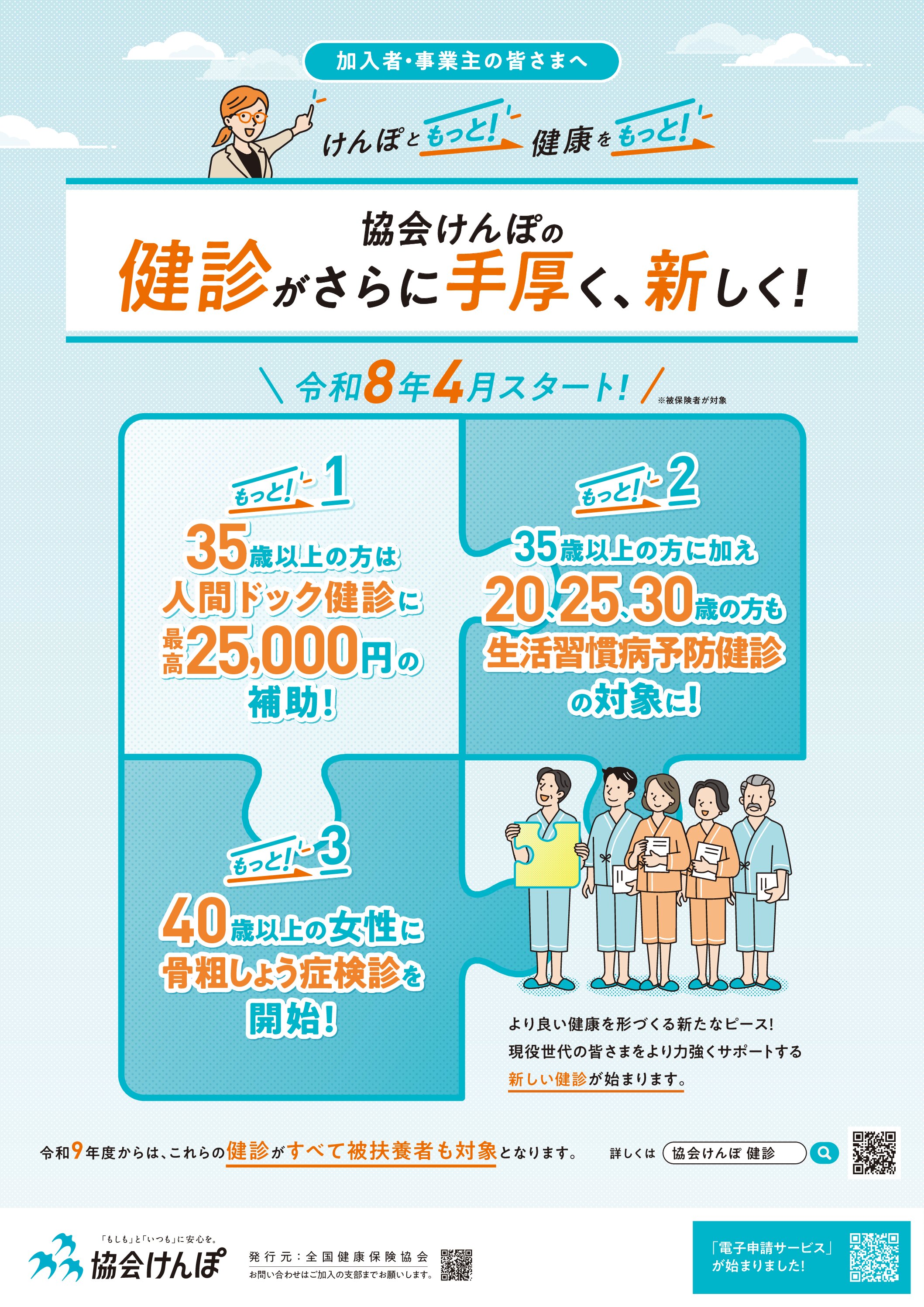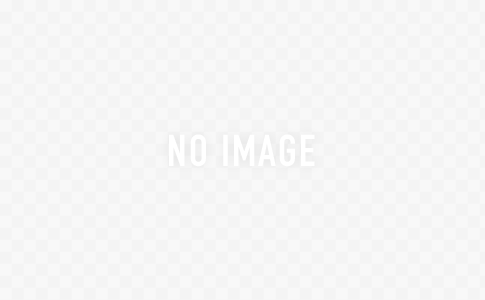うつ病で仕事ができなくなると、「収入がなくなって生活できないのでは…」という不安に直面します。
しかし、実際には複数の公的な制度を利用することで生活費を補うことが可能です。
代表的なのは「傷病手当金」「失業保険」「障害年金」といった給付金。
さらに医療費を軽減できる制度や、生活に困ったときの支援策も整っています。
本記事では、うつ病で働けないときに利用できるお金の仕組みをまとめて解説します。
「働けない=収入ゼロ」ではありません。
制度を知って準備することで、生活の安心につなげましょう。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

うつ病で働けなくても生活費を守る制度はある
「うつ病で働けない=収入ゼロ」というイメージは強いですが、実際には制度を活用すれば収入をある程度確保できます。
例えば、会社員であれば傷病手当金が最長1年半支給され、給与の約3分の2を受け取ることが可能です。
さらに退職後には失業保険、症状が長引けば障害年金や生活支援制度も選択肢になります。
つまり「辞めたら収入が途絶える」というのは誤解であり、制度を組み合わせれば生活費を安定的に確保する方法があるのです。
最初に検討すべきお金の制度
公的制度の中でも、最初に検討すべき代表的なものは次の2つです。
傷病手当金(会社員向け)
うつ病で休職する場合、まず検討したいのが傷病手当金です。
- 対象者:健康保険に加入している会社員
- 条件:業務外の病気やケガで、連続4日以上働けず、給与が支給されない場合
- 支給額:給与のおおむね3分の2
- 支給期間:最長1年6か月
一定の条件を満たせば、給与の約3分の2が最長で1年半支給されるため、生活費をカバーする大きな支えとなります。
失業保険(退職後)
退職した場合でも、条件を満たせば失業保険を受け取れる可能性があります。
- 対象者:雇用保険に加入していた人
- 条件:離職票の提出+医師の意見書により「就職困難者」と認定される場合あり
- 支給期間:通常90〜150日だが、就職困難者認定を受けると最大300日(45歳以上の場合360日)まで延長可能
うつ病で退職すると「働けないから失業手当はもらえない」と誤解されがちですが、実際には医師の意見書次第で通常より長く給付を受けられるケースがある点は見逃せません。
この2つ(傷病手当金・失業手当)は、まず最初に検討すべき基本的な制度です。
ここで生活の基盤を整えた上で、さらに長期的な支援制度へとつなげていきましょう。
長期的な生活を支える制度
もし症状が長引いたり、収入が途絶えてしまったときには次の制度が頼りになります。
障害年金
うつ病が慢性化したり、症状が重くなって長期的に働くことが難しい場合は、障害年金の対象になる可能性があります。
- 対象者:うつ病など精神疾患で長期間にわたり日常生活や就労が制限されている人
- 条件:初診日から1年6か月後に障害状態が続いていること、かつ保険料納付要件を満たしていること
- 支給額:等級によって異なり、障害基礎年金・障害厚生年金のいずれかが支給される
申請には医師の診断書や初診日の証明が必要ですが、認定されれば長期的に安定した収入源となります。
生活保護・住居確保給付金
「貯金も収入も尽きてしまった…」という場合には、生活保護や住居確保給付金といった制度が最後のセーフティネットとなります。
- 生活保護:最低限度の生活を保障する制度。資産や収入の状況に応じて受給できるかが判断されます。
- 住居確保給付金:離職や収入減で家賃が払えない場合に、一定期間家賃相当額を支援してもらえる制度。
どちらも申請のハードルはありますが、生活の立て直しを支える大切な制度です。
このように「傷病手当金や失業手当ではカバーできない長期のケース」に備えて、障害年金や生活支援制度も選択肢に入れておくことが重要です。
医療費を軽減できる制度
生活費だけでなく、医療費の負担を減らす制度も整っています。
自立支援医療制度
うつ病の治療は長期にわたることが多く、通院にかかる医療費は大きな負担になります。
そこで活用したいのが自立支援医療制度です。
- 精神科や心療内科での通院医療費が1割負担になる
- 長期的に通院が必要なうつ病患者にとって大幅な負担軽減となる
経済的な理由で通院を控えてしまうリスクを減らすことができ、治療を継続しやすくなります。
高額療養費制度
もう一つ押さえておきたいのが高額療養費制度です。
- 医療費が高額になった場合、自己負担額に上限が設けられている
- 上限を超えた分は払い戻される仕組み
- 入院や長期治療が必要なケースで特に安心できる
突発的に医療費がかさんでも、上限以上の自己負担が戻ってくるため、生活費の計画が立てやすくなります。
うつ病の治療は「時間」と「費用」がかかるもの。
こうした医療費軽減制度を活用することで、経済的な負担を和らげ、安心して治療に専念できる環境を整えられます。
公的な減免制度を申請して負担を減らす
うつ病で働けないときは、収入が減るだけでなく、社会保険料や税金といった固定的な出費が重くのしかかります。
こうした負担を軽減できる減免制度を申請しておくことが重要です。
国民健康保険料の減額・免除
退職後に収入が大幅に減った場合、市区町村に申請することで保険料を軽減できることがあります。
関連記事:国民健康保険(国保)の支払いが厳しいときは?減免申請と放置リスクをわかりやすく解説
国民年金保険料の免除・猶予制度
所得が少ないときは全額または一部の免除を受けられます。
将来の年金額は減りますが、受給資格期間にはカウントされるため安心です。
関連記事:退職後の国民年金、払えないなら免除できる?条件や手続きまとめ
住民税の減免制度
失業や大幅な所得減少があった場合、市区町村に申請すれば住民税が減額または免除される場合があります。
関連記事:退職して住民税が払えないときはどうする?減免・分割・放置リスクまで徹底解説
これらの制度を使うことで、生活費の固定的な支出を抑え、働けない期間の負担を軽減できます。
制度は自治体ごとに条件が異なるため、早めに役所に確認して申請しておくことが大切です。
お金以外のサポート制度
うつ病で働けないときに利用できるのは給付金や医療費の制度だけではありません。
精神的な支えや、再び働くための準備を助けてくれるサポート制度もあります。
就労移行支援事業所
復職や新しい働き方を目指す人を支援する施設です。
就労に必要なスキルを学んだり、生活リズムを整える練習をすることができ、社会復帰へのステップとして活用できます。
地域の相談窓口
自治体やハローワークには、制度の利用方法や生活に関する相談を専門的に受け付ける窓口があります。
「自分に合った制度が分からない」というときは、まずここで相談してみると安心です。
社会福祉協議会の貸付制度
「緊急小口資金」や「総合支援資金」といった貸付制度を利用すれば、一時的に生活費を借りられます。
返済の猶予や免除の仕組みもあり、困ったときの頼れる選択肢のひとつです。
このように、お金の直接的な支援だけでなく、心のサポートや社会復帰を後押しする仕組みを利用することで、生活再建の可能性が広がります。
まとめ
うつ病で仕事ができなくなると、「生活費をどうやって確保すればいいのか」と不安になるのは自然なことです。
ですが、傷病手当金や失業手当といった短期的な支援から、障害年金や生活保護などの長期的な制度まで、状況に応じて利用できる仕組みは整っています。
さらに、自立支援医療制度や高額療養費制度を活用すれば、医療費の負担も大きく抑えることができます。
大切なのは、自分に合った制度を早めに確認し、準備しておくことです。
制度を正しく活用すれば、働けない期間を安心して過ごし、生活再建の第一歩を踏み出すことができます。
私たち 社会保険給付金アシスト では、失業手当や傷病手当金をはじめとした各種制度を最大限利用できるようサポートを行っています。
「自分の場合はどの制度が使えるのか不安…」という方は、ぜひ一度ご相談ください。