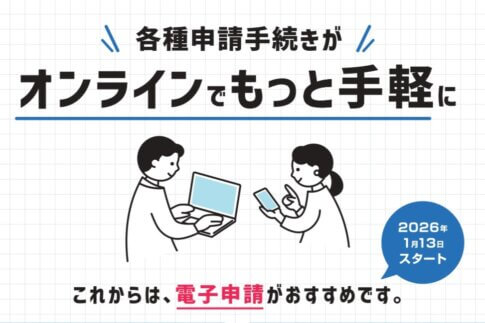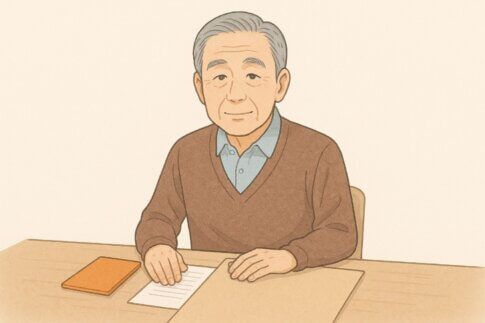住居確保給付金は、失業や収入の減少で家賃の支払いが困難になった人を対象に、最大9か月間家賃を支援してくれる制度です。
家を失わずに生活を立て直すための強力なサポートですが、メリットだけではなくデメリットも存在します。
制度の仕組みをよく理解せずに利用すると、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性もあります。
本記事では、住居確保給付金のデメリットと利用前に知っておくべき注意点、その対策を詳しく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

住居確保給付金とは?
住居確保給付金は、厚生労働省が実施する「生活困窮者自立支援制度」の一部で、離職や休業などで家賃の支払いが難しくなった人を対象に、最大9か月間の家賃を支援してくれる制度です。
- 対象者:離職、休業、収入減少により住居を失う恐れのある人
- 支給内容:原則3か月(最長9か月)分の家賃相当額
- 支給方法:自治体から大家や不動産会社へ直接振り込み(本人の口座には入らない)
- 利用要件:収入・資産の基準を満たすこと、就職活動を行うこと
一見すると頼もしい制度ですが、申請から実際の利用に至るまでにはいくつかの注意点があります。
条件を満たしていないと「利用できなかった」「思ったより支援されなかった」と後悔するケースも少なくありません。
結論:住居確保給付金には大きなデメリットがある
住居確保給付金は、短期的に家賃を支えてくれる心強い制度です。
しかし一方で、利用条件や仕組みには多くの制限があり、長期的な生活再建の手段としては不十分なのが実情です。
収入や資産の要件が厳しかったり、支給まで時間がかかったりと、利用前に理解しておくべきデメリットが存在します。
ここからは、具体的な注意点を5つに分けて解説します。
住居確保給付金の主なデメリット
1. 申請条件が厳しい
住居確保給付金は誰でも利用できるわけではありません。
- 収入が地域ごとに設定された上限を超えている場合は対象外
- 一定額以上の貯金があると利用不可
- 利用中は定期的に「就職活動の実績報告」が必要
特に就職活動を怠ると、途中で給付が打ち切られるケースもあります。
制度を利用するためには、日々の生活だけでなく報告の管理も欠かせません。
2. 支給までに時間がかかる
申請をしてすぐに家賃が支払われるわけではありません。
役所による書類審査や確認作業に時間がかかり、実際に支給が始まるまで1か月以上かかるケースも多いです。
その間の家賃は自分で工面しなければならないため、滞納や督促に悩む人も少なくありません。
3. 現金が手元に入るわけではない
住居確保給付金は、本人の銀行口座に振り込まれるわけではなく、大家さんや不動産会社に直接振り込まれる仕組みになっています。
そのため、自由に使えるお金は増えません。
生活費や食費、光熱費の不足に悩んでいる場合には「思ったより助からなかった」と感じることもあります。
4. 最長9か月で終了する
支給期間は原則3か月、延長を含めても最長9か月までです。
支給が終われば通常通り家賃を支払う必要があり、収入が安定していないと再び困窮してしまうリスクがあります。
「とりあえず今をしのぐため」の制度であり、長期的な生活再建には別の対策が必要です。
関連記事:住居確保給付金の裏ワザとは?延長申請で最長9か月まで受給する方法を解説
5. 再利用が難しい
住居確保給付金は、原則として同じ世帯では再利用できません。
一度利用してしまうと、次に困ったときには頼れない制度です。
このため、「本当に必要なタイミング」で利用することが求められます。
言い換えれば、最後のセーフティーネットの一つとして位置づけられている制度だといえます。
デメリットを回避・軽減するための対策
住居確保給付金にはさまざまな制約がありますが、事前に対策を取ることでデメリットを最小限に抑えることができます。
ここでは、具体的な5つのポイントを紹介します。
1. 事前確認を徹底する
まずは、自分が制度の対象に当てはまるかをしっかり確認しましょう。
収入や資産の条件は自治体ごとに細かく設定されており、少しでも基準を超えると不支給になるケースがあります。
条件が分かりにくい場合は、役所の窓口に相談するか、専門家のアドバイスを受けるのが安心です。
2. 支給までの生活費を確保する
申請してから実際に家賃が支給されるまでには時間がかかります。
1か月以上待たされることもあるため、その間の生活費や家賃をどう工面するかが重要です。
親族に一時的に支援を頼む、地域のNPOや民間支援制度を活用するなど、事前に資金繰りの計画を立てておきましょう。
3. 就職活動を計画的に進める
給付を受け続けるためには、就職活動を継続して行い、定期的に報告する必要があります。
ハローワークで求人検索をした履歴や、面接に参加した記録を残しておくと安心です。
「証明できる形」で活動を積み重ねることが、給付継続の鍵となります。
4. 他制度との併用を検討する
住居確保給付金だけで生活を支えるのは難しい場合もあります。
状況によっては、生活保護、傷病手当金、雇用保険の失業給付など、他の制度と併用できるケースがあります。
自分にとって最も有利な制度の組み合わせを把握し、複数の制度を賢く活用することが生活再建への近道です。
関連記事:退職後の家賃補助(住居確保給付金)と失業保険は両方もらえる?受給条件や受給金額を詳しく解説!
5. 終了後を見据えた準備
住居確保給付金は最長でも9か月で終了します。
支援が終わった後の生活を見据えて、利用中に資格取得や転職活動を進めておくことが大切です。
「今の支援をどうつなげるか」を考えながら行動することで、制度終了後に再び困窮するリスクを減らせます。
これらの対策を実践することで、制度の弱点をカバーし、安心して住居を確保できる可能性が高まります。
住居確保給付金の利用が向いている人/向いていない人
住居確保給付金は、誰にでも適している制度ではありません。
利用を検討する際は、自分の状況と制度の特性が合っているかどうかを見極めることが大切です。
ここでは「向いている人」と「向いていない人」の特徴を整理します。
向いている人
- 一時的に収入が減少している人
- 再就職の見込みがある人
- 例えば、契約満了や一時的な休業で収入が途絶えたが、再就職活動を進めている人
こうしたケースでは、住居確保給付金を利用することで、住まいを失わずに生活を立て直す時間を確保できます。
向いていない人
- 恒常的に収入が不安定な人
- 長期的な生活支援が必要な人
このような場合には、住居確保給付金は最長9か月で終了してしまうため、根本的な解決にはつながりません。
生活保護など、より長期的な支援制度の利用を検討した方が適しているケースがあります。
判断のポイント
住居確保給付金は「一時的なピンチをしのぐ制度」としては非常に有効ですが、長期的な安定を求める人には不十分です。
制度の対象になるかどうかだけでなく、「今この制度を使うべきかどうか」を冷静に判断することが重要です。
まとめ
住居確保給付金は、家賃の支払いを一時的に支えてくれる心強い制度です。
しかし、収入や資産の条件が厳しかったり、支給が遅れることがあったり、利用期間が最長9か月に限られているなどのデメリットも存在します。
制度を十分に理解しないまま申請すると、「支給されなかった」「途中で打ち切られた」といった失敗につながるリスクがあります。
だからこそ、事前に正しい知識を持ち、必要に応じて専門的なサポートを活用することが大切です。
弊社 「社会保険給付金アシスト」 では、住居確保給付金だけでなく、失業保険や傷病手当金など複数の制度を組み合わせて、最も有利な申請方法を提案しています。
確実に給付を受け、生活を立て直すためのサポートを行っていますので、不安を感じている方はお気軽にご相談ください。