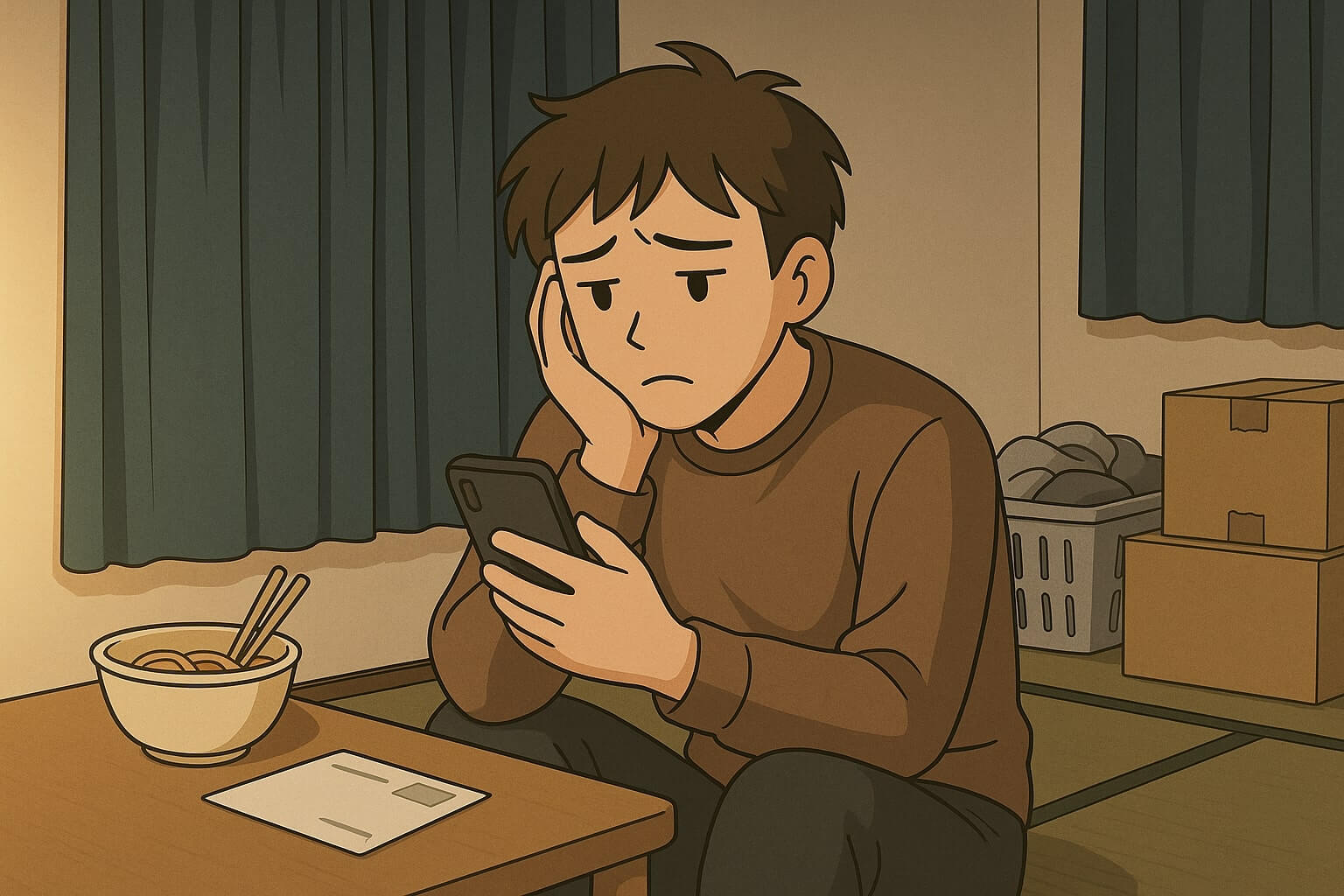一人暮らしは自由で快適な反面、すべての生活費を自分ひとりでまかなわなければならず、想像以上にお金がかかるものです。
この記事では、一人暮らしにかかる代表的な生活費の目安を紹介するとともに、節約のコツや使える制度、支出の見直し方法なども解説していきます。
「一人暮らしって実際どれくらいお金がかかるの?」
「毎月の支出を減らすにはどうしたらいい?」
「収入が不安定だけど、一人暮らしを続けられる?」
そんな悩みをお持ちの方に向けて、今すぐ使える知識をまとめました。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

一人暮らしにかかる生活費の内訳(都内の場合の目安)
東京都内で一人暮らしをする場合、毎月の生活費は想像以上にかかることがあります。
特に家賃の比率が高いため、収入とのバランスを見誤ると、生活が苦しくなりやすいのが現実です。
以下は、都内で一人暮らしをする際の代表的な生活費の目安です。
| 項目 | 月額目安(円) |
|---|---|
| 家賃 | 60,000〜100,000 |
| 食費 | 25,000〜40,000 |
| 光熱費 | 7,000〜12,000 |
| 通信費 | 5,000〜10,000 |
| 日用品 | 3,000〜5,000 |
| 交通費 | 5,000〜10,000 |
| 趣味・交際費 | 10,000〜30,000 |
| 合計 | 約120,000〜210,000 |
※住んでいる地域やライフスタイルによって大きく異なります。
家賃が高い地域では、それだけで生活費全体のバランスが崩れやすくなります。
特に初めて一人暮らしを始める方は、収入に対して無理のない家賃設定を心がけることが大切です。
節約のために見直すべき5つの支出項目
一人暮らしで生活費が厳しいと感じたときは、支出の見直しが第一歩です。
なかでも節約効果が大きい5項目を紹介します。
1. 家賃
生活費の中で最も大きな負担です。
- 駅から離れたエリアやUR賃貸、市営住宅を検討
- ルームシェアで家賃を分担するのも一つの方法
2. 通信費
スマホ・Wi-Fi代は意外と大きな固定費。
- 格安SIMへの乗り換え
- 使っていないサブスクの解約
- 通話はWi-Fiアプリを活用
3. 食費
自炊を増やすだけで大幅な節約に。
- 業務スーパーや特売を活用
- もやし・豆腐・卵などコスパ食材を中心に
- 冷凍保存や作り置きで食材ロス防止
4. 光熱費
日々の小さな工夫が節約につながります。
- エアコン温度の見直し(夏28℃、冬20℃)
- LED電球や節水グッズを導入
5. 趣味・交際費
気づかぬうちに増える支出です。
- 飲み会は月1回に抑える
- 無料イベントや図書館を活用
- 散歩などお金のかからない趣味に切り替える
生活が厳しいときに使える支援制度
一人暮らしでは収入が途絶えると、すぐに生活が立ち行かなくなるリスクがあります。
特に家賃や固定費の支払いが続く中で、生活費の確保に困る方は少なくありません。
そんなときは、以下の公的支援制度を活用することで、生活の再建に向けた時間と余裕を得ることができます。
住居確保給付金|家賃の支援が受けられる制度
離職や大幅な収入減により家賃の支払いが困難になった方に対して、自治体が家賃相当額を補助してくれる制度です。
支給期間は原則3ヶ月、最大9ヶ月まで延長可能です。
- 支給対象:離職や減収から2年以内の人など
- 条件:収入・資産要件あり、求職活動の実施が必要
- 支給方法:家主や管理会社への直接振込
「退去の危機」を防ぐためにも、早めの相談・申請が大切です。
緊急小口資金・総合支援資金|無利子で生活費を借りられる
全国の社会福祉協議会が窓口となって実施している公的貸付制度で、失業や収入減で一時的に生活が苦しい方を対象としています。
- 緊急小口資金:一時的な出費向け(最大10万円程度)
- 総合支援資金:生活費の継続支援(数十万円の貸付が可能)
- 利息:無利子・保証人不要
- 一部は条件次第で返済免除の対象となることも
即日対応できるケースもあるため、早めに地域の窓口に相談しましょう。
傷病手当金|退職後も受け取れることがある制度
在職中にうつ病や適応障害などで「就労不能」と診断されていれば、退職後も最長1年6ヶ月間、給与の約3分の2にあたる傷病手当金が支給される可能性があります。
- 条件:在職中に医師の診断があること、健康保険の加入実績があること
- 支給額:標準報酬日額の約2/3(所得補償として受給)
- 特徴:失業手当より支給額が高くなることも
退職してからの申請も可能なため、対象になるかどうか一度確認してみましょう。
国民年金・健康保険料の免除・減免制度
収入が減ったにもかかわらず保険料の支払いが続くと、家計の負担はさらに大きくなります。
ですが、これらの保険料にも「免除」「減免」「納付猶予」などの制度があります。
- 国民年金:前年所得に応じて全額・一部免除や納付猶予が可能
- 健康保険料:市区町村や協会けんぽにより減額・分納対応あり
- 条件:失業や所得減少が明確であることが必要
いずれも「申請しなければ適用されない」ため、放置せず早めに相談することが大切です。
生活費が足りないときにやってはいけないNG行動
一人暮らしで生活が厳しくなると、「とにかく今をしのがなければ」という思いから、誤った選択をしてしまうことがあります。
ですが、そうした行動は、後になってさらに深刻な問題を引き起こすリスクがあります。
以下は、生活費が足りないときに避けるべき代表的なNG行動です。
クレジットカードでのリボ払いに頼る
リボ払いは月々の支払い額を抑えられる仕組みですが、実際には高い利息がかかり、返済総額が大きく膨れ上がる危険性があります。
支払いを先延ばしにすることで、一時的には楽に感じても、長期的にはさらに家計を圧迫することになります。
家賃や光熱費を滞納したまま放置する
家賃や電気・ガス・水道などの支払いを滞納し続けると、ライフラインの停止や最悪の場合は退去命令につながる可能性があります。
事情がある場合は、まずは大家や自治体、供給会社に相談することが大切です。
分割払いや支払猶予など、対応策を講じてもらえる場合があります。
誰にも相談せずに孤立する
「お金の悩みを人に話したくない」と感じてしまうこともあるかもしれませんが、一人で抱え込むと、正しい情報や支援にたどり着けず、状況が悪化してしまうことがあります。
家族、信頼できる友人、そして専門機関(自治体や社労士など)に早めに相談することで、活用できる制度や解決策が見えてきます。
アルバイト・副業で収入を補う方法
生活費が不足しているとき、「支出を減らす」ことに加えて「収入を増やす」という選択も非常に有効です。
特に一人暮らしでは、自分ひとりで収入源を確保しなければならないため、早めの行動が重要になります。
短時間でもできるバイトを活用する
体力やスケジュールに無理のない範囲で、コンビニやスーパー、清掃、デリバリーなどの短時間アルバイトを始めてみましょう。
求人サイトには「週2日~」「1日3時間からOK」といった柔軟な募集も多く見られます。
スキルを活かせる副業に挑戦する
文章を書くのが得意ならWebライティング、動画編集やデザインの経験があるなら、そういったスキルを活かした副業に取り組むことで、時給換算の効率が高くなります。
スキルのある人は、実績を積むことで継続的な収入につなげることも可能です。
在宅ワークで効率よく働く
クラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングサービスを使えば、自宅にいながら収入を得られる仕事を探すことができます。
タイピングや事務作業、データ入力など、初心者でも対応できる案件も多数あり、スキマ時間を有効活用できます。
まとめ|一人暮らしでも支援を活用すれば立て直せる
一人暮らしは自由な反面、すべての生活費を自分で負担する必要があり、収入が途絶えたときの不安は大きくなります。
しかし、支出の見直しと公的制度の活用によって、生活の再建は十分に可能です。
住居確保給付金や失業手当、傷病手当金など、知っていれば使える制度は多く存在します。
「社会保険給付金アシスト」では、状況に応じた制度の組み合わせや書類の準備、医療機関の案内、就職困難者認定のフォローまで一人ひとりに合わせたサポートを行っています。
困ったときこそ、一人で抱え込まず、支援を使って早めに動くことが大切です。