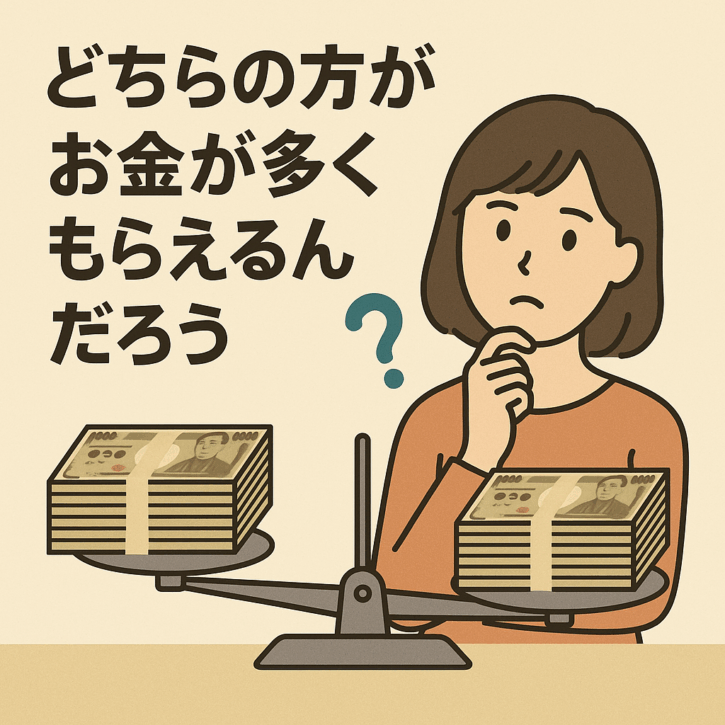退職後の生活費をどう確保するか——。
病気やうつで退職せざるを得ない方にとって、**「傷病手当金(健康保険)」と「失業保険(雇用保険)」**は、生活を支える命綱となる制度です。
しかし、多くの相談者様がこのような疑問を持たれています。
「両方とも受け取ることはできるの?」
「どっちを先に申請すべき? 順番を間違えると損をするって本当?」
結論から言うと、この2つの制度は同時には受け取れません(併給禁止)。
しかし、「正しい順番」で申請することで、両方の制度をフル活用することは可能です。
逆に、順番を間違えてしまうと、本来もらえるはずだった数百万円を受け取り損ねるリスクさえあります。
この記事では、制度の複雑な仕組みを整理し、あなたが「どの順番で受給すれば一番得をするのか(受給額を最大化できるか)」を、社会保険の制度活用に特化した専門アドバイザーが、プロの視点から金額シミュレーション付きで分かりやすく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

1. 傷病手当金と失業保険、何が違う?(比較表)
名前が似ていたり、退職後に使うタイミングが重なるため混同されがちですが、これらは「管轄」も「目的」も全く別の制度です。
まずは以下の比較表で、決定的な違いを押さえましょう。
| 項目 | 傷病手当金 | 失業保険 |
| 管轄 | 健康保険(協会けんぽ・健保組合) | ハローワーク(雇用保険) |
| 前提条件 | 「病気で働けない」状態 | 「働ける(求職活動できる)」状態 |
| 支給額 | 給与の約2/3 | 給与の約45〜80% |
| 最大期間 | 最長 1年6ヶ月 | 90日〜330日(約3〜11ヶ月) |
| 制度概要 | 傷病手当金の受給条件や計算方法はこちら | 失業保険の計算式や受給日数の詳細はこちら |
最大のポイントは「働けるか、働けないか」
この2つは受給の「前提」が正反対です。
-
傷病手当金 = 治療のために働きたくても働けない人がもらうお金
-
失業保険 = 健康だけど仕事に就いてない人がもらうお金
つまり、「働けない状態」でありながら「求職活動のサポート(失業保険)」を受けることは矛盾するため、同時受給はできない(併給禁止)というルールになっています。
2. どっちを先に? 受給額が変わる「2つのルート」
では、両方の制度を無駄なく活用するにはどうすればよいのでしょうか?
代表的な2つのパターンを比較します。
まずは1秒チェック!あなたにおすすめの順番は?
以下の質問に答えるだけで、どちらを優先すべきかわかります。
- Q1. 医師から「休職・療養が必要」と言われている(または言われそう)
👉 YESなら… 「傷病手当金」を先に申請!(王道ルートへ)
- Q2. 病気は治っており、明日からでもフルタイムで働ける
👉 YESなら… 「失業保険」を申請!
【正解】王道ルート:先に傷病手当金 → 回復後に失業保険
「まずはしっかり療養して、元気になってから仕事を探す」という、最も理にかなった、かつ経済的メリットが最大になるルートです。
-
退職〜療養中: まず「傷病手当金」を受給(最長1年6ヶ月)
-
回復後: 医師から就労許可が出たら、ハローワークで求職申込
-
求職活動中: 「失業保険」を受給
このルートのメリット:
-
傷病手当金(最大1年半)+ 失業保険(数ヶ月)= 最大約2年以上の生活費を確保できる。
-
焦って復職せず、体調回復を最優先にできる。
【要注意】一般ルート:失業保険からもらう
退職してすぐにハローワークへ行き、失業保険を受け取ろうとする一般的なパターンです。
もしあなたが「病気で退職した(すぐには働けない)」場合、このルートを選ぶと以下のリスクがあります。
- 失業保険がもらえない
ハローワークで「病気で働けない」と判断されると、受給資格がないとみなされます。
- 傷病手当金への切り替え不可
失業保険の受給中に体調が悪化しても、そこから傷病手当金に切り替えることは原則できません。
- 不正受給のリスク
働けないのに「働けます」と嘘をついて申請すると、不正受給とみなされる危険性があります。
結論:医師から「休養が必要(労務不能)」と診断されているなら、迷わず「傷病手当金」を優先してください。
3. 金額シミュレーション:どっちが得?
「期間」だけでなく「金額(月額)」で見ても、実は傷病手当金の方が手厚いケースがほとんどです。
月給30万円の人を例に計算してみましょう。
支給額の比較(月給30万円モデル)
| 制度 | 計算式(目安) | 月額の受給イメージ |
| 傷病手当金 | 標準報酬日額の 2/3 | 約 20万円 / 月 |
| 失業保険 | 賃金日額の 50〜80% | 約 18万円 / 月 ※1 |
(※1) 失業保険の給付率は年齢や賃金により変動しますが、30代・月給30万円の場合は概ね60%弱になることが一般的です。
トータルの受給可能額(最大値)
もし両方の制度をフル活用できた場合(王道ルート)、総額はここまで変わります。
-
失業保険のみの場合:
-
約18万円 × 3ヶ月(90日) = 約54万円
-
-
王道ルート(傷病手当金+失業保険)の場合:
-
(20万円 × 18ヶ月)+(18万円 × 3ヶ月) = 約414万円
-
その差は300万円以上にもなります。
「知っているか、知らないか」だけで、退職後の生活防衛資金にこれだけの差が生まれるのです。
4. 絶対に忘れてはいけない「延長申請」の手続き
「じゃあ、傷病手当金を先にもらって、治ったらハローワークに行けばいいんだね!」
そう思った方、ここが最大の落とし穴です。ただ待っているだけでは、後から失業保険をもらうことはできません。
必ず「受給期間延長申請」という手続きを行う必要があります。
なぜ延長申請が必要なの?
失業保険には「退職から1年以内に受け取り切らないと権利が消滅する(時効)」という厳しいルールがあります。
傷病手当金を1年6ヶ月もらっている間に、この「1年の期限」が過ぎてしまい、失業保険が0円になってしまうのです。
これを防ぐために、ハローワークに「今は病気で働けないので、期限を延ばしてください(最大4年まで)」と申請する必要があります。
延長申請の重要ポイント
-
期限: 退職日の31日後から1年以内(早めに行うのが鉄則です)
-
場所: 管轄のハローワーク
-
効果: 傷病手当金が終わった後でも、失業保険を受け取れます。
※具体的な申請書の書き方や必要書類については、別記事で詳しく解説しています。
5. よくある質問(FAQ)
Q. 退職後に病気が見つかりました。今から傷病手当金はもらえますか?
A. 残念ながら、原則対象外です。傷病手当金を退職後も受け取るには、「在職中に初診を受け、3日以上の休み(待期期間)を完成させている」など、退職日前の実績が必須条件となります。
Q. 傷病手当金の受給中にアルバイトはできますか?
A. できません。少しでも就労(給与が発生)すると「働ける状態」とみなされ、傷病手当金がストップするだけでなく、失業保険の受給要件とも矛盾が生じます。
Q. 延長申請を忘れました。どうなりますか?
A. 退職から1年を過ぎてしまうと、失業保険の受給権が消滅します。後からの救済措置はほぼないため、何よりも優先して手続きを行ってください。
まとめ|「順番」と「タイミング」がすべてです
傷病手当金と失業保険は、どちらもあなたを守る大切な制度です。
しかし、「どちらが先か」を間違えると、そもそも片方が使えなくなったり、もらえるはずの金額を大幅に失うリスクがあります。
成功のポイントまとめ:
- 病気で退職するなら、まずは「傷病手当金」を最優先。
- その間に、ハローワークで必ず「受給期間延長申請」を済ませる。
- 回復したら「失業保険」へ切り替える。
この流れを組むためには、退職前からの準備(医師への診断書依頼や、退職日の調整など)が欠かせません。
- 「自分の場合はいくらもらえる?」
- 「申請のタイミング、これで合ってる?」
不安な方は、手遅れになる前に一度専門家へご相談ください。
弊社では、あなたの状況に合わせた最適な受給プランの設計から、面倒な書類チェックまでトータルでサポートしております。