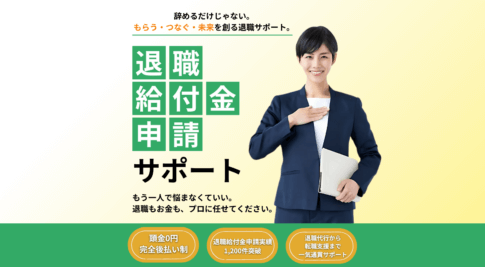「正社員なのに退職金がないっておかしくない?」
そう感じたことがある人は少なくないでしょう。
近年では、終身雇用の崩壊や成果主義の浸透により、退職金制度を設けない企業も増えています。
一方で、「退職金なし=ブラック企業なのか」「法律的に問題はないのか」と不安を感じる人も多いはずです。
この記事では、退職金がない会社の実態とその理由、そして将来に備えるための対策を、データと制度の両面からわかりやすく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

結論:退職金がなくても違法ではないが、将来リスクは大きい
まず結論から言うと、退職金がない会社は違法ではありません。
労働基準法などの法律で退職金制度の設置は義務づけられていないため、制度を設けるかどうかは企業の判断に委ねられています。
ただし、退職金制度がない会社にはいくつかの共通点があります。
それは「従業員の定着率が低い」「短期雇用を前提にしている」「福利厚生にコストをかけない」という傾向です。
つまり、退職金がないこと自体は合法でも、長期的な安定雇用を重視していない会社である可能性が高いといえます。
将来の備えという観点から見れば、退職金がない会社で働くことはリスクが大きいのが現実です。
退職金制度がない会社の割合と傾向
厚生労働省「就労条件総合調査」によると、退職金制度がない企業は全体の約37%にのぼります。
特に中小企業ではその割合が高く、従業員100人未満の企業では約4割が退職金制度を設けていません。
業界別に見ると、以下のような傾向があります。
- IT・ベンチャー業界:成果主義や短期契約が多く、制度がない企業が多い
- 飲食・小売業界:人の入れ替わりが激しく、長期雇用を前提としていない
- 介護・福祉業界:人材不足と経営の厳しさから退職金制度を維持できない企業が多い
一方で、金融・製造・公務員などの業界では退職金制度が一般的であり、制度があることが“企業の安定性の象徴”とされることも少なくありません。
退職金がない理由3つ
退職金制度を設けない企業には、それぞれ合理的な理由があります。主な3つを見ていきましょう。
1. 人件費を抑える経営判断
退職金は「将来の支出」を前提とするため、長期的に資金を積み立てる必要があります。
中小企業では資金繰りに余裕がないケースも多く、あえて退職金制度を設けずに給与をやや高めに設定して即時報酬に回すという方針を取る会社もあります。
2. 定着率が低く長期雇用を想定していない
人の入れ替わりが多い業界では、退職金制度を維持するメリットが小さいと考えられています。
特に若年層中心の企業では「数年で転職してしまう人が多い」ため、長期勤続者を優遇する退職金制度が機能しづらいのです。
3. 成果主義型の報酬体系
スタートアップや外資系企業では、年功序列を排し、個人の成果に応じて報酬を払う成果主義を採用している場合が多くあります。
こうした企業では、退職金の代わりにストックオプションや賞与制度を充実させる傾向があります。
退職金が支給されないのには、会社ごとの事情や法的な背景があります。
もし「自分の会社で退職金がないのは違法なのでは?」と感じる方は、以下の記事も参考にしてください。
法律上の位置づけや、実際に取るべき行動を詳しく解説しています。
「退職金なしはやばい」と言われる本当の理由
SNSや口コミでは「退職金なしはやばい」という声をよく見かけます。
その理由は感情的なものだけではなく、明確なデータと将来設計上のリスクに裏づけられています。
1. 老後資金が不足しやすい
退職金の平均支給額は、大企業で約1500万円、中小企業で約500万円といわれています。
つまり、退職金がないということは数百万円〜1000万円単位の老後資金を失うということです。
老後の生活資金に直結するため、将来の備えが不十分になりやすいのです。
2. 転職時の不利
転職市場では「退職金制度あり」は福利厚生の一部として評価されます。
制度がない会社は「社員を長く雇う意思が薄い」と見られることもあり、優秀な人材の採用・定着が難しくなる悪循環に陥ることもあります。
3. 社員への信頼・還元意識の欠如
退職金は、長く働いた社員への“感謝と報酬”の意味を持ちます。
それを用意していない会社は、「短期的な利益を優先」「社員への投資意識が低い」と受け取られることも少なくありません。
結果的にモチベーションが低下し、離職率が上がる原因にもなります。
退職金がない場合の代替策
退職金がない会社に勤めていても、自分で将来資金を準備する方法や、公的制度を活用する手段があります。
1. 企業型DC・iDeCoを活用する
確定拠出年金(DC)は、会社または個人が拠出した掛金を自ら運用し、将来受け取る制度です。
特に個人型のiDeCoは、全額所得控除の対象となり節税効果も高いため、退職金の代替手段として非常に有効です。
2. 退職所得控除を理解しておく
退職金を受け取る際には「退職所得控除」があり、課税額が大幅に軽減されます。
退職金がない人はこの恩恵を受けにくいため、代わりにiDeCoやNISAでの運用益非課税制度を組み合わせることが重要です。
3. 退職後に使える公的制度をフル活用
退職金がない場合でも、退職後に受け取れる公的な給付金制度があります。
- 失業手当(基本手当):次の職が決まるまでの生活費を支援
- 就業促進定着手当:再就職後の収入が減少した場合の差額補填
- 傷病手当金:退職前後にうつ病などで働けない場合の所得補償
退職後に利用できる制度は意外と多く、手続きを知っているかどうかで受け取れる金額も変わります。
以下の記事では、失業保険や再就職手当などの受給タイミング・申請の流れを詳しく紹介しています。
退職金がなくても安心できる支援制度を活用しよう
退職金がないと、将来の生活資金に不安を感じる方も多いでしょう。
しかし実際には、退職後でも社会保険の各種給付金を活用すれば、退職金に近い金額を受け取ることが可能です。
社会保険給付金アシスト では、次のような公的制度の申請を一気通貫でサポートしています。
傷病手当金申請サポート
うつ病など体調不良で働けない方が、退職後も継続して給付を受け取れるように支援。書類の整備や医師との連携も代行します。
失業手当(雇用保険)申請サポート
自己都合退職でも、より早く・より多くもらえるようにサポート。**申請のタイミングや書類の書き方などを最適化します。
再就職手当の申請サポート
再就職が決まった際に支給される「再就職手当」の活用をサポート。申請条件の整理から書類作成まで徹底的にフォローします。
また、再就職後の給与が減った場合に追加支給される「就業促進定着手当」についても併せてご案内し、漏れのない受給を支援しています。
医師の紹介と申請書類取得サポート
提携のオンライン診療クリニックを紹介し、申請に必要な診断書や意見書をスムーズに取得できるようサポートします。
これらのサポートを通じて、退職後でも数十万〜百万円単位の給付を受け取れるケースもあります。
専門スタッフが制度の仕組みや申請手順を丁寧に説明し、複雑な書類提出や申請ミスを防ぐ体制を整えています。
また、アシストでは「自分がどの制度を使えるのか」「どれくらいの給付を受けられるのか」を無料で診断する個別面談も実施中です。
現状を整理しながら、あなたに最も合った申請方法を提案します。
「退職金がない=将来が不安」と感じている方も、制度を正しく活用すれば、安心して次のステップへ進むことができます。
実際にアシストを利用した方の体験談や口コミは、こちらの記事で詳しく紹介しています。
まとめ
退職金がない会社に勤めていても、それ自体が違法というわけではありません。
ただし、退職後の生活資金や老後の備えを自分で考える必要がある点では、大きなリスクを伴います。
今のうちから社会保険制度や給付金を上手に活用し、将来に向けた準備をしておくことが大切です。
不安な方は、一度専門のサポートを受けてみるのもおすすめです。