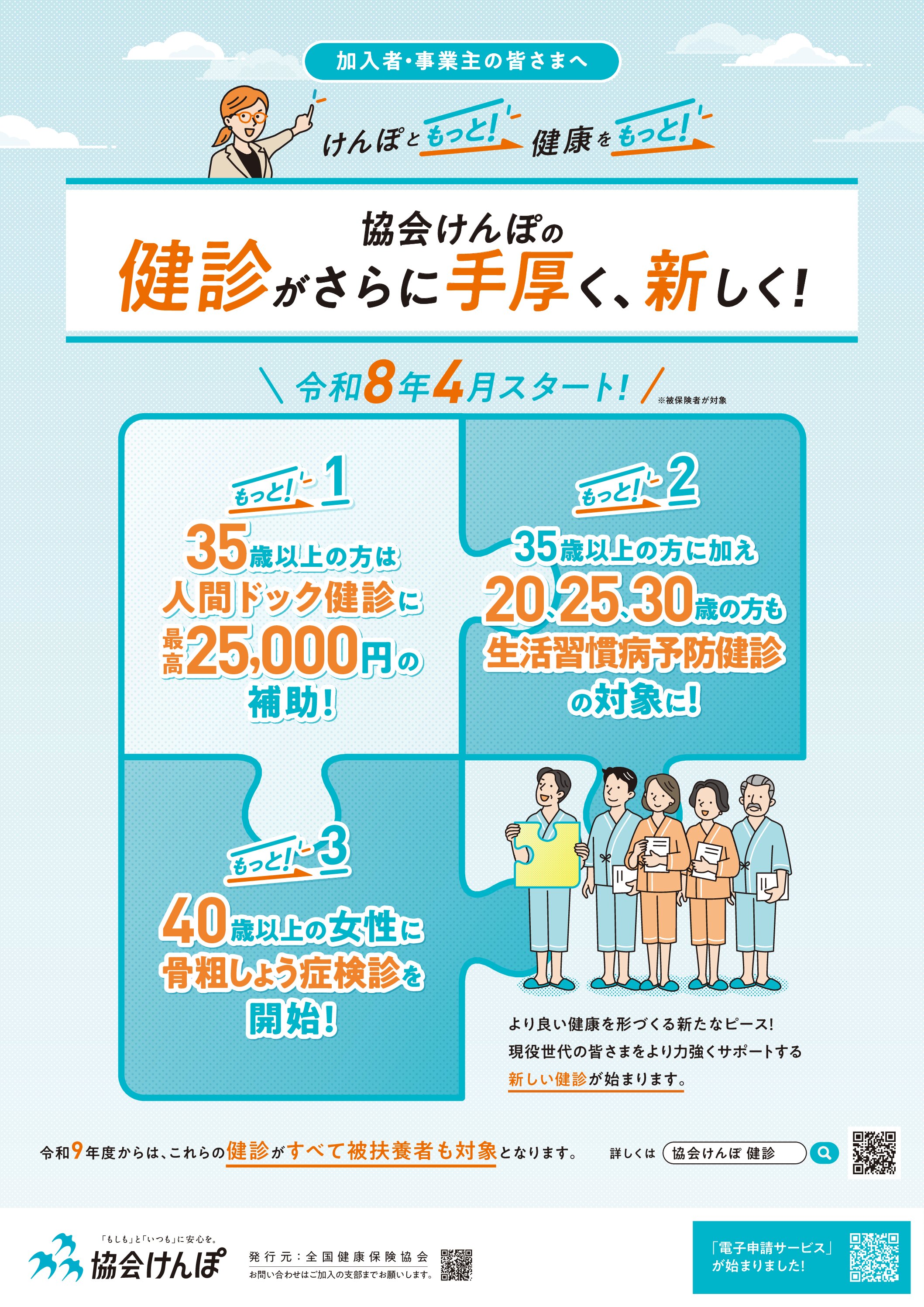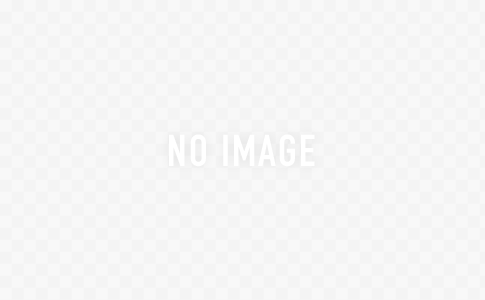社会人になると、仕事・家事・通勤に追われ、1日があっという間に過ぎてしまうもの。
「勉強したい」「資格を取りたい」と思っても、時間が取れずにあきらめてしまう――
そんな人が少なくありません。
「気力が足りないのでは?」と自分を責める人もいますが、実は違います。
勉強できない理由の多くは、環境と生活リズムが勉強に向かない構造になっているからです。
本記事では、社会人の勉強時間の現実と、時間を確保できない背景、
さらに仕事を辞めても給付金をもらいながら安心して学ぶ方法までを解説します。
「もう一度本気で学びたい」と思うあなたへ、現実的な選択肢を紹介します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

社会人の平均勉強時間はたった6分|“時間がない”は努力不足ではない
総務省の「社会生活基本調査」によれば、20〜50代の社会人が1日に勉強へ充てる時間は、平均わずか6分。
つまり、ほとんどの人は「勉強する時間がない」のが当たり前の状況です。
OECD(経済協力開発機構)の統計でも、日本の社会人は学習時間が加盟国の中でも最低クラスに位置しています。
仕事が終わるころには体力も気力も尽き、休日はリフレッシュに使う――
これが多くの人の実情です。
この数字は「やる気がないから」ではなく、
仕事・家庭・ストレス・通勤など、生活の中に勉強を挟む余地が少ない構造的な問題を示しています。
それでも、「今のままでは不安」「資格を取ってキャリアアップしたい」と感じている人は多いはず。
だからこそ、“時間を作る”のではなく、“時間を取り戻す方法”を考えることが大切です。
次章では、そのために必要な「勉強時間と資格難易度の現実」を整理します。
資格別に必要な勉強時間を比較してみよう
では、実際に資格を取るにはどれくらいの勉強時間が必要なのでしょうか。
ここでは、社会人に人気の資格を中心に、合格までのおおよその学習時間を一覧で整理しました。
| 資格名 | 必要勉強時間(目安) | 難易度・特徴 |
|---|---|---|
| 簿記3級 | 100〜150時間 | 会計の基礎。初心者に人気 |
| 簿記2級 | 200〜300時間 | 実務レベルで需要が高い |
| 宅建 | 400〜500時間 | 不動産・営業職で有利 |
| 社労士 | 800〜1000時間 | 法律系の国家資格。独立も可能 |
| 税理士 | 2500〜4000時間 | 高度な専門職。年単位の学習が必要 |
| 公認会計士 | 3000〜5000時間 | 専念型学習が前提 |
| 司法試験 | 5000時間〜 | 最難関。フルタイム勉強が必須 |
| 公務員試験 | 800〜1200時間 | 幅広い教養・専門対策が必要 |
1日6分では、1年で約36時間しか勉強できません。
つまり、多くの資格は社会人の平均ペースでは一生かかっても合格できない計算になります。
社会人が勉強時間を確保できない3つの理由
「勉強したいのに時間がない」と感じるのは、やる気の問題ではありません。
多くの社会人は、環境そのものが勉強を難しくしているのです。
① 時間が物理的にない
仕事・通勤・家事・育児で1日が終わり、勉強に使える時間はほとんど残りません。
休日も疲れの回復で終わってしまう人が多いのが現実です。
② 精神的に余裕がない
仕事のストレスや疲労で集中力が続かず、「今日は無理」と先延ばしになりがち。
気持ちの余裕がない状態では、学習を続けるのは難しいです。
③ 学習の優先順位が下がる
資格の勉強は成果が見えにくく、つい後回しになります。
緊急ではないため、日常の中で埋もれてしまうのです。
多くの人が自分を責めがちですが、問題は意志ではなく環境。
次章では、その環境を変えて「勉強時間を生み出す方法」を紹介します。
それでも勉強時間を作るための3つの工夫
忙しい社会人でも、少しの工夫で勉強時間を「生み出す」ことは可能です。
ここでは、無理なく続けられる3つの方法を紹介します。
① 朝活・通勤時間を活用する
朝は脳がリフレッシュしており、短時間でも集中力が高まります。
通勤電車ではスマホアプリで資格学習や音声講義を聞くのもおすすめです。
夜に疲れて勉強できない人ほど、「朝に15分」から始めると効果的です。
② 目的を明確にする
「資格を取って転職する」「年収を上げる」など、具体的なゴールを数字で設定しましょう。
目的が曖昧だと、忙しい日々の中で勉強が後回しになりがちです。
「何のために学ぶのか」を意識することで、継続力が生まれます。
③ 学習環境を固定化する
人は“環境”で行動が決まります。
「机に座ったら勉強する」「カフェに行ったら教材を開く」といったルール化で習慣が定着します。
場所を決めるだけで、集中力が格段に上がります。
こうした工夫を重ねれば、少しずつ勉強時間は確保できます。
ただし、それでも限界を感じる人は少なくありません。
次章では、思い切って“環境を変える”ことで勉強時間を確保する現実的な方法を紹介します。
時間が取れない人へ|仕事を辞めて“給付金で学ぶ”という選択
「仕事を辞めて勉強に専念したい」——
そう思っても、収入がなくなる不安から踏み出せない人は多いでしょう。
しかし、実は退職しても給付金を受け取りながら勉強できる制度がいくつか存在します。
制度を正しく使えば、「生活を守りながら学ぶ」ことが可能です。
① 失業保険
会社を退職した人が受け取れる給付金で、最大10〜12ヶ月の支給が可能です。
さらに、ハローワーク経由で職業訓練校に通う場合は、訓練延長給付が受けられるため、
生活費を得ながら資格取得の勉強に集中できます。
例:簿記や宅建、パソコンスキル講座なども対象。
「仕事を辞めて勉強に専念したい」人にとって現実的な選択肢です。
② 教育訓練給付金
社会人のキャリアアップを支援する制度で、
受講費用の20〜70%が国から還付されます。
対象講座には、簿記・宅建・社労士・医療事務など人気資格も多数。
通学でも通信講座でも利用できるため、働きながらでも使いやすい制度です。
③ 傷病手当金
うつ病や過労など、心身の不調で働けない人を支援する制度です。
休職中でも給与の約2/3が最長1年半支給され、生活を維持しながら回復と勉強に専念できます。
「いったん仕事を離れて立て直したい」という人にとっても、非常に現実的な手段です。
これらの制度をうまく活用すれば、
「収入がなくなる不安」を抱えることなく、安心して学びに集中する環境を整えられます。
無理に仕事を続けて疲弊するよりも、一度立ち止まり、制度を使って“学び直す時間”を確保するという考え方が今の時代には求められています。
社会保険給付金アシストでできること
「時間を作りたい」「本気で学び直したい」と思っても、制度の仕組みや申請の流れが分からずに行動できない人は多いものです。
社会保険給付金アシスト では、そんな方のために失業手当・傷病手当金などの公的制度を正しく活用し、生活を支えながら勉強に専念できる環境づくりをサポートしています。
サポートの特徴
- 失業手当・傷病手当金の申請支援
ハローワークや健康保険組合との手続き、クリニックとの連携で必要書類の準備まで一括でサポート。 - 生活を守りながらの学習を実現
受給中も安心して資格勉強や転職準備に集中できるよう、状況別に個別支援。 - オンライン対応・24時間相談可
全国どこからでも相談可能。LINEやメールでスムーズにやり取りできます。
「仕事を辞めて勉強したいけれど不安…」という方も、
制度を正しく使えば“生活と学びを両立する”ことは可能です。
社会保険給付金アシスト は、その第一歩を一緒に支えるパートナーとして、
給付金の受給から新しいキャリアのスタートまで、安心して進められるよう伴走します。
まとめ
社会人の平均勉強時間は、わずか1日6分。
多くの人が「勉強したい」と思いながらも、仕事・生活・疲労の中で思うように時間を確保できていません。
それは努力不足ではなく、環境の制約によるものです。
小さな工夫で時間を生み出すことも大切ですが、
本気で人生を変えたいなら、環境そのものを見直す勇気も必要です。
仕事を辞めても、失業手当や傷病手当金、教育訓練給付金といった制度を活用すれば、
生活を守りながら学びに専念することができます。
焦らず、一度立ち止まって「学び直す時間」をつくることが、将来の大きな資産につながります。
社会保険給付金アシストでは、そのような方が安心して次のステップに進めるよう、
給付金申請から受給までを丁寧にサポートしています。