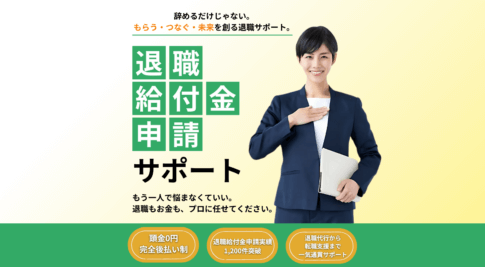「うつ病になったら、もう働けないのでは…」
そんな不安を抱える方は少なくありません。
けれど実際には、うつ病の状態に合わせて無理のない仕事を選べば、再び社会と関わることは十分に可能です。
本記事では、うつ病の症状に合わせた仕事の選び方や、復帰のタイミング、注意すべきポイントをわかりやすく紹介します。
「焦らず、少しずつ」を合言葉に、あなたに合った働き方を一緒に見つけていきましょう。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

うつ病でも働ける?結論:症状と環境次第で“できる仕事”はあります
結論から言えば、うつ病でも働くことは可能です。
ただし、「どんな状態で」「どんな環境で働くか」によって、続けられるかどうかは大きく変わります。
うつ病には軽度・中等度・重度があり、軽症なら日常生活をこなしながら働けることもあります。
一方で中等度以上では、朝起きられない・人と話すのがつらい・集中力が続かないなどの症状が強く、まずは休養が必要です。
重要なのは、“仕事の内容”より“環境との相性”。
人間関係のストレスが少なく、静かで自分のペースで進められる職場なら、うつ病の方でも無理なく働けます。
特に在宅ワークや短時間勤務、リモート事務などは体調に合わせやすく現実的です。
復職の判断は必ず主治医と相談し、「もう少し頑張れそう」と思う時ほど慎重に。
体調が安定してから段階的に戻ることで、再発を防ぎながら長く働き続けられます。
軽いうつ病の人に向いている仕事・働き方
軽いうつ病の方でも、環境を選べば無理なく働くことは可能です。
気分の落ち込みや集中力の波があるため、ノルマが厳しい・人間関係が濃い職場は避けるのがポイントです。
プレッシャーの少ない仕事を選び、安定したペースを保ちましょう。
軽いうつ病におすすめの仕事4選
① 在宅ワーク(ライター・データ入力・Web制作など)
一人で黙々と作業ができるため、人間関係のストレスが少なく、通勤の負担もありません。
自分のペースで仕事を進められるのが大きな魅力です。
最近ではクラウドワークスやランサーズなど、在宅案件の選択肢も増えています。
② 事務補助・経理サポート
社内のサポート的な立ち位置で、業務内容が比較的安定している仕事です。
静かな環境で働けることが多く、一定のリズムで作業できるため、心身への負担が少なめです。
③ コールセンター(受電のみ)
問い合わせ対応など、マニュアルに沿って進める仕事であれば精神的な負担は軽くなります。
ただし、クレーム対応などストレスが大きい部署は避け、受電中心の業務を選ぶと良いでしょう。
④ 図書館・倉庫作業などの軽作業
人との関わりが少なく、単調な作業をコツコツとこなすタイプの仕事は、うつ病の方に向いています。
ルーチンワークを繰り返すことで安心感を得られる場合もあります。
軽度うつ病の働き方のコツ
軽い症状だからといって無理をすると、再発や悪化につながることがあります。
ここでは、軽度うつ病でも安定して働くためのコツを3つ紹介します。
-
勤務日数や時間を減らす
最初は週3〜4日勤務、もしくは短時間勤務から始めましょう。
「まだ余力がある」と感じるくらいのペースが理想です。 -
作業環境を柔軟に変える
自宅で気分が落ちる場合は、カフェや図書館など環境を変えてみるのも効果的です。
気分転換ができるだけで、集中力が戻るケースもあります。 -
生活リズムを最優先にする
仕事よりもまず、睡眠・食事・通院のリズムを安定させることが大前提です。
体調が整うと、自然と仕事への意欲も少しずつ戻ってきます。
中等度うつ病の人は“休む勇気”も大切|復職の目安と段階的リワーク
中等度のうつ病になると、外出や人と話すことがつらくなり、集中力が続かない、体が思うように動かないといった症状が出やすくなります。
この段階では、無理に働こうとするよりもしっかり休むことが何より大切です。
焦って職場に戻ると、再発や悪化を招くリスクが高くなるため、「今は治療に専念する時期」と割り切ることが必要です。
仕事に戻るまでの流れ
- まずは休職や退職を検討する
職場の環境が原因で症状が悪化している場合は、一時的に離れる勇気を持ちましょう。 - 生活の安定のために傷病手当金を活用
休職中の収入減を補うため、健康保険から給与の約3分の2が支給されます。
生活の不安を減らし、回復に集中できる環境を整えましょう。 - 医師と相談しながらリワークプログラム(職場復帰訓練)を利用
病院や地域の支援機関で行われるリワークでは、実際の職場復帰に向けた体力・集中力の回復トレーニングが受けられます。 - 主治医の「就労可」判断後に短時間勤務から復帰
いきなりフルタイムではなく、短時間勤務や週数日の出勤から慣らしていくのが現実的です。
復帰の目安
- 朝起きて生活リズムが安定している
- 外出や会話が苦にならない
- 数時間の集中作業ができる
これらのサインが見えてきたら、少しずつ社会との接点を増やす時期です。
再就職の選択肢
- 就労移行支援事業所を活用し、段階的に働く練習をする
- 障害者雇用(精神障害者保健福祉手帳の活用)で安定した職場を選ぶ
- 短時間・委託・在宅型の仕事で体調に合わせてリハビリ的に働く
自分のペースで「少しずつ戻る」意識が何より大切です。
焦らず、治療と回復の時間を確保しましょう。
うつ病からの復職・再就職を成功させる5つのステップ
うつ病から社会復帰を目指すときに大切なのは、「焦らず、段階を踏むこと」です。
いきなりフルタイムで働こうとすると、再発のリスクが高まります。
ここでは、安心して復職・再就職を進めるための5つのステップを紹介します。
① 主治医と「働けるレベル」を確認する
復職の第一歩は、医師に現在の状態を正直に伝え、「仕事に戻っても大丈夫か」を確認することです。
医師の判断なしに動くと、無理が重なって再発するケースが少なくありません。
仕事を始めるタイミングだけでなく、勤務時間や仕事内容の調整も含めて相談しましょう。
② 就労支援制度(リワーク・職業訓練)を活用する
リワークプログラムやハローワークの職業訓練を利用すると、復職前のリハビリとして社会との接点を少しずつ取り戻せます。
リワークでは、グループワークや模擬勤務などを通して「職場のペースに慣れる練習」ができます。
いきなり職場に戻るのではなく、段階的に体を慣らすことが重要です。
③ 給付金制度(傷病手当金・失業手当・再就職手当)で生活を安定
収入が減る時期に無理をすると、体より先に生活が崩れてしまいます。
そんなときは、以下の制度を積極的に活用しましょう。
- 傷病手当金:休職中の生活を支える(給与の約3分の2)
- 失業手当:退職後の求職活動をサポート
- 再就職手当:早期に職に就いた場合のボーナス的支援
これらを活用することで、経済的な不安を減らし、治療に専念できます。
④ 短時間勤務からリハビリ的に復帰する
復職するときは、いきなりフルタイムではなく、週数日・短時間勤務から始めましょう。
最初のうちは「午前中だけ」や「週3日だけ」など、体調を見ながらペースを調整するのが理想です。
焦らず、仕事を生活の一部として少しずつ慣らす意識を持つことが、長く続けるコツです。
⑤ 通院・服薬・環境調整で再発を防ぐ
復職後も、定期的な通院と服薬は欠かせません。
また、働きすぎない・無理しない・相談できる相手を持つことも再発防止に効果的です。
仕事のペースが上がってきても、自分の体調の変化を見逃さず、必要に応じて勤務形態を調整しましょう。
うつ病で仕事を辞めるか迷っている人へ|生活を支える制度一覧
うつ病がつらく、仕事を続けるかどうか迷っている方も多いでしょう。
無理をして働き続けるよりも、一度休む・退職するという判断も前向きな選択です。
その際に大切なのが、生活を支える制度を正しく活用することです。
傷病手当金
在職中にうつ病で休職する場合、健康保険から給与の約3分の2が支給されます。
最大で1年半まで受給でき、仕事を辞めずに療養に専念できる制度です。
失業手当
退職後に働けない状態が続く場合でも、うつ病などが原因で求職活動が難しい人は「就職困難者」として特例の支給を受けられることがあります。
通常は90〜150日程度の受給期間ですが、就職困難者に該当すれば最長で300日まで延長されるケースもあります。
また、うつ病で退職した場合は「特定理由離職者」として扱われ、給付制限(2か月→1か月)も短縮されます。
医師の診断書など、状態を示す書類をハローワークに提出することで判断されます。
就業促進定着手当
再就職後に前職より給与が下がった場合、その差額の一部を補ってくれる制度です。
再出発を経済的にサポートしてくれるため、安心して次のステップに進めます。
住居確保給付金・生活困窮者支援制度
家賃補助や生活資金の支援が受けられる制度です。
自治体の窓口で申請でき、家賃を数か月分代理納付してもらえる場合もあります。
こうした制度を活用すれば、収入が途切れても生活を維持しながら回復に専念できます。
ただし、申請書類が多く複雑なため、「どの制度が使えるかわからない」という方も少なくありません。
そのようなときは、社会保険給付金アシスト のような専門サポートを活用するのも一つの方法です。
制度の選定から申請サポートまで一貫して行うことで、時間や手続きの負担を減らし、より確実に給付を受け取ることができます。
まとめ|「うつ病でもできる仕事」は必ずあります。焦らず、あなたのペースで。
うつ病になったからといって、「もう働けない」と思う必要はありません。
症状の程度に合わせて環境を整えれば、少しずつ社会と関わることは十分に可能です。
軽いうつ病の方は、プレッシャーの少ない仕事や在宅ワークなど自分のペースを大切にできる働き方を。
中等度の方は、まずしっかり休養を取り、医師や支援機関と連携しながら段階的な復帰プランを立てることが大切です。
また、無理に収入を得ようとせず、傷病手当金・失業手当・住宅給付金などの制度をうまく活用することで、
経済的にも心の面でも安定した回復期間を確保できます。
もし「自分にはどの制度が使えるかわからない」「申請が難しそう」と感じる場合は、
社会保険給付金アシスト のような専門サポートに相談するのも一つの方法です。
あなたの状況に合わせて最適な給付金制度を案内し、安心して生活を立て直すお手伝いをしています。