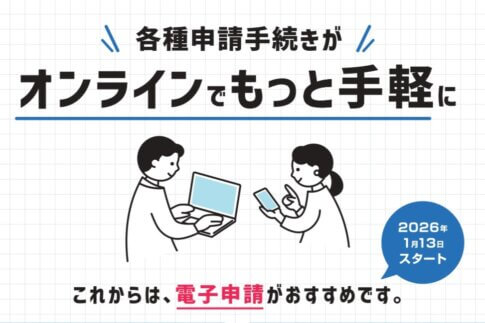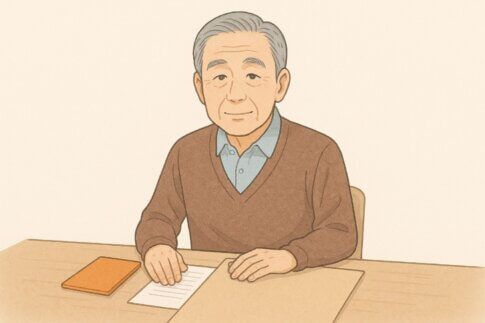「住居確保給付金」とは、失業や収入減少によって家賃の支払いが難しくなったときに、自治体が家賃相当額を補助してくれる制度です。
原則3か月の支給とされていますが、実は条件を満たせば延長でき、最長9か月まで利用できる“裏ワザ” が存在します。
この記事では、住居確保給付金の基本から、延長申請の方法・条件、知っている人だけが得をするポイントまでわかりやすく解説していきます。
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

住居確保給付金とは?
住居確保給付金は、失業や収入の減少で家賃の支払いが困難になった人を支援する制度 です。
自治体を通じて申請し、審査に通ると 原則3か月間、家賃相当額を自治体が大家さんや不動産会社に直接振り込む 仕組みになっています。
大きな特徴は「直接振り込み」であること。
手元に現金が入るわけではありませんが、家賃の支払いを心配しなくて済むため、生活再建や就職活動に集中できるメリットがあります。
住居確保給付金と失業保険をあわせてもらえるのか気になる方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
「裏ワザ」=延長申請の仕組み
「住居確保給付金は3か月で終わり」と思い込んでいる人が少なくありません。
しかし実際には、延長申請を行うことで最大9か月まで利用できる 場合があります。
これが知っている人だけが得をする“裏ワザ”と呼ばれる理由です。
延長できる期間
住居確保給付金は以下のように延長可能です。
- 初回:3か月間
- 延長1回目:さらに3か月
- 延長2回目:さらに3か月
→ 合計で 最長9か月間 の支給が受けられる可能性があります。
延長の条件
延長を受けるためには、次のような条件を満たす必要があります。
- 就職活動を継続していること(ハローワークへの登録や活動報告など)
- 世帯の収入が自治体の基準額を超えていないこと
- 一定の資産要件を満たしていること
これらをクリアしていれば、延長が認められる可能性が高まります。
申請のタイミング
注意すべきは、延長は自動的に行われない点です。
必ず 自分で自治体に延長申請を行う必要があります。
申請は初回の3か月が終了する直前に行うのが一般的なので、余裕を持って窓口へ確認しておくと安心です。
延長申請のメリット
延長申請を活用することで、住居確保給付金は単なる一時的な支援にとどまらず、生活再建のための大きな助けとなります。
具体的には、次のようなメリットがあります。
- 家賃負担を長期間軽減できる
最大9か月間、家賃の支払いを心配せずに済むため、生活の安定が格段に高まります。 - 生活再建までの時間を確保できる
短期間で焦って就職先を決める必要がなくなり、スキルアップや希望に合った職探しに集中できます。 - 心理的な安心感
「住まいが守られている」という安心感は大きく、精神的にも落ち着いて生活や就職活動に取り組めます。
このように、延長申請は単なる制度上のオプションではなく、将来の生活を安定させるための大切な仕組みといえます。
延長申請の注意点
「裏ワザ」といっても、誰でも自動的に延長できるわけではありません。
あくまで条件を満たして初めて認められるため、次の点には注意が必要です。
- 申請は必ず自分で行う
延長は自動更新ではありません。自分で手続きをしなければ、その時点で支給は終了してしまいます。 - 就職活動実績の報告が必要
ハローワークでの求職活動や応募実績など、自治体が求める報告を行わないと延長は認められません。 - 収入・資産基準を超えると対象外
パート収入や臨時収入などで基準額を超えてしまうと、延長が認められないケースがあります。 - 自治体ごとの運用差がある
延長の判断基準や必要書類は自治体によって異なる場合があります。必ず事前に窓口で確認しておきましょう。
このように、延長申請には条件と注意点があります。
申請を忘れたり基準を超えてしまうと支給が打ち切られる可能性もあるため、余裕を持った準備と確認が大切です。
延長申請の流れ
住居確保給付金の延長は「申請を繰り返す」ことで最大9か月まで利用できます。
ただし、流れを理解していないと期限切れで支給が止まってしまうこともあるため、手続きのステップを詳しく見ていきましょう。
1. 初回申請で3か月分の給付を受ける
最初は通常の住居確保給付金と同じく、自治体に申請して3か月間の支給を受けます。
申請時には収入・資産の確認や、ハローワークへの求職登録証明などが必要です。
ここで認定されると、家賃相当額が大家さんや不動産会社に直接支払われます。
2. 期間終了前に延長申請書を提出
3か月が終了する直前に「延長申請書」を自治体へ提出します。
このタイミングを逃すと支給が終了してしまうため、余裕を持って申請準備を始めることが重要です。
多くの自治体では終了1か月前から相談可能です。
3. 就職活動実績や収入状況を報告
延長申請では「就職活動をきちんと行っているか」が審査のポイントになります。
例えば、
- ハローワークでの職業相談記録
- 求人への応募履歴
- 職業訓練や資格取得の実績
といった具体的な記録を提出することになります。
あわせて、世帯収入や預貯金の状況も再確認されます。
4. 条件を満たしていれば延長が承認
提出書類や状況をもとに自治体が審査し、条件を満たしていれば延長が承認されます。
その後、再び3か月間の支給が開始されます。
この手続きを繰り返すことで、最長9か月まで利用できる仕組みです。
実際の活用例
延長申請によってどのくらいの支援が受けられるのか、具体的なケースで考えてみましょう。
例えば、月6万円の家賃を支払っている方 が住居確保給付金を受給した場合、次のようになります。
- 初回3か月:18万円の補助
- 延長3か月:さらに18万円の補助
- 延長さらに3か月:さらに18万円の補助
合計すると、最大54万円分の家賃が肩代わりされる 計算になります。
毎月の家賃という大きな固定費を長期的に支援してもらえることで、生活再建までの時間を十分に確保できるのは大きなメリットです。
就職活動やスキルアップに集中できるだけでなく、「住む場所を失うかもしれない」という不安から解放され、精神的な余裕も生まれます。
よくある質問(Q&A)
Q1. 住居確保給付金は誰でも延長できますか?
A. 誰でも自動的に延長できるわけではありません。
就職活動の継続、収入・資産が基準内であることなどの条件を満たす必要があります。
Q2. 延長申請はいつすればいいですか?
A. 初回の3か月が終わる直前に自治体へ申請するのが基本です。
申請が遅れると支給が途切れてしまう可能性があるため、1か月前から準備しておくと安心です。
Q3. 延長しても家賃は必ず全額補助されますか?
A. 家賃全額ではなく、自治体が定める「上限額」の範囲内で支給されます。
実際の補助額は家賃や地域の基準によって異なるため、必ず事前に確認しましょう。
まとめ
住居確保給付金の「裏ワザ」とは、不正や抜け道ではなく、延長申請を活用して最長9か月まで受給できる仕組み のことです。
多くの人が「3か月だけ」と思い込んでしまいますが、制度を正しく理解すれば、生活再建までの大きな助けとなります。
家賃補助を長く受けられるかどうかは、あなたが制度を理解し、延長手続きを忘れずに行うかどうかにかかっています。
利用を検討している方は、必ず自治体の窓口で確認し、正しい手続きを行うことをおすすめします。
また、弊社「社会保険給付金アシスト」では、退職後の傷病手当金や失業保険を最大限受給できるようサポートを行っています。
加えて、希望される方には今回ご紹介した住居確保給付金の申請についても案内していますので、あわせてお気軽にご相談ください。