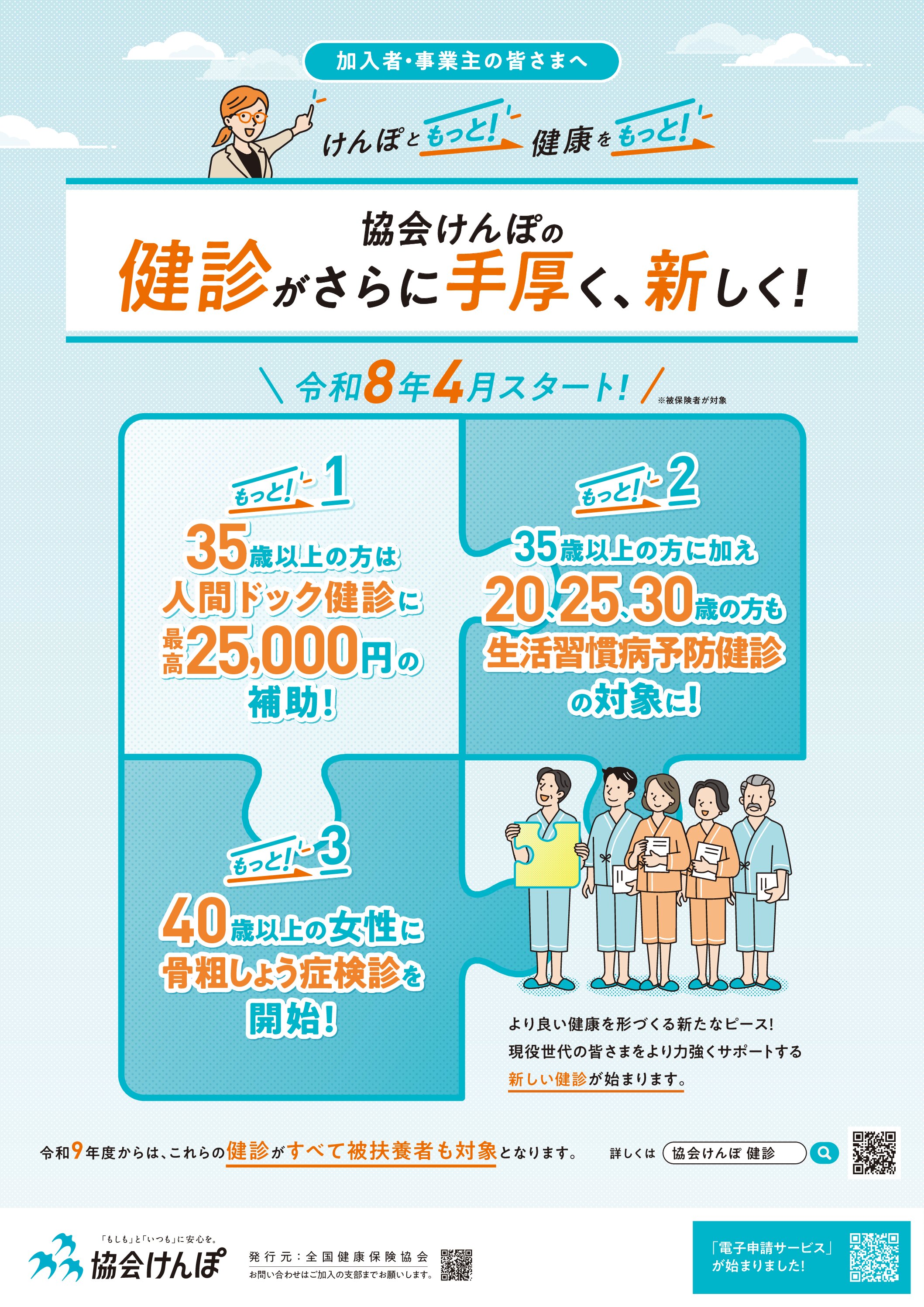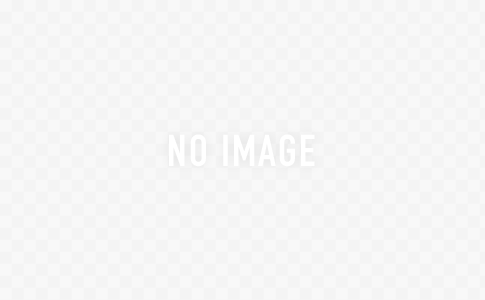退職後の生活費に不安を感じている方へ。多くの人が「退職金」「失業保険」「傷病手当金」などを同じ意味だと思い込み、結果として“本来もらえるお金を取り逃している”のが実情です。
まず結論です。
「退職給付金」とは、会社が支給する退職金だけでなく、国が支給する公的給付(傷病手当金・失業保険など)全体の総称です。
しかし多くの方がここを混同しているため、申請の順番を間違えたり、手続きが遅れたりして、受給額が数十万〜数百万円変わるケースが珍しくありません。
本記事では、この“公的な退職給付金”に絞って、もらえる条件・期間・手続き・最大化のポイントを徹底的にわかりやすく解説します。
さらに、社労士受験生として制度を深く学んでいる管理人が、給付額を最大化するための正しい順番についてもアドバイスします。
↓この記事に書かれてあることの動画版↓
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

退職給付金とは?(定義を明確化)
退職給付金には、大きく分けて2種類あります。
| 種類 | 内容 | 支給主体 |
|---|---|---|
| 企業の退職金 | 勤続年数に応じて会社が支給 | 会社 |
| 公的な退職給付金(本記事のテーマ) | 傷病手当金・失業保険など | 国(健康保険・雇用保険) |
本記事で解説する「退職給付金」は後者の 公的給付 を指します。
会社の規定に関係なく、条件を満たせば誰でも受け取れるのが特徴です。
そして、最も重要なポイントは次の1文に集約されます。
申請の順番によって、受け取れる給付総額が100万円以上変わることがある。
退職後の生活を守るためには、制度を理解し、正しい順番で申請することが絶対条件です。
退職給付金として代表的な制度(主要3つ)
公的な退職給付金として特に重要なのが、以下の3制度です。
- 傷病手当金
病気やケガで働けない状態になった場合に、健康保険から支給される生活補償です。
給与のおよそ3分の2が最長18か月支給され、療養中の生活を支える制度です。 - 失業保険(基本手当)
離職後、働ける状態で再就職を目指す人が対象です。
雇用保険から支給され、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって給付日数が異なります。 - 再就職手当
失業保険を受給中に早期に再就職した場合に受けられる給付です。
残りの失業給付日数の一部をまとめて現金で受け取れる仕組みで、早めに就職しても損をしないように設けられています。
これらの制度を状況に応じて組み合わせることで、退職後も安定した生活を維持することが可能になります。
傷病手当金の詳細
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときに、収入の一部を補うために支給される制度です。
退職後であっても一定の条件を満たしていれば、継続して受給することができます。
支給条件
傷病手当金を受け取るためには、次の条件を満たす必要があります。
- 病気やケガにより働けない状態であること
- 連続する3日間を含めて4日以上仕事を休んでいること
- 休んでいる間に給与が支払われていない、または減額されていること
支給額と期間
支給額は 給与の約67% で、最長 1年6か月(18か月) にわたり受け取ることができます。
また、退職後であっても 「資格喪失日の前日までに受給要件を満たしている」 などの条件をクリアしていれば、引き続き受給が可能です。
療養が長期化しても生活を支えられる仕組みとなっています。
失業保険(基本手当)の詳細
失業保険(基本手当)は、仕事を失った後の生活を支えながら再就職を目指す人のための制度です。
働く意思と能力を持ち、積極的に求職活動を行うことが前提条件となります。
支給条件
失業保険を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者期間が 原則12か月以上
※退職理由によっては 6か月以上 で受給可能な場合あり - 働く意思と能力があり、実際に求職活動をしていること
支給額と期間
支給額は 退職前6か月の給与を基準 に計算されます。
支給期間は、年齢や被保険者期間によって異なり、 おおむね3〜5か月 です。
- 自己都合退職の場合:原則 3〜5か月
- 就職困難者認定を受けた場合: 10〜12か月 に延長されるケースもあり
退職理由や就職活動の状況によって受給期間が変わるため、自分がどのケースに当てはまるかを確認しておくことが大切です。
再就職手当の詳細
再就職手当は、失業保険の受給中に早期に就職した人が受け取れる特別な給付制度です。失業給付をすべて受け取り切る前に就職した場合、その“残りの給付日数”に応じて一部がまとめて現金で支給されます。
早く就職するほど支給額が増える仕組みであり、退職後の生活再建に大きな後押しとなる制度です。
● 支給条件
再就職手当を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 失業保険の所定給付日数が 3分の1以上残っている
- 再就職先で 1年以上継続して働く見込みがある
● 支給額と計算方法
支給額は 残っている失業保険の日数 × 失業保険1日分の金額 × 支給率(60か70%) で計算されます。
- 失業給付の残日数が2/3以上→ 70%支給
- 失業給付の残日数が1/3以上2/3未満 → 60%支給
支給率が段階的に変わるため、早く決まれば決まるほど受取額が大きくなる仕組みです。
退職給付金の受給の流れ
傷病手当金と失業保険は、どちらも退職後の生活を支える制度ですが、同時に受給することはできません。
なぜなら、それぞれの制度が対象としている人が正反対だからです。
- 傷病手当金:病気やケガで 働けない人 が対象
- 失業保険:働く意思と能力があり、積極的に活動できる 働ける人 が対象
一般的な受給の順番
退職給付金の制度を最大限活用する場合、以下の流れが基本です。
- 退職後に病気やケガで働けない期間 → 傷病手当金を受給
- 回復して働ける状態になったら → 失業保険を申請
この順序を守ることで、最長で数年間にわたり生活を保障できる可能性があります。
さらに、再就職が早ければ 再就職手当 を受け取れることもあり、経済的に大きな後押しとなります。
手続きに必要な書類
退職給付金を受け取るには、それぞれの制度ごとに必要書類が決められています。
申請のタイミングや提出先を間違えると支給が遅れたり、最悪の場合は受け取れなくなる可能性もあるため注意が必要です。
傷病手当金の場合
- 医師の意見書(傷病手当金支給申請書)
- 事業主の証明(在職中の場合)
これらを健康保険組合へ提出します。
退職後も継続して受給できる場合があるため、退職前に医師と会社に依頼しておくことが大切です。
失業保険(基本手当)の場合
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 証明写真(縦3cm×横2.5cm程度)
- 通帳やキャッシュカード(振込先口座の確認用)
提出先は ハローワーク です。
離職後すぐに手続きできるよう、書類を早めに揃えておきましょう。
再就職手当の場合
-
就職先の雇用契約書や採用通知書など、就職を証明できる書類
就職先が決まったら速やかにハローワークに申請します。
早期再就職をした場合の特典として、残りの失業給付の一部を一括で受け取れる制度です。
退職給付金を最大限活用するポイント
退職給付金を無駄なく受け取り、生活の安定につなげるためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
1. 順序を守る
「傷病手当金 → 失業保険 → 再就職手当」という流れを徹底しましょう。
同時受給はできないため、病気で働けない間は傷病手当金、回復して就職活動が可能になったら失業保険、そして早期就職をしたら再就職手当へと切り替えるのが正しい順番です。
2. 証明書類を確実に用意する
診断書、離職票、雇用保険被保険者証など、申請に必要な書類は制度ごとに異なります。
どれか一つでも欠けていると申請ができず、給付の開始が遅れてしまうため、早めの準備を心がけましょう。
3. 申請期限に注意する
- 傷病手当金:時効は2年。申請が遅れるとさかのぼって受給できないケースがあります。
- 失業保険:退職後1年以内に受給しなければ権利が消滅します。
病気療養中の場合は「受給期間延長」の手続きをしておくことが必須です。
4. 就職困難者認定を検討する
就職状況によっては「就職困難者」と認定され、失業保険の受給期間が10〜12か月に延びる場合があります。
通常の自己都合退職では3〜5か月にとどまることが多いため、条件を満たす人は大きな差となります。
【追加】その他の公的給付制度一覧
| 制度名 | 概要 | 対象者 |
| 教育訓練給付金 | 資格取得の受講費用の20〜70%を給付 | 雇用保険の加入期間が一定以上ある人 |
| 住居確保給付金 | 家賃の一部を国が負担 | 失業中・低所得で家賃負担が厳しい人 |
| 未払賃金立替払制度 | 会社倒産時に未払い賃金を国が立替 | 倒産企業の元従業員 |
| 高年齢雇用継続給付 | 給与が下がった60歳以降に支給 | 高年齢被保険者 |
| 介護休業給付 | 介護休業中の給与の67% | 家族の介護が必要な労働者 |
| 寄宿手当 | 仕事のために自宅を離れる際の手当 | 寄宿を伴う就労者 |
| 移転費 | 求職活動・就職のための移転費用を支援 | 就職のために転居が必要な人 |
退職給付金についてよくある質問(FAQ)
退職給付金(社会保険給付)に関して、当サイトへ多く寄せられる質問にお答えします。
Q1. 会社の「退職金」とは違うのですか?
A. はい、まったく別のものです。
一般的に言われる「退職金」は会社からご褒美として支払われるものですが、本記事で解説している「退職給付金」は、国(保険制度)から支払われるものです。
そのため、会社の退職金制度がない方でも受け取れますし、会社の退職金と国の給付金を「ダブルで受け取る」ことも可能です。
Q2. パート・アルバイトや公務員でも受給できますか?
A. 働き方によって異なります。
パート・アルバイトの方でも、社会保険・雇用保険に加入していれば対象になります。
一方で、公務員の方は雇用保険ではなく独自の補償制度があるため、失業保険の対象外となるケースが一般的です。ご自身の雇用形態が対象かどうかは、以下の記事で詳しく解説しています。
Q3. 「最大28ヶ月・200万円受給」というのは詐欺ではないですか?
A. 制度を正しく活用した「正当な権利」であり、詐欺ではありません。
通常、失業保険だけだと3,4ヶ月で終わりますが、傷病手当金(最大18ヶ月)を組み合わせることで、受給期間が2年以上、総額が数百万円になることは法律上、十分にあり得ます。
ただし、誇大広告を出している悪質な業者も存在するため、正しい知識を持つことが重要です。
Q4. 申請することに「デメリット」はありますか?
A. いくつかの注意点があります。
例えば、受給中は「原則、扶養に入れない(国民健康保険料がかかる)」、「厚生年金の加入期間が空く」といった点が挙げられます。
しかし、それらのコストを差し引いても、手元に残る給付金のメリットの方が大きいケースがほとんどです。
Q5. 受け取った給付金に税金はかかりますか?
A. いいえ、非課税です。
傷病手当金や失業保険は、税法上の所得には当たらないため、所得税や住民税はかかりません。
そのため、受け取った金額がそのまま生活費として使えます。
【管理人(社労士受験生)からの重要アドバイス】
残念ながら、ほとんどの人が「失業保険から申請」して損しています。
結論、退職直後にまず確認すべきなのは次の2点です。
- 今の体調で働けるのか?
- 傷病手当金の対象になるのか?
実際、当サイトに相談いただく方の多くが、「傷病手当金 → 失業保険」 という正しい順番を知らないことで、受給総額が100万〜200万円減っているケースが非常に多いです。
一度失業保険の手続きを始めてしまうと、後戻りはできません。
まずは「自分がいくらもらえる可能性があるのか」を知ることから始めましょう。
▼ステップ1:受給額の目安を確認する
年収や勤続年数によって、受給額は大きく変わります。
まずは以下の記事で、一般的なモデルケース(平均的な受給額)を確認してみてください。
▼ステップ2:あなたの正確な金額を算出する
「記事の例ではなく、私の年収だといくら?」「いつまでもらえる?」と正確に知りたい方は、当サイトの公式LINEで個別シミュレーションを行っています。
30秒で終わる質問に答えるだけで、あなたの受給額を算出します。
▼ステップ3:不安な方はプロに相談する
「計算してみたけど、書類の書き方が不安」「会社とのやり取りが怖い」という方は、私たち専門家がサポートします。
社会保険給付金アシストでは、以下のサポートを行っています。
- 退職後も継続して傷病手当金を受給できるよう支援
- 失業保険をより多く、確実に受け取るための申請サポート
あなたの退職後の生活が、少しでも安心できるものになるよう応援しています。
詳しいサポート内容は以下からご覧ください。