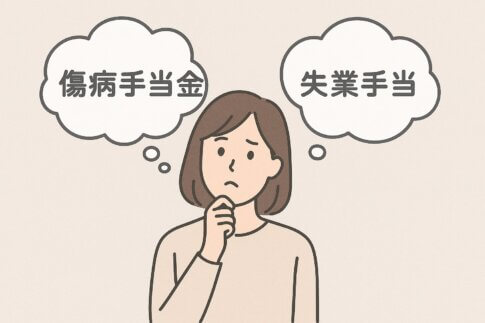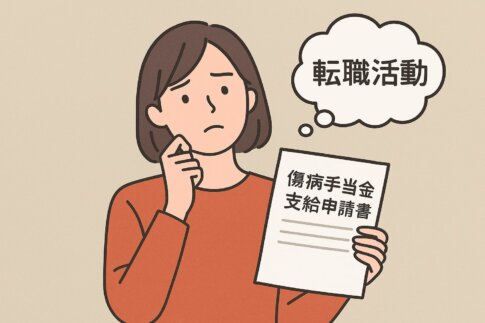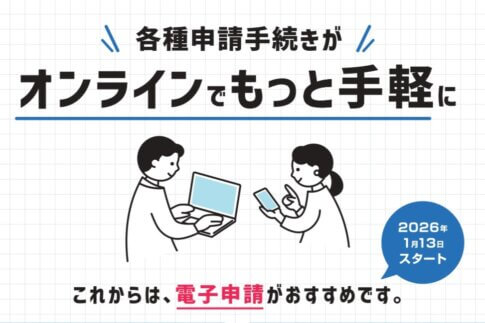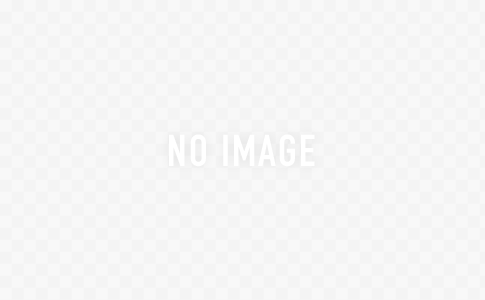「今の病院から別の病院に転院したいけれど、その場合でも傷病手当金はもらえるのだろうか?」と不安に思う方は少なくありません。
実際、治療の都合や引っ越し、担当医との相性などで転院するケースは多くあります。
結論から言えば、条件を満たせば転院後も傷病手当金は受け取れます。
ただし、診断の継続性を証明するために必要な手続きや書類があり、注意を怠ると不支給になってしまうこともあります。
この記事では、転院しても傷病手当金を受給するためのポイントをわかりやすく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

傷病手当金は転院しても受給できる?
結論から言うと、転院しても傷病手当金は受給可能です。
傷病手当金の目的は「働けない期間の生活を保障すること」であり、どの病院で診察を受けたかは本質的には問題ではありません。
ただし、重要なのは以下の2点です。
- 病気やケガが継続していて、治療の必要があること
- 医師が「働けない状態である」と証明していること
つまり、病院が変わったとしても「労務不能状態が継続している」ことを医師の証明で一貫して示せれば、傷病手当金の受給には支障がありません。
転院時に必要な手続きと書類
転院しても傷病手当金は受給できますが、申請には新しい病院での証明が欠かせません。
スムーズに受給を続けるためには、以下の点に注意しましょう。
- 新しい主治医の記載した申請書
傷病手当金を申請する際には、医師が記入する「傷病手当金支給申請書」が必要です。
転院先の医師に、これまでの治療経過や現在の症状を伝えたうえで、「働けない状態」であることを証明してもらう必要があります。 - 前の病院での診断とのつながり
転院前に診断書や紹介状をもらっておくことは非常に重要です。
これらがあれば病気が継続していることを裏付けやすくなります。
逆にこれがないと、転院後に「別の病気」とみなされ、支給が途切れるリスクもあるため注意が必要です。 - 事業主の証明
会社員の場合、申請書には勤務先の証明欄もあります。
転院そのものとは関係なく、従来どおり勤務先を通じて手続きを行う必要があります。
転院でトラブルになりやすいケース
転院そのものは傷病手当金の受給に支障はありません。
しかし、以下のようなケースでは申請がスムーズに進まず、トラブルになることがあります。
- 診断名が変わってしまう
例として、最初は「うつ病」と診断されていたのに、転院後に「適応障害」と記載された場合があります。
病気の内容が変わってしまうと「同じ傷病による継続」と認められず、支給が途切れる可能性があります。 - 病気の継続性が証明されない
前の病院で診断書や紹介状を受け取らずに転院すると、治療に空白期間が生じてしまうことがあります。
その結果「病気が続いていない」と判断され、申請が却下されるリスクがあります。 -
医師の証明が得られない
転院先の医師が、前医との診断のつながりや労務不能状態を十分に理解できない場合、傷病手当金の申請書に必要な証明を書いてもらえないことがあります。
特に精神疾患などは診断の仕方に差があり、証明拒否で困るケースもあります。
退職後に転院する場合の手順
退職後に転院しても、傷病手当金は継続して受給できます。
ただし、前の病院(A病院)と転院先(B病院)の間に「空白期間」を作らないことが重要です。
具体的な転院例
例1:1日も空けずに転院するケース
- 7月31日 … A病院を受診し、診断書や紹介状を取得 申請書に記入してもらう
- 8月1日 … B病院を受診し、翌日からの労務不能を証明してもらう
→ A病院とB病院の間に空白がないため、スムーズに継続受給可能。
例2:日をまたいでも空白を作らないケース
- 7月15日 … A病院を受診し、診断書や紹介状を取得
- 7月20日 … B病院を受診して治療を継続
- 7月31日 … A病院で申請書に記入してもらう(7月分の労務不能証明)
- 8月31日 … B病院で申請書に記入してもらう(8月分の労務不能証明)
→ 受診の間隔は空いているが、7月と8月それぞれで証明が取れているため、病気の継続性が認められる。
つまり、月ごとの証明に途切れがないことがポイントです。
転院のタイミングがずれても、きちんと前後で証明を揃えれば傷病手当金は止まりません。
【NG例】:空白期間ができてしまうケース
- 7月30日 … A病院を最後に受診
- 8月5日 … B病院を初めて受診
→ 7月31日〜8月4日の間が「空白期間」になるため、この時点で傷病手当金の受給がストップ。
注意すべきなのは、退職後は1日でも空白ができてしまうと、以降の傷病手当金が再度支給されなくなる点です。
現役の会社員であれば「次の申請から再開」という扱いが可能ですが、退職後は資格が喪失しているため、受給権そのものが消滅してしまいます。
転院する際の注意点
傷病手当金をスムーズに受給し続けるためには、転院時にいくつかの重要なポイントがあります。
以下を必ず押さえておきましょう。
- 退職後の転院は空白期間を作らない
退職後は、受診が1日でも途切れると傷病手当金の受給権が消滅します。
基本は、前の病院の最終受診日の翌日に転院先の初診日を設定することです。
ただし、例2のように通院が切れ目なく継続していると認められる場合は受給権が維持されることもあります。
いずれにせよ、「病気の継続性」と「通院の連続性」を証明できるよう、受診日の調整が欠かせません。 - 転院先の予約は早めに取る
病院は予約制で混み合うことが多く、希望日に受診できないケースがあります。
特に退職後は1日の空白でも致命的になるため、前の病院の受診日と近い日程で診てもらえるよう、早めに予約を入れておきましょう。 - 紹介状や診断書を必ずもらう
転院先の医師がスムーズに「労務不能」を証明できるよう、前の病院で紹介状や直近の診断書を受け取っておきましょう。
これにより「病気が継続している」ことを裏付けられます。 - 病名の一貫性を保つ
転院先で診断名が変わると、「別の病気」と扱われるリスクがあります。
これまでの診断内容や症状を正確に伝え、病名の一貫性を保つようにしてください。 - 申請書類の記載と提出を忘れない
傷病手当金の申請には、医師の証明(意見欄)と、在職中であれば事業主の証明も必要です。
転院後も毎月申請が必要になるため、忘れずに依頼・提出しましょう。
社会保険給付金アシストのサポートについて
弊社『社会保険給付金アシスト』では、傷病手当金をスムーズに受給できるよう、転院に伴う手続きや調整もサポートしています。
- オンライン診療の提携クリニックを紹介
自宅から受診できるオンライン診療をご案内できるため、転院先が見つからない・予約が取れないといった不安を軽減できます。 - 転院時のスケジュール調整をサポート
前の病院と新しい病院の受診日が空かないように、適切なスケジュール調整を一緒に進めます。
特に退職後の転院では「1日も空白を作らない」ことが重要なため、安心して準備できます。 - 紹介状や診断書の取得もサポート
転院に必要な紹介状や診断書の取得についてもアドバイスし、申請書類を整えやすいようにサポートします。
転院はどうしても不安が伴いますが、社会保険給付金アシストを利用すれば、受給権を失わずに安心して転院・申請を進めることができます。
まとめ
転院しても傷病手当金は原則として受給可能です。
大切なのは、病気の継続性を証明できることと、医師による「働けない状態」の証明が切れ目なく揃っていることです。
転院前に診断書や紹介状を受け取っておくことで、申請のスムーズさや病気の一貫性を示しやすくなります。
逆に、証明の空白期間や病名の変更などがあると、不支給のリスクにつながるため注意が必要です。
転院は決して珍しいことではありませんが、事前の準備と書類の確保が安心して給付を受け続けるためのカギとなります。
制度を正しく理解し、しっかり備えておくことで、生活保障を途切れさせずに続けることができます。