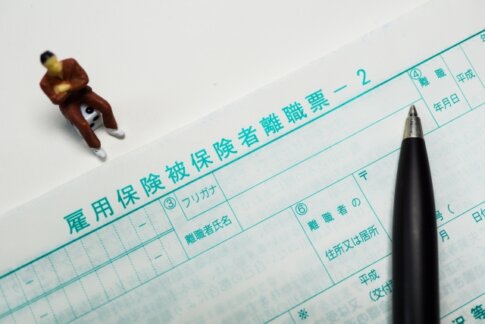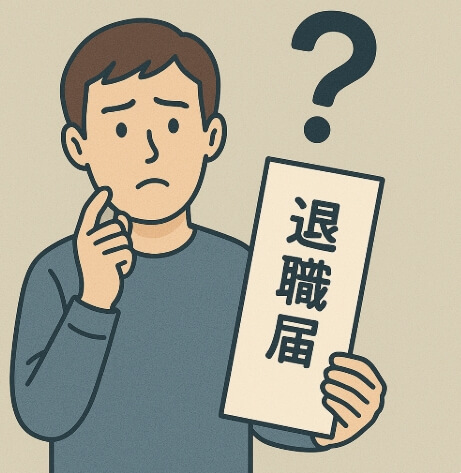退職後は収入が減少し、国民健康保険料(国保)の負担が重く感じられる人も少なくありません。
前年の所得を基に保険料が算定されるため、退職直後でも高額になることがあります。
支払いが厳しいからといって放置すると、延滞金や財産差押えなど深刻なリスクにつながります。
しかし、状況によっては減免制度や徴収猶予などの救済措置を利用できる可能性があります。
本記事では、国保の減免制度の内容、申請方法、放置した場合のリスク、そして負担を軽減するためのその他の方法までをわかりやすく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

国民健康保険料が高くなる理由と退職後の負担感
国民健康保険料(国保)は、前年の所得を基準に計算されます。
そのため、退職直後で現在の収入が減っていても、前年の収入額がそのまま反映されるため、保険料が高く感じられるケースが多いのです。
保険料の計算方法は、大きく以下の3つで構成されています。
- 所得割:前年の所得に応じて課される部分
- 均等割:加入している人数に応じて課される部分
- 平等割:世帯ごとに定額で課される部分
前年の所得が高かった人ほど「所得割」が大きくなるため、退職直後は特に負担が重くなります。
さらに、社会保険に加入していたときは保険料の半分を会社が負担していましたが、国保は全額自己負担です。
そのため、体感的には保険料が倍近くに跳ね上がったように感じる人も少なくありません。
支払いが厳しいときの選択肢
国民健康保険料の支払いが困難なときは、放置せずに早めに役所へ相談することが重要です。
状況に応じて、以下のような制度や方法が活用できます。
1. 減免制度
所得の大幅な減少や失業など、やむを得ない事情がある場合に、保険料の一部または全部を軽減してもらえる制度です。
前年所得や現在の状況を証明する書類(離職票、給与明細など)の提出が必要になります。
2. 徴収猶予制度
災害、病気、失業などで一時的に支払えない場合、納付を一定期間猶予してもらえる制度です。
猶予期間中は延滞金が発生しない場合もありますが、猶予後の支払い計画を立てる必要があります。
3. 分割納付の相談
一括での支払いが難しい場合、役所と相談して毎月の負担を減らす分割払いに変更できます。
無理のない返済計画を提示することで、滞納による差し押さえや保険証の資格制限を回避できます。
4. 生活保護の検討
長期的に収入の見込みがなく、生活が成り立たない場合は、生活保護の申請も選択肢のひとつです。
生活保護が認定されると、国民健康保険料は免除され、医療費も原則自己負担なしになります。
国保の減免制度の詳細
国民健康保険の減免制度は、収入状況や生活環境の変化に応じて保険料を軽減できる仕組みです。
対象理由や減免率は自治体によって異なりますが、主なポイントは以下の通りです。
対象理由
- 失業:退職により給与収入がなくなった場合
- 大幅な所得減少:前年と比べて一定割合以上収入が減った場合
- 災害:火災・水害などによる被害
- 障害:就労困難な障害状態になった場合
特例対象被保険者(非自発的失業者)
倒産・解雇・雇止めなど、本人の意思によらない理由で離職した人(特定受給資格者、特定理由離職者)は、前年の給与所得を30%として算定する特例が適用される場合があります。
この特例により、保険料が大幅に軽減されるケースもあります。
申請には離職票や雇用保険受給資格者証などが必要です。
減免率と期間
減免の割合や適用期間は自治体ごとに異なりますが、1年単位での軽減が一般的です。
更新申請が必要な場合もあるため、期限前に再申請の準備をしておきましょう。
対象外になるケース
- 単なる支払忘れや滞納
- 自己都合退職で所得が大きく減っていない場合
- 収入証明や必要書類を提出できない場合
減免を受けられるかどうかは、申請内容と証拠書類によって判断されます。
制度を利用する際は、必ず早めに役所へ相談し、条件や必要書類を確認しましょう。
減免申請の流れと必要書類
国民健康保険料の減免を受けるには、必ず市区町村役場の国保担当課で申請手続きを行う必要があります。
自治体によって細かな手順や必要書類は異なりますが、一般的な流れは次の通りです。
1. 申請窓口
- 市区町村役場の国民健康保険担当課へ直接訪問、または電話で相談します。
- 一部自治体では郵送やオンライン申請にも対応しています。
2. 必要書類の例
- 減免申請書(役所の窓口やホームページで入手可能)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 離職票や雇用保険受給資格者証(失業による申請の場合)
- 前年の所得証明書(市役所で取得可能)
- 収入見込みが分かる資料(給与明細、年金通知書など)
3. 申請期限
多くの自治体では、申請月以降しか減免が適用されないため、早めの申請が大切です。
申請が遅れると、それ以前の期間については減免が受けられない場合があります。
4. 相談のポイント
申請前に、現在の収入状況や今後の支払い見込みを整理しておくと、窓口でのやり取りがスムーズに進みます。
また、家計の全体像を説明できると、分割納付や猶予制度など他の選択肢も提案してもらえる可能性があります。
国保を放置するとどうなる?(滞納リスク)
国民健康保険料の支払いを放置すると、時間の経過とともに状況は悪化し、生活に大きな影響を及ぼします。
代表的なリスクは以下の通りです。
1. 延滞金の発生
納期限を過ぎると延滞金が加算されます。
延滞金の利率は自治体や滞納期間によって異なりますが、長期間滞納すると負担額が大きく膨らみます。
2. 資格証明書の交付
滞納が続くと、通常の保険証ではなく資格証明書が交付されます。
資格証明書では、医療機関の窓口で医療費を一時的に全額自己負担し、後日申請して一部を払い戻す形になります。
結果として、急な病気やケガの際に大きな出費が必要になります。
3. 財産差押え
さらに滞納が長期化すると、預金口座や給与などの財産が差し押さえられる場合があります。
差押えは事前通知なく行われることもあり、生活資金が突然引き出せなくなる危険性があります。
4. 実際の事例
自治体によっては、数か月の滞納で差押えに至ったケースもあります。
特に高額の保険料を短期間で滞納した場合は、対応が早期に行われる傾向があります。
国保の滞納は、延滞金や差押えなどの法的措置に直結します。
支払いが難しいときは、必ず早めに役所へ相談し、減免や分割納付などの制度を利用することが大切です。
支払い負担を減らすための他の方法
国民健康保険料の支払いが厳しい場合、減免制度や猶予制度だけでなく、次のような方法も併せて検討することで、生活全体の負担を軽減できます。
1. 任意継続との比較
退職後は、最大2年間まで健康保険の任意継続被保険者制度を利用できる場合があります。
任意継続は、国民健康保険より保険料が安くなるケースもあり、特に前年の所得が高く国保が高額になる見込みの人には有効です。
ただし、保険料は全額自己負担(会社負担分なし)となります。
また、一度任意継続をやめて国保へ切り替えると、再び任意継続に戻ることはできないため注意が必要です。
2. 他の公的支援制度との併用
- 失業手当:退職後、一定条件を満たせば雇用保険から基本手当が支給され、生活費の補填に活用できます。
- 傷病手当金:病気やケガで働けない期間の収入補填。
- 住居確保給付金:家賃の一部を一定期間補助。
- 生活福祉資金貸付(緊急小口資金・総合支援資金):生活費の一時的な貸付。
これらを組み合わせることで、医療・住居・生活費といった複数の支出をカバーでき、国保の納付資金を確保しやすくなります。
関連ページ
・【2025年最新版】失業保険の申請から受給まで完全ガイド|申請時の注意点・必要書類・社会保険も解説
・傷病手当金のもらい方を完全ガイド|申請から受給までの流れ・必要書類・注意点を解説
・傷病手当金と失業保険は両方もらえる?切り替えタイミングや条件を解説
・退職後の家賃補助(住居確保給付金)と失業保険は両方もらえる?受給条件や受給金額を詳しく解説!
3. 短期的な収入確保
短期バイトや在宅ワークなど、一時的な収入を得る方法も効果的です。
特に在宅ワークなら、体力的負担を抑えながら収入を確保できます。
ただし、失業手当受給中の場合は収入や就業日数によって減額される可能性があるため、事前にハローワークへ確認しておきましょう。
まとめ
国民健康保険料の支払いが厳しいと感じたら、放置せずに減免や徴収猶予などの制度を早めに活用することが重要です。
滞納を続けると、延滞金の加算や資格証明書の交付、さらには財産差押えといった深刻な事態に発展する可能性があります。
一方で、減免制度や公的支援をうまく組み合わせれば、負担を大幅に軽減し、生活の安定を取り戻すことも可能です。
大切なのは、早めの相談と具体的な行動です。
多くの方は退職理由に人間関係や会社の労働環境を理由としています。それであれば何かしら心身の不調を感じている部分はあるでしょうから、心当たりがあれば退職する前に通院しておくことで国保の保険料を安くすることも可能です。
退職理由によっては、↓失業保険の受給期間を大幅増やすことも可能です。↓
社会保険給付金アシストでは、国保の減免制度をはじめとした各種制度活用や公的給付金の組み合わせをサポートし、あなたの状況に合わせた最適なプランをご提案します。
まずは無料相談で現状を整理し、最適な制度活用の第一歩を踏み出しましょう。