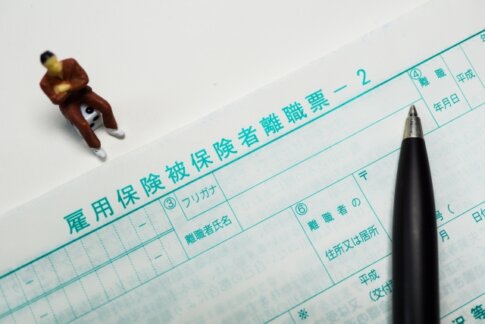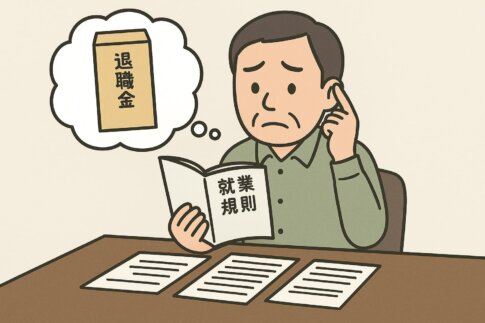退職勧奨という言葉を初めて聞いた方や、実際に会社から打診されて戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
「これはクビなのか?」
「退職届を書かなきゃいけないのか?」
「失業保険はどうなる?」
など、不安や疑問は尽きないものです。
本記事では、退職勧奨の基本から、会社都合・自己都合の違い、応じるべきかの判断ポイント、拒否の可否、そしてその後の手続きや給付制度の活用までをわかりやすく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

退職勧奨とは?制度の基本と他の退職との違い
「退職勧奨(たいしょくかんしょう)」とは、会社が従業員に対して自主的な退職を促す行為を指します。
あくまで話し合いベースのものであり、法的な強制力はありません。
会社側が「辞めてもらえませんか?」と働きかけ、本人が納得したうえで合意に至る形が基本です。
退職の種類には、大きく分けて以下の3つがあります。
- 自己都合退職:従業員が自発的に辞めるケース。通常、失業手当には給付制限がかかります。
- 会社都合退職:人員整理や事業縮小など、会社の事情で辞めさせられるケース。失業手当がすぐに支給されるなど、自己都合より有利な点が多いです。
- 退職勧奨:会社都合に近い性質を持ちながらも、最終的には本人の「同意」によって成立する中間的なケースです。
注意すべきなのは、退職勧奨が行われたにもかかわらず、退職届を提出させられたり、「自己都合で退職してください」といった形で会社都合が自己都合にすり替えられるケースが少なくない点です。
そのため、退職勧奨を受けた際は内容や言い回しに十分注意し、書面や録音などの証拠を残しておくことが、後々のトラブル防止につながります。
退職勧奨は自己都合?それとも会社都合?
退職勧奨に応じて退職した場合、その本質は「会社都合退職」であるべきです。
なぜなら、退職のきっかけを作ったのは会社側であり、従業員が自主的に辞めたわけではないからです。
しかし、実務上はこのような原則が軽視されることも少なくありません。
たとえば、会社から退職届の提出を求められたり、退職合意書にサインをさせられることで、結果的に「自己都合退職」として処理されてしまうケースがあります。
これにより、失業手当の給付開始が遅れる、もらえる期間が短くなるなど、従業員にとって大きな不利益が生じる可能性があります。
こうした不利益を避けるためには、以下のような対応が重要です。
- 退職届の提出を避け、「会社都合退職通知書」の交付を求める
→ 自分の意思ではなく会社都合であることを明確にするための証拠になります。 - 離職票の退職理由欄を必ず確認する
→ ハローワークに提出する際、「自己都合退職」と誤って記載されていないか確認しましょう。 - 必要に応じて、ハローワークに異議申し立てを行う準備をしておく
→ 退職の経緯を説明し、会社都合であることを主張できます。
退職勧奨を受けた際は、感情的に流されることなく、「書類」と「記録」によって自分の立場を守ることが大切です。
退職勧奨されたらどうする?判断のポイントと対応手順
突然、会社から「退職を考えてほしい」と言われたら、戸惑ってしまうのは当然です。
しかし、退職勧奨を受けたからといって、その場ですぐに応じる必要はまったくありません。
まずは冷静に状況を把握し、納得できる形で判断することが大切です。
以下のポイントを参考に、慎重に対応を進めましょう。
1. 退職理由を明確に確認する
「なぜ退職を勧めているのか」「パフォーマンスに問題があるのか」「部署の縮小なのか」など、会社側の理由を明確に聞き出しましょう。
曖昧な説明のまま退職を迫られる場合は、無効な退職勧奨となる可能性があります。
2. 書面の内容を必ず確認する
退職届や同意書にその場でサインを求められることがありますが、その場で書く必要はありません。一度持ち帰って内容を確認し、納得がいかない場合は署名しないようにしましょう。
3. 有給休暇の消化について確認する
退職前に残っている有給休暇をしっかり使えるかどうかを確認してください。
会社によっては「繁忙期だから」などの理由で有給を使わせないケースもありますが、原則として退職時には全日数を消化する権利があります。
4. 離職票の退職理由を確認・予告してもらう
会社に「離職票の退職理由は会社都合で処理してほしい」とあらかじめ伝えておきましょう。
退職理由が自己都合と記載されてしまうと、失業手当の受給に大きく影響するため注意が必要です。
もし納得できない点がある場合は、労働組合や社労士、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
退職は人生に関わる大きな決断です。情報とサポートをしっかり得た上で、自分にとって最善の道を選びましょう。
退職勧奨は拒否できる?断る権利とその後のリスク
退職勧奨とはあくまで会社からの「お願い」であり、法的な強制力はありません。
そのため、従業員には退職勧奨を拒否する権利があります。
納得がいかない場合や、辞めたくない理由がある場合は、堂々と断って問題ありません。
しかしながら、現実には退職勧奨を断った後に、以下のような会社側の対応が見られるケースもあります。
よくある“その後”の会社の対応
- 配置転換や業務内容の大幅な変更
意図的に不慣れな部署に異動させるなど、精神的・肉体的にプレッシャーをかける行為。 - 無視・排除・叱責などのハラスメント行為
これは明らかに違法行為(パワハラ)に該当する可能性があります。 - 最終的に整理解雇を検討される
業績悪化などを理由にした整理解雇の手続きに進むことも。とはいえ、整理解雇には厳格な条件(人員整理の必要性・解雇回避努力・対象選定の妥当性など)が必要です。
拒否するときの注意点
退職勧奨を拒否する場合には、後々のトラブルを避けるために、次のような対策を取ることが重要です。
- やり取りは書面またはメールで残す
口頭のみのやり取りはトラブルの元です。誰がいつ何を言ったか、記録を残しましょう。 - ICレコーダー等で録音しておく(可能な範囲で)
後から「そんなことは言っていない」と否定されないように、音声記録も有効です。 - 必要があれば第三者に相談する
労働組合や社労士、弁護士など、外部の力を借りることで会社との交渉がスムーズになります。
退職勧奨を受けたからといって、必ず辞めなければならないというルールは存在しません。
自分の意思を大切にし、必要なときには冷静かつ計画的に「断る」ことも立派な選択です。
退職勧奨を受け入れたあとの手続きと注意点
退職勧奨に応じて退職することになった場合でも、その後の手続きや確認事項をしっかりと押さえておくことが大切です。
合意退職であっても、対応を誤ると「自己都合退職」として処理されてしまったり、退職金や有給の取り扱いで不利益を被ることがあります。
退職届は必要か?
会社によっては「退職届の提出が必要です」と言われることがありますが、退職勧奨は本来、会社側からの申し出によるものです。
そのため、合意書のみで手続きを進めることも可能です。
退職届を出すことで、形式上「自己都合」として扱われるリスクがあるため、慎重に判断しましょう。
退職理由の記載内容を確認
離職票や退職合意書に記載される退職理由が「自己都合」になっていないか必ず確認しましょう。
退職勧奨に応じた場合は、原則として「会社都合退職」となるべきです。
不安な場合は、離職票のコピーをもらい、ハローワークでも確認してもらうと安心です。
有給休暇や退職金の取り扱い
有給休暇の残日数がある場合は、しっかりと消化できるようスケジュールを調整し、事前に申請しておきましょう。
また、退職金の有無や計算方法についても事前に確認し、納得できる内容であるかをチェックしておくことが重要です。
離職票は必ず受け取り、内容もチェック
失業手当などの制度を利用する際に必要となる離職票は、発行を希望しなければ交付されないこともあります。
必ず「離職票を希望します」と伝えておきましょう。
退職理由や退職日などの記載内容も後の給付に影響するため、細かい点まで確認が必要です。
社会保険給付を活用して、退職後の備えを万全に
退職勧奨によって離職した場合、失業手当の給付制限がなく、早期に給付が始まるのが大きなメリットです。
また、退職時の心身の不調があれば、傷病手当金を活用できるケースもあります。
弊社【社会保険給付金アシスト】では、退職後の生活を支える制度を最大限活用するためのサポートを提供しています。
- 失業手当を有利に受給する方法
- 傷病手当金との切り替えや併用のアドバイス
- 申請書類の準備とハローワーク対応のサポート
退職勧奨を受けたあと、生活への不安を感じる方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
退職勧奨は、法的強制力を伴わない「会社からの提案」に過ぎません。
しかし、対応を誤ると自己都合扱いにされてしまうなど、損をする可能性も。
「流されない判断力」と「正しい知識」が何より重要です。
そして、退職後の手続きや制度の活用も、生活の安心に直結します。
必要に応じて、専門家のサポートを活用することをおすすめします。