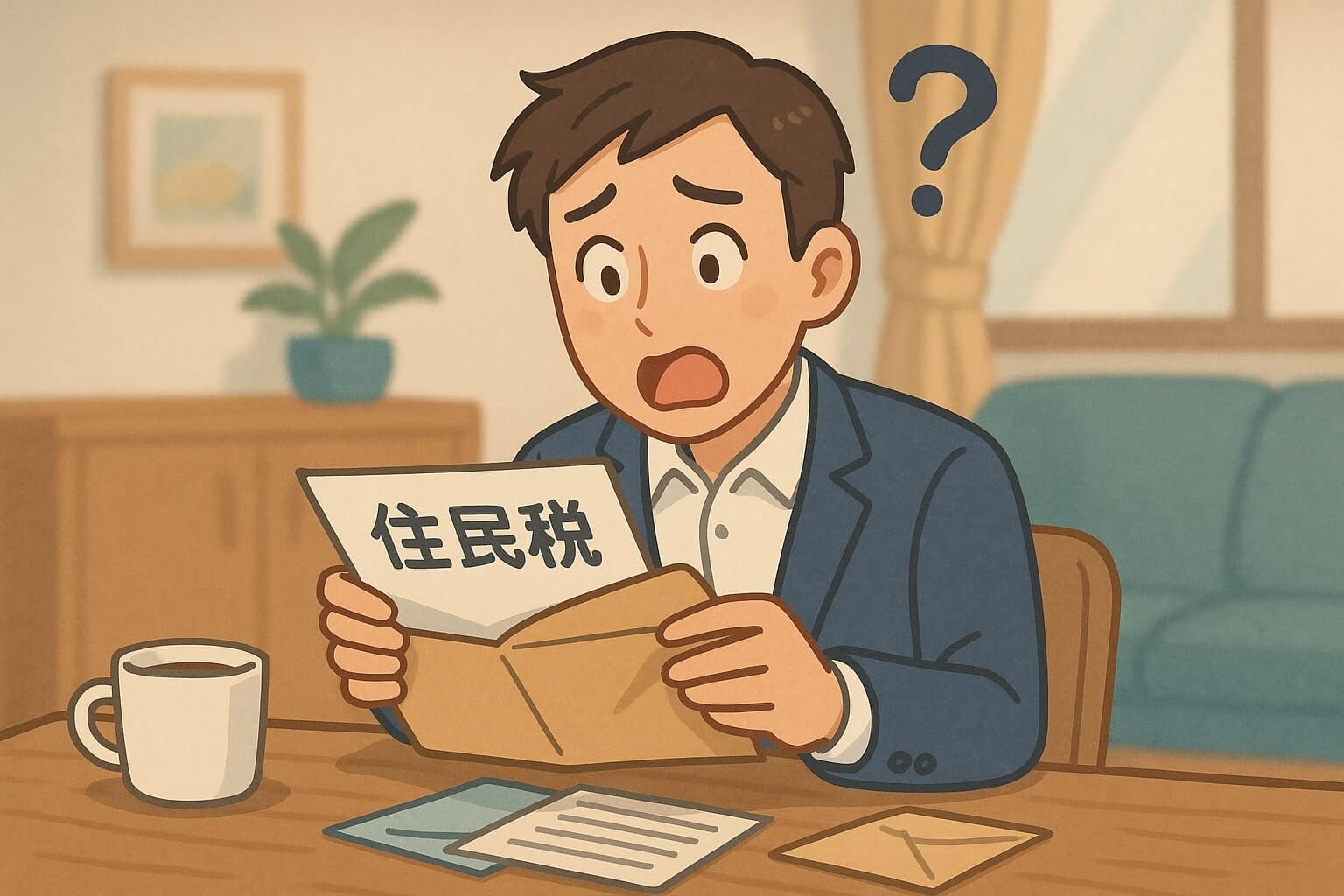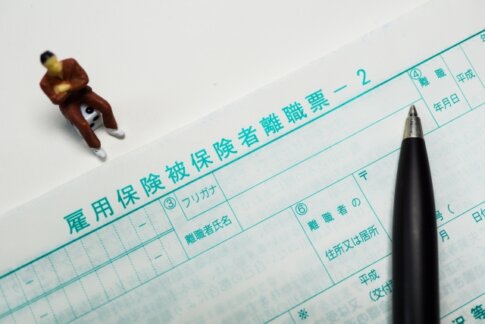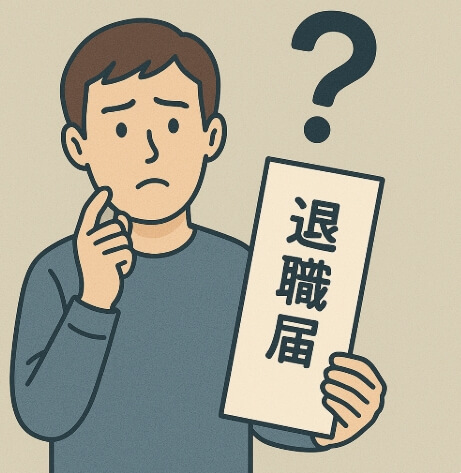退職を控える方やすでに退職された方の中には、「住民税の支払いはどうなるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
実際、退職後に予期せぬ住民税の請求が届いて驚くケースは珍しくありません。
この記事では、住民税の基本から一括徴収と普通徴収の違い、免除制度や支払いが厳しいときの対処法までを、分かりやすく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

住民税とは?退職後も支払い義務は続くの?
住民税は、前年の所得に応じて課税される地方税で、通常は6月から翌年5月までの12か月間で支払う仕組みになっています。
たとえ退職して収入がなくなったとしても、「前年に収入があった」のであれば、その分の住民税を翌年に支払わなければなりません。
つまり、退職後に収入がゼロになっても住民税の支払いは発生するため、「退職したから住民税は免除される」と考えていると大きな誤解を招いてしまいます。
一括徴収と普通徴収の違いとは?退職時にどう決まる?
住民税の支払い方法には「一括徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
- 一括徴収:退職時の給与や退職金から、残りの住民税全額が差し引かれる方法です。
- 普通徴収:後日、自宅に納付書が届き、自分で納付する方法です。
会社が住民税の特別徴収(給与天引き)をしていた場合、退職月が5月以前であれば一括徴収になるケースが多く、6月以降の退職であれば普通徴収に切り替わることが一般的です(自治体によって対応が異なることもあります)。
退職時に一括徴収されるかどうかの確認方法
退職前に、給与明細や会社の経理・総務担当に確認することで、一括徴収されるかどうかを把握できます。
「残りの住民税を退職金から引かれてしまうと生活が厳しくなる」といった不安がある場合は、早めに相談して普通徴収へ切り替えられないか交渉してみるのも一つの手です。
一部の企業では、本人の意思で徴収方法を選べることもあります。
普通徴収になったらどう支払う?納付書・支払い方法・スケジュール
退職後、住民税の納付方法が「普通徴収」に切り替わった場合、会社を通じた天引きではなく、自分で納付を行う必要があります。
以下の内容を押さえておけば、慌てず確実に支払いを進めることができます。
納付書はいつ届く?
普通徴収に切り替わると、退職後しばらくしてから市区町村の税務課より「住民税納付書」が郵送されてきます。
発送時期は自治体によって異なりますが、一般的には毎年 6月中旬〜7月上旬 に届くケースが多いです。
封筒には以下のような書類が同封されています。
- 納付書(分割用が複数枚入っている)
- 納付スケジュールの案内
- 支払い方法に関する説明文
なお、年度途中で退職し普通徴収に切り替わった場合は、年度末(3月)までの残額を再計算したうえで送られてきます。
支払いのスケジュールは?
標準的な納付スケジュールは以下のとおり、年4回の分割払いです。
| 納付期 | 納付期限(例) |
|---|---|
| 第1期 | 6月末 |
| 第2期 | 8月末 |
| 第3期 | 10月末 |
| 第4期 | 翌年1月末 |
※納付書には、期別の納付書(各1枚)と「一括前納用の納付書」も同封されていることが多く、まとめて一括納付も可能です。
分割にするか一括にするかは、自分の都合で自由に選べます。
支払い方法の選択肢
支払い方法は意外と多く、ライフスタイルに応じた方法を選べます。
-
コンビニ支払い:納付書のバーコードを使って、全国の主要コンビニで支払えます(深夜でも対応可能)。
-
金融機関(銀行・郵便局)窓口:窓口で納付書を提示すればその場で支払いできます。
-
スマホ決済:対応自治体であれば、以下のアプリからの納付も可能です。
(PayPay、LINE Pay、d払い、au PAY など)
一部自治体ではクレジットカード払いにも対応しています。
支払い忘れに注意!
普通徴収は「自分で納付する」ため、うっかり納付を忘れてしまうケースが少なくありません。
期限を過ぎると延滞金が加算され、さらに督促状が届いたり、最悪の場合は差し押さえのリスクも発生します。
対策としては、
- スマホのカレンダーやリマインダーに納付日を登録する
- LINE公式アカウントなどで納期限の通知が受け取れる自治体サービスを活用する
- 納付書が届いた時点で一括前納してしまう
などが有効です。
住民税は免除・減額される?退職後の救済制度を解説
退職後、収入が激減してしまった方や、病気・災害などで生活が困難な状況にある方は、住民税の減免や徴収猶予といった救済措置を受けられる可能性があります。
減免・猶予制度とは?
住民税は本来、前年の所得に応じて課税されるため、退職して無収入になった後でも課税されることがあります。
こうした人に向けて、自治体は以下の制度を設けています。
- 減免制度:住民税の全部または一部の支払い義務を免除する制度
- 徴収猶予制度:一定期間、住民税の納付を猶予する制度(延滞金も猶予)
※あくまで「制度がある」というだけで、申請しても必ず通るわけではありません。
各自治体の判断により決定されます。
対象となりやすいケース
以下のような事情がある方は、減免または猶予の対象として認められる可能性があります。
- 退職後、無収入・低所得状態になっている
- 失業保険も受給しておらず、貯金も乏しい
- 病気やけがにより長期療養中
- 自然災害や火災などで家計に大きなダメージがある
- 生活保護を受給している、もしくは受給申請中
減免の基準は自治体ごとに異なりますが、特に「病気・ケガ」「災害」「生活困窮」のいずれかが明確な場合は、審査に通りやすい傾向があります。
申請手続きの流れ
①市区町村の税務課へ相談(電話や窓口)
自分が対象になる可能性があるかを確認しましょう。
②必要書類を揃えて申請
代表的な書類:
- 退職証明書(退職日と理由が記載されたもの)
- 所得証明書または課税証明書
- 離職票や雇用保険受給資格者証(失業手当の有無を確認するため)
- 医師の診断書(療養中の場合)
- 世帯の収支がわかる資料(家計簿や通帳コピーなど)
③審査・決定通知
申請後、1~2か月程度で結果通知が届きます。
減額が認められれば、新しい納付書が再発行されます。
注意点
- 減免申請は 後からでは受け付けてもらえないことが多いため、納期限前の申請が原則です。
- 自治体によっては申請書式が異なるため、必ず事前に役所に相談してから申請しましょう。
- 減免が通らなかった場合でも、分割納付や納付相談には応じてもらえるケースがあります。
住民税の納付に不安があるなら、「払えないから放置」ではなく、すぐに役所へ相談するのが正解です。
申請しなければ、減免の可能性があっても絶対に通りません。
住民税が払えない…そんなときの対処法
退職後、急に収入がなくなってしまい、「住民税が払えない…」と悩む方も多くいらっしゃいます。
しかし、請求書を放置してしまうのは絶対に避けるべき行動です。
住民税は地方税法に基づく義務であり、滞納が続くと延滞金の加算や財産の差押えといった厳しい措置が取られる可能性があります。
支払いが難しいと感じた時点で、早めに行動を起こすことが重要です。
支払いが難しいときの主な対処法
- 分割納付の相談
住民税は、通常4期に分けて納める仕組みですが、事情を説明すればさらに細かい分割納付に応じてくれる自治体もあります。市区町村の税務課に相談し、無理のない支払計画を立てましょう。 - 支払期限の延長(徴収猶予)
一時的な経済的困難や病気・けがなどにより納付が困難な場合は、住民税の納期限を先延ばしにしてもらえる「徴収猶予」の制度を利用できることがあります。審査がありますが、事情を正直に伝えることで柔軟に対応してもらえるケースもあります。 - 減免申請
所得の著しい減少や生活困窮など、一定の条件に当てはまる場合は、住民税の減免(全額または一部免除)が認められる可能性もあります。
社会保険給付を活用して住民税負担を軽くする方法
退職後に頼りになるのが、失業手当や傷病手当金などの社会保険給付制度です。
これらを活用することで、住民税の支払い原資を確保しやすくなります。
弊社「社会保険給付金アシスト」では、退職後の生活を支える各種給付制度(失業手当・傷病手当金など)を、より有利に活用するための総合サポートを行っています。
制度に詳しくない方でも安心して手続きを進められるよう、丁寧に支援しています。
正しい手続きを踏むことで、結果的に住民税や保険料の負担も軽減されるケースが多いため、不安のある方はぜひご相談ください。
まとめ|住民税は退職しても発生。事前準備と制度活用で安心を
退職後の住民税については「知らなかった」では済まされない部分も多く、油断していると突然の出費に慌てることになります。
- 住民税は前年所得に応じて課税され、退職後も支払い義務はある
- 一括徴収か普通徴収かでタイミングと負担が変わる
- 減免制度や公的支援制度を活用することで、負担軽減が可能
しっかりとした理解と準備をすることで、退職後の生活にゆとりと安心を持たせましょう。