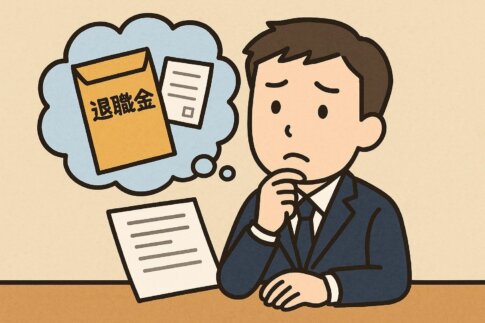「年の途中で退職したけど、確定申告って必要?」
「会社を辞めたあと、何をすればいいのか分からない」
こうした不安を抱えている方は少なくありません。
特に年末調整をしていない場合、所得税の還付を受けるためには自分で確定申告を行う必要があります。
この記事では、途中退職後の確定申告が必要なケースや、申告のやり方、必要書類、注意点などをわかりやすく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

途中退職した人は確定申告が必要?
年末調整を受けていないと、自分で申告する必要があります。
会社員として働いている人の多くは、年末に「年末調整」でその年の所得税を精算します。
これは、年末時点で在籍している社員に対して、会社側が行う手続きです。
しかし、年の途中で退職した場合、年末調整を受ける機会がありません。
そのため、退職後に転職していない、もしくは新しい勤務先で年末調整がされていない場合は、自分で「確定申告」を行って、所得税を調整する必要があります。
確定申告を行うことで、払いすぎた税金の還付を受けられるケースも多く、忘れずに手続きをすることが大切です。
どんなケースで確定申告が必要になるのか
以下のようなケースに該当する場合は、確定申告を行うことで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
- 年の途中で退職し、その後年末まで再就職していない
- 転職して複数の会社に勤務した
- 退職後にアルバイトなど別の収入があった
- 医療費控除やふるさと納税などの控除申請をしたい
- 源泉徴収されていた所得税の還付を受けたい
特に、年末までに再就職していない方は、会社による年末調整が行われていない状態のまま年を越すことになります。
この場合、確定申告はほぼ必須といえます。
確定申告が不要なケース
すべての退職者が必ず確定申告をしなければならないわけではありません。
以下のようなケースでは、確定申告が不要になることもあります。
- 退職時に「年末調整済み」の源泉徴収を受けている場合
- 収入が一定額以下だった場合(所得税がそもそもかかっていない)
- 公的年金のみで受給額が少ない場合
- 所得税の還付を特に求めていない場合
退職後に収入がなくても申告すべき?
「退職してからは無収入だから、確定申告は必要ないのでは?」と考える方も多いかもしれません。しかし、退職前の給与から所得税が源泉徴収されている場合、その金額が本来納めるべき税額よりも多くなっているケースがあります。
その場合、確定申告をすることで払いすぎた所得税が還付される可能性があるため、収入がなかった年であっても申告する価値は十分にあります。
確定申告をすると何が得なの?
「自分に関係ない」と思われがちな確定申告ですが、実は手続きをすることで“お金が戻ってくる”ケースが少なくありません。
①払いすぎた所得税が戻ってくる(還付)
年の途中で退職した場合、月々の給与から天引きされた所得税が過剰になっていることがあります。本来、年末に会社が行う「年末調整」でその過不足が調整されるのですが、退職者の場合は自分で確定申告をして精算しなければなりません。
確定申告を行うことで、払いすぎた税金が「還付金」として口座に振り込まれます。
②医療費控除やふるさと納税の控除も受けられる
退職後に医療費がかさんだ、あるいはふるさと納税をしていたという場合も、確定申告でその情報を申告することで税金の還付が受けられます。
特に以下のような人は、控除を申告することで戻ってくる金額が大きくなる可能性があります。
- 退職後に通院が続いた
- 家族の医療費を多く負担した
- 年内にふるさと納税をしたがワンストップ特例を使っていない
つまり、確定申告をすることで「払いすぎた税金を取り戻せる」だけでなく、「本来使える控除を反映させて追加の還付が受けられる」というメリットがあります。
退職後の確定申告のやり方
確定申告の期間はいつからいつまで?
確定申告は、通常その年の所得について翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。
ただし、税金の還付(払いすぎた所得税の返金)だけを目的とする「還付申告」の場合は、1月から申請可能です。
確定申告の手順(概要)
退職後に確定申告をする場合、以下の流れで手続きを行います。
- 源泉徴収票を用意する
退職時に会社から受け取った源泉徴収票は、申告のベースとなる重要な書類です。 - 控除証明書など必要書類を集める
生命保険料控除、医療費控除、ふるさと納税などがある場合は、各種証明書を揃えておきましょう。 - 申告書を作成する
国税庁の「e-Tax」システムを使うか、書面で申告書を作成します。パソコンやスマホでの申請も可能です。 - 申告書を提出する
完成した申告書を税務署に郵送・持参するか、電子申請で提出します。 - 還付金の振込を待つ
還付がある場合、通常申告から1〜2か月程度で指定口座に振り込まれます。
手続きは一見面倒に感じるかもしれませんが、払いすぎた税金を取り戻すためにはとても重要です。必要書類を揃え、スムーズに進められるよう準備をしておきましょう。
必要書類と準備すべきもの一覧
退職後に確定申告をする際は、以下の書類や情報を事前に揃えておくと、スムーズに申告手続きが行えます。
- 源泉徴収票
退職時に会社から交付されるもので、その年に支払われた給与や天引きされた税額などが記載されています。申告の基本資料として必須です。 - マイナンバーカードまたは本人確認書類
マイナンバーカードの他、通知カード+免許証などの組み合わせでもOKです。 - 各種控除証明書
生命保険料控除や地震保険料控除、国民年金保険料控除などを受ける場合に必要です。年末に保険会社や年金機構から送られてくる証明書を保管しておきましょう。 - 医療費の明細書(医療費控除を使う場合)
医療費控除を申請する際には、1年分の医療費をまとめた明細書(領収書ベース)が必要です。 - 離職票や雇用保険受給資格者証(参考用)
確定申告には直接使いませんが、退職時の状況確認や税務署とのやり取りの参考になる場合があります。
これらの書類は申告内容に応じて必要となるため、少しでも該当しそうなものは早めに整理しておくのがおすすめです。
退職金・失業手当は確定申告が必要?
退職金について
退職金は「退職所得」として扱われ、多くの場合は会社側が「退職所得の受給に関する申告書」をもとに源泉徴収を行って完結しているため、基本的に確定申告は不要です。
ただし、受給に関する申告書を提出していない場合や、複数箇所から退職金を受け取った場合などは、申告が必要になるケースもあります。
失業手当について
ハローワークから支給される失業手当(雇用保険の基本手当)は非課税です。
そのため、確定申告の対象にはなりません。
なお、弊社では失業手当をできるだけ有利に受け取るためのサポートも行っています。
よくある誤解と注意点まとめ
確定申告にまつわる情報は複雑で、誤解されやすいポイントも多くあります。
以下は、退職後の確定申告で特に注意すべき点と、よくある勘違いの例です。
源泉徴収票が会社から届かない → 再発行を依頼できる
退職後に会社から源泉徴収票が送られてこない場合でも、元の勤務先に連絡すれば再発行してもらうことが可能です。
申告には必須の書類なので、届かないまま放置せず、早めに依頼しましょう。
「少額のバイトだから申告不要」は危険 → 所得額を確認すべき
短期アルバイトや単発の仕事でも、収入が一定額を超えると申告義務が発生します。
仮に申告が必要な収入なのに申告をしなかった場合、後から追徴課税を受けるリスクもあるため注意が必要です。
医療費控除は家族分も合算OK → ただし上限に注意
医療費控除は、自分だけでなく生計を一にする家族の分もまとめて申請できます。
ただし、控除の計算には上限や条件があるため、事前に国税庁のサイトなどで確認するのが安心です。
書面よりe-Taxの方が還付が早い
確定申告の方法には「書面提出」と「e-Tax(電子申告)」がありますが、e-Taxで申告した方が還付までの期間が短い傾向にあります。
マイナンバーカードやICカードリーダーの準備ができる方は、ぜひ活用を検討しましょう。
まとめ|「途中退職者は確定申告」が基本。必要書類と流れを押さえよう
途中退職した場合、年末調整がされていないことで還付申告が必要なケースが多くなります。
申告を怠ると、払いすぎた税金を取り戻せないままになることも。
無職で収入が少ない方でも、申告によって生活資金の一部が戻るケースもあります。
手間を惜しまず、必要な書類を揃えて正しく手続きしましょう。
なお、弊社では退職後の公的制度や給付金に関するサポートも行っております。
申告や制度利用でお困りの方は、お気軽にご相談ください。