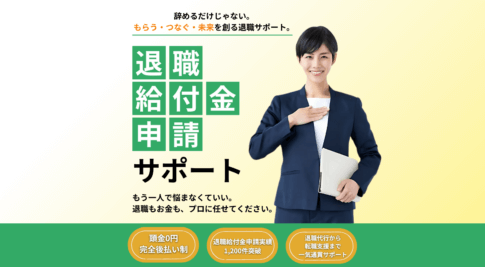退職時に「誓約書へのサインをお願いします」と会社から言われて戸惑った経験はありませんか?
これまで何年も勤めてきた会社から、最後の最後に何かを誓わされることに、不安や疑問を感じるのは当然のことです。
「これってサインしなきゃいけないの?」
「同業他社に転職できなくなる?」
「拒否したら退職金がもらえないのでは?」
この記事では、そうした悩みを持つ方に向けて、退職時の誓約書の効力や拒否の可否、同業他社への転職制限の実態まで、法的視点からわかりやすく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

退職時に提出を求められる「誓約書」とは?
誓約書とは、退職者に対して会社が「今後守ってほしいこと」を文書化して署名を求める書面です。
多くの場合、以下のような内容が含まれています。
- 守秘義務(会社の機密情報を漏らさない)
- 社用物の返却
- 同業他社への転職禁止(競業避止義務)
- 会社への不利益行為の禁止
これらの内容は会社にとっては重要ですが、あくまで「契約書」とは異なり、法的な義務としてサインが強制されるものではありません。
会社によっては「退職合意書」と混同しているケースもありますが、内容と目的は異なります。
誓約書にサインしないとどうなる?拒否は可能?
結論から言えば、誓約書へのサインは拒否可能です。
サインを拒否したからといって退職できなくなることはなく、また法律上のペナルティが科されることもありません。
しかし一部の会社では、
- サインしないと退職金を支払わない
- 同意しないと離職票を出さない
といった不当な対応をしてくるケースもあります。
このような行為は労働基準法や判例上、明確な違法行為となる可能性があります。
退職金は就業規則や労働契約に基づいて支払われるものであり、「サインしたかどうか」で左右されるものではありません。
また、離職票はハローワークへ提出する法定書類であり、交付の義務があります。
誓約書に含まれやすい守秘義務・同業他社への転職制限の効力
退職時に渡される誓約書には、「会社の秘密を守ること」や「同業他社には転職しないこと」などが記載されていることがあります。
これらの条項は、本当に法的に効力があるのでしょうか?それぞれ詳しく見ていきましょう。
守秘義務の効力について
まず、「守秘義務」はたとえ誓約書に明記されていなかったとしても、不正競争防止法や民法上の信義則に基づいて、一定の範囲では自動的に課される義務とされています。
とはいえ、その範囲には限界があります。
たとえば、以下のような情報は守秘義務の対象外となる可能性があります。
- すでに一般に公表されている情報(例:会社ホームページやプレスリリースに載っている内容)
- 自分が業務とは無関係に独自に知った情報
つまり、すべての情報を一律に「外部に漏らすな」と制限することはできず、秘密として保護される情報には一定の基準があるのです。
同業他社への転職制限(競業避止義務)は有効?
「今後2年間、同業他社への転職を禁止する」といった条項が誓約書に書かれていることもあります。
ですが、このような内容は、個人の職業選択の自由(憲法22条)を不当に制限するものとして、原則として無効になる可能性が高いです。
ただし、以下のような条件が整っていれば、一定の効力が認められることもあります。
- 業種・地域・職種が明確に限定されていること
- 制限の期間が合理的であること(通常1年以内が目安)
- 対価(補償金など)を支払っていること
これらの条件が揃っていない誓約書については、「一方的に従業員の自由を奪う内容」として、後に法的に争われた際に無効と判断される可能性が非常に高いです。
法的に効力のある誓約書と無効な誓約書の違い
退職時に渡される誓約書は、すべてが法的に効力を持つわけではありません。
内容によっては、そもそも効力がなく、後で無効と判断されるものも存在します。
ここでは、有効と認められやすい誓約書と、無効になりやすい誓約書の違いを解説します。
有効とされやすい誓約書の特徴
以下のような条件を満たしていれば、誓約書は法的にも有効と認められる可能性が高いとされています。
- 内容が具体的で、本人が理解できる表現になっている
- 制限の範囲が明確に定められている(例:業種・地域・企業名など)
- 制限に見合った対価(補償金や退職金上乗せ)が用意されている
たとえば、次のようなものは実務上も比較的よく見られるパターンです。
- 「退職後6ヶ月間、当社が指定する競合企業への転職を控えること」
- 「この条件に同意した場合は、特別退職金として30万円を支給する」
このように、期間や対象が限定的で、対価が支払われる形であれば、裁判でも有効と判断される可能性があります。
無効とされやすい誓約書の特徴
一方、以下のような内容が含まれている誓約書は、明らかに労働者に不利すぎるとして無効になる可能性が高いです。
- 「今後一切、同業他社に転職しないこと」といった過度で抽象的な制限
- 「守秘義務違反があれば一律500万円の損害賠償」といった、実際の損害額に見合わない高額ペナルティ
これらは「労働者の職業選択の自由」や「契約の公平性」に反するものであり、実際の裁判でも無効と判断されたケースが数多く存在します。
誓約書を拒否したいときの対応方法と注意点
退職時に誓約書へのサインを求められたものの、内容に納得がいかない…。
そんなとき、どう対応すればよいのでしょうか?
まず大切なのは、感情的にならず冷静に対処することです。
「サインしない権利」はある。まずは持ち帰って検討を
誓約書はあくまで会社からの提示であり、その場で即座にサインする義務はありません。
内容に少しでも不安がある場合は、無理に応じずにこう伝えてみましょう:
「一度持ち帰って、よく検討させてください。」
この一言だけでも、不用意なサインによるトラブルを防ぐことができます。
修正や交渉も可能
誓約書の内容に問題があると感じた場合は、「この文言だけ削除できませんか?」「ここはもう少し明確にしてほしい」など、具体的な修正案を提示して交渉することも可能です。
ただし、企業側の反応によっては応じてもらえないこともあるため、あくまで交渉は冷静かつ記録を残しながら行うのがベストです。
それでも強引にサインを迫られたら
会社がしつこくサインを求めてきたり、「サインしないと退職できない」などと脅すような態度をとってきた場合は、以下のような第三者に相談しましょう。
- 労働組合(加入していれば、交渉代行やアドバイスを受けられる)
- 労働基準監督署(明らかに違法な圧力がある場合に対応してくれる)
- 弁護士や退職代行サービス(法的リスクや対応方針について相談可能)
特に、うつ症状など心身の不調がある場合は、誓約書のプレッシャーが大きなストレスになることもあるため注意が必要です。
「一度サインしてしまうと後戻りできない」こともあります。
不安な場合は一人で抱え込まず、第三者のサポートを上手に使うことが、自分を守る第一歩になります。
不当な誓約書・トラブル対応は専門家に相談を
退職は一生に数回の重要な節目です。誓約書の内容によっては、今後のキャリアに不利益をもたらす可能性もあります。
「面倒だからとりあえずサインしておこう」と考える前に、少し立ち止まって検討してみましょう。
不安がある場合は、退職代行や社労士、労働問題に強い弁護士などの専門家に相談することで、安心して円満退職を実現できます。
会社から不当なプレッシャーを受けている方は、一人で抱え込まずに、外部の専門機関やサービスを活用してください。
退職後の生活を少しでも安定させるために
退職時には、誓約書や会社とのやりとりだけでなく、「この先の生活はどうなるのか」といった不安を抱える方も少なくありません。
そんなときに役立つのが、失業手当などの社会保険給付制度を上手に活用することです。
正しく制度を使えば、退職後の生活を安定させる大きな助けになります。
弊社では、失業手当をより早く、より多く受給できるよう支援する『社会保険給付金アシスト』というサービスを提供しています。
制度を理解し、自分に合った方法で活用することで、退職後の見通しは大きく変わります。
気になる方は、以下のページからお気軽にご相談ください。