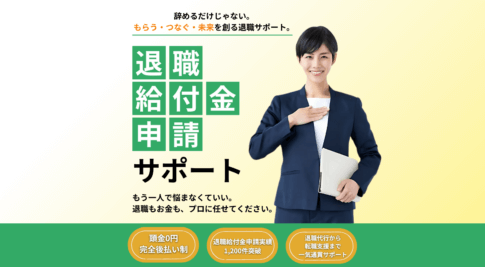「長年働いたのに退職金がないなんて…違法じゃないの?」
そんな不安や疑問を持つ方も少なくありません。
特に、いざ退職を迎えた際に「退職金は出ません」と言われると、今後の生活設計そのものが狂ってしまうことも。
この記事では、退職金が出ない理由や違法性の有無、そしてその後に取るべき現実的な選択肢までを詳しく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

退職金がないのは違法なのか?
結論から言えば、「退職金が出ないこと自体は違法ではありません」。
退職金制度は、企業が任意で設ける制度であり、法律で一律に義務付けられているわけではないのです。
労働基準法にも、退職金の支給を義務付ける条文は存在しません。
しかし、企業が就業規則や労働契約書、退職金規程などで退職金の支給について明記している場合は、その内容に従う必要があります。
この場合に退職金が支払われないとすれば、契約違反となる可能性があります。
なぜ退職金が出ない?よくある4つの理由
「退職金が出ると思っていたのに、実際には支給されなかった…」
そんなケースは決して珍しくありません。
退職金は法律で義務付けられている制度ではないため、企業ごとに支給の有無や条件が異なります。
ここでは、退職金が支給されない代表的な理由を4つご紹介します。
1. そもそも退職金制度がない会社だった
意外に思われるかもしれませんが、退職金制度そのものを設けていない企業も存在します。
特に中小企業では「退職金制度なし」と明示しているケースも少なくありません。
これは違法ではなく、就業規則や退職金規程に制度がなければ、そもそも支給の対象にはなりません。
2. 雇用形態が退職金制度の対象外だった
退職金制度があっても、パート・アルバイト・契約社員などの非正規雇用者は制度の対象外となっていることがあります。
正社員であっても、試用期間中の退職など、条件によっては対象から外れることもあるため、あらかじめ制度の規定を確認しておくことが重要です。
3. 勤続年数が短かった
退職金には「在籍〇年以上」などの支給要件が設けられていることが一般的です。
たとえば「3年以上勤務した場合に支給」といったルールがあり、それに満たないと不支給になる場合があります。
数ヶ月~1年未満で退職した場合は、たとえ正社員であっても退職金がもらえない可能性があるのです。
4. 自己都合退職による減額・不支給
同じ会社でも、「会社都合退職」と「自己都合退職」では、退職金の支給条件や金額に差が出るケースがあります。
企業によっては、自己都合退職の場合に退職金を支給しない、あるいは大きく減額する規程を設けていることもあります。
自分が退職金の対象かを確認するには?
退職金が支給されるかどうかは、個々の会社や自分の雇用条件によって異なります。
「退職金制度がある会社なのか」「自分が対象になっているのか」を事前に確認することが、後々のトラブル回避に直結します。
ここでは、自分が退職金の対象者かどうかを確認するための基本的なステップを紹介します。
① 就業規則・退職金規程を確認する
まず確認すべきは、会社の就業規則や退職金規程です。
ここには、退職金制度の有無、支給対象となる雇用形態や勤続年数、支給額の計算方法などが詳細に記載されています。
社内のイントラネットや総務部から配布される資料などに掲載されていることが多いため、まずは社内で確認できる資料をチェックしましょう。
② 人事・総務に問い合わせる
制度の内容や自分の適用対象かどうかについて不明点がある場合は、人事部門や総務部門に直接問い合わせるのが確実です。
退職直前ではなく、できれば数か月前の余裕のあるタイミングで確認しておくことで、計画的な資金設計が可能になります。
③ 雇用契約書を見直す
意外と見落とされがちなのが、入社時に交わした雇用契約書の内容です。
ここに「退職金制度の適用を受ける」といった記載があれば、会社の制度に基づき、退職金の支給が見込まれます。
逆に、「退職金制度の対象外」「退職金は支給しない」といった文言がある場合、支給対象外となる可能性もありますので、文面をよく確認することが重要です。
退職金がない場合、どうすればいい?
退職金が出ないからといって、すべてを諦める必要はありません。
実は、退職後にもらえる「公的なお金」は複数存在しており、それらを活用することで退職後の生活資金を確保することが可能です。
退職金がなくても使える主な制度3つ
「退職金がもらえなかった…」という場合でも、公的な支援制度を使えば、退職後の生活をしっかりサポートできます。
ここでは、代表的な3つの制度をご紹介します。
1. 失業手当(基本手当)
ハローワークで求職の申し込みをすれば、一定の条件を満たすことで失業手当を受け取ることができます。
- 最大330日間の給付(年齢・雇用保険の加入期間などによる)
- 退職金の有無は関係ありません
- 自己都合退職でも条件を満たせばOK
2. 再就職手当
早く再就職が決まった場合には、残っている失業手当の60~70%が一括で支給されます。
たとえば、60日分が残っていれば、そのうちの70%=42日分相当の金額がもらえます。
3. 傷病手当金
退職前から病気やケガで会社を休んでいた方は、退職後も「傷病手当金」を受け取れる場合があります。
- 最長で1年6か月間、支給される可能性あり
- 精神的な不調(うつ病など)で退職した方にも利用されることが多い制度です
これらの制度をうまく活用すれば、退職金がない場合でも、しっかりと生活を立て直すことができます。まずは自分が使える制度を確認してみましょう。
退職金がなくても、“退職後の支出を抑える”工夫とは?
退職金がもらえなかった場合、頼れる収入がない分、支出を抑える工夫が非常に重要になります。
実は「受け取るお金」を増やすだけでなく、「支出を減らす」ことで生活資金にゆとりを持たせることが可能です。
以下のような制度を活用すれば、手元に残るお金を増やすことができます。
①国民健康保険の減免制度を活用する
退職後に加入する国民健康保険は、前年の所得を基に保険料が決定されますが、所得の急減があった場合は減免申請が可能です。
たとえば、「退職して収入がゼロに近くなった」場合、保険料が大幅に軽減されることがあります。
申請先はお住まいの市区町村役所。退職証明書や離職票、収入見込みのわかる資料を添えて申請することで、年間数万円単位で保険料が下がるケースもあります。
②住民税の非課税世帯に該当する可能性も
退職後に収入が下がると、住民税が「非課税」扱いになる可能性も出てきます。
住民税非課税世帯になると、以下のような公的支援も受けやすくなります。
- 国民健康保険料の軽減幅がさらに広がる
- 医療費の自己負担限度額が引き下げられる
- 公共料金や各種助成制度(保育料・奨学金など)で優遇されることも
自分が非課税世帯に該当するかどうかは、自治体の住民税課などで確認できます。
③高額療養費制度を使って医療費の負担を軽減
退職後に通院や治療が必要な方は、高額療養費制度の利用も視野に入れましょう。
これは、ひと月の医療費が一定額を超えた場合に、超えた分があとから払い戻される制度です。
たとえば、低所得世帯の場合、1か月の自己負担限度額が月3万円以下に抑えられるケースもあり、突然の入院や長期通院に備えることができます。
④国民年金の免除・減額制度を活用しよう
退職後、収入がなくなって国民年金の保険料(月額約17,000円)が負担に感じる方も多いかと思います。
そんなときは、市区町村の窓口で免除や納付猶予の申請をすることで、保険料の支払いを減らしたり先送りしたりすることができます。
- 全額免除・一部免除:所得に応じて支払いを減らせる
- 納付猶予:50歳未満で収入が少ない人は、あとで支払うことも可能
免除や猶予を受けても、将来の年金受給資格にはカウントされるので、未納にするより安心です。
まとめ:退職金がなくても、生活を立て直す選択肢はある
退職金が支給されないことは必ずしも違法ではありませんが、制度の有無や条件は自分でしっかり確認しておく必要があります。
そして、退職金がなかったとしても、失業手当・再就職手当・健康保険や年金の減免制度など、公的な支援を上手に活用すれば、生活を安定させることは十分に可能です。
「自分がどの制度を使えるのか分からない」「うまく手続きを進められるか不安」という方は、早めに専門サポートを利用してみてください。
社会保険給付金アシストでは、退職後の制度活用について丁寧にサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。