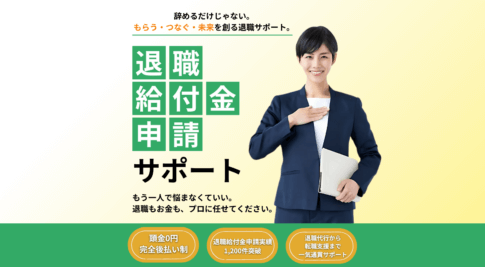退職後、突然届いた国民年金の納付書に驚いた経験はありませんか?
「仕事を辞めて収入がないのに、どうして払わないといけないの?」と感じる方も多いでしょう。
実は、退職後に利用できる“免除制度”が存在します。
この記事では、国民年金の免除制度の仕組みや申請方法、注意点までわかりやすく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

なぜ退職後に国民年金を払う必要があるの?
会社員時代は、厚生年金に加入しており、保険料は給与から天引きされていました。
しかし退職後は、原則として国民年金への切り替えが必要になります。
国民年金は、20歳から60歳までのすべての人に加入義務があるため、無職であっても支払う必要があるのです。
「収入がゼロだから支払いは不要」というわけではなく、納付書が届いたら放置せず対応することが大切です。
国民年金の免除制度とは?
国民年金の保険料が払えない…
そんなときに頼れるのが「免除制度」です。
これは、収入が少ない方や失業中の方などを対象に、年金保険料の負担を軽減・猶予してくれる制度です。
主な免除の種類
免除制度にはいくつかの種類があり、経済状況に応じて適用されます。
①全額免除
保険料の全額が免除されます。所得が極めて少ない方が対象です。
②一部免除
- 3/4免除
- 半額免除
- 1/4免除
上記のように、一部のみ支払えばよい仕組みです。
③納付猶予制度
50歳未満の人などが対象で、「今は払えないが、後で払いたい」場合に利用できます。
審査基準について
免除の審査では、本人・配偶者・世帯主の所得状況が見られます。
前年の所得をもとに基準額以下であれば、免除や猶予が認められます。
原則として、1年ごとの申請と審査が必要になります。
「払えないから放置」ではなく、こうした制度を活用することで、将来の年金受給権を守ることができます。
経済的に厳しい状況でも、まずは申請することが大切です。
退職後に使える「特例免除」とは?
退職後に国民年金の支払いが難しいという方には、通常の免除制度に加えて「特例免除(失業等による特例)」という仕組みがあります。
この制度では、離職によって収入がなくなったことを証明することで、前年の所得を「ゼロ」とみなして審査されるため、通常よりも格段に免除が通りやすくなります。
特例免除の主なポイント
- 自己都合退職でも利用可能
会社都合だけでなく、自主的に辞めた場合でも対象になります。 - 所得審査が実質不要
提出書類により、前年の所得がゼロと扱われるため、通常の免除よりもハードルが低いです。 - 申請期限は離職から2年以内
過ぎると利用できなくなるため、早めの手続きが必要です。
申請方法
申請は、お住まいの市区町村役所の年金窓口で行います。
持参すべき書類は以下の通りです。
- 離職票 または 雇用保険受給資格者証
- 年金手帳 または 基礎年金番号がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
退職してすぐに収入が途絶える中で、国民年金の支払いが不安になるのは当然のこと。
この「特例免除」は、そうした方に向けた強力なサポート制度です。
まずは役所で相談して、条件に該当するかを確認してみましょう。
国民年金免除のメリット・デメリット
国民年金の免除制度は、経済的に厳しい状況でも「未納」にならずに年金制度へ継続加入できる大切な仕組みです。
ただし、メリットだけでなく、いくつかの注意点もあります。
メリット
- 未納扱いにならず、年金加入期間としてカウントされる
免除期間中も「加入期間」として認められるため、将来の受給資格に影響しません。 - 受給資格の10年要件に含まれる
年金をもらうためには原則10年以上の加入が必要ですが、免除期間もこの計算に含まれます。 - 一部免除でも生活負担の軽減に
たとえば「半額免除」であれば、保険料は半分で済み、残り半分の支払いで年金額が一部保障されます。
デメリット
- 将来の年金額が減る
免除中は保険料を全額支払った場合よりも、受給額が少なくなります。 - 追納しないと満額受給にならない
免除期間中の保険料を10年以内に追納すれば、将来の年金額を満額に近づけることも可能ですが、追納しなければその分受給額は減ります。
免除申請を出すことが大切
経済的に保険料を支払うのが難しい場合でも、「何もしない=未納」にするのはNGです。
未納は年金加入期間にカウントされず、将来的に年金が一切もらえなくなる可能性もあります。
一方、免除申請を出して認定されれば、加入期間として扱われ、将来の受給資格を守ることができます。
「払えないから放置」ではなく、「払えないから手続きする」ことが、将来の安心につながります。
国民年金免除の申請時に気をつけたいポイント
国民年金の免除制度を利用する際は、以下の点に注意が必要です。
- 申請は年度単位(毎年7月〜翌年6月分)で行う必要があります。
1回申請すれば永続的に免除されるわけではなく、あくまで1年ごとの審査・認定です。 - 継続して免除を希望する場合も、更新手続きが必要です。
前年に免除されていても、翌年度分は自動的に延長されません。期限内に再申請しないと「未納扱い」になってしまう恐れがあります。 - 失業特例の申請も「離職後2年以内」が期限です。
離職票などの証明書が必要になるため、紛失せずに保管しておきましょう。
こうしたポイントを知らずに手続きを忘れてしまうと、本来使える制度を逃してしまいます。
制度を正しく理解し、必要なタイミングで申請することが大切です。
退職後に他にも使える支援制度は?
国民年金の免除制度だけでなく、退職後の生活を支える公的制度は他にも存在します。
以下のような制度を組み合わせて活用することで、金銭的な不安を大きく軽減することができます。
①失業手当(基本手当)
ハローワークに求職の申し込みをすると、雇用保険に加入していた期間や退職理由に応じて失業手当が支給されます。
給付日数は90~150日となり、再就職までの生活資金として役立ちます。
なお、弊社では失業手当をできるだけ有利に受け取るためのサポートも行っています。
②再就職手当
失業手当の支給途中に早期で再就職が決まった場合、残りの給付日数に応じて「再就職手当」が一括で支給されます。
受給できる金額は、残りの失業手当の60~70%相当です。
再就職を目指す人にとっては、重要なインセンティブになります。
③傷病手当金
退職前に病気やケガで休職していた場合、健康保険からの「傷病手当金」を退職後も受給できるケースがあります。
条件を満たせば、最長で1年6か月間、月給のおよそ2/3が支給されます。
うつ病など精神的な疾患も対象になるため、体調がすぐれない人にとっては特に重要です。
これらの制度は併用や時期をずらして活用することも可能です。
「退職後にお金がない…」と悩む前に、どの制度が自分に該当するのかを確認しておきましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 国民年金の免除制度って誰でも利用できるの?
A. 所得が少ない人や失業中の人が対象です。
審査では「本人・配偶者・世帯主」の前年所得が基準になります。失業した場合には「特例免除」も使えます。
Q. 免除と猶予の違いは何ですか?
A. 「免除」は支払い義務を減らす制度で、将来の年金受給資格にもカウントされます。
「猶予」は支払いを先延ばしにする制度で、主に50歳未満の方が対象です。
Q. 退職して収入がゼロでも、年金免除の審査に通らないことはある?
A. 本人の収入がゼロでも、配偶者や世帯主の所得が多い場合は免除が通らないこともあります。
失業者特例を利用すれば、本人の所得のみで審査されます。
Q. 免除制度を利用すると、将来の年金はもらえなくなる?
A. いいえ、免除期間も「受給資格期間」としてカウントされます。
ただし、支払った期間より年金額は少なくなります。
将来「追納」すれば満額に近づけることも可能です。
Q. 免除申請はいつまでにすればいいの?
A. 対象となる年度(7月〜翌年6月)の末までに申請が必要です。
失業特例を使う場合は、退職から2年以内が期限です。
Q. 離職票がないと特例免除は受けられない?
A. 離職票または雇用保険受給資格者証など、失業を証明できる書類のいずれかが必要です。
手元になければ、ハローワークで再発行が可能です。
まとめ:退職後は“払わない”ではなく“免除を使う”が正解
退職後、国民年金の支払いが難しいと感じたら、そのまま放置せず「免除制度」を活用しましょう。
免除を申請すれば、年金加入期間としてカウントされ、将来の年金受給にもつながります。
さらに、失業手当や再就職手当、傷病手当金などの制度を組み合わせることで、退職後の生活資金を安定させることが可能です。
社会保険給付金アシストでは、退職後の給付制度を無料でご相談いただけます。
ご自身に合った制度を知りたい方は、こちらからお気軽にご相談ください。