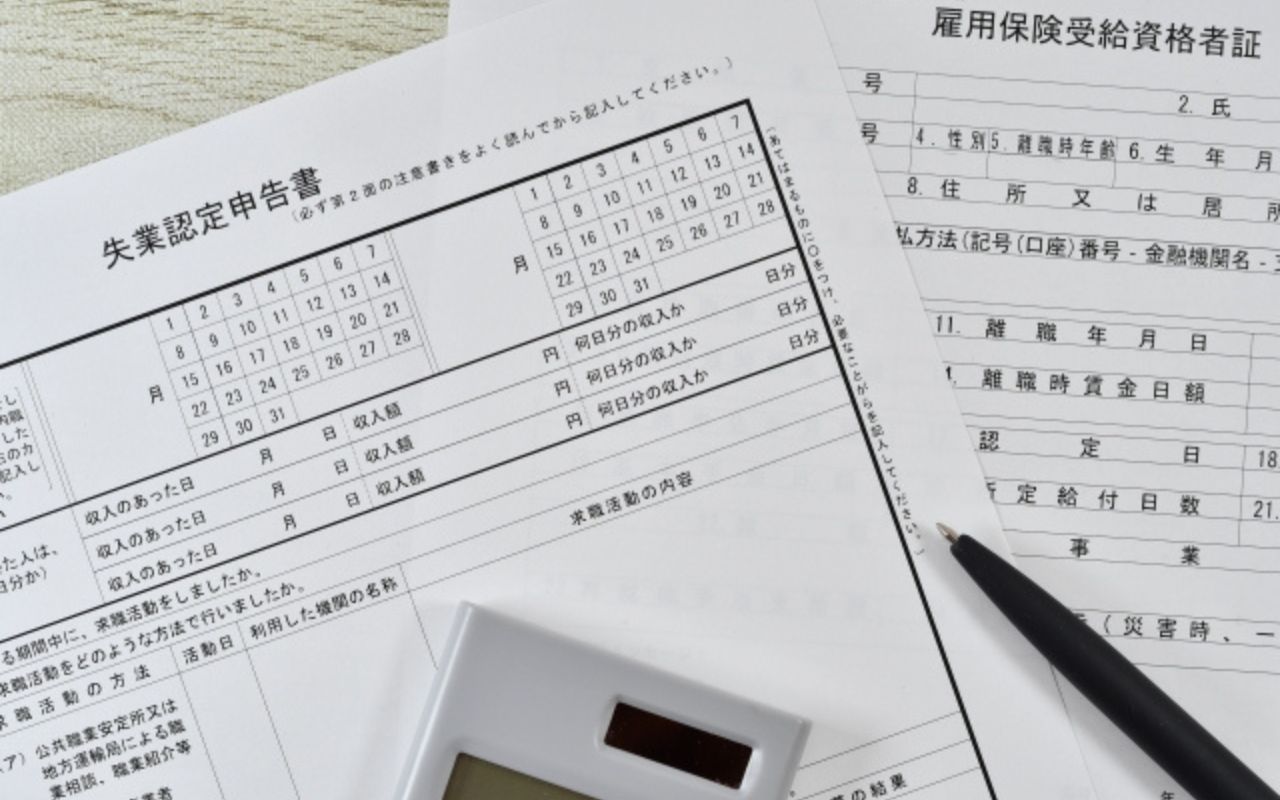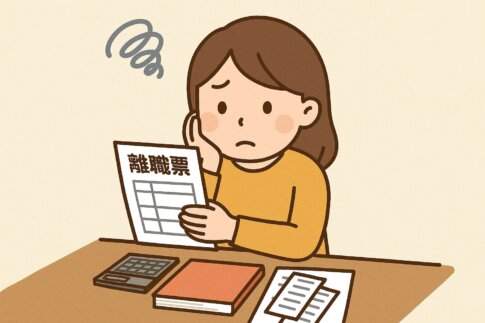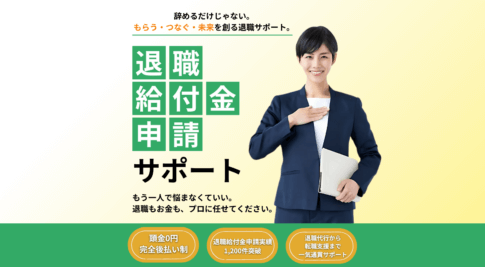「うつ病で退職したけど、この先どうしたらいいかわからない」
「お金の不安ばかりが募って、余計に気が滅入ってしまう」
そんな悩みを抱えていませんか?
うつ病によって仕事を辞めざるを得なくなるのは、決して特別なことではありません。
ですが、いざ退職すると、収入が途絶える・手続きが複雑・制度がわからない…といった壁に直面し、不安だけが膨らんでしまう人が少なくありません。
この記事では、うつ病で退職した後に「今すぐ働かなくても大丈夫な制度」と、「生活を立て直すためにできること」を丁寧に解説していきます。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

うつ病で仕事を辞める人は増えている
うつ病や適応障害など、メンタルヘルスが理由で退職する人は年々増加傾向にあります。
厚生労働省の調査によると、職場で強いストレスを感じている労働者の割合は5割を超え、20代〜40代の退職理由として「精神的な不調」が上位に挙げられるケースも増えています。
しかし、退職=逃げではありません。
むしろ、心と身体を壊してまで働き続けることのほうが、将来的に深刻な影響をもたらす可能性があります。
まずは「回復のための時間を取る」ことを第一に考えましょう。
そのためには、金銭面を支える制度の活用が欠かせません。
退職後に“すぐに働かなくていい制度”がある
うつ病などで退職しても、すぐに働き始める必要はありません。
以下のような公的制度を使えば、休養しながら経済的支援を受けることができます。
①:傷病手当金(最長1年6ヶ月)
会社員(健康保険加入者)だった人が対象。
- 条件:退職前に医師から「労務不能」の診断を受けていること
- 金額:おおよそ給与の2/3(月収30万円なら約20万円)
- 期間:最長で1年6ヶ月間
- ポイント:退職後も継続受給可能(※初診が在職中であることが必須)
②:失業手当(就職困難者扱いなら最長10~12ヶ月)
症状が続き、「今は働けない」と医師から判断されれば、「就職困難者」として失業手当の特例を受けることができます。
- 条件:退職後、ハローワークに「主治医の意見書」を提出
- 金額:前職の給与により変動(月収30万円なら約18万円)
- 期間:通常3〜5ヶ月 → 特例で最大10~12ヶ月
- ポイント:傷病手当金との併用は不可/時期をずらして申請可能
制度を使うための“正しい順番”と注意点
うつ病などで退職した後に使える制度は複数ありますが、正しい手順で進めなければ受給できないことも少なくありません。
特に重要なのが、「タイミング」と「書類の記載内容」です。
ここでは、傷病手当金や失業手当を確実に活用するための4つのステップと、それぞれの注意点を解説します。
ステップ①:退職前に必ず初診を受けておく
傷病手当金を退職後も受給するには、「在職中に医師の診察を受けていること」=初診日が退職前であることが必須条件となります。
市販薬の自己判断や、医療機関を受診していない場合は対象外になるため注意が必要です。
必ず、精神科や心療内科を受診し、「労務不能」と診断されたことを記録として残しておきましょう。
ステップ②:診断書には「うつ病」など明確な病名を記載してもらう
傷病手当金や就職困難者認定の審査においては、診断書の記載内容も非常に重要です。
「体調不良」「ストレス反応」などのあいまいな記述では、申請が通らない可能性が高くなります。
病名としては、「うつ病」「適応障害」など、医学的に明確な名称が必要です。
主治医には、日常生活や仕事に支障がある症状を具体的に伝え、正確な診断名を書いてもらえるようにしましょう。
ステップ③:退職後すぐに申請を開始する
制度の多くには「申請期限(時効)」があるため、早めの行動が何より重要です。
傷病手当金は、支給対象期間(待期3日+労務不能)から2年以内に申請しなければ時効で受給できなくなります。
失業手当も、退職後にハローワークへ行くまでの期間が空いてしまうと、給付開始が遅れたり、給付日数が減ったりするリスクがあります。
「少し落ち着いたら申請しよう」と思っている間に、損をしてしまうケースが多いため、退職後できるだけ早く申請準備を始めましょう。
ステップ④:書類の不備や記入ミスに注意する
制度申請では、書類の記入内容や不備が大きな落とし穴になります。
傷病手当金の申請書は三者が関与
- 本人記入欄:症状や出勤状況、連絡先などを正確に
- 医師記入欄:傷病名や労務不能の期間を正確に
- 事業主記入欄:勤務状況や給与の有無などを記載(退職後は元勤務先に依頼)
失業手当の「主治医の意見書」も重要
- 就職困難者としての認定を受けるには、専用のフォーマットで意見書を作成してもらう必要があります。
- 形式や記載内容に不備があると、再提出になったり、認定されなかったりすることも。
制度を活用して“立て直す”3つのステップ
うつ病などで退職したあとは、心身ともに大きなダメージを受けている状態です。
しかし、公的制度を正しく使えば、焦らずに生活を立て直すことができます。
ここでは、「お金・心身の回復・将来の準備」という3つの軸で、制度を活用した“回復ロードマップ”を提案します。
ステップ①:経済的に安心する(生活費の確保)
まず何より大切なのは、生活の不安を減らすことです。
収入が途絶えてしまっても、以下の制度を活用することで、一定期間の生活費をカバーできます。
- 傷病手当金:病気やケガで働けない期間に、給与の約2/3を最長1年6ヶ月支給
- 失業手当(就職困難者扱い):うつ病などの理由で「すぐに働けない」場合でも、医師の意見書があれば最大10~12ヶ月間受給可能
- 自立支援医療制度:精神科などの通院医療費を1割負担に軽減
これらを上手く組み合わせることで、最長で約28~30ヶ月間経済的支援が得られるケースもあります。
「とにかくお金の心配が大きい」という方こそ、制度の活用によって“安心”を取り戻すことが第一歩です。
ステップ②:心と身体を回復させる(焦らず療養)
制度によって生活費がある程度カバーされれば、次に大切なのは心と身体をゆっくりと癒やす時間を確保することです。
- 無理に働こうとせず、「今は休む時期」と割り切る
- 規則正しい生活・睡眠・栄養を意識する
- 医師の診断・指導に従い、定期的に通院しながら治療を継続する
うつ病の回復には時間がかかります。
焦って再就職を目指すと、逆に再発や悪化を招くリスクもあるため、「休むことは回復へのステップであり、将来の準備期間」と考えることが大切です。
ステップ③:将来に備えてゆっくり準備する(働き方の見直し)
心身が少しずつ落ち着いてきたら、次は「将来の働き方」について考えるタイミングです。
とはいえ、すぐにフルタイムで働く必要はありません。
たとえば…
- 就労移行支援:障害やメンタル不調のある方向けに、就労訓練や職場体験などを行う福祉サービス
- 職業訓練:公共の無料訓練で、パソコンスキルや資格取得などの再就職準備
- 在宅ワークや副業:自分のペースで働ける方法を模索
- SNSやブログなどでの発信活動:無理なくできる小さなアウトプットから自信を積み上げる
「前と同じ働き方に戻らなければならない」と思う必要はありません。
むしろ、「自分に合った働き方を探す旅」のスタートと捉えることで、今後の人生が大きく変わっていく可能性があります。
よくある質問(Q&A)
Q. 軽度のうつ病でも傷病手当金は申請できますか?
A. 可能です。症状の重さよりも「仕事に支障が出ているか」「医師が労務不能と判断しているか」が重要です。
Q. 退職後に初めて受診した場合でも、傷病手当金は受け取れますか?
A. 退職後に初診を受けた場合は傷病手当金の対象外です。在職中の初診が必須です。
Q. 退職した会社に書類を依頼するのが気まずいのですが…
A. 退職後でも会社に申請書類の一部を記入してもらう必要があります。郵送でのやり取りも可能です。
Q. 就職困難者に認定されると何が変わるの?
A. 通常3〜5ヶ月の失業手当が、最大10~12ヶ月に延長されます。求職活動の頻度も軽減されます。
Q. ハローワークでは何を聞かれるの?症状を話さないとダメ?
A. 医師の意見書がある場合、詳細な病状説明は求められませんが、就労意欲や今後の見通しについて簡単に聞かれることがあります。
Q. 傷病手当金と失業手当は同時にもらえますか?
A. 同時には受け取れません。時期を分けて、まず傷病手当金→その後に失業手当、という流れで受け取るのが一般的です。
ひとりで抱え込まないで。制度サポートの選択肢も
制度は充実していますが、申請のハードルが高く、途中で諦める人も多いのが現実です。
社会保険給付金アシストでは、以下のようなサポートを提供しています。
- 提携医師の紹介と診断書取得サポート
- 傷病手当金・失業手当の制度設計と申請サポート
- 必要書類のチェック、ハローワーク対応のアドバイス
- お金の不安に寄り添いながら“回復と準備”の支援
無料相談も可能です。
まずは「今の状況でも使える制度があるか?」を確認してみてください。
まとめ|焦らず、自分を責めずに、立て直していこう
うつ病で退職することは、決して弱さではありません。
必要なのは、「休んでもいいんだ」と自分に許可を出すこと。
そして、制度を知り、支援を受け、安心して療養し、少しずつ自分のペースで人生を立て直していくことです。
一人で抱え込まなくて大丈夫です。
あなたの未来に必要な時間とお金の備えを、今から一緒に始めましょう。