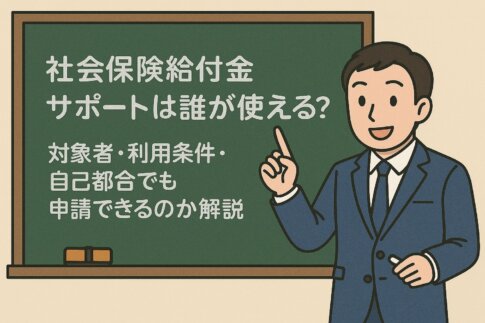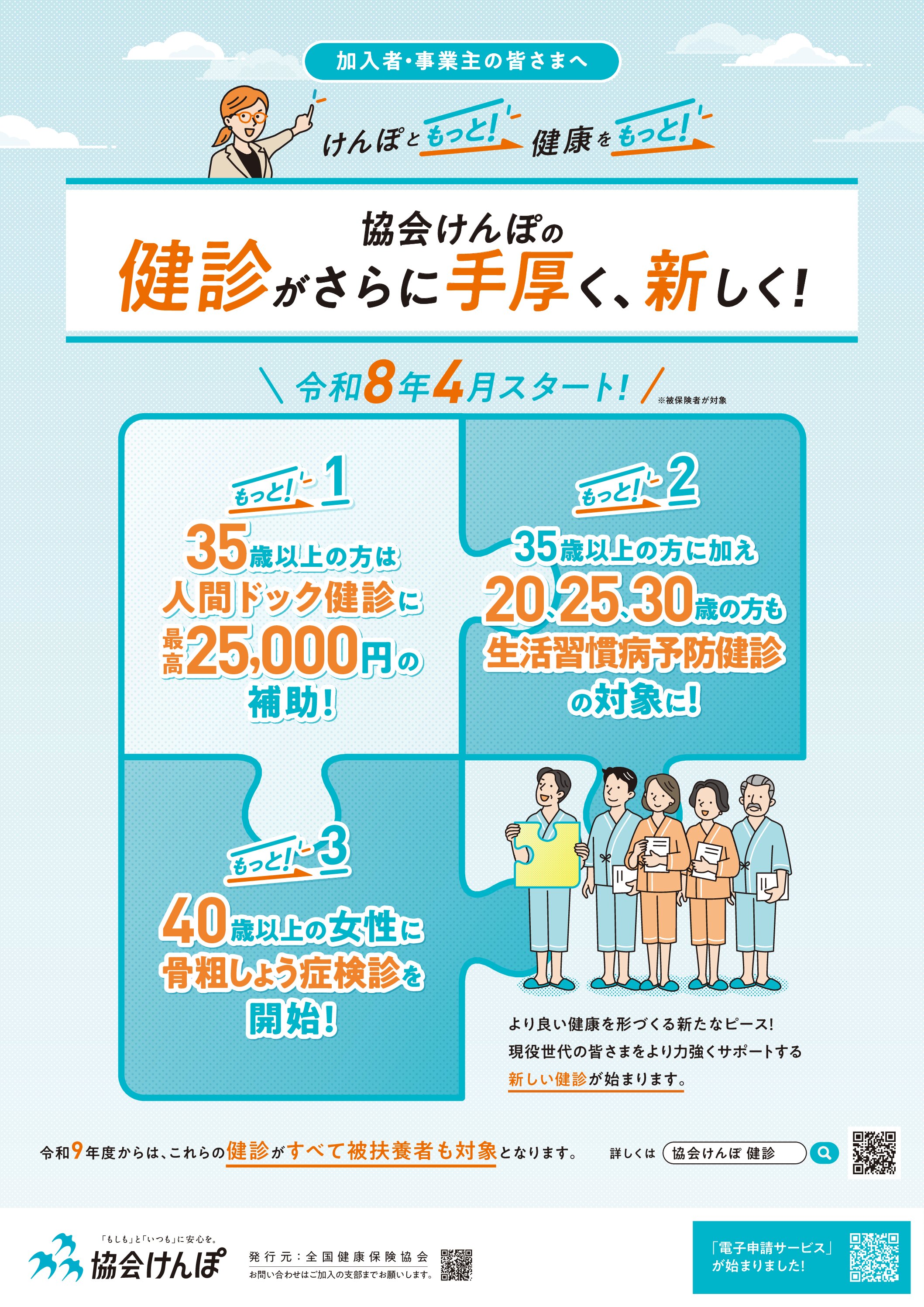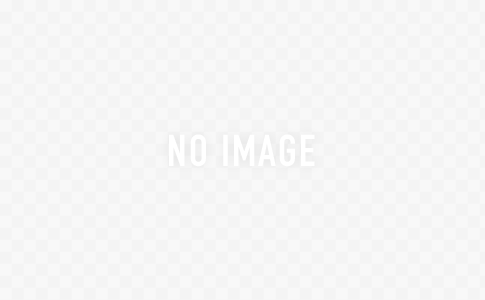傷病手当金の申請は、仕組みや書類が複雑な分、つまずきやすいポイントが多い制度です。
この記事では、制度の細かい説明ではなく、「傷病手当金支給申請書の書き方や提出方法」に特化して解説します。
「書類がややこしくて手が止まっている」「会社や病院に何を頼めばいいかわからない」という方は、このページの順番どおりに進めれば、そのまま申請までたどり着けるように構成しています。
なお、制度の仕組みそのもの(条件・金額・不支給リスクなど)をまとめて知りたい方は、以下の“全体ガイド”を先に読むのがおすすめです。
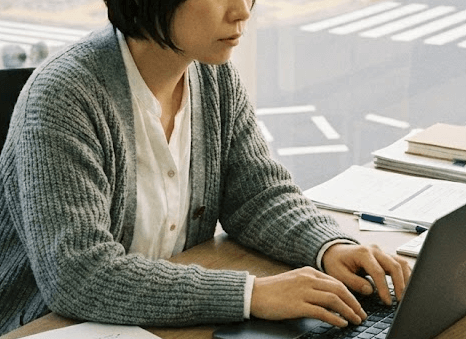
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

傷病手当金の申請はいつ・どこで行う?
傷病手当金の申請は、「いつ申請するのか」「どこに提出するのか」を理解しておくとスムーズに進みます。
まずは全体の流れをシンプルに確認しておきましょう。
申請のタイミング
初めて申請するときは、連続する3日間の休業(待機期間)を満たし、4日目以降も働けなかった場合に提出できます。
その後は、1か月ごとにまとめて申請する“後払い形式”となり、毎月の継続申請が必要です。
提出ルート
申請書の提出先は、在職中か退職後かで異なります。
在職中の場合
病院(医師の記入) → 本人記入 → 会社(事業主欄の記入)→ 健康保険組合(または協会けんぽ)
会社が書類を取りまとめて提出してくれるのが一般的です。
退職後の場合
病院(医師の記入) → 本人記入 → 健康保険組合(または協会けんぽ)
退職後は会社の記入欄が不要になるため、自分で直接提出します。
在職中であれば勤続年数に関係なく申請できますが、退職後に受け取る場合は加入期間の扱いが注意点になります。
入社1年未満のケースについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
申請に必要な書類一覧と入手方法
傷病手当金を申請するためには、いくつかの書類をそろえる必要があります。
やや複雑に見えますが、基本的には「申請書+必要に応じて会社の資料」というシンプルな構成です。
ここでは、どんな書類が必要で、どこで入手できるのかを整理します。
申請に必要な書類一覧
まず、申請の際によく使う書類は次のとおりです。
①健康保険傷病手当金支給申請書
- 被保険者記入欄:本人が記入する部分
- 療養担当者記入欄:医師に書いてもらう部分
- 事業主記入欄:会社(人事・総務)が記入する部分
※退職後に申請する場合、この欄は不要になります。
②場合によって必要になるもの
これらは会社側が主に管理している資料です。
- 出勤簿・シフト表(休職・欠勤の状況が分かるもの)
- 賃金台帳・給与明細(給与の支払い状況を確認するため)
申請書の入手方法
傷病手当金支給申請書は、勤務先を通じて入手するか、加入している健康保険組合から直接ダウンロードできます。
- 勤務先の人事・総務に依頼する
「傷病手当金の申請書をいただきたいです」と伝えれば用意してもらえます。 - 健康保険組合の公式サイトからダウンロードする
あなたが加入している健康保険組合のページに、申請書のPDFが掲載されています。 - 協会けんぽ加入者の場合
協会けんぽのサイトからダウンロード、または支部に郵送請求も可能です。
注意点
健康保険の種類によって、使う申請書式が異なります。
そのため、「自分が加入している健康保険組合はどこか?」を最初に必ず確認しましょう。
医師に申請書を書いてもらうときの注意点
傷病手当金の審査では、医師が記入する「療養担当者意見欄」が最も重視されます。
この欄の内容が弱いと、ほかの条件を満たしていても、支給が見送られるケースがあります。
確実に受給するためには、医師に正しく状況を伝え、適切なタイミングで依頼することが重要です。
医師に依頼するベストなタイミング
傷病手当金の申請書は、初診の段階では書いてもらうことができません。
初診では症状の経過がまだ確認できないうえ、申請書に“未来の日付”を記載することが制度上認められていないためです。
そのため、実務では 2回目以降の受診 で依頼するのが確実です。
経過が分かっている状態であれば、医師も療養担当者意見欄に必要な内容(労務不能の状況・発症時期・今後の見通しなど)を書きやすくなります。
医師に伝えておくべき情報
診察では、以下のポイントを整理して伝えると、医師も状況を理解しやすく、正確な記載につながります。
- 仕事内容の具体的な内容
(例:立ち仕事が多い/対人対応が多い/長時間集中が必要 など) - 実際に困っていること・休んでいる理由
(例:動悸・吐き気で出勤できない/集中できずミスが増える など) - 会社を休んでいる期間(いつから休んでいるか)
- 休職の予定や会社とのやり取り状況
ここで注意したいのは、「傷病手当金のために重く書いてください」などは絶対に言わないこと。
事実を冷静に、客観的に伝えるのがポイントです。
具体的な伝え方や、申請書を通りやすくするコツは、こちらの記事で詳しく解説しています。
診断書と申請書の違いにも注意
傷病手当金の申請では、「診断書」と「傷病手当金支給申請書」は全く別の書類です。
健康保険組合によっては、
- 申請書のみでOK
- 申請書+診断書の提出が必要
といった違いがありますが、診断書は申請書の代わりにはなりません。
診断書は「病名・症状の証明」にとどまり、審査で重視される
“労務不能の状態” は申請書の「療養担当者意見欄」で判断されるためです。
また、会社側が
- 休職の根拠として診断書の提出を求める
- 事業主記入欄を書く前に診断書を提出させる
といったケースもありますが、これは会社独自の運用です。
診断書を提出しても、それだけでは申請は完了しません。
傷病手当金には、必ず「医師記入欄(療養担当者意見欄)」が必要です。
会社(事業主)欄の記入依頼方法
在職中に傷病手当金を申請する場合、「事業主記入欄」が空白のままでは申請が進みません。
とはいえ、会社へどう依頼すればいいか分からず手続きが止まってしまうケースは多くあります。
ここでは、依頼の基本スタンスから実際に使える文例までまとめます。
依頼の基本スタンス
まず押さえておきたい重要ポイントは、
傷病手当金は会社が支払うお金ではない
→ 健康保険(協会けんぽ・組合健保)が支給する給付金
ということです。
会社が行うのは、
- 出勤状況・給与支給状況を正しく記入すること
- 申請書をまとめて健康保険組合へ提出すること
だけで、金銭的な負担もリスクもありません。
そのため、落ち着いたトーンで丁寧に依頼すれば、多くの会社は通常対応してくれます。
依頼メールの文例(そのまま使える)
会社が非協力的な場合はどうする?
まれに、「うちでは傷病手当金の申請は対応しない」「申請書には記入しない」など、協力が得られないケースもあります。
ただし誤解しないでほしいのは、事業主記入欄は“求められたら会社が記入する義務がある”項目です。
健康保険法でも、事業主は申請に必要な情報提供を行う立場とされているため、安心して依頼して大丈夫です。
こうしたケースでの具体的な対処法は、こちらの記事に詳しくまとめています。
健康保険組合へ提出する方法と提出期限
傷病手当金の申請書は、必要書類がそろったら健康保険組合(または協会けんぽ)へ提出します。
提出方法はシンプルですが、いくつか注意点があります。
提出方法
傷病手当金の申請書は、在職中か退職後かで提出の流れが変わります。
手続きミスを防ぐため、この区別は非常に重要です。
在職中の場合
在職中は、会社(総務・人事)に提出します。
会社が事業主記入欄を記載し、そのまま保険者へ郵送してくれます。
会社へ提出する方法は「持参」「社内便」「社内メール」など会社の運用に従えばOKです。
退職後の場合
退職後は会社を経由しないため、本人が直接、健康保険組合(または協会けんぽ)へ郵送します。
郵送で提出する際のポイントは次のとおりです。
- 申請書のコピーを必ず手元に残す
→ 審査中の問い合わせや紛失に備える。 - 追跡できる方法で送る
→ 簡易書留・レターパックライト・レターパックプラスが安全。 - 封筒に「傷病手当金支給申請書 在中」と明記
→ 書類仕分けで迷子になりにくくなる。
提出期限
傷病手当金には明確な時効があり、支給対象となった期間の翌日から2年 が申請期限(=時効)となっています。
この2年を過ぎると、法律上どれだけ事情があっても受給できません。
時効の例
2026年1月分の傷病手当金
→ 2028年1月末頃までが申請期限
退職後は会社の記入欄が不要になるため「まとめ出し」しがちですが、退職後は制度がやや複雑になる点に注意が必要です。
退職後の扱いについてはこちらも参考にしてください。
よくある不備と再提出を防ぐポイント
傷病手当金の審査では、ちょっとした記載ずれや押印漏れだけで差し戻しになるケースが珍しくありません。
特に在職中と退職後では書類の扱いが変わるため、実務では“もったいない不備”が起きがちです。
ここでは、実際に起こりやすい記入ミスと、再提出を防ぐチェックポイントをまとめます。
ありがちな不備例
1. 休業期間と労務不能期間の日付がズレている
- 医師欄:10/1〜10/31(初診が10/1のため)
- 本人欄:9/28〜10/31
この場合、支給されるのは医師が労務不能と認めた10/1以降のみです(※初診後の待機3日間は支給対象外)。
9/28〜9/30は医師の判断がないため、不支給となります。
2. 待機3日間が連続になっていない
待機3日(=連続する3日間の休業)は、初診日の翌日以降に連続して取る必要があります。
この3日間は「実際に働けなかった日」である必要があるため、遅刻、早退、時短勤務、半日勤務などが混ざると待機が成立しません。
一方で、有給休暇(有休)、会社の休日(公休)は「労務に服していない日」として扱われるため、待機に含めても問題ありません。
3. 給与支給状況の記載ミス
- 有給を使ったのに「給与支払いなし」と記載
- 会社から休業手当が支給されているのに、給与ゼロで申請
など、給与と実態が合わないと審査に通りません。
4. 押印・署名の漏れ
- 本人記入欄の記入漏れ
- 事業主記入欄の押印漏れ
- 医師欄の署名忘れ
など、どれか一つでも空白があると再提出になります。
不備を防ぐチェックリスト
提出前に、最低限次のポイントは確認しましょう。
- 医師欄・事業主欄・本人欄で日付の整合性が取れているか
- 待機3日間が「完全に連続した休業」になっているか
- 給与支給状況(有給・休業手当)が正しく反映されているか
- 押印・署名漏れがないか
- 申請期間に過不足(1日足りない / 1日多い)がないか
特に日付のズレは最も多い不備の一つで、審査遅延の原因になります。
不支給リスク全体を網羅的に知りたい場合は、こちらの記事が参考になります。
申請書の記入例とチェックポイント(画像付き)
傷病手当金の申請書は、被保険者記入欄・事業主記入欄・療養担当者(医師)記入欄の3つで構成されています。
それぞれ書く内容が異なるため、まずは全体像を把握することが大切です。
今回は加入者数が最も多い「協会けんぽ」の申請書を例に、書き方をわかりやすく解説します。
参照:全国健康保険協会「傷病手当金支給申請書の記入の注意点(令和7年6月作成版)」
① 被保険者記入欄の書き方のポイント
傷病手当金申請書の 1.2ページ目は本人(被保険者)が記入する欄 です。
1ページ目は「基本情報(氏名・住所・保険者番号・振込口座)」を書くパート、
2ページ目は「休業期間・仕事内容・初診日・報酬の有無」など、審査で重要な内容を書くパートです。
特に2ページ目はミスが多いため、協会けんぽの記入例を参考にしながら、押さえるべきポイントを分かりやすくまとめます。

- 申請期間
・医師が記入した「労務不能期間」と必ず合わせて記入する
・待機期間(連続3日間の休業)も含めて記入する
・未来の日付では申請できない
・毎回必ず記入する(2回目以降も同じ)
- 仕事内容
・具体的に記入する(例:「経理担当」「接客業」「ライン作業」など)
・退職日後の申請でも必ず毎回記入する
- 傷病名
・毎回必ずチェック(レ点)を入れる
- 発病・負傷年月日
・医師の記載と合わせて記入する
・毎回必ず記入する - 傷病の原因
・労災や通勤災害ではない場合「1」 と記入(=業務外)
・毎回必ず記入する - 報酬(給与)の有無
・申請期間中に1日でも出勤・有休・休業手当などがある場合、①-1 も ①-2 も「1」と記入
(報酬あり)
・退職後などで報酬がまったくない場合、①-1 のみ「2」と記入、①-2 は空欄
(誤って①-2にも「2」を書くケースが多いため注意)
② 事業主記入欄のポイント
在職中に申請する場合、3ページ目は会社が記入する欄です。
退職後は会社記入欄が不要になるケースがほとんどですが、在職中は必須になります。

- 勤務状況
・本人が記入した申請期間を含む年月をそのまま記入
・出勤した日は「〇」を記入(早退・遅刻・半休などの細かい区分は記入不要)
・申請期間内に休業手当・有給などで報酬が発生していた場合は、その「期間」と「金額」を記入 - 事業主証明日は「申請期間の最終日以降」で記入
・未来日での記入は不可(例:申請期間が月末まで→翌月1日以降の日付で記入) - 会社情報(所在地・名称・事業主名・電話番号)を記入、または会社印を押す
③ 療養担当者(医師)記入欄のポイント
4ページ目は医師が記入する、最も重要な審査資料です。
労務不能の期間・傷病名・療養の必要性など、支給可否を左右する情報がここに書かれます。

- 必ずすべて医師が記入するページ。空欄があると申請不可。
- 労務不能と認めた期間が明記されているか確認
・未来日での記入は不可
・「労務不能と認めた期間」と、本人記入欄(2ページ)の申請期間が一致している必要がある - 傷病名が正しく記載されているか確認する
- 症状・経過・治療内容などが具体的に記載されているか確認
- 医療機関証明日は「労務不能と認めた期間の最終日の翌日以降」で記入する
(例:最終日が2月9日 → 証明日は2月10日以降) - 医療機関情報(所在地・名称・医師氏名・電話番号)を記入、または医療機関印を押す
申請後にやるべきこと(支給時期・問い合わせ方法)
傷病手当金は、申請からおおむね1〜2か月程度で支給されるのが一般的です。
ただし、申請が混み合う時期や、書類に不備があった場合は、さらに時間がかかることがあります。
なかなか振り込まれないときの問い合わせ方法
「いつまで待っても振り込まれない…」という場合は、加入している健康保険組合 or 協会けんぽ支部に電話で確認してみましょう。
問い合わせの際は、次の3点を手元に準備しておくとスムーズです。
- 被保険者証番号
- 申請した期間(例:2026年1月分)
- 申請書を送付した日
かなか振り込まれない場合の原因や、いつどこへ問い合わせればよいのかは、こちらの記事でさらに詳しくまとめています。
退職後の人は「失業保険との関係」にも注意
退職後に、傷病手当金と失業保険(基本手当)の両方の受給を視野に入れている場合は、申請の順番・タイミングによって受給総額が変わる場合があります。
どちらを先に申請すべきか迷う人は、以下の記事もあわせて確認してください。
まとめ|正しい申請手順を理解すれば、受給は難しくありません
傷病手当金の申請は複雑に見えますが、実際に重要なのは次のポイントだけです。
- いつ申請するか(初回は待機3日+4日目以降の休業が出てから)
- どの書類を使うか(加入している健康保険の申請書を使用する)
- 本人・会社・医師の記載内容がそろっているか
- 提出後の支給時期を把握し、遅ければ保険者へ確認する
この4つを押さえておけば、スムーズに申請が進み、不支給リスクも大きく減らせます。
とはいえ、「申請の進め方がわからない」「支給申請書の書き方に自信がない」「自分のケースで本当に申請できるのか不安」といった場合、ひとりで抱え込むと手続きが止まってしまいがちです。
申請方法や支給申請書の書き方に迷ったら、弊社「社会保険給付金アシスト」の利用もご検討ください。
申請の要否判断から、書類のチェック・進め方のアドバイスまで、あなたの状況に合わせてサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。