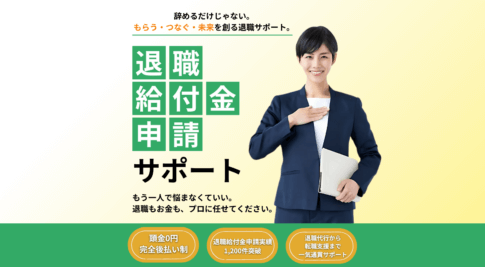「今の仕事、もう辞めたい」
「でも転職活動をする時間がない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
仕事をしながら新しい仕事を探すのは、体力的にも精神的にも負担が大きいものです。
「時間がないまま適当に転職して、また後悔したくない」
そんな方にこそ、“一度立ち止まって、ゆっくり仕事を探す”という選択肢があります。
実は、退職後に利用できる給付制度を活用すれば、収入の不安を最小限に抑えながら、次の仕事をじっくり選ぶことが可能です。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

退職してゆっくり仕事を探すという選択
「退職してから仕事探しを始める」と聞くと、「ブランクが不利になるのでは?」「生活費はどうするの?」と不安に感じる方も多いかもしれません。
確かに、何の備えもなく退職してしまうのはリスクが高いですが、実は一定の条件を満たせば、退職後も公的制度を活用して生活を安定させることが可能です。
給付金や支援制度を上手に使えば、「焦って転職先を決めて後悔…」ということを避けることができ、自分に本当に合った仕事をじっくり探すための“時間”を確保することができます。
ここでは、退職後すぐに利用しやすい代表的な制度を紹介します。
退職後にもらえる主な給付金
退職後は収入が途絶える不安がありますが、実は条件を満たせば受け取れる給付金がいくつかあります。
ここでは、退職後すぐに申請できる代表的な給付金をご紹介します。
1. 失業保険(基本手当)
ハローワークで求職活動をする意思がある人を対象に支給される給付金です。
【対象】過去2年間で12か月以上雇用保険に加入していた人
【期間】90日〜330日(退職理由・年齢・加入年数で変動)
【支給額】退職前の給与のおよそ50〜80%程度(日額上限あり)
給付開始までの7日間の待機期間と、自己都合退職なら1か月の給付制限があります(病気などが理由なら免除される場合もあり)。
2. 傷病手当金(条件付き)
退職前に「うつ病」「適応障害」などの診断を受けており、労務不能と認められた場合、退職後も最長1年半の給付が受けられることがあります。
【条件】退職前に継続して12か月以上健康保険加入+在職中に病気で受診歴あり+退職後も療養中
【支給額】標準報酬日額の約2/3(日給換算)
3. 再就職手当
失業手当を受け取り途中で早期に再就職した場合、一定条件を満たせば再就職手当が支給されます。
【支給額】残りの失業手当の60%または70%
【条件】雇用保険の適用がある再就職先/1年以上継続見込みなど
資格取得やスキルアップのチャンスにもなる
仕事を辞めたあと、時間的余裕ができることで「勉強する時間」「新しいスキルを身につける時間」が確保できます。
1. ハローワークの職業訓練を活用
求職者向けの「職業訓練校」では、パソコンスキル、医療事務、プログラミング、Webデザインなど多様な分野の訓練が無料で受けられます。
条件を満たせば、職業訓練受講給付金(月10万円+交通費)も支給されます。
2. 独学で資格取得を目指す
自宅で自分のペースで学べる資格も多数あります。
例:
- 社会保険労務士、行政書士などの国家資格
- Web系(HTML/CSS、Photoshop、WordPress)
- 英語(TOEIC、英検)
- 会計系(簿記2級、FP)
書店・YouTube・通信講座など教材も豊富にあるため、コストを抑えて学べるのも魅力です。
退職前にやっておくべき準備リスト
退職を決めたら、すぐに行動を起こすのではなく、しっかりと準備を整えることが大切です。
退職後の給付金の受給や、生活の安定をスムーズにするためにも、以下のポイントを事前に確認しておきましょう。
1. 退職日を慎重に決める
退職日は、給付金の支給タイミングや在職中の待遇に大きく関わります。
- 失業保険の支給開始タイミングを意識して日程を調整する
- 賞与(ボーナス)や有給休暇の消化ができる時期を見極めてから決定する
特にボーナス支給月や年度の切り替えタイミングは、金銭面で大きな違いが出るため注意が必要です。
2. 雇用保険の加入期間を確認しておく
失業保険を受け取るためには、過去2年間で通算12か月以上の雇用保険加入実績が必要です。
退職前に以下を確認しておきましょう。
- 雇用保険にきちんと加入していたか(給与明細や雇用契約書で確認)
- 退職後に必要となる離職票の発行を会社に依頼する手順を把握
3. 病気の診断がある場合は通院を開始しておく
うつ病などで体調に不安がある場合は、退職前に医療機関での通院を開始しておくことが重要です。
- 傷病手当金などの給付は、「退職前に初診を受けておくこと」が受給条件になります
- 通院実績があれば、退職後にスムーズに給付金の申請や受給が可能になります
4. 離職理由の記載内容を必ず確認する
失業保険の支給条件や給付日数は、「退職理由」によって大きく変わります。
- 会社側が作成する離職票の「離職理由」が自己都合退職か会社都合退職かを必ず確認
- 内容に誤りがあれば、ハローワークで異議申し立ても可能
退職理由は、受給資格や給付制限期間に直結するので、記載ミスには注意しましょう。
5. 貯金と生活予算の見直し
退職後すぐに収入が入るわけではないため、最低でも3か月分の生活費を準備しておくと安心です。
- 家賃・通信費・サブスクなど、固定費の見直しで支出を抑える
- 支出を把握し、余裕のある予算計画を立てておく
よくある質問(Q&A)
Q. 退職後すぐに失業手当はもらえますか?
A. 申請後に7日間の待機期間があり、自己都合退職の場合、さらに1ヶ月の給付制限期間があります。
Q. 職業訓練を受けながら失業手当はもらえますか?
A. はい、訓練期間中も受給可能です。条件によっては訓練給付金(月10万円)も追加されます。
Q. 給付金をもらいながら資格の勉強をしてもいいの?
A. はい、問題ありません。
むしろハローワークでは、職業訓練やスキルアップを支援しているため、積極的に活用するのが推奨されます。
Q. 退職後に医師の診断を受けても制度は使えますか?
A. 傷病手当金などは退職前に診断・通院が必要です。必ず在職中に受診してください。
Q. 副業をしながら失業手当はもらえますか?
A. 原則NGですが、収入や日数が極端に少ない場合は例外あり(要申告)。
Q. 「自己都合退職」と「会社都合退職」で何が違うの?
A. 給付開始までの期間や、支給日数が異なります。
会社都合退職の方が早く受給が始まり、支給期間も長くなる傾向があります。
まとめ:時間とお金の“備え”があれば、働き方はもっと自由になる
退職後にすぐ働かなくても、制度や給付金をうまく活用すれば、収入の不安を減らしながら、自分に合った仕事探しができます。
焦って転職を繰り返すより、一度立ち止まって、じっくりと自分の「働き方」や「生き方」を見つめ直してみませんか?
資格取得、職業訓練、スキルアップ、そして公的制度の活用など、あなたの選択肢はたくさんあります。
「何から始めればいいかわからない…」
「制度の内容が難しくて不安…」
そんなときは、私たち社会保険給付金アシストにご相談ください。
受給の仕組みや手続きのサポートはもちろん、医師の紹介や書類の準備、失業保険・傷病手当金の活用法まで、制度のプロがしっかりとお手伝いします。
あなたが「ゆっくり、でも確実に」前に進むための土台を、一緒に整えていきましょう。