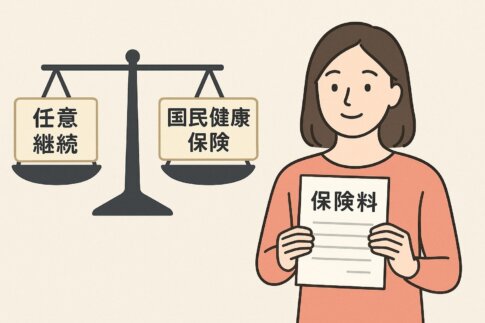退職を考えているあなた。生活費の不安を少しでも軽くするために、退職前に確認すべき「給付金制度」があるのをご存じですか?
特に「傷病手当金」と「失業手当」は、条件を満たせば数十万円以上の給付を受けられる可能性があります。
しかし、これらの制度は“退職後に初めて調べても手遅れ”というケースが多いため、退職前の準備が非常に重要です。
このページでは、退職前にやっておくべき給付金対策をわかりやすく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

傷病手当金は退職前の初診がカギ
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、健康保険から支給される生活保障制度です。
支給金額は「標準報酬日額の約3分の2程度」で、最長1年6ヶ月間の受給が可能です。
ただし、退職後もこの傷病手当金を継続して受け取るには、“退職前に初診を受けていること”が絶対条件になります。
退職前にやるべき準備とは?
傷病手当金を退職後も確実に受け取りたい場合、退職前にいくつかの重要な準備を済ませておく必要があります。
特に「初診日」と「待期期間の完成」は、退職後の給付可否に直結するため注意が必要です。
- 退職前に医療機関を受診して「初診日」を確保する
傷病手当金の支給において、「退職前に初診を受けていること」は絶対条件です。
退職後に初めて病院へ行っても、制度上の対象外となるため注意しましょう。 - 医師による「就労不能」の証明を準備しておく
申請には医師の記載が必要です。
具体的には、傷病手当金支給申請書にある「医師の意見欄」に、労務不能の状態であることを記入してもらいます。
なお、診断書の提出は必須ではありませんが、「うつ病」など明確な病名や就労不能の根拠が明記されている診断書があると、審査がスムーズになります。 - 待期期間(3日間)を退職前に完成させておく
傷病手当金には「3日間の連続した待期期間」が必要です。
この待期が退職前に完成していれば、退職後も継続受給が可能になります。
待期期間とは、病気やケガで働けなくなった日から連続して3日間休み(この間に給与の支払いがないこと)、4日目以降から傷病手当金が支給対象になります。 - 退職日には出勤しないようにする
退職日が「出勤日」になってしまうと、制度上「就労可能な状態」とみなされてしまい、傷病手当金の受給条件を満たさなくなることがあります。
退職日は「働けない状態」である必要があるため、当日は出勤せず、病気療養中であることを示す状態にしておきましょう。
場合によっては、有給を使って欠勤扱いにすることも検討してみてください。
必要な準備を漏れなく行うことで、退職後もスムーズに傷病手当金を受給できる可能性が高まります。
不安な方は、当社のような申請サポートサービスにご相談いただくのも一つの方法です。
失業手当の受給準備
雇用保険に加入している方で、退職後に就職の意思と能力がある場合は、「失業手当(正式には基本手当)」を受給することができます。
ただし、受給にはハローワークへの求職申込みと定期的な活動実績が必要となります。
退職後にあわてないためにも、以下のような準備を退職前に済ませておきましょう。
退職前にやっておくべきことは?
- 離職票を会社に必ず発行してもらうよう依頼
退職後、失業手当の申請には「離職票(1・2)」が必須です。
スムーズに手続きを進めるためにも、退職前に人事・総務部門へ発行を依頼しておきましょう。 - 退職理由の確認(自己都合か会社都合か)
給付開始時期や給付日数に大きく関わります。
会社都合であれば7日間の待機後すぐに給付が始まりますが、自己都合の場合は通常1ヶ月の給付制限があります。
離職票に記載される「離職理由」の内容は、きちんと確認しておくことが重要です。 - ハローワークで必要となる書類を事前に準備
マイナンバーカードや通帳、写真、印鑑など、退職後すぐに手続きができるように必要書類を揃えておきましょう。
体調不良で働けない人は注意
体調不良やうつ病などの理由で、退職後も「すぐに働ける状態ではない」場合は、失業手当の対象外となる可能性があります。
このようなケースでは、失業手当の前に「傷病手当金」の申請を優先すべきです。
傷病手当金を先に受給し、就労可能な状態になった段階でハローワークに申し込めば、失業手当の受給がスムーズに移行できます。
傷病手当金と失業手当は併給できない?
傷病手当金と失業手当は、どちらも「働けない状態の人を支援する」ための社会保険給付制度ですが、原則として同時に受け取ること(併給)はできません。
そのため、どちらの制度を優先して申請すべきかは、現在の健康状態や就労の意志・可能性によって判断する必要があります。
判断のポイントは「働けるかどうか」
- 病気やうつ病などで働けない状態が続いている場合
→ 「傷病手当金」が優先されます。
就労不能であることが医師により認められている場合は、失業手当の対象にはならず、まず傷病手当金の受給が優先されます。 - 健康状態は回復していて、すぐに働ける状態である場合
→ 「失業手当」の申請が可能になります。
この場合、ハローワークに求職申込を行い、失業手当(基本手当)の給付を受ける流れとなります。
たとえば、最初はうつ病などで傷病手当金を受給していても、体調が回復して「すぐ働ける状態」になれば、その後に失業手当の受給に切り替えることも可能です。
このように、「いつ、どの制度を使うか」で受給できる金額や期間は大きく変わってきます。
制度選びを間違えると損をすることも
傷病手当金と失業手当のどちらを優先すべきか、また切り替えのタイミングなどは非常に重要な判断ポイントです。
制度の理解不足や申請のミスによって、本来受け取れるはずの給付金を逃すケースも少なくありません。
退職前の段階で、自分にとって最適な制度利用のシミュレーションをしておくことが大切です。
不安な方は、当社のサポートサービスもご活用いただければ、申請書類の準備や制度選択のアドバイスを含めて、手続きをトータルで支援いたします。
よくある質問(Q&A)
Q. 退職前に病院を受診すれば、傷病手当金は退職後ももらえますか?
A. はい、退職前に初診を受けておけば、退職後も支給される可能性があります。
Q. 自己都合退職でも失業手当はもらえますか?
A. もらえますが、会社都合よりも給付開始が遅れます(7日+1ヶ月の給付制限)
Q. 傷病手当金と失業手当、どっちが得ですか?
A. 金額だけでなく、「今働けるかどうか」で判断することが大切です。
Q. 医師の診断書は必ず必要ですか?
A. 診断書は必須ではありませんが、就労不能の証明として取得しておくとスムーズです。
医師の意見欄の記載は必要です。
Q. 傷病手当金をもらい終えた後に失業手当を申請できますか?
A. はい、可能です。傷病手当金の受給後に就労可能な状態であれば、失業手当を申請できます。
Q. ハローワークの手続きは退職前にできる?
A. できません。求職申込は退職日以降でないとできません。
退職後に速やかに手続きしましょう。
まとめ:退職前の準備で受給の可能性が大きく変わる
退職は大きなライフイベントだからこそ、給付金制度を上手に活用することで生活の安定を確保することができます。
特に「退職前に病院を受診する」「離職票など必要書類をきちんと確認しておく」などの準備ができているかどうかで、数十万円〜百万円以上の差が出ることも。
当社では、こうした制度を活用して“もらえるべき給付金をきちんと受け取れるように”専門スタッフが一人ひとりに合わせたサポートを行っています。
「制度が難しそうで不安」「失敗したくない」「確実に受け取りたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。