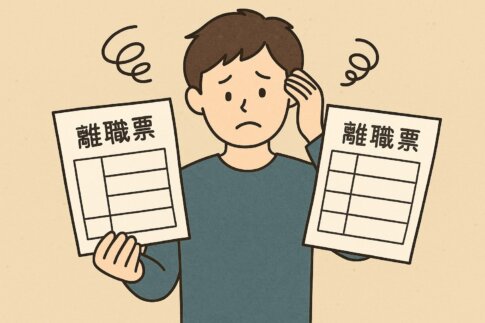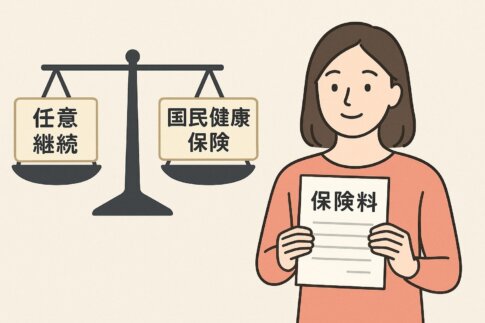退職後は自由な時間が増える一方で、思わぬ出費に悩まされる方も少なくありません。
特に大きな負担となるのが、国民健康保険・国民年金などの”保険料”です。
収入がないにもかかわらず、これまでと変わらない金額を請求されて驚いた経験のある方も多いのではないでしょうか?
でも安心してください。
退職前にちょっとした知識を得て、計画的に準備しておけば、数万円から十数万円の節約が可能です。
この記事では、退職後の保険料負担を軽減するために、退職前に知っておきたい4つの節約ワザに加えて、退職後にもらえる可能性のある給付金制度についてもご紹介します。
ぜひ最後まで読んで、損をしない選択をしてください。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

1. 社会保険の資格喪失日を”月末”に合わせる
社会保険の資格喪失日は、退職日の「翌日」と決まっています。
たとえば、4月30日に退職すれば、資格喪失日は5月1日です。
社会保険を支払うのは資格喪失日の前月までとなります。
つまり4月分はまるまる社会保険に加入していた扱いになります。
一方、4月15日に退職した場合は、資格喪失日は4月16日となるので
資格喪失日の前月の3月までしか社会保険に加入していなかったことになります。
では、その4月分の保険はどうなるのかというと
多くの場合、社会保険の任意継続か国民健康保険の加入が必要となります。会社負担がない分一人で倍近くの保険料を払う必要がでてきます。
そのため、退職日はできる限り月末に設定するのが保険料を無駄にしない最もシンプルな選択といえます。
2.国民健康保険料の”減免制度”を活用
退職後の健康保険の選択肢は主に3つあります。
- 国民健康保険に加入する
- 配偶者の扶養に入る
- 任意継続を選ぶ(退職前の健康保険を最長2年間継続)
国民健康保険料は、原則として「前年の所得」に基づいて計算されます。
そのため、退職後に収入がなくても、前年の給与が高かった場合は高額な請求が来ることも。
ですが、多くの自治体では、失業手当の申請時に「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する場合に、国民健康保険料の減免制度が設けられています。
- 特定受給資格者(例:倒産・解雇など会社都合による離職)
- 特定理由離職者(例:雇い止め、病気・ケガ、家族の介護、パワハラなどやむを得ない自己都合退職)
たとえば、前年の収入に基づく保険料が年間30万円だった場合でも、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」と認定されれば、最大5~7割減額されるケースもあります。
ただし、単なる自己都合退職の場合は、このような減免制度の対象にはなりません。
ですが、体調不良や家庭の事情など、一定の正当な理由がある場合には、「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
弊社では、このような認定を受けるための離職理由の整理や申請書類の作成もサポートしており、「特定理由離職者」として認定されれば、国民健康保険料の減免制度も正式に活用することができます。
また、申請には「雇用保険受給資格者証」が必要ですので、ハローワークで失業手当の申請をした際に取得しておく必要があります。
3.社会保険の任意継続を検討
任意継続は、退職前の標準報酬をもとに保険料が決まります。
在職中は会社と折半で支払っていた保険料を、退職後は社会保険に引き続き加入しているとはいえ全額自己負担することになります。
そのため、保険料が思った以上に高く感じる方も少なくありません。
また、保険料が高くなると思われがちですが、実は任意継続の保険料には上限が設けられており、一定額以上にはなりません。
- 退職前の収入が高く、国民健康保険料が高額になる人(前年度の年収が500万円以上など)
- 扶養家族(配偶者や子ども)が複数いる人
- 傷病手当金を受給予定で、国民健康保険料の軽減措置が受けられない人
このような場合は、任意継続の方がトータルで見てお得になるケースも多いのです。
ただし、任意継続の申請は「退職日の翌日から20日以内」に行う必要があります。
一日でも過ぎると継続加入できなくなるため、忘れずに手続きしましょう。
退職前に保険料を比較しよう
退職後の保険料は、加入している健康保険組合やお住まいの自治体(市区町村)に問い合わせれば、見込み額を教えてもらえることがほとんどです。
「任意継続」と「国民健康保険」の両方を見積もってもらい、保険料や保障内容を比較することで、自分にとってどちらが負担が少なく、メリットが大きいかを判断しやすくなります。
退職前のタイミングで一度問い合わせておくと、スムーズに手続きが進められるのでおすすめです。
参考動画:
4. 国民年金の免除・納付猶予制度を利用する
退職後は「厚生年金」から外れ、自分で「国民年金」に加入する必要があります。
しかし、国民年金の保険料は月額17,510円(2025年度)と、収入が減ったタイミングでは大きな負担です。
そこで活用したいのが、国民年金保険料の「免除制度」「納付猶予制度」です。
| 区分 | 対象者 | 内容 | 将来の年金への影響 |
|---|---|---|---|
| 全額免除 | 所得が一定基準以下の方 | 保険料の支払いが全額免除される | 1/2分が年金額に反映される |
| 一部免除 | 所得が免除基準よりやや高い方 | 保険料の一部を納付 | 納付した割合に応じて年金額に反映される |
| 納付猶予 | 50歳未満の方で、収入が少ない場合 | 一時的に保険料の納付が猶予される | 年金額には反映されない(後納可能) |
必ずお住まいの市区町村の役所または年金事務所で手続きを行う必要があります。
失業や退職直後で所得が低くなると見込まれる場合は、早めの相談・申請をおすすめします。
番外編:住民税の減免・分割納付を申請する
保険料とは異なりますが、意外と見落とされがちなのが、退職後に請求される「住民税」です。
住民税は“前年の所得”をもとに課税されるため、退職して収入がゼロになっても請求は続きます。
特に、前年にボーナスや残業代が多かった方は、思いのほか高額な請求が来るケースも少なくありません。
実は、退職したことを理由に、住民税の【分割納付】や【減免】の相談ができる自治体もあります。
実際に、多くの自治体では「離職による生活困窮」などを理由とした減免制度が用意されており、申請することで負担を大きく軽減できる可能性があります。
自治体別の事例
山梨県甲府市の場合
甲府市では、失業や病気などで所得が大幅に減った人に対して、住民税の減免制度があります。
前年の所得が500万円以下で、今年の所得がその半分以下になると対象となり、
状況に応じて最大で全額免除される可能性もあります。
詳細:甲府市公式サイト
神奈川県厚木市の場合
厚木市では、失業や傷病などで生活が困難になった人を対象に、住民税の減免制度を運用中。
退職などによる収入の急減がある場合、個別の相談により減免されるケースもあります。
詳細:厚木市公式サイト
神奈川県川崎市の場合
川崎市では、退職や病気による所得減(3割以上の減少)を条件に、
前年の所得が300万円以下の方を対象に、最大で全額免除が受けられる制度があります。
詳細:川崎市公式サイト
申請のポイント
- 納期限前に申請が必要です。遅れると減免が認められないことも。
- 雇用保険受給資格者証や退職証明書、収入が減ったことを証明する資料の提出が求められるケースが多いです。
- 制度の内容や条件は自治体によって異なるため、必ずお住まいの市区町村の税務課に事前確認を行いましょう。
重要なのは、“何もせず放置しないこと”
自治体の税務課に早めに相談することで、分割納付の計画や、減免の対象になるかどうかを確認できます。
給付金制度を利用し、生活費+保険料をカバー
退職後、一番の不安は「生活費」と「保険料」の支払いではないでしょうか?
働いていた頃は給与から天引きされていた社会保険料も、退職後はすべて自分で負担しなければなりません。
しかし、「無収入で毎月数万円の保険料を払うのは無理…」とあきらめる必要はありません。
実は、公的な給付金(傷病手当金や失業手当)を上手に活用すれば、一定期間の生活費や保険料をしっかりカバーすることができます。
病気やケガが理由の退職なら「傷病手当金」の活用を
もし退職の理由が、うつ病や適応障害、腰痛など病気やケガによるものであれば、まず検討すべきは「傷病手当金」です。
これは、健康保険に加入していた会社員が、就労不能の状態になったときに受け取れる給付金で、最大で1年6ヶ月間、収入の約2/3が支給されます。
退職後も一定の条件を満たせば受給可能なため、療養に専念しながら生活費や保険料をカバーできる大きな支えになります。
「働きたくても体調的にすぐには無理…」という方こそ、傷病手当金の活用をご検討ください。
労災だと収入の80%を受給できますが、会社は評価が下がるので交渉が長引くことがあります。そのため傷病手当金をまずは受給することが多いです。
働ける状態であれば「失業手当」を申請しよう
退職後、働く意欲と能力がある状態であれば、すぐに「失業手当(基本手当)」の申請を行いましょう。
これは、再就職までの生活を支える制度で、離職前の収入や年齢、雇用保険の加入期間に応じて、90日〜最大360日分の給付を受け取ることができます。
就職活動をスタートする時点で手続きが必要になるため、早めのハローワークでの申請が肝心です。
弊社では、退職後も傷病手当金を継続して受給できるようにするためのサポートや、失業手当をより多く受け取れるようにするための申請支援を行っております。
すぐ再就職すれば保険料の空白なし|退職後すぐ働くメリットとは?
退職後にすぐ再就職すれば、新たな勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することができます。
その結果、以下のようなメリットがあります。
- 国民健康保険や国民年金の加入が不要に
→ すぐに次の会社の社会保険に加入するので不要となります。
弊社では、「再就職手当」や「就業促進定着手当」など、早期に再就職する場合でもしっかり給付金を受け取れるよう、手続きや条件整理を含めたサポートを行っています。
転職活動に不安がある方も、制度を知っておくことで安心して次の一歩を踏み出せます。
よくある質問(FAQ)
Q. 社会保険料は退職月の日数に関係なく、1ヶ月分かかるのですか?
A. いいえ。中途退職の場合、その月は社会保険に未加入となるので発生しません。ただ処理が間に合わずにその月が引かれることもあります。その場合はあとで還付されます。
Q. 社会保険を抜けたあと、国民健康保険と年金はいつから加入する必要がありますか?
A. 社会保険の資格喪失日の「翌日」から、国民健康保険と国民年金への加入義務が発生します。ただし、退職日と同月に再就職するのであればその月は再就職先の会社の社会保険に加入することになるので加入しなくても良いです。病院にかかると10割負担となるのでその点だけ注意。
Q. 国民健康保険料を減免してもらうにはどうしたらいいですか?
A. 多くの自治体では、離職理由が「特定理由離職者」または「特定受給資格者」に該当する場合、申請により最大7割程度の減免を受けられる可能性があります。
申請には雇用保険受給資格者証などが必要です。
Q. 扶養に入れるなら、健康保険料や年金は払わなくてよいのですか?
A. 配偶者(会社員・公務員など)の扶養に入ることができれば、国民健康保険料・国民年金保険料の支払い義務は基本的に発生しません。
ですが、傷病手当金や失業手当などの給付金をもらっている場合は、収入や条件によって扶養に入れるかどうか決まります。2025年現在、年間130万円以上収入があると扶養に入れません。
Q. 退職後の住民税の支払いも減免できますか?
A. 一部自治体では、退職などによる生活困窮を理由に、分割払いや減免の相談が可能です。
困ったときは早めに市区町村の税務課に相談しましょう。
Q. 保険料が高くて支払えないときはどうすればいいですか?
A. 未納のままにせず、市区町村の窓口で減免・分割・猶予の相談をしてください。
相談せずに放置すると督促や延滞金が発生することがあります。
まとめ|退職後の保険料は「知識と準備」で大きく差がつく
退職後に初めて、保険料や税金の重さに驚く方は少なくありません。
しかし、退職前から制度を正しく理解し、できる対策を講じておくことで、その負担は確実に軽くすることができます。
- 退職日の設定ひとつで、保険料の“二重払い”を防げる
- 減免制度を活用すれば、数万円単位の節約も可能
- 傷病手当金や失業手当を上手く使えば、保険料をまかなう資金も確保できる
つまり、「保険料を節約したい」と思ったときには、保険料を抑える工夫+給付金の活用の両方を視野に入れることが重要です。
弊社では、退職前後に使える給付制度の診断や申請サポートを通じて、「損しない退職」を支援しています。
少しでも不安がある方は、ぜひお気軽にLINEからご相談ください。
あなたにとって最適な選択肢をご提案いたします。