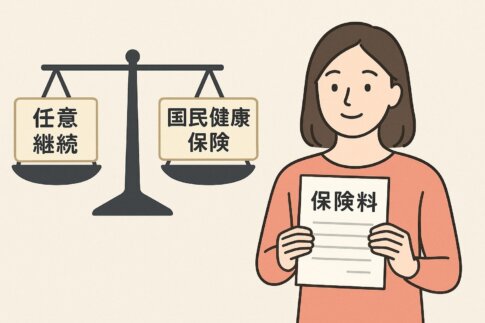「限界…会社を辞めたい」
「今退職をすべきか迷う」
「辞めたら周りに迷惑をかけてしまう」
こうした悩みを抱えていませんか?
退職は法律で認められた“あなたの権利”ですが、理由が曖昧なまま勢いで辞めてしまうと後悔につながることもあります。
一方で、明らかに辞めるべき職場に居続けて心身を壊してしまうケースも少なくありません。
この記事では、会社を辞めるべきか迷っているあなたに向けて、辞めるべき職場の特徴・今すぐ辞めなくても良いケース・不安を減らすための具体的な行動・退職後に使える制度まで分かりやすく解説していきます。
また、退職のタイミングや伝え方に不安がある人は、次の記事も参考になります。
※本記事は、雇用保険や社会保険制度に詳しい編集チームが、厚生労働省・ハローワーク・協会けんぽなどの公的情報を参照し、日々の退職相談や給付金サポートの実務経験に基づいて作成しています。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

【結論】限界なら退職しても良い
結論から言うと、心身が限界なら、退職してもまったく問題ありません。
退職は民法627条1項により、あなた自身の意思だけで可能です。
多くの人が誤解していますが、退職に「会社の許可」は不要です。
なお、正社員のような無期雇用だけでなく、契約社員・派遣社員などの有期雇用でも「期間満了を待たずに辞められるケース」があります。
(例:やむを得ない事由がある場合、契約更新の意思がない場合など)
退職の流れをよりスムーズに進めたい人は、次の記事も参考にしてください。
【逃げても良い】辞めるべき職場の特徴11選
ここでは、「ここに居続けると危険」という職場の特徴を11個紹介します。
1つでも該当する場合は注意。複数該当すれば退職を考えるタイミングです。
1. 体調不良が続いている
朝起きられない、涙が出る、会社へ行くと動悸がする──
これは典型的なストレス過多のサインです。
長時間労働の継続は、厚生労働省が「過労死ライン」と明確に定義しています。
2. ハラスメントが横行している
パワハラ・セクハラは“慣れれば大丈夫”ではありません。
職場風土として許容されている場合、改善の見込みはほぼゼロです。
3. 人間関係が良くない
上司や同僚と良好なコミュニケーションが取れず、毎日ストレスが蓄積していく状態は危険です。
人間関係の悪さは仕事以上に負担になります。
4. 慢性的な人手不足
一時的ではなく“ずっと人が足りない職場”は危険です。
人手不足はあなたの責任ではありません。
5. 会社に将来性がない
業績悪化・古い商習慣・若手が育たない──
伸びる見込みのない会社は早めに離れた方が賢明です。
6. 給与や福利厚生に不満がある
同じ仕事でも会社によって待遇は大きく違います。
あなたの価値に見合わない低待遇が続くなら、職場選びを間違えている可能性があります。
7. 今の職場ではやりたいことができない
明確なキャリア目標があるのに、今の職場では実現できない場合は行動すべきサイン。
時間は戻らないので、機会損失の方が大きくなります。
8. 人の入れ替わりが激しい
新入社員がすぐ辞める、ベテランも続かない――
そんな会社は内部に構造的な問題を抱えています。
定着しない環境はあなたにも同じ負担が降りかかります。
9. 労働環境が劣悪
残業が多すぎる、休憩がない、休日が取れないなど、健全に働けない状態なら、長く続けるほど健康リスクが上がります。
10. 労働基準法を守っていない
残業代未払い、有給拒否、長時間労働の放置など、法律を守らない会社はあなたを守りません。
改善される可能性も極めて低いです。
11. 職場で自殺者が出ている
職場で自殺者が出ている、またはその噂が真実味を帯びている場合は、会社として重大な問題を抱えています。
すぐに距離を置くべき環境です。
退職をもう少し様子見しても良いケース3つ
ただ「辞めたい」と感じても、必ずしも今すぐ退職すべきとは限りません。
状況によっては、少し様子を見ることで改善するケースもあります。
ここでは、その代表的な3つを紹介します。
1. 入社または異動したばかり
入社直後や異動直後は、業務に慣れないストレスから「辞めたい」と感じやすい時期です。
仕事の理解が深まり、周囲との関係ができてくると負担が軽くなるケースも多いため、まずは少し様子を見るのも選択肢です。
2. 問題のある人が1人だけ
職場全体の雰囲気が悪いわけではなく、特定の一人だけが問題という場合は改善の余地があります。配置転換・上司への相談・距離の取り方などで状況が変わる可能性もあるため、「職場そのものが終わっている」状態とは異なります。
3. 新しい企画が始まったばかりで一時的に人手不足
新規プロジェクト立ち上げ時は、どの会社も一時的に業務量が増えるものです。
人員補充や業務の整理が進めば落ち着く可能性があるため、恒常的なブラック環境とは区別して判断しましょう。
「どうしても仕事に行きたくない…」と感じる日は誰にでもあります。
無理をしすぎる前に、休む判断の基準を知っておきたい人はこちらも参考になります。
辞めるべき職場だけど不安な人がやった方が良いこと5選
退職した方が良い職場だと分かっていても、生活費・転職先・家族への影響などが不安で一歩を踏み出せない人は多いです。
ここからは、不安を解消しながら行動するための5つの方法を紹介します。
1. 転職エージェントに登録する
自力で転職活動を始める前に、まずは “選択肢の数”を知ることが不安解消の第一歩です。
今の職場しか知らない状態では、選択肢が狭く感じて辞められません。
エージェントに相談すると、自分では想像していなかった働き方や条件の会社を提案されることもあります。
2. 今の会社を続けるメリット・デメリットを書き出す
頭の中だけで悩んでいると、不安や焦りが先に立って冷静な判断ができなくなりがちです。
そんなときは、今の会社に残るメリットとデメリット、辞めるメリットとデメリット を紙に書き出してみてください。
視覚化することで状況が整理され、「本当に辞めるべきなのか」「もう少し続ける価値があるのか」をより客観的に判断できるようになります。
3. 失業保険をもらえるか確認する
退職後に収入がゼロになるのは誰でも不安です。
しかし、失業保険を受給できれば生活の不安は大きく減ります。
4. 節約できる部分がないか調整する
転職活動が長引いても困らないよう、出費を見直しておきましょう。
固定費や生活習慣を少し整えるだけでも、手元に残るお金が増え、精神的な余裕が生まれます。
5. 覚悟が決まったら直属の上司へ報告する
退職の伝え方に悩む人は多いですが、結論から言うと “相談ではなく、意思表示” をすることが大切です。
退職を伝える際の注意点はこちらが参考になります。
退職後に使える制度の基本だけ押さえておこう
退職後は、次の仕事がすぐに決まらなくても利用できる公的制度がいくつかあります。
経済的な不安を減らすためにも、最低限このあたりは押さえておきましょう。
特に重要なのが以下の制度です。
- 失業保険(基本手当)
収入が途切れないように国がサポートしてくれる制度です。 - 傷病手当金(メンタル不調や病気で働けない場合)
うつ病や適応障害などで働けない人が活用できる大切な制度です。 - 住居確保給付金(家賃補助制度)
収入が減って家賃が払えない人を支援する制度です。 - 健康保険の任意継続
会社の健康保険を最大2年間継続できる仕組みです。 - 国民健康保険の減免制度
収入が大きく減った人向けの保険料軽減制度です。
これらを理解しておくと、「退職=生活ができなくなる」という不安を大きく減らせます。
制度をまとめて確認したい人は、こちらが参考になります。
まとめ
退職は不安もありますが、傷病手当金・失業保険・国保の減免制度など、生活を支える仕組みはしっかり用意されています。
大切なのは、それらを自分の状況に合わせて正しく活用することです。
社会保険給付金アシストでは、退職後の 傷病手当金・失業保険のサポート をはじめ、
保険の選び方や減免制度の案内 まで、生活面の不安を減らす支援を行っています。
退職後の手続きや給付金について不安がある方は、まずはこちらからご相談ください。