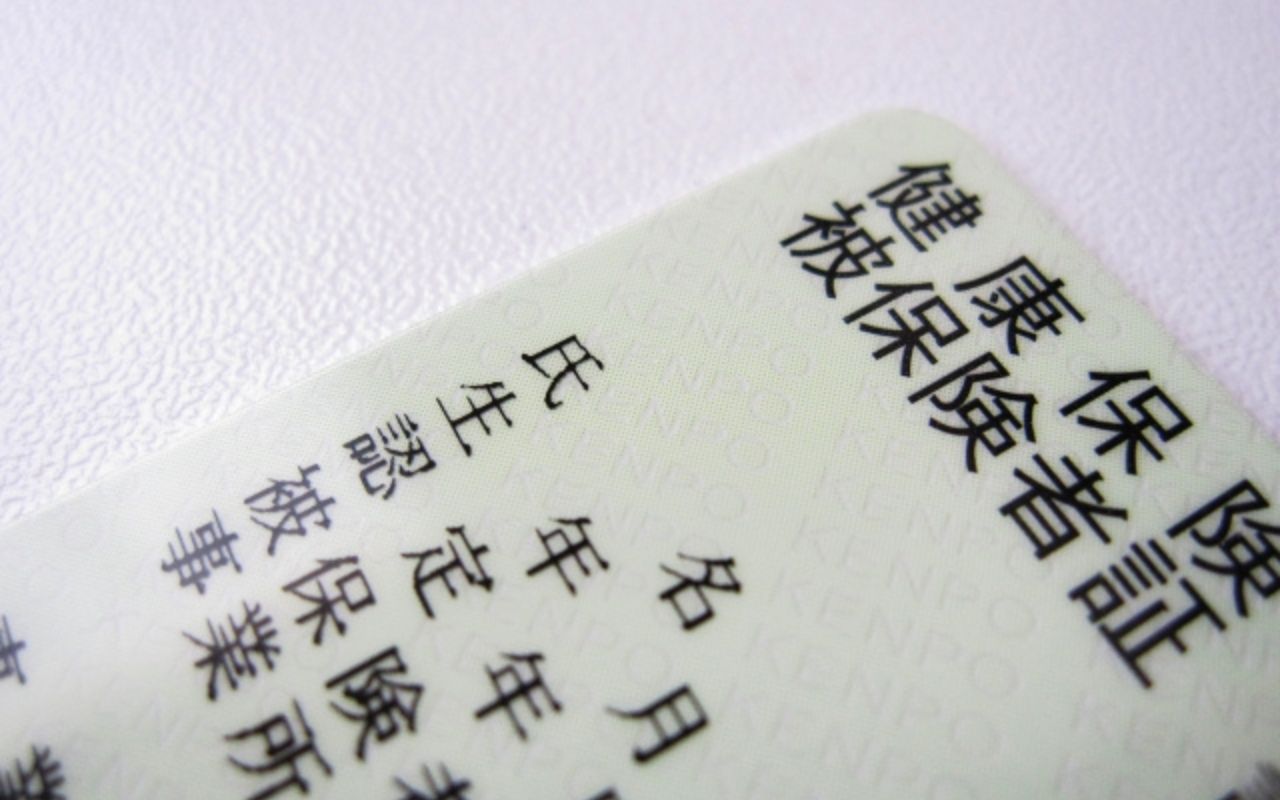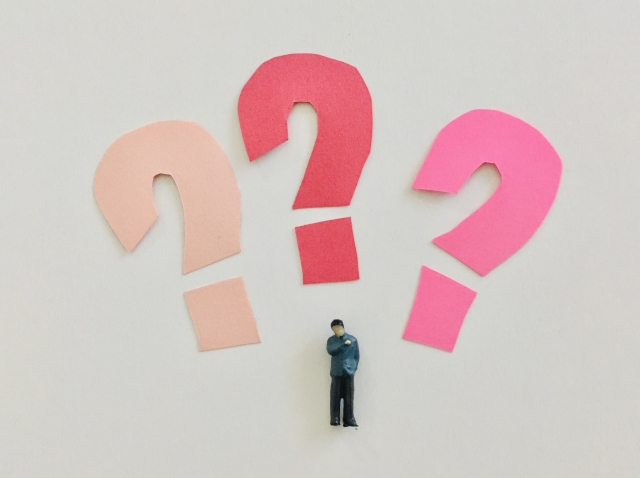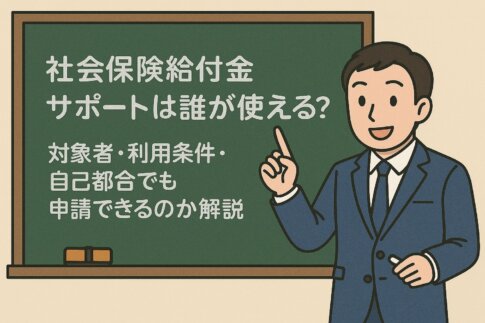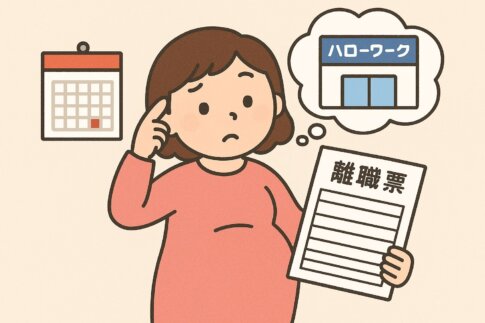「雇用保険の給付金の種類は何があるの?」
「雇用保険の給付金をもらう条件は何?」
「雇用保険の給付金はどれくらいの金額がもらえるの?」
雇用保険は、労働者をサポートしてくれる大切な保険です。正社員だけではなく契約社員や派遣社員でも雇用保険に加入しているケースが多いでしょう。また、アルバイト、パートでも雇用保険に加入している方が少なくありません。
ただ、どのような場合に受給できるのかを知らないと、制度を利用できずに損をするかもしれません。雇用保険から受けられる給付金は「基本手当(いわゆる失業保険)」が有名ですが、それ以外にも支給されるお金は4種類あります。
今回は雇用保険の種類を一覧で紹介し、どういった場合で受給できるのか要件を紹介します。退職、失業した方は、是非最後まで読んで参考にしてみてください。
目次

社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
雇用保険とは

雇用保険とは、労働者が失業したときや、教育訓練を受けたいときに、失業給付などを支給する保険のことです。支給を受けるためには一定の条件があります。
雇用保険の保険者は国(政府)、窓口は公共職業安定所(ハローワーク)であり、雇用保険の保険料は事業主と労働者の両方が負担します。
一定の条件を満たす従業員を雇い入れるとき、会社は必ず雇用保険へ加入させなければなりません。
具体的な加入条件は以下の通りです。
- 勤務開始時から31日以上働く見込みがある
- 1週間に20時間以上働く
正社員や契約社員だけではなくパートやアルバイト従業員でも雇用保険へ加入している方は多数存在します。対象者は雇用保険からの手当を受給できる可能性があります。
雇用保険の給付は4種類

雇用保険には求職者給付、就業促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4種類があります。
1.求職者給付
雇用保険における失業等給付の1つで、失業した労働者が就職活動をするときに支給される給付のことです。一般的に「失業保険」と言われているのは、求職者給付のうち「基本手当」を指します。
求職者給付には、基本手当以外にも以下のようなものがあります。
- 技能習得手当
- 寄宿手当
- 傷病手当
- 高年齢求職者給付金
- 特例一時金
- 日雇労働者給付金
具体的な内容については、「3.求職者給付」で詳しく解説します。
2.就業促進給付
再就職を支援するための給付金であり、早期に再就職できたときや就職のために引っ越しするときの費用などを支援してもらえます。
就業促進給付には、以下の3つがあります。
- 就業促進手当
- 移転費
- 求職活動支援費
具体的な内容については、「4.就業促進給付」で詳しく解説します。
3.教育訓練給付
スキルや能力を身に付けて、キャリアアップを目指す労働者を支援する給付金です。パソコンや医療事務などの資格や技能を取得する際、受講料の一定までの金額が給付されます。
以下の3種類があります。
- 一般教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練給付金
- 教育訓練支援給付金
具体的な内容は、「5.教育訓練給付」で詳しく解説します。
4.雇用継続給付
育児や介護などで働くのが困難となった方が、仕事を継続できるように支援するための給付金です。
以下の3種類があります。
- 育児休業給付
- 介護休業給付
- 高年齢雇用継続給付
具体的な内容な、「6.雇用継続給付」で詳しく解説します。
求職者給付

求職者給付には、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働者給付金があります。それぞれ詳しく解説します。
基本手当(失業保険)
働く意思と能力があって、求職活動をしているにもかかわらず、職に就けない失業者に対する給付です。一般的に、失業保険と呼ばれるのはこの「基本手当」のことを言います。
基本手当の受給は、居住する地域の公共職業安定所(ハローワーク)が窓口です。事業主から受け取った離職票を提出し、ハローワークへの求職の申し込み後7日間は待期期間となります。自己都合の離職の場合には、待機後原則2ヶ月間(最長3ヶ月)の給付制限となり、基本手当は受給されません。
受給条件、給付金額、給付日数・期間、受給期間は以下の通りです。
受給要件
基本手当の受給要件は以下の通りです。
- 原則として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
- 倒産や解雇などの会社都合の場合には、離職前の1年間に被保険期間が6ヶ月以上あれば受給可能
- 求職の意思と能力がある
- 求職活動をしている
給付金額
離職前6ヶ月間の賃金日額の45%(60歳未満は50%)~80%が支払われます。
給付日数・期間
給付日数は、被保険者であった期間によって90~150日と定められています。会社都合の場合には、90~330日まで延長されます。
受給期間
離職日の翌日から原則1年間です。受給期間中に病気やケガ、妊娠、出産、育児などの理由で30日以上職に就けない場合には、受給期間を3年間延長して、最長4年間に変更可能です。
技能習得手当
雇用保険受給者が再就職するために公共職業訓練を受けるときに支給される給付金です。受講手当と通所手当の2種類があります。
受講手当
基本手当を受給できる期間内に職業訓練を受けた日にもらえる手当のことです。支給額は日額500円で、上限は20,000円(最大40日分)に設定されています。
通所手当
職業訓練を受ける人が、職業訓練を行う施設に通うために電車やバスなどを使用した場合に支給されます。車を利用する場合のガソリン代も支給され、上限額は月額42,500円です。
なお、職業訓練の受講料は無料ですが、テキスト代などは自分で負担する場合があります。
寄宿手当
公共職業訓練を受ける場合に家族と別居して宿泊しなければならないときに支給されます。上限額は月1万700円であり、以下の条件のどれかを満たす必要があります。
- 訓練場所までの移動時間が往復で概ね4時間以上
- 訓練場所までの交通機関の便が著しく悪い
- 訓練場所の特殊事情により、宿泊が必要
寄宿手当は、職業訓練受講給付金が支給されないときは、受け取れません。職業訓練受講給付金とは、求職者支援制度を利用した場合に一定の条件を満たす方に支給されます。
求職者支援制度では、雇用保険を受給できない方が公的職業訓練によってスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援してくれます。職業訓練受講給付金では、月額10万円+通所手当+寄宿手当が支給されます。
傷病手当
失業保険の受給中に病気やケガをして求職活動ができなくなったときに支給される手当です。支給期間は最長1年6ヶ月までであり、支給条件は以下の通りです。
- 失業保険の受給資格がある
- 失業保険の手続き後に病気、ケガをした
- 病気やけがによって15日以上働けない
- 健康保険による傷病手当金や労災保険による休業補償給付を受けていない
健康保険の傷病手当金は、被保険者が在職中に病気やケガで働けなくなった場合に受け取る手当金であり、雇用保険の傷病手当とは同時に利用できません。
高年齢求職者給付金
離職した65歳を超える人が、働く意思と能力をもって求職活動を行うときに支給される給付金です。申請すると、一括で給付が行われます。受給要件と、給付金額は以下の通りです。
高年齢求職者給付金を受け取るためには、居住する地域の公共職業安定所(ハローワーク)に行き、事業主から受け取った離職票を提出します。ハローワークへの求職の申し込み後7日間は待期期間となります。
自己都合の離職の場合には、待機後原則2ヶ月間(最長3ヶ月)の給付制限となり、高年齢求職者給付金は受給されません。
受給要件
高年齢求職者給付金の受給要件は以下の通りです。
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
- 失業状態にあること
失業状態でも、就職する意思や能力がないと判断されると受給できない点に注意が必要です。
給付金額
高年齢求職者給付金の受給要件は以下の通りです。
- 日額手当=6カ月間の給与÷180日×50~80%
- 被保険者期間1年以上=日額手当×50日分
- 被保険者期間1年未満=日額手当×30日分
求職の申し込みが遅れた場合には、上記の日数分をできない場合もあるので、早めに求職の申し込みをする必要があります。
特例一時金
基本手当を受けられない雇用保険が1年未満の季節労働者(短期雇用特例被保険者)などが受給できます。「退職前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険への加入」という基本手当の受給要件を満たさなくても受給可能です。
日雇労働者給付金
日雇労働者や30日以内の期間労働者が失業したときに支給される手当です。
就業促進給付

再就職を支援するための給付金であり、就業促進手当、移転費、求職活動支援費の3種類があります。
就職促進手当
就職促進手当は、早期に再就職できた方を対象とする手当であり、再就職手当、就業促進定着手当、就業手当、常用就職支度手当の4種類があります。
再就職手当
基本手当の受給中に早期に再就職すると受給できます。具体的には、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、要件に当てはまる場合に支給されます。
支給額は再就職時の残り給付日数によって異なり、一定の要件と手当金額は以下の通りです。
- 給付残日数が3分の2以上であれば日額手当の70%
- 給付残日数が3分の1以上であれば日額手当の60%
ただし、雇用期間が1年以上となる見込みがなければなりません。
就業促進定着手当
再就職先の企業で6ヶ月以上雇用されたとき、受け取った賃金が前職の賃金より低かった場合に支給されます。支給額は、前職における賃金額と就職先での賃金額の差額です。
就業手当
アルバイトなど臨時的な就労で「1年以上の雇用見込み」がなく再就職手当の支給条件を満たさない場合に支給される手当です。常用雇用等以外の形態で就業した場合に受け取れる給付です。
また、失業保険の給付日数が3分の1以上残っている状態で就職したときに支給されます。
常用就職支度手当
身体障害者、精神障害者や高齢者などの「就職困難者」が就職できたときに支給される手当です。
移転費
ハローワークから紹介された企業に就職したときや職業訓練を受けるとき、引っ越しが必要となったら支給される給付金です。電車代、車、飛行機、船の代金、移転料、着後手当が支給されます。
親族も一緒に引っ越しする場合、支給額を増やしてもらえる可能性もあります。支給条件は以下の通りです。
- 就職先や訓練施設への移動時間が往復4時間以上
- 就職先や訓練施設までの交通の便が著しく悪い
- 就職先や訓練施設の特殊事情により、引っ越しせざるを得ない
求職活動支援費
求職活動をするときにかかる交通費や宿泊費、教育訓練受講費が支援される制度です。広域就職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費の3種類があります。
広域就職活動費
広いエリアで就職活動をして高額な費用がかかった場合には、広域就職活動費として電車代、新幹線代、バス代、飛行機代、船賃や宿泊費などの支給を受けられます。
支給金額は、交通費については全額、宿泊費については8000円前後です。
支給条件は、交通費の場合ハローワークからの距離が200km以上、宿泊費の場合ハローワークからの距離が400km以上とされています。
短期訓練受講費
再就職に向けて1ヶ月未満の教育訓練を受講するときに支給されます。コースを修了すると、支払い済みの教育訓練費の20%を受け取れます。
ただし、上限は10万円です。
求職活動関係役務利用費
企業の就職説明会に参加、面接や試験を受けに行く、あるいは職業訓練を受講するために、保育所や幼稚園、子ども園などに子どもを預けるときの費用を支給してもらえます。
支給額は、保育サービスの利用料の80%です。
教育訓練給付

スキルや能力を身に付けてキャリアアップを目指す労働者を支援する給付金には、一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金の3種類があります。
一般教育訓練給付金
厚生労働大臣が指定する教育訓練コースを修了したときに受け取れる給付金です。教育訓練の期間として1年未満のものが対象となります。簿記や介護関係の資格などが該当する場合が多いでしょう。
支給額は教育訓練費用の20%であり、上限は10万円です。
専門実践教育訓練給付金
看護師や保育士、建築士などの専門的な資格を取得するために教育訓練を受ける際、支給されます。受講期間が1~3年のものが対象であり、支給額は教育訓練にかかった費用の50%(上限は年間40万円)、3年間で最大168万円を支給されます。
支給条件は以下の通りです。
- 初めて支給を受ける方:通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間がある
2回目以降の支給を受ける方の支給条件は次の通りです。
- 以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に3年以上雇用保険被保険者期間を有している
さらに、条件によっては以下に紹介する教育訓練支援給付金が支給される場合もあります。
教育訓練支援給付金
専門実践教育訓練給付金の支給を受けている方の中で、さらに以下の条件を満たす方が対象です。
- 初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制は除く)を受講する
- 受講開始時に45歳未満である
- 離職してから1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
- 訓練期間中に失業状態であること
日額は、離職前の6か月間に支払われた賃金から算出された基本手当日額の80%です。
雇用継続給付
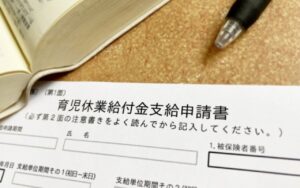
働けない理由がある場合に、所得を保証する制度であり、育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付の3種類があります。
育児休業給付
育児休業する際に受け取れる給付金です。基本的には子どもが1歳になるまでの期間、支給されます。ただし、以下のような場合は、子どもが1歳6ヶ月、さらには2歳になるまで支給期間を延ばしてもらえる可能性があります。
- 待機児童となって育児休業期間の延長が認められた場合
- 離婚して配偶者が子どもと別居することになった場合
- 再度妊娠した場合
また、母親と父親の両方が育児休業を取得する場合、1年2ヶ月まで延長可能です。支給金額は、育児休業開始から180日目までは月給の67%、181日目以降は月給の50%です。
介護休業給付
家族の介護のために介護休業を取得して充分な給料を受け取れなくなったときに支給される給付金です。男女、年齢を問わず受け取れます。
介護の対象となる親族は「配偶者、父母、子ども、配偶者の父母」です。同居であれば「祖父母、兄弟姉妹、孫」も対象とされます。
支給される金額は、休業開始時の給与の40%で、支給期間は最長3ヶ月です。
高年齢雇用継続給付
60歳以降も継続して働く場合に、60歳到達時の賃金に比べて75%未満になった高齢者に支給され、高年齢雇用継続基本給付金と高齢者再就職給付金の2種類がある。
高年齢雇用継続基本給付金
60歳を過ぎて再雇用となり、給与額が75%未満になったときに支給される給付金です。60歳を超えて継続雇用される場合、それまでと比べて大きく給与額をカットされるケースが多いため、支給されます。
高齢者再就職給付金
60歳から65歳未満の人が再就職できたときに支給される給付金であり、1年以上雇用される見込みがある場合が支給対象です。
雇用保険の給付申請は専門家へ相談がおすすめ

今回紹介した雇用保険の給付を受けるためには、ハローワークに必要書類を提出する必要があります。
ただし、多くの種類があり自分がどの給付を受けられるのかわからないという方も多いでしょう。本当は受給できる給付金についてわかっていないと、受け取れる給付金を受け取らずに損をしてしまうかもしれません。
専門家に相談して、支援を受けるのがおすすめです。
弊社では、社会保険給付金サポートサービスを行っており、申請書類の作成や必要書類の準備など支援をしております。退職して就職活動を行う方、育児や介護で休業する方、定年退職や再雇用となった方、教育訓練を受講する方など、ぜひとも一度ご相談ください。