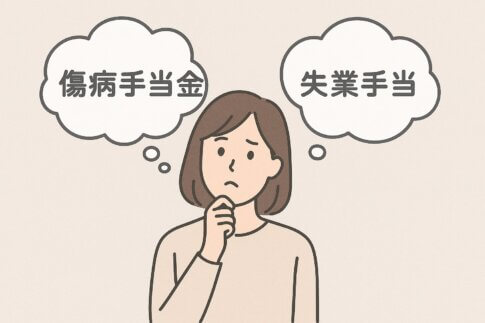「退職届の書き方って決まっているの?」
「辞表と退職願の違いは?」
「退職届に、退職理由はなんて書けば良いか教えて欲しい」
と気になっていませんか。
会社を辞める時に、退職届の提出が求められます。
- 退職届
- 退職願
- 辞表
のどれを、どのように書いたら良いかわからない人もいますよね。
そこで、この記事では
- 退職届と辞表は大きく異なる
- 退職届を書くときのポイント
- 退職までの流れ
- 退職届を提出するときの注意点
などを詳しく紹介します。これから退職を考えている人は、ぜひ最後までご覧ください。
目次

社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
退職届は理由を書きたくなければ「一身上の都合」で良い

退職届に書く退職理由は、「一身上の都合により」とするのが基本です。会社にはあなたの退職を止める権利がないからです。
ただし、一身上の都合とは、自分の希望で退職することを意味しています。
そのため、会社都合で退職を行う人は退職理由をしっかりと書くようにしましょう。「一身上の都合」で退職届を出してしまうと、会社側に自己都合退職として処理される可能性が高いです。
- 人員整理
- 希望退職
- 退職勧奨
- ハラスメント
などが理由の場合は、失業保険をすぐにもらうためにも退職理由をしっかりと退職届に記入してください。
退職届と辞表は大きく異なる

退職届と辞表の違いが分からない人も、多いです。
また、退職願もあり会社員が会社を辞めるときは何が正解かしっかりと知っておきたいですよね。
こちらでは、
- 退職願
- 退職届
- 辞表
の違いを1つずつ詳しく解説します。
1.退職願
まだ退職していない従業員が、会社に対し「退職したい」という意向を伝えるための書類です。退職願を出し、会社が了承すれば雇用契約が終了し、退職できます。
退職するために退職願は必ずしも必要ではありません。口頭で退職希望を伝え、了承を得られれば省いてもかまいません。
2.退職届
退職届は、すでに会社と話をして退職が確定した後に退職を届け出るための書類です。
退職する際には、通常退職届を作成して提出する必要があり、会社からも求められるでしょう。
3.辞表
雇用契約にない人が職を辞するときに提出する書類です。社長や取締役などの経営層、公務員が退職するときに職場に提出します。
一般の従業員の方は、退職時に「退職届」を作成して会社へ提出するのが通常です。会社から退職届の提出を求められるケースも多いので、正しい書き方を把握しておきましょう。
【理由はどうする?】退職届の書くときの流れ3ステップ

退職届を実際に書くときの流れを3つのステップで紹介します。
- 用意するもの
- 退職届の書き方
- 封筒にいれる
1.用意するもの
退職届は、パソコンで作成してもかまいません。ただ一般的には手書きで作成します。その方が誠意や気持ちが伝わりやすいと考えられているためです。
まずは用紙とペンを用意しましょう。
最終的に封筒に入れるので、B5かA4の白色の便せんを使うようおすすめします。ペンは黒のボールペンまたは万年筆を使いましょう。
封筒は郵便番号枠のない白地のものを用意します。便せんがB5なら長形4号、A4なら長形3号を選びましょう。
2.退職届の書き方
退職届は簡潔に書きましょう。
- 退職届とタイトルを書く
- 1行空けて本文1千行目の一番右に「私義」または「私事」と記入
- 退職理由と退職日付を書く
- 「退職いたします」で文の最後を締める
- 届出年月記入
- 署名押印
退職届の書き方例文も合わせて紹介します。
| 退職届
2020年〇月〇日 株式会社〇〇〇〇 代表取締役 〇〇〇〇殿 商品開発部 第1課 〇〇〇〇 印
私議 このたび一身上の都合により、2020年〇月〇日をもって退職いたします。
以上
|
退職願の場合は、「退職いたしたく〜お願い申し上げます」と願い出ます。退職届は、承諾されている状態なので、「退職いたします」と書いてください。
3.封筒にいれる
退職願や退職届ができたら、封筒に入れて会社へ提出しましょう。封入するときには、便箋を三つ折りにします。
三つ折りの方法
- 下から上に3分の1を折り上げる
- 上から下に折り重ねる
退職までの流れ5ステップ

退職届を書いて、退職は終わりではありません。退職するまでの流れを5つのステップで紹介します。
- 必要であれば退職願を作成
- 直属の上司に退職を申し出る
- 退職日と最終出勤日を決める
- 退職届を制作・提出
- 業務の引き継ぎ、挨拶回り
1つずつ順番に確認しましょう。
1.必要であれば退職願を作成
必要であれば、退職願を作成しましょう。
退職する決意を固めたら、会社にその意思を伝えねばなりません。
直接上司に伝えれば良いです。しかし、書面によって退職の意思を伝えたい場合、事前に退職願を作成しましょう。
退職願には「~(退職理由)により、退職したく、ご了承お願いいたします」などと記入しましょう。
2.直属上司に退職を申し出る
直属の上司に退職したい意向を伝えます。
退職申出は口頭でもかまいませんが、退職願を用意したならその書面を渡しましょう。
上司に伝えるときのポイントは、「相談したいことがある」ではなく「退職することを決めました」と伝えましょう。そうしないと、引き止め合う可能性があるからです。
会議室や個室などの人目に触れないところをお勧めします。いきなり上司を呼び止めるのではなく、事前にアポイントをとって時間的に余裕のある状態で渡しましょう。
3.退職日と最終出勤日を決める
退職が認められたら、退職日と最終出勤日を決めます。
有休が残っている場合は、有休消化をしたい旨を伝えてくださいね。会社によっては、有給休暇の買取をしてくれます。
4.退職届を作成・提出
退職日が決まったら、退職届を作成しましょう。
会社で書式が決まっている場合もあります。決まった書式が無い場合には本記事を参考に、自分で作成してください。できあがったら会社へ提出しましょう。
もし、会社と揉めていて退職届を受け取ってくれない場合は、内容証明郵便で退職届を送付します。提出した証拠を残しましょう。
第3者が介入することで、確実に退職届を提出した証明ができます。退職届が会社に到着する日から2週間後を、退職日にするようにしましょう。
5.業務の引き継ぎ、挨拶回り
退職手続きが完了したら、社内や社外での業務引継ぎに対応しましょう。退職の挨拶まわりを行うこともよくあります。
後任者が決まっていないのであれば、引き継ぎファイルなどを作っておくと良いです。上司とも打ち合わせをして、現在の進捗状況を説明しておくと退職後に会社から連絡が来ることもありません。
退職届を出すときの注意点5選

退職届を提出するときの注意点を、5つ紹介します。円満に退職するためにも、ぜひ意識してみてくださいね。
- 早めに退職の意思を伝える
- 会社都合で辞める場合は退職理由に明記する
- 一度退職届を提出したら取り下げられない
- 有給休暇について確認する
- 退職届を受け取ってくれなかったら内容証明で送る
詳しく説明します。
1.早めに退職の意思を伝える
退職したいときには、遅くとも希望日の1か月前には直属の上司へ退職意思を伝えましょう。3か月くらい前に伝えても早すぎることはありません。
あまり直前になると引継ぎにも充分な時間をとれず、会社側へ迷惑をかけてしまうおそれがあります。スムーズに退職するためにも余裕をもって退職願を出しましょう。
2.会社都合で辞める場合は退職理由に明記する
退職願や退職届は、自己都合退職のみ提出するイメージがあります。実際には、会社都合退職でも退職届を求められることが多いです。
また会社都合退職の場合、退職願や退職届に「一身上の都合」と書いてはいけません。一身上の都合は、自己都合退職の理由だからです。
退職すると失業保険を受給できますが、自己都合退職になると受給できる時期が2か月も延びて総支給額を減らされるなど、大きなデメリットが発生します。
会社都合退職なら、必ず具体的な事情を書きましょう。退職勧奨を受けたなら「退職勧奨に従い」とはっきり書く必要があります。会社から「一身上の都合により」と書くよう求められても、応じてはなりません。
3.一度退職届を提出したら取り下げられない
退職届は一度提出すると、取り下げができません。安易な気持ちで提出してはなりません。
退職願の場合、会社が退職を認めるまでは取下げ可能です。ただ、会社が即退職を承認してしまったら、もはや撤回できません。
また退職願を取り下げさせてもらえたとしても、「会社を辞めたい」と伝えてしまっているので、その後会社から警戒される可能性が高くなります。異動させられたり昇進が難しくなったりして不利益を受けるリスクも発生するでしょう。人間関係も変化するかもしれません。
4.有給休暇について確認する
退職が決まった後、まだ消費していない有給があれば消化できます。有給を取得するのに会社側の許可は要りません。また、取得理由も不要です。
基本的に労働者が「有給を利用したい」と希望すれば会社は許可しなければならないので、退職日までの期間、なるべく多くの有給を使ってしまうのが良いでしょう。
退職希望日ぎりぎりに伝えてしまった場合、有給を充分に消化できない可能性が高まります。その意味でも、退職希望は3か月程度前に伝えるのがお勧めです。
5.退職届を受け取ってくれなかったら内容証明で送る
退職届を受け取ってくれない場合は、内容証明郵便で退職届を送付しましょう。提出した証拠を残せるからです。
第3者が介入することで、確実に退職届を提出した証明ができます。退職届が会社に到着する日から2週間後を、退職日にするようにしましょう。
退職後は失業保険を申請しよう

退職したら、多くの方が失業保険を受け取れます。会社都合退職だけではなく
- 自己都合退職
- アルバイト
- パート
- 派遣社員
- 契約社員
にも、条件はありますが失業保険は適用されます。
退職後に会社から送られてくる離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ行き、失業保険の申請をしましょう。
会社が離職票を送ってくれない場合には、問い合わせて早めに送ってもらいましょう。無視されたり拒否されたりしたら、ハローワークへ相談してみてください。
失業保険を受給することで、心に余裕を持って就職活動が行えます。失業保険について、1人で申請できるのか心配な人におすすめなのが社会保険給付金サポートです。
プロがあなたの状況に合わせたベストなサポートを行ってくれます。
退職届の理由の書き方で迷ったら一身上の都合にしよう

退職届の理由の書き方に迷ったら、一身上の都合にしましょう。詳しく退職理由を書く必要はありません。
しかし、会社都合退職の場合は話が違います。失業保険を待機期間無しでもらうためにも、しっかりと退職理由を記入しましょう。
会社都合退職とは、
- 退職勧奨
- 倒産
- ハラスメント
- 仕事のストレスによる体調不良
- 仕事中のケガ
などが当てはまります。
自己都合退職の場合のみ「一身上の都合」と書いてくださいね。