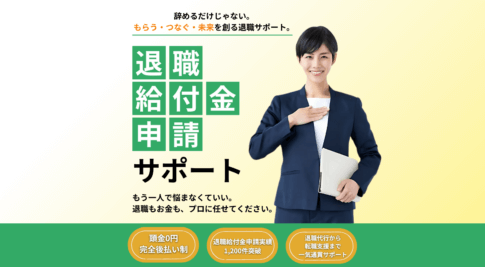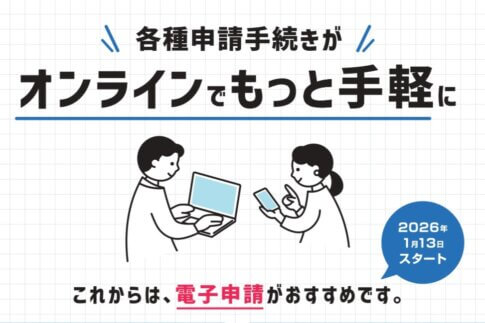仕事や通勤中にケガをした場合と、私生活の病気やケガで働けなくなった場合では、利用できる制度が異なります。
業務や通勤に起因するなら「労災保険」、私的な病気やケガなら「傷病手当金」が中心です。
しかし実際には「どちらを優先すべきか」「同時に受け取れるのか」と悩む人も少なくありません。
本記事では、両制度の特徴を整理し、優先順位や併用ルール、注意点をわかりやすく解説します。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

労災保険と傷病手当金の基本を整理
働けなくなったときに生活を支えてくれる制度には、労災保険と傷病手当金があります。
名前はよく聞くものの、「どんなときに使えるのか」「違いは何か」が分かりにくく、混同してしまう人も少なくありません。
まずは両制度の特徴を整理してみましょう。
労災保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事中や通勤中に起きたケガや病気を補償する制度です。
治療費が全額補償される「療養補償給付」や、休業中の生活を支える「休業補償給付」、後遺障害が残った場合の「障害補償給付」など、幅広いサポートが用意されています。
保険料はすべて会社が負担するため、労働者自身が支払う必要はありません。
傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険に加入している人が私的な病気やケガで働けなくなったときに支給される制度です。
給与の約3分の2が支給され、最長で1年6か月間受け取ることができます。
現役世代を中心に、休職中や退職後でも条件を満たせば受給可能で、幅広い人にとって生活の支えとなる仕組みです。
共通点と違い
労災保険と傷病手当金には、いずれも「働けないときの生活を補償する」という共通点があります。
ただし、労災は「業務や通勤が原因」であることが条件で、傷病手当金は「私的な病気やケガ」が対象です。
つまり、利用できるかどうかは“原因”によって大きく変わるのが特徴です。
労災と傷病手当金は同時にもらえる?
「労災と傷病手当金を同時に受け取れたら安心なのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、両制度の仕組みには明確なルールがあり、原則として同時受給はできません。
ここでは、その理由と例外的なケースを解説します。
原則は併給不可
同じ病気やケガについて、労災保険と傷病手当金を両方受け取ることはできません。
たとえば業務中の事故で骨折した場合は、労災保険で医療費や休業補償がカバーされるため、同じ傷病で傷病手当金を請求することはできない仕組みになっています。
別の理由なら同時受給も可能
ただし「業務に起因するケガ」と「私的な病気」が同時に発生した場合には、それぞれの制度を利用できるケースがあります。
たとえば、業務中のケガで労災を受けつつ、同時期に私的な病気で傷病手当金を受給するといったケースです。
とはいえ実務上はまれで、審査も厳しく行われます。
実務的な優先順位
基本的には「労災に該当する状況では労災を優先する」のが原則です。
業務や通勤に起因する傷病を健康保険に切り替えて請求することはできません。
逆に、私的な病気やケガであれば労災は使えず、傷病手当金を利用することになります。
どちらを優先すべき?
労災と傷病手当金は、対象となる「原因」が異なるため、状況に応じて優先すべき制度が変わります。
ここでは、それぞれを選ぶべき典型的なケースを整理します。
労災を優先すべきケース
- 業務中の事故や通勤途中のケガ
- 長期療養が必要となる業務上の病気
- 医療費を自己負担せずに治療を受けたい場合
労災は治療費が全額補償され、さらに休業中も給与の約8割が支給されます。
会社が保険料を負担しているため、業務や通勤に起因する場合は迷わず労災を選ぶべきです。
傷病手当金を優先すべきケース
- 私生活での病気(がん、生活習慣病、私的な事故など)
- 短期的な療養が必要なケース
- 業務に関係のないケガ
傷病手当金は給与の約3分の2が支給され、最長1年6か月間利用できます。
私的な病気やケガでも安定した生活を続けられるよう設計された制度です。
比較まとめ
- 労災:業務や通勤が原因。補償は手厚く、医療費全額+給与8割をカバー。
- 傷病手当金:私的な病気やケガが原因。期間は最長1年6か月で、給与の約3分の2を補償。
つまり、制度を選ぶ基準はシンプルで「原因が業務や通勤なら労災」「私的な病気やケガなら傷病手当金」と覚えておけば迷いません。
制度を利用する際の注意点
労災と傷病手当金は、いずれも生活を守る大切な制度ですが、申請の流れや条件を理解していないと、受け取れるはずの給付を逃してしまうこともあります。
ここでは、特に注意したいポイントを解説します。
申請窓口が異なる
- 労災保険:労働基準監督署に申請(基本的には会社を通じて手続き)
- 傷病手当金:健康保険組合や協会けんぽに申請
それぞれ申請先が異なるため、どの制度を利用するのかを正しく把握して進めることが重要です。
医師の診断書の重要性
両制度とも、医師の診断書が認定可否に大きく関わります。
特に労災では「労働と傷病の因果関係」が明確に記載されているかがポイントです。
不備があると不支給になる可能性があるため、内容を確認してから提出することをおすすめします。
会社が協力しない場合
労災では「労災隠し」と呼ばれるように、会社が申請に協力しないケースがあります。
しかし、その場合でも労働者本人が直接労働基準監督署に申請することが可能です。
会社に遠慮して諦める必要はありません。
時効に注意
労災保険・傷病手当金のいずれも、原則として2年以内に申請しなければ支給されません。
期限を過ぎると受け取れなくなるため、早めの手続きが大切です。
労災が認められなかったときの救済制度
労災はとても心強い制度ですが、必ずしも認められるとは限りません。
業務との因果関係を証明できなかったり、申請が遅れて時効を過ぎてしまったりすると、不支給になるケースもあります。
とはいえ、その場合でも他の制度を組み合わせることで生活を支えることは可能です。
- 傷病手当金
労災が不認定となった場合でも、私的な病気やケガとして健康保険から傷病手当金を受給できる可能性があります。
給与の約3分の2が最長1年6か月支給されるため、療養期間の生活を下支えしてくれます。 - 障害年金
長期的に働けない状態が続くときには、障害年金の対象となることがあります。
等級に応じて年金が支給されるため、長期的な生活の安定につながります。 - 失業保険
退職後で「働ける状態」と判断されれば、雇用保険から失業手当を受給できます。
労災による障害が残っていても、就労可能とみなされれば対象になる場合があります。 - 生活支援制度
住居確保給付金や生活福祉資金貸付といった制度も併用可能です。
生活の立て直しや就労再開までの支援として利用できます。
まとめ:状況に合わせて制度を正しく選ぼう
労災と傷病手当金はいずれも「働けないときの生活を支える制度」ですが、利用できる場面や内容には明確な違いがあります。
業務や通勤が原因であれば労災、私的な病気やケガであれば傷病手当金と、原因によって選ぶ制度は変わります。
同じ傷病で両方を同時に受け取ることはできないため、状況に応じた判断が必要です。
また、労災が認められなかったとしても、傷病手当金や失業手当など他の制度を組み合わせて生活を支えることは可能です。
重要なのは「受け取れるはずの給付を逃さないこと」。
どの制度が利用できるか迷ったときは、専門機関に確認するのが安心です。
弊社「社会保険給付金アシスト」でも関連制度に関するご相談に対応していますので、気になる方はぜひご覧ください。