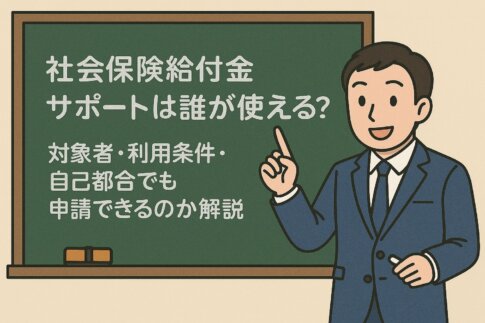退職後にまずやるべきこと——
それが「社会保険の切り替え手続き」です。
在職中は会社が行っていた健康保険や年金の加入・支払いも、退職後はすべて自分で行う必要があります。
手続きを後回しにすると、医療費が全額自己負担になったり、年金受給額に影響が出るおそれもあります。
一方で、退職後の収入が減った人は「国保の減免」や「年金の免除」などで負担を抑えることも可能です。
この記事では、退職後に必要な社会保険の手続きを「健康保険・年金・扶養・任意継続」の4つに分けて、わかりやすく解説します。
それぞれの手続き期限や注意点、そして少しでも出費を抑える方法までしっかり整理していきましょう。
※本記事は、雇用保険・社会保険制度に精通した編集チーム(ハローワーク・保険者確認体制あり)が、厚生労働省・協会けんぽ・日本年金機構などの一次情報をもとに作成しています。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

社会保険とは?
社会保険とは、会社員や公務員などが加入する公的な保険制度のことです。
病気やケガ、老後、失業など、もしもの時に生活を支えてくれる仕組みです。
社会保険と一口に言っても、実は大きく分けて5つの種類があります。
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
このうち、「健康保険・介護保険・厚生年金保険」の3つを狭い意味での“社会保険”と呼び、
「雇用保険」と「労災保険」は“労働保険”に分類されます。
会社員の方は、これらすべてに自動的に加入しており、毎月の給与から天引きされている保険料で支え合う仕組みになっています。
つまり、社会保険は“働く人の生活を守るセーフティネット”のような存在です。
退職後に加入する保険の手続き方法3選
退職後は、会社を通じて加入していた社会保険を自分で切り替える必要があります。
代表的な方法は次の3つです。
① 国民健康保険と国民年金に加入する
会社を退職したあとは、原則としてお住まいの市区町村で「国民健康保険」と「国民年金」に加入する必要があります。
どちらも「自分で保険料を支払う」仕組みになるため、在職中より負担が増える点に注意しましょう。
- 国民健康保険:前年の所得に応じて保険料が決まります(所得割+均等割など)
- 国民年金:全国一律で 月額17,510円(2025年度)
会社員時代は保険料の半分を会社が負担していましたが、退職後は全額自己負担になるため、
実質的に在職中の約2倍の支出になるケースもあります。
加入の手続きは、市区町村の役場で行います。
退職日の翌日から14日以内が目安ですが、多少遅れても罰則はありません。
② 家族の被扶養者になる
配偶者など、家族が会社員として社会保険に加入している場合は、その扶養に入ることで自分の保険料負担をゼロにできます。
退職後すぐに再就職の予定がない方や、収入が一時的に途絶える方におすすめの方法です。
被扶養者として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 生計維持関係があること(同居、または定期的な仕送りなど)
- 年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
※上限は「今後1年間の見込み収入」で判断されます。
退職後の失業手当は、収入として扱われる場合があるため要注意です。
認定を受けるには、収入証明書や住民票などの書類を提出します。
手続きは「扶養者(家族)」の勤務先に申請します。
審査には数日~数週間かかる場合があるため、早めに相談しておくと安心です。
③ 任意継続被保険者になる
会社員時代に加入していた健康保険を、最長2年間そのまま継続できる制度が「任意継続被保険者制度」です。
退職後も同じ健康保険証を使いたい方や、扶養家族が多い方に向いています。
任意継続の条件は次のとおりです。
- 退職前に継続して2か月以上の被保険者期間がある
- 退職日の翌日から20日以内に申請を行う
参考:協会けんぽ|任意継続被保険者制度
任意継続では、これまで会社が負担していた分も含めて保険料を全額自己負担します。
そのため在職中より高くなりますが、家族の人数や所得状況によっては国民健康保険より安くなるケースもあります。
また、途中で再就職が決まった場合は、任意継続を途中でやめて切り替えることも可能です。
退職後の保険料が軽減・免除されるケース
退職すると、会社が負担していた社会保険料の半分を自分で全額支払うことになるため、保険料負担は一時的に大きくなります。
しかし、一定の条件を満たせば「減免」や「免除」を受けられる制度があります。
減免の対象となる主な条件
次のようなケースに当てはまる場合、国民健康保険や国民年金の保険料が軽減・免除される可能性があります。
- 会社都合・雇止め・退職勧奨など、本人の責めに帰さない離職
- 収入が大幅に減少し、前年より所得が一定額以下になった
- 病気・ケガ・災害などで就労が困難になった
特に「会社都合に近い退職(特定理由離職者)」に該当すると、国民健康保険料が大幅に減額されるケースがあります。
国民健康保険の減免制度
退職して収入が減った人は、国民健康保険料が軽減される制度を利用できる可能性があります。
減免の対象になると、保険料が 7割・5割・2割 のいずれかに下がり、月々の負担がぐっと軽くなります。
審査は世帯全体の前年所得や家族構成をもとに行われ、市区町村役場で申請します。
承認されると、翌月分から自動的に減額が適用される仕組みです。
退職後は収入が途絶えるタイミングなので、申請しておくだけで数万円単位の差が出ることもあります。
対象になるかどうかは、市区町村の窓口や公式サイトで確認してみましょう。
国民年金の免除・猶予制度
退職によって収入が減ったり、無職の期間が続く人は、国民年金保険料の免除・猶予制度を利用できます。
承認されれば、保険料を 全額・4分の3・半額・4分の1 のいずれかで軽減してもらうことが可能です。
また、20代前半の人や学生であれば「納付猶予制度」を使って、一時的に支払いを先送りすることもできます。
いずれの制度も「未納」とは扱われず、将来の年金額には一部反映されるため安心です。
生活が安定したあとに追納(あとから支払う)することもできるので、「今は払えない」という人でも柔軟に対応できます。
減免・免除の申請期限と注意点
退職後の国保・年金の減免や免除を受ける際は、次の3点に注意しましょう。
- 申請は「その月」からが対象
原則として、申請した月以降の保険料が軽減されます。
過去分へのさかのぼりは基本的に不可(一部自治体を除く)。 - 必要書類・判定基準は自治体ごとに異なる
離職票・源泉徴収票などの提出が求められる場合があります。
詳細は市区町村の窓口または公式サイトで確認を。 - 年度途中でも再申請できる
収入が変動したときや再就職・独立など環境が変わった場合は、再申請により見直しが可能です。
制度を活用すれば、年間で数万円単位の負担軽減につながることもあります。
退職時の社会保険手続きとあわせて、早めに確認しておきましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1. 退職後すぐに国民健康保険へ加入しないとどうなりますか?
A. 退職後は、会社の健康保険資格が退職日の翌日で喪失します。
そのため、次の健康保険(国民健康保険・任意継続・扶養など)に加入しない期間があると、その間に病院へ行っても医療費が全額自己負担になります。
ただし、手続きが多少遅れても罰則はなく、さかのぼって加入することも可能です。
医療費をあとから一部返還してもらえるケースもありますが、手間がかかるため早めの申請がおすすめです。
Q2. 任意継続と国民健康保険、どちらを選ぶべきですか?
A. どちらが得かは、人によって異なります。
任意継続は、退職前に加入していた健康保険を最長2年間そのまま継続できる制度で、扶養家族も引き続き加入できます。
ただし、保険料は在職時の標準報酬月額をもとに計算され、会社負担分も含めて全額自己負担となるため、在職中より高くなるケースがあります。
一方、国民健康保険は前年の所得をもとに保険料が決まり、収入が減った人ほど軽減される仕組みです。
退職後に所得が下がった場合は、国保のほうが安くなることもあります。
一般的には、扶養家族が多い人は任意継続のほうが有利で、収入が減る人は国民健康保険を選ぶほうが負担を抑えやすい傾向があります。
最終的な判断は家族構成や所得額によって異なるため、迷ったときは加入していた健康保険組合やお住まいの市区町村役所に相談してみましょう。
退職したら「失業保険の申請」を忘れずに
社会保険の手続きが終わったら、次はハローワークでの「失業保険の申請」を行いましょう。
退職後の生活を支える大切な給付であり、手続きを早めに行うことで受給開始もスムーズになります。
申請には、離職票・身分証・マイナンバー・通帳などが必要です。
申請後は「雇用保険説明会」や「失業認定」を経て、初回の給付が振り込まれます。
制度を正しく理解しておくと、受給額を減らさずに済むだけでなく、再就職支援などのサポートも受けやすくなります。
まとめ:退職後の手続きに迷ったら「社会保険給付金アシスト」へ
退職後は、健康保険・年金・扶養・失業保険など、やるべき手続きが一気に増えます。
手続きを誤ると、本来もらえるはずの給付金を逃してしまうことも少なくありません。
社会保険給付金アシストでは、
- 自己都合退職でも失業保険を最大限もらえるようサポート
- 国保・任意継続・扶養など、どの制度を選ぶと最も得かを個別にアドバイス
- 保険料の減免・年金免除など、申請をスムーズに進めるための相談対応
といった支援を行っています。
退職後の不安を一人で抱え込まず、制度に詳しいプロに相談してみませんか?
あなたの状況に合った最適な手続きと給付プランを一緒に整理します。